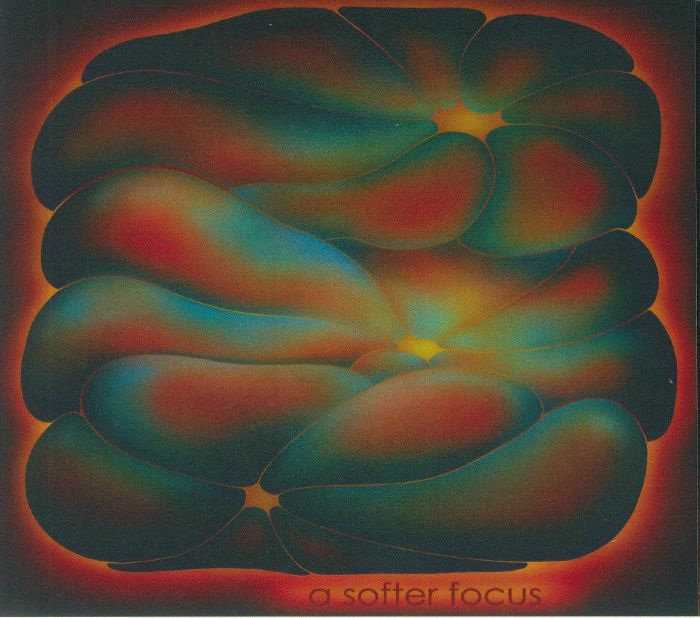MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kelly Ruth- Persistence Beyond All Truth
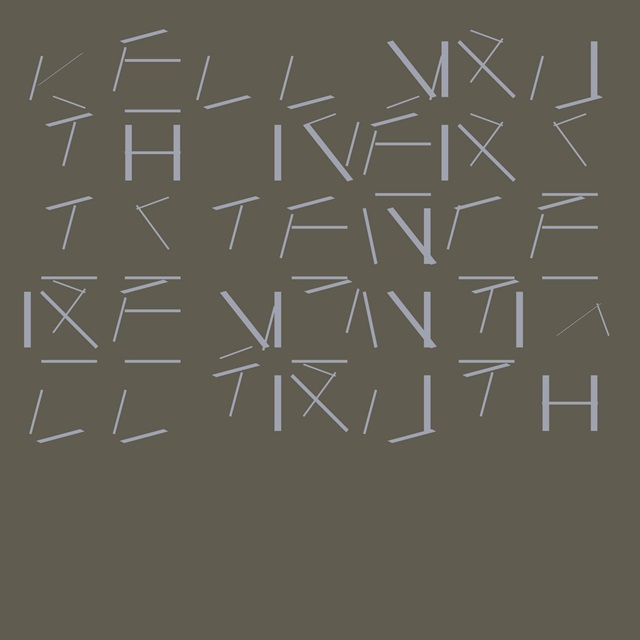
本作『Persistence Beyond All Truth』は、エクスペリメンタルなドローン/コラージュ作品だが、織りあげられていく音たちの持続、変化、質感、接続など、そのコンポジションの手腕は独創性に満ちていて、まるで短編映画を「聴く」かのように鑑賞できたアルバムだった。音の向こうに世界が「ある」感覚とでもいうべきだろうか。全1曲39分の長尺のなかに展開される音世界に、私はただ、ただ呆然として聴き入ってしまった。
まさに傑作というほかない『Persistence Beyond All Truth』を生みだしたサウンド・アーティストが、カナダ出身のケリー・ルースである。彼女は織り機や紡ぎ車にコンタクト・マイクやエフェクターを付けて、その音を丁寧に録音し、電子的に加工・編集を施し、デジタルとアナログ音の境界線を溶かしていく様な音響を生みだしているサウンド・アーティストである(サウンドのみならずヴィジュアル・アートも制作している)。
ケリー・ルースは、2019年にカナダはエドモントンのレーベル〈Pseudo Laboratories〉からカセット・アルバム『Forms』をリリースしすでにマニアたちの耳に静かな衝撃を与えていたが、本年になってシドニーを拠点とする〈Longform Editions〉からアルバム『Persistence Beyond All Truth』をリリースしたことで、その存在は決定的なものとなった。このレーベルに名を連ねることは、そういう意味だ。
〈Longform Editions〉(https://longformeditions.bandcamp.com/)はその名のとおり長尺のトラックのみを収録したアルバムを延々と送り出し続けている実験音楽レーベルである。何はともあれリリース・アーティストが凄いのだ。リチャード・ヤングス、カテリーナ・バルビエリ、サン・アロウ、パン・アメリカン、リサ・ラーケンフェルド、グレッグ・フォックス、ジャスミン・ガフォンド、セラー、畠山地平、グリーン・ハウス、テイラー・デュプリー、クレア・ラウジー、ロバート・クルゲンベン、サム・プレコップ、
ブルット・ナウケ、石橋英子などなど、若手からベテランまで国籍も音楽性も異なるさまざまなアーティスト/音楽たちが名を連ねているのである。そんな彼ら/彼女たちの貴重な長尺曲を、とにかく休むことなく(?)われわれの耳を潤すかのように、送り届けくれる貴重なレーベルなのだ。
なかでもこの『Persistence Beyond All Truth』は本当に素晴らしいアルバムだった。緻密にして優雅、精密にして情景的。聴き込むほどにサウンドスケープが聴覚をとおして聴き手の脳内に、知覚に、感覚に生成するようなアルバムに仕上がっていたからだ。今年にリリースされたエクスペリメンタル・ドローン作品の中でも頭一抜けた見事な完成度である。
ケリー・ルースが作り出す音にはデジタルのなかにアナログな手触りがある。木や布地などの質感やテクスチャーが音の隅々まで感じることができる。しかもここが重要なのだが、そうした個々の音が折り重なって、一つ(複数の)の大きな持続と層になったとき、それらの音は、その音の正体からそっと離れて、まるで環境音のように、サウンドを構成していくエレメントになるのである。そう、ピエール・シェフェールが提唱した「アクースマティック 」サウンドの継承者ともいえよう。
そして、その音の層をずっと聴き込んでいくと、まるで仮想世界の中に紛れ込んで、その世界に満ちている環境音を全身で浴びているような感覚になってくるから不思議だ。まるでデヴィッド・チュードアの「レインフォレスト」のようだ、とは言い過ぎだろうか。チュードアの「レインフォレスト」がさまざまなオブジェ(モノ)の発する音によって、まるで森の中の音のような音響を生成したように、ケリー・ルースはさまざまな音素材を用いながら架空の環境音を生成してみせる。
サウンドのコンポジションが実に見事で、聴き手をひっそりと見知らぬ世界の音の旅へと連れ出してくれるのである。どうやらこのアルバムは、コロナ禍でライヴに行ったり、外出をしたりすることができなくなったことで生まれたサウンドのようである。ケリー・ルースは、部屋の中で仮想世界を夢想し、その音の世界に没入していったらしい。
となれば、この『Persistence Beyond All Truth』を聴くということは、「仮想世界の旅」のごとき音響体験なのだろう。私がこのアルバムのサウンドスケープに惹かれた理由もそこにあるのかもしれない。いわば「音をめぐる旅」のごときリスニング体験だったのだ。言い方を変えれば音によって仮想世界の音響を「演出」するような感覚かあったのである。まるで一本の音だけの短編映画を「編む」ように、サウンドが演出すれ、編集されていく。
このアルバムの横に並べるべき作品は、タイプはまるで違うが、イーライ・ケスラーの最新作にして、傑作『アイコンズ』ではないか。『アイコンズ』もまたロックダウン下の都市の音を集め、織るようにしてでき上がったエクスペリメンタル・アンビエントの傑作である。本作『Persistence Beyond All Truth』もまた自宅隔離を余儀なくされたコロナ禍だから生まれえた仮想空間的なアンビエント・サウンドだ。それぞれ作品の色合いや個性、質感は違うが、コロナ禍の世界だからこそ生まれた現代的なエクスペリメンタル・ミュージックという点では共通している。
この不自由な時代において、先端の実験音楽/エクスペリメンタル・ミュージックは、仮想空間に中に「新しい自由」を手に入れたのではないか。どんなに不自由な時代であっても、人の尽きることのないイマジネーションこそ創作と鑑賞の源泉に思えてならない。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE