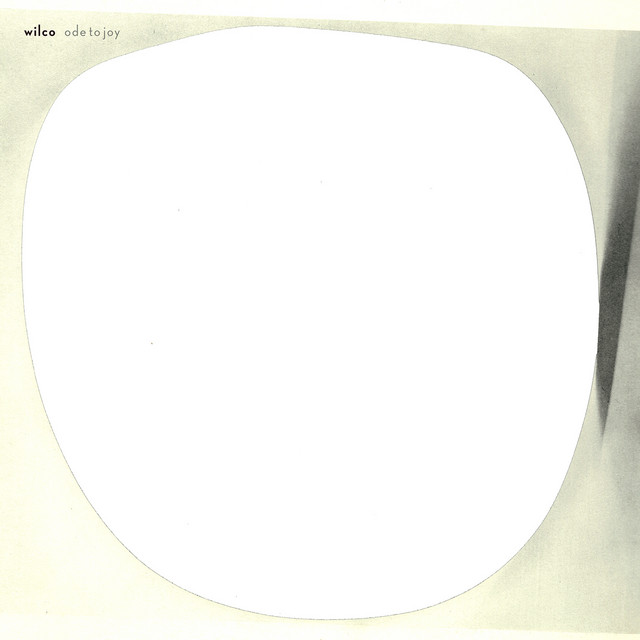MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Douglas J. Cuomo featuring Nels Cline and the Aizuri Quartet- Seven Limbs

クラインの法則をごぞんじだろうか。別名をクライン症候群(シンドローム)ともいい、日ごとの寒暖差がはげしく夏のつかれのでやすいこの時期によくみかけるこの症状にかかると、巷間をにぎわす音楽より腰をおちつけ滋味ある作品に耳を傾けたくなるが、やおら昔のレコードをひっぱりだしても年寄りくさいし、サブスクのいいなりになるのもシャクにさわる。そう考える向きが手にとる音盤に、しばしば彼の名をみとめることからこの呼び名がさだまった──ということの真偽のほどはさておき、今年もどうやらネルス・クラインの関連作を聴きたくなる季節がおとずれたみたいである。
本家ウィルコのアルバムこそ2019年の『Ode To Joy』以来ご無沙汰とはいえ、クラインはその後も継続的に活動をおこなっている。コロナパンデミックは2020年初頭がひとつの境だったが、クラインひきいるネルス・クライン・シンガーズの『Share The Wealth』は同年11月リリース、コロナ禍が炙りだした格差、不平等を想起させる題名もさることながら、ジャズとロックとインプロとオルタナを攪拌しつつ絶妙な濁りをのこすスタイルにはいよいよ磨きがかかっていたのも記憶にあたらしい。アルバムにも参加した私生活のパートナーでもあるチボ・マットの本田ゆかとは CUP 名義でイマジナリーな『Spinning Creature』をその前年にリリースするなど、活動領域は形式を問わない。リーダー作以外でも、霞たなびく演奏が持ち味の即興トリオ、ハンツヴィルの『Bow Shoulder』や、2020年のエルヴィス・コステロの『Hey Clockface』ではその道の先輩格であるビル・フリゼールとの共作もおこなうなど、客演に呼ばれてもサイドにまわってもいかんなく本領を発揮するタチといえるであろう。
ところが今回はいささか趣がちがう。客演作ではあるものの、母体は弦楽四重奏、いわばクラシックにギターで参加する体である。作曲者は90年代末に話題をとったテレビ・ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のテーマ曲で名をあげたダグラス・J・クオモ。1958年生まれのクオモはマックス・ローチやアーチー・シェップに薫陶を受けたジャズのギター奏者だったが、テレビをふりだしに劇判を数多く手がけるにいたって作曲家に転身、映像のほかにも舞台の音楽でも注目をあつめている。私はクオモの音楽に上述の『セックス・アンド~』はもとより舞台も未見のため、ネルス・クラインの名前にひかれてはじめてふれたクチだが、これがまたなかなかに味わい深い。
タイトルの『Seven Limbs』とは仏教用語でいう「七覚支」をさすという。七覚支とは37種の修行方法を7つの部類にわけたものの第6で、悟りのための7種の修行方法からなる。すなわち真実の法を思いとどめて忘れない「念覚支」、智慧により真実を考え選びとる「択法覚支」、たゆみなく努力する「精進覚支」から修業によろこびをおぼえる「喜覚支」とつづき、心身を快適な状態に保つ「軽安覚支」と集中を乱さない「定覚支」、心の平安を保つ「捨覚支」へいたる七覚支がそれで、クオモ自身日々実践しているというが、じっさいに仏門の徒であるかマインドフルネス的なかかわり方なのかはさだかではない。オリエンタルな意匠よりも瞑想的で内省的な曲調をかんがみるに、仏教的な記号は道具立てにとどまらないとは予想はつくが、本作の聴きどころはむしろそれらを音楽的な動機に昇華しクラインの好演をひきだしたクオモの巧みさである。
『Seven Limbs』はクラインの点描的な演奏で幕をあけ、ほどなく提示する五連符のリフレインをきっかけにストリングスが姿をみせる。弦を担当するのは結成9年目で現在はニューヨークを拠点に活動する女性4名からなるアイズリ・カルテット。4人とクラインがテーマとも断片ともつかないフレーズを交換するなかで、3部10分ほどの演奏時間の1曲目の “Prostration” は静かに展開していく。さきに述べたように本作は仏教用語の「七覚支」に対応すべく、7曲からなるが、1曲はさらにいくつかのパート(楽章というほど大袈裟ではなさそう)にわかれ、微細な変化を強調している。曲どうしは「七覚支」の教えがそうであるように緊密に連関しあうはずだが、「礼拝」「供養」「勧請」などといった表題のもつ意味にことさらにこだわらずとも、聴きすすめれば、タイトルにこめた心の移ろいはサウンドにあらわれているのがわかる。それを綴るクオモの筆はいたずらに饒舌にながれず、寡黙にすぎず。劇伴でつちかった物語性をかいまみせるが、本作の物語はクライマックスに収斂する類のものではなく、むしろ終点が起点にかさなる円環構造を描くかにみえる。輪廻と解脱を旨とする仏教がテーマであるためか、きりつめた音数の動機を効果的に配置した構成力の妙味か、あるいは弦楽曲の形式からくる志向性とクラインのギターの螺旋状のからみあいが楽曲に水平(時間)的な持続力をあたえるためか、聴き手は弦が刻む伸縮する時間感覚を体感することになる。ナイマンの弦楽四重奏曲の4番あたりを想起する “Confession & Purification(懺悔と浄化)” の弓の返し、“Rejoicing(随喜)” でのジャズ・コンボ風の弦のピチカットや、“Beseeching(祈願)” のフィリップ・グラス的なミニマリズムなど、クオモのスコアは随所に仕掛けがあるが、クラインとアイズリ・カルテットのアンサンブルにはいかに激しい曲調であっても輪郭がかすむような滲みがある。演奏はむろんのこと、楽器ごとの音色の差異にも由来する響きからくるものだが、なかでも幾多のアタッチメントを駆使しエレクトリックとアコースティックを持ち替えるネルス・クラインの音色のゆたかさは聴き逃せない。クラインのツボとでもいいたくなる、本作のポイントであろう。
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE