MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Live Reviews > 100% Silk x Diskotopia- @渋谷 WWW
オイは生まれてはじめてミラーボールば見たんばい......筆者は生まれてはじめてミラー・ボールをこの目に見た。ききかじりの長崎弁もどきをつかうのは、そうストレートに告白するのがしのびないからである。はずかしながら、このように4つ打ちがとどろく場所に来たことがなく、押すのか引くのかわからない重い扉を開けてものすごい音の波動が押し寄せてきたとき、筆者はほんとうに驚いた。前日に諸先輩方から「外国にも行きたくない、クラブにも行かない、××もやったことがない、それではいかんというか異常。」というような説教を受けてきたが、じつのところオールナイトも初めてで、いろんな先入観からやや腰が重かった。だが、緊張しながらも筆者は仮眠をとり、尋常に準備をととのえ、24時過ぎに人の群れを逆行して渋谷へたどりついたのである。おお、免許証がいるのか。後ろのひと大変すみません。初めてなもので......と、受付に見知った担当者の方の顔をみつけてほっとしながら、ご挨拶もそこそこに混みあったロビーに足を踏み入れると、ビールを手に入れるのもひと苦労なほどの人の入りようだ。〈100%シルク〉というから、マーク・マグワイヤのときのようなムードや客層を漠然と思い描いていたのだが、それはくだんの音圧とともに吹き飛んだ。同じように混んでいるが雰囲気は真逆である。たぶん、シルクが何なのか知らないできている人もいる。だが、ジュリア・ホルターが来ていたならともかく、彼らのプレイはその客層にうまく機能していた。マグワイヤには(そしておそらくジュリア・ホルターやアマンダ・ブラウンなどにも)ステージへの集中があったが、ここには発散がある。ここはダンスをするところだ。なるほど思ってもみないところに来てしまった。そのときはじまっていたマジック・タッチがなにか特別に優れていたり目立っていたりしたわけではないと思うのだが、とにかくバキバキに4つ打ちで、「パワー」というより「フォース」というに近いその音圧には意外なほどわくわくした。なにか、人生で初の部類のことに触れようとしていたのだ。明確にそう直感された。よって、ここまでお読みくださって苦笑されているみなさんも、どうかそんなおぼこいやつの体験記としてあたたかくお目こぼしいただければと思います。
ただ、そのときたまたまうしろのモニターが摩天楼の夜景をレトロなタッチで映し出していたのにはすこし笑った。まさに幻想のエイティーズというか、ヘリからの空撮といった趣でゴージャスに、なかばアイロニカルに街が輝いている。そして時おりシルクのロゴがひらめく。オーソドックスで制圧的な力にみちたマジック・タッチに似合っていた。それに比して、概して隙間の多めの音響構築、ウラ拍とズレをいかしたマーク・バートルズのほうは、最大の盛り上がりポイントでVJがいい仕事をして盛り上がった。温泉・カラオケ・大人数宴会やその他設備を盛ったスーパー旅館のCMが用いられていて、人々の髪型や大写しになったすきやきの色合いや画質などから、これまた失われし80年代への、そして80年代ノスタルジーじたいへのシニカルなオマージュがうかがわれる。タイミングは完全に偶然なのかもしれないが、それならば彼は偶然をうまく引き寄せた。

小さい前ならえほどのスペースをあけて人々が踊りあっている空間は居ごこちがよかった。みなよく相手の耳もとに大きな声で話しかけていたが、ちっともうるさいと感じなかった。そこでは自分もただ大勢のなかのひとりで、音が互いの距離をほどよく遮蔽している。そして暗さがやさしく意識をまもってくれる。ビートと音量が圧倒的で、あまりなにも気にしなくてよくなる。自我や自意識を相対化されるというか、インディ・ロックを聴きにいくときの一種独特の緊張感からは自由であった(その緊張感も大事なものであるが)。ぼーっとしている人もいる。スポーツ観戦に近いのかもしれない。ある瞬間には一体感が訪れる。さまざまな例外はあるものの、ロックの場合、たとえみんなで合唱したとしても一体感はステージ側との1:1の関係で生まれる精神的なものであることが多いのではないだろうか。ここに時おり生まれる一体感とは、もっと動物的な、たとえば一羽のカモが方向を変えるといっせいにみなついていくというような種類のものであるように思われた。
さて、2杯めのビールの調達に手間どっているあいだにサファイア・スロウズがはじまってしまっていた。先のふたりの手練とはちがい、音圧がうすく、出音はやや平面的な印象であったが、彼女は果敢に、その場にライヴを取り戻した。あれだけガンガンと4つ打ちに支配されていたフロアには、いまやメランコリックにピアノの旋律が響いている。生演奏による単純なメロディが、一瞬は場違いにも思われた。目の前のふたり連れが「なんだ、ただのライヴじゃん」と言っていたが、そうした当初の当惑を、彼女はじつに堂々と変えていった。マイクをつかみ、ハイ・プレイシズとナイト・ジュエルのあいだを縫うような感覚で反復するフレーズを丁寧に歌いつづけ、繊細なエレクトロニカは叙情をやめようとしない、そうしているうちにすっかり会場が説得されてしまった。ほとんどの人が踊りをやめていたが、ゆるやかに音に身をもたせて、最後はとてもよい雰囲気で終わった。マジック・タッチとの共作というトラックを披露して幕。非常に勇気のあるステージだったと思う。
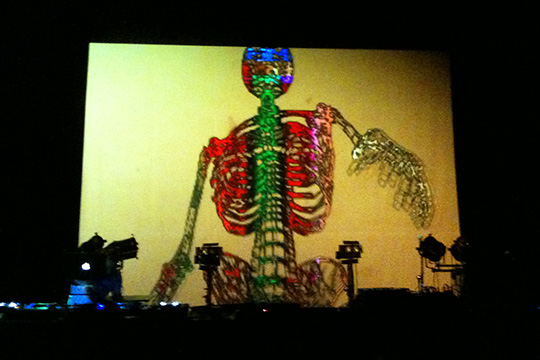
さあ、そしてアイタルの独壇場がはじまる。あたまから唐突に、半端なくナルシスティックでわがままで横暴な高音ヴォーカルがすさまじいノイズとともに押しつけられ、なんというか完全に場が異化された。これはなにかが違う。と誰もが感じるのを、またしてもカモの一羽のように察知した。間髪をいれずモニターにはきのこ雲......これも偶然なのか。激しいドンツクの上に、満ち潮のようにノイズが這い上がってきて、そのある一点をとらえ、海鳥のように鋭い彼の鳴き声が滑降する。まさにブラック・アイズが、しかし思ってもみなかったところで重なった。異様なくらいに彼という人間のエネルギーがほとばしっている。ちょっとのあいだ、言葉を失うほどにかっこよかった。インダストリアル風の音もじつにエモーショナルに取り込んでいたと思う。ローファイなテクスチャーも生きていた。なぜ、これがこんなふうにパッケージされないのか? CD作品とのあいだには深い乖離を感じずにはいられない。間違いなく、CDやアナログのメディアに落とし込まれた段階で、彼の中心のエネルギーは20パーセントくらいに削られてしまっている。背景にはきのこ雲を茂らせた木々が動き、星の夜空がまわる。ほとんどシューゲイズと呼べる展開をみせ、突如としてケトルばりの叙情性がはさみこまれてまもなく、大興奮につつまれてアイタルはライヴを終えた。つづくBD1982はすこしかわいそうだった。ナードで落ち着いた趣向をみせたが、みんな外に出て行ってしまって。みんな、どこへ行ったんだろうか。この間、ちょうど2、3人の知人にバタバタと出会ったが、そのうちのひとりはこれから寝ようと思っていたとのことだ。寝る、どこで? ここで? ワイルドだ。
つづくミ・アミにむけて、よい場所を取っておくことにした。ケータイで写真も撮らなければならない。筆者のようにひとりで突っ立ってとくに踊りもせずにいる人間は、ぶつかられたり何だか不明な水沫を浴びたりすることになるのだ。ということも学習した。ステージが収まる写真など、いい場所じゃないと撮れないにきまっている。べつに、それでまったく腹も立たないのがこの空間の不思議さだ。

そしてミ・アミもまたすばらしかった。マジック・タッチとアイタルは、デュオでの立ち姿もとんでもなくきまっている。彼らには華がある。アイタルのノイズ感は薄れてタイトな印象のステージだったが、ビートが入るとともにまたしてもブラック・アイズなハイ・トーンの機関銃ヴォーカルにあおられ、足元と脳が揺れた。地面にはいつくばってペダルやツマミをいじりながら叫びまくるというスタイルもいいだろうが、卓とサンプラーやミキサー一式のむこうで直立してマイクを握ってさけぶのもいい。叫びながらも手元をするどく見つめてせわしく音を調節し、またときどき言葉を交わしてなにごとか確認しあう、その動作ひとつひとつがわれわれを惹きつけた。ラストは先のアイタルと同様にエモーショナルな展開をみせ、ひと刷毛のメランコリーが加えられた。オーディエンスの動物的な神経はいつしか精神の琴線へと抜き替えられ、微量のものがなしさを含んだコード感と、身体のなかに残存する昂揚感を、迎えつつある夜明けのけだるさのなかに迎え入れた。非常に充実したライヴだった。その後はぼちぼち始発の時間で、知的でミニマルなプレイをするア・トウト・ラインの途中で筆者も出てきてしまった。4割ほどの人たちが思い思いに休んだり話したり、あるいはまだ中で踊ったりしている。
こうして初のオールナイトはつつがなく楽しんだ。ちなみにミラー・ボールはいちども回っていない。最後に驚いたのは、早朝の渋谷にこんなにも帰路につく人々がいるのか、ということでした。
文、写真:橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE












