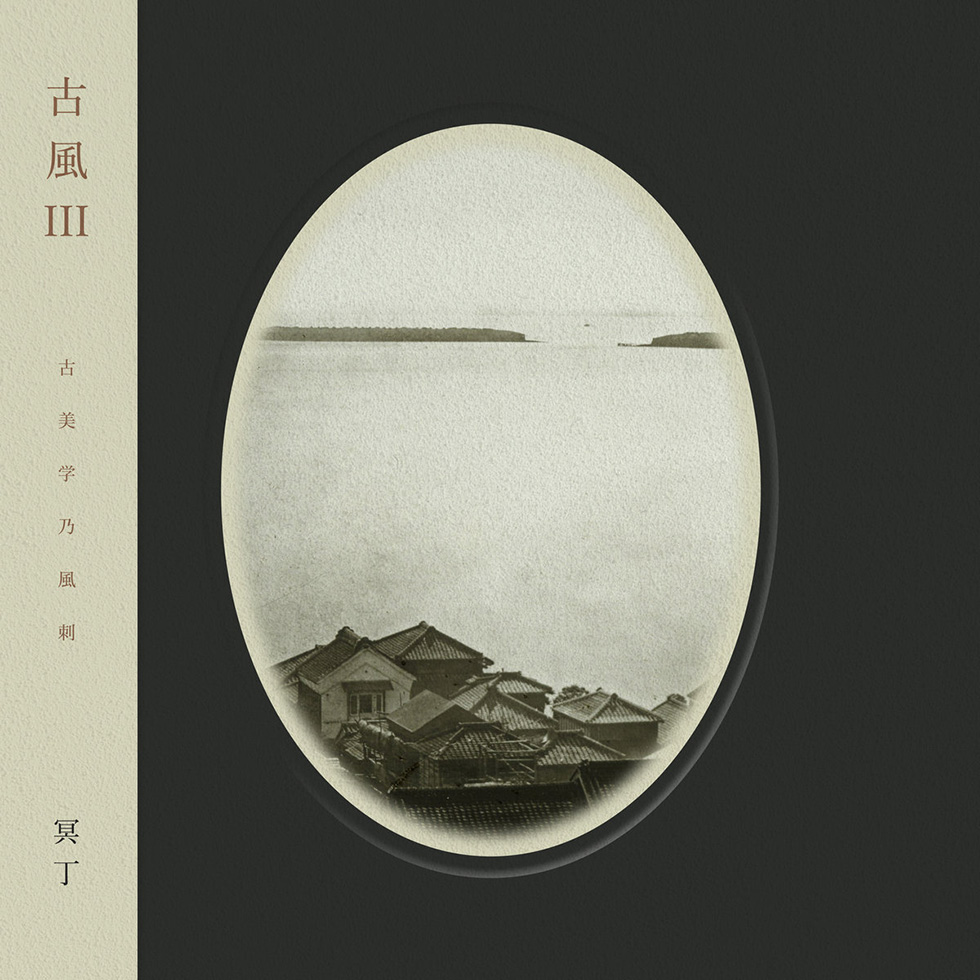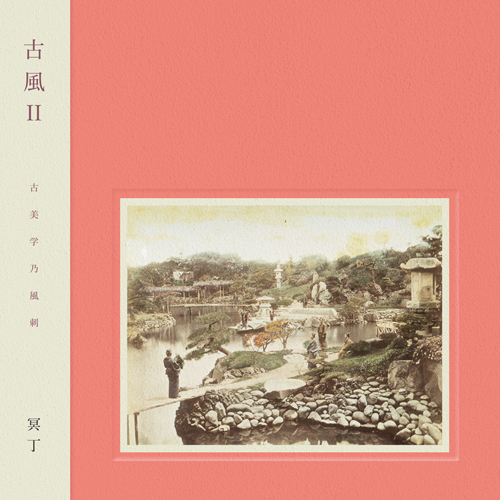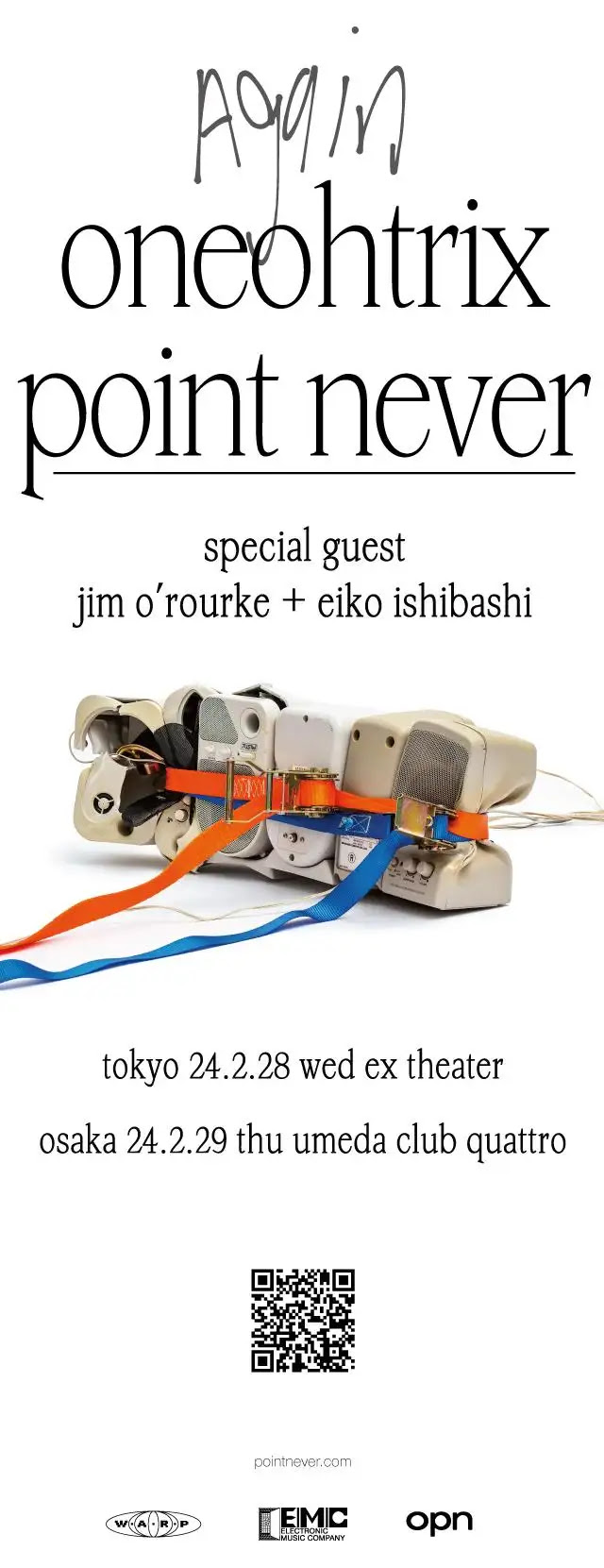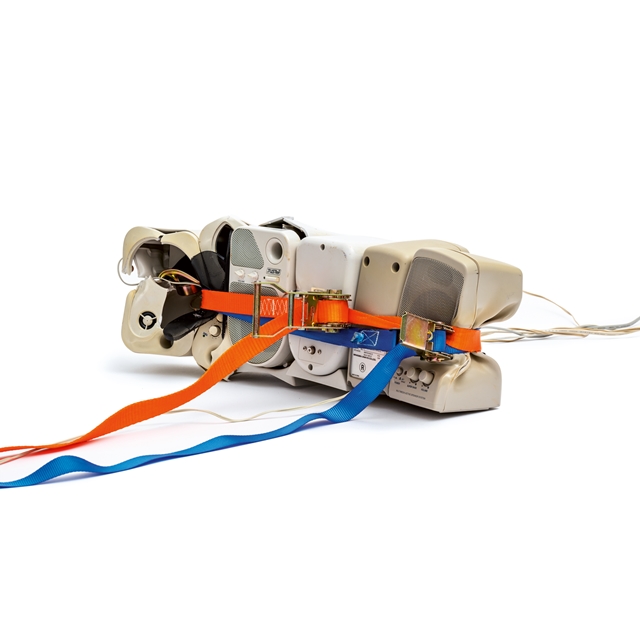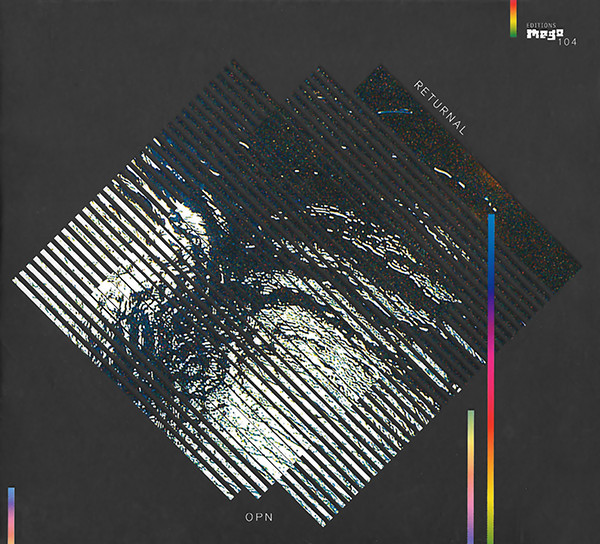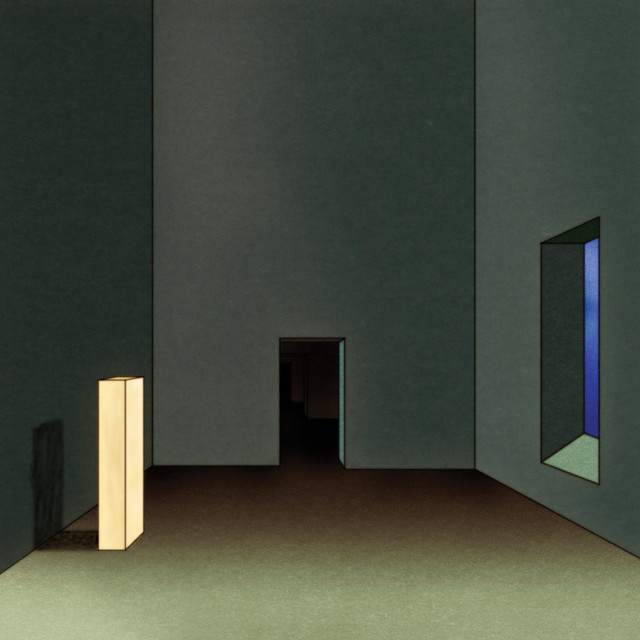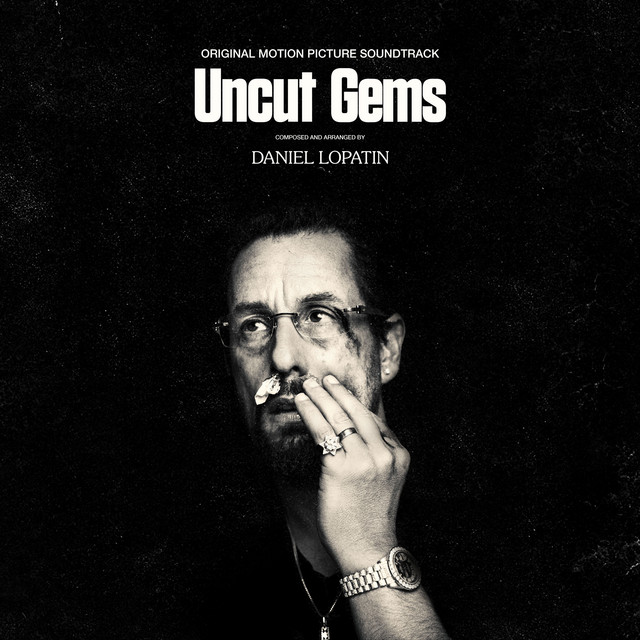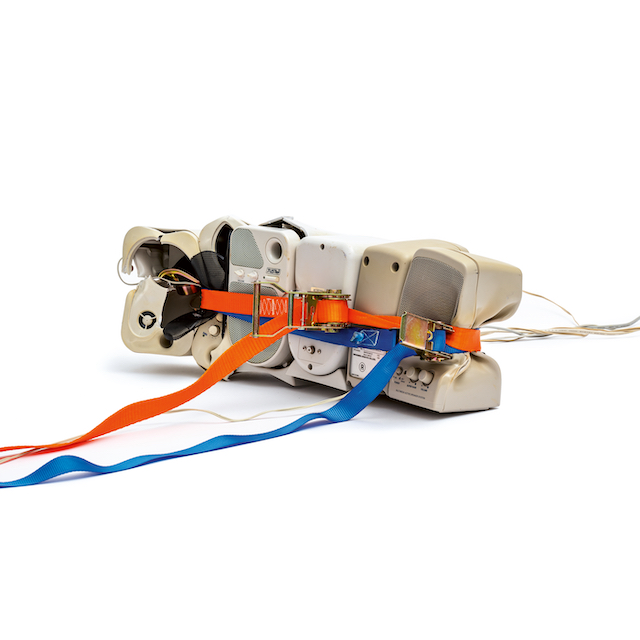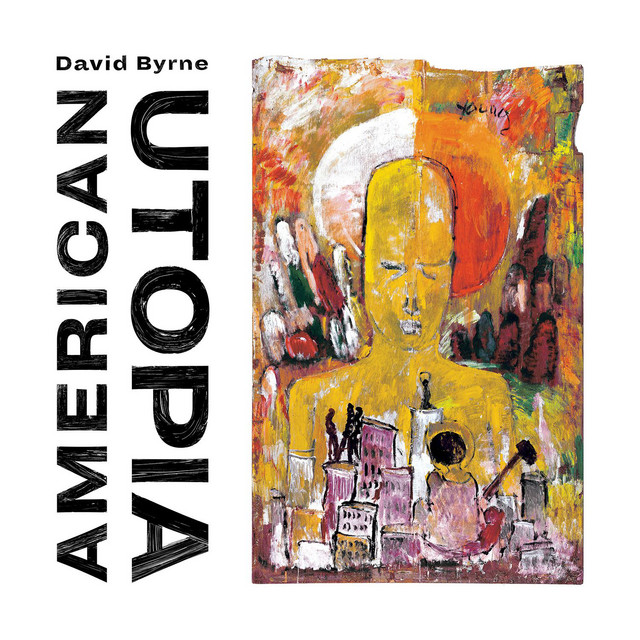ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの来日までいよいよ1か月。ジム・オルーク&石橋英子の出演も楽しみな公演ですが、ここへ来てさらに嬉しいお知らせです。最新作『Again』がカセットテープにてリリースされます。フィジカル限定のボーナストラックもあり。これはTOWER VINYL SHIBUYAのリニューアルを記念した企画で、同店(と来日公演会場)のみでしか買えません。この機を逃さないように!
なお紙エレ最新号にはOPNのインタヴューを掲載しています。来日に向け予習しておきましょう。
来日まであと1ヶ月!
最新アルバム『Again』が超限定カセットで登場!
待望のジャパンツアーとTOWER VINYL SHIBUYAリニューアルオープンを記念して
ライブ会場とTOWER VINYL SHIBUYAのみで
数量限定カセットテープの販売決定!

いよいよ来月、最新アルバム『Again』をひっさげた新たなライブセットをここ日本で世界初披露するワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下OPN)。ジャパンツアーには最新アルバムでも客演したジム・オルークが石橋英子と共にスペシャルゲストとして出演することも決定し、コーチェラ出演も発表されるなど話題が続く中、ジャパンツアーとTOWER VINYL SHIBUYAのリニューアルオープンを記念して、最新アルバム『Again』の数量限定カセットテープが、ライブ会場とTOWER VINYL SHIBUYA(タワーレコード渋谷店6F)のみで発売決定! こちらのカセットテープにはフィジカルフォーマット限定のボーナストラック「My Dream Dungeon Makeover」が収録されている。

ONEOHTRIX POINT NEVER『Again』数量限定カセットテープ
※タワーレコードではTOWER VINYL SHIBUYA(渋谷店6F)のみの販売となります。
※予約不可(店頭・電話・ネットからの予約は一切できませんのでご了承下さい)
※販売開始日:2024年2月29日(木)のリニューアルオープン日より
※商品の購入はお一人様1個までとさせて頂きます。
https://tower.jp/article/news/2024/01/29/ta001
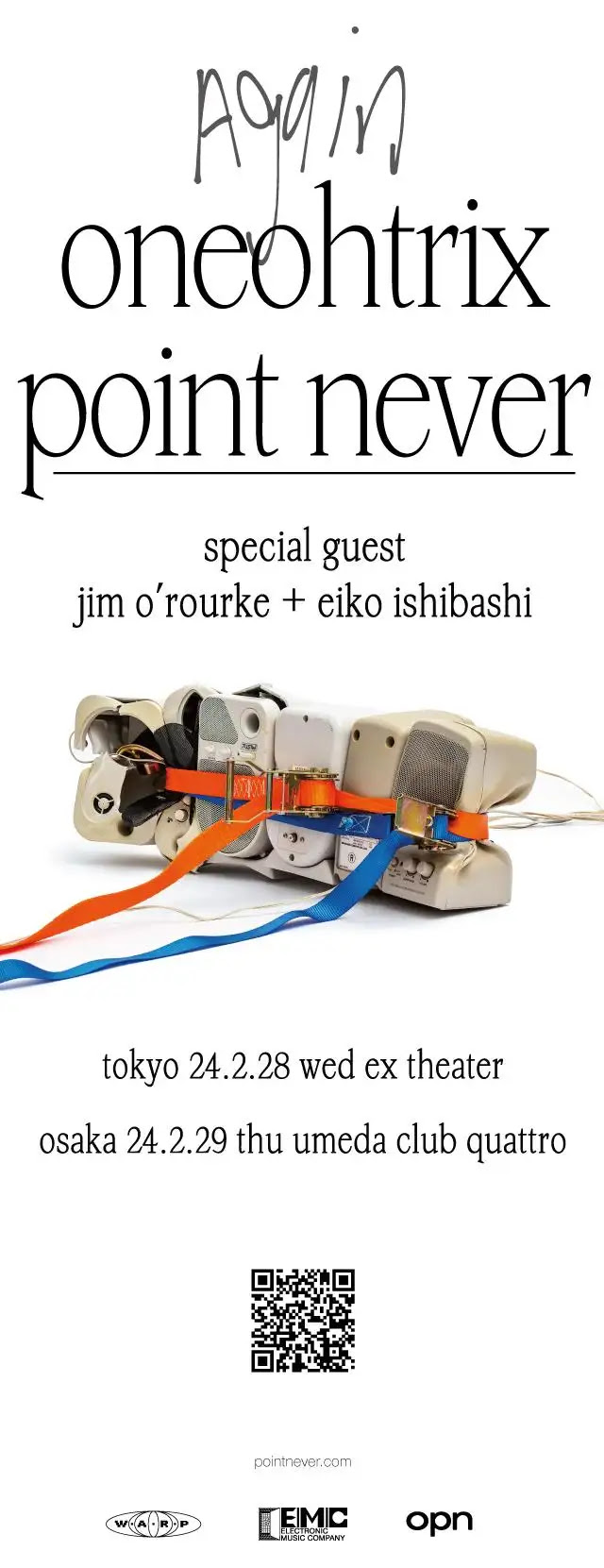
ONEOHTRIX POINT NEVER
special guest: JIM O'ROURKE + EIKO ISHIBASHI
[東京]
公演日:2024年2月28日(水)
会場:EX THEATER
OPEN:18:00 / START:19:00
TICKET:前売 1階スタンディング¥8,000(税込) / 2階指定席¥8,000(税込)
※別途1ドリンク代 ※未就学児童入場不可
INFO:BEATINK www.beatink.com / E-mail: info@beatink.com
[Tickets]
● イープラス [https://eplus.jp/opn2024/]
● ローソンチケット [http://l-tike.com/opn/]
● BEATINK (ZAIKO) [https://beatink.zaiko.io/e/opn2024tokyo]
[大阪]
公演日:2024年2月29日(木)
会場:梅田CLUB QUATTRO
OPEN:18:00 / START:19:00
チケット料金:前売¥8,000(税込)(オールスタンディング)
※別途1ドリンク代 ※未就学児童入場不可
INFO:SMASH WEST https://smash-jpn.com
[Tickets]
● イープラス [https://eplus.jp/opn2024/]
● ローソンチケット [http://l-tike.com/opn/]
● ぴあ 【Pコード】254-196
● BEATINK (ZAIKO) [https://beatink.zaiko.io/e/opn2024osaka]
公演詳細 >>> https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13709
企画・制作 BEATINK www.beatink.com
INFO BEATINK www.beatink.com / E-mail: info@beatink.com
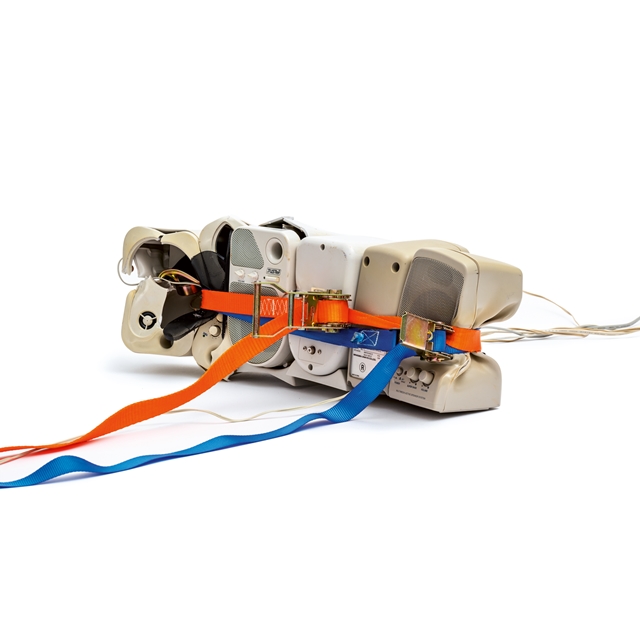
label: Warp Records / Beat Records
artist: Oneohtrix Point Never (ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー)
title: Again (アゲイン)
release: 2023.9.29 (FRI)
商品ページ:
https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13613
Tracklist:
01. Elseware
02. Again
03. World Outside
04. Krumville
05. Locrian Midwest
06. Plastic Antique
07. Gray Subviolet
08. The Body Trail
09. Nightmare Paint
10. Memories Of Music
11. On An Axis
12. Ubiquity Road
13. A Barely Lit Path
14. My Dream Dungeon Makeover (Bonus Track)
国内盤CD+Tシャツ

限定盤LP+Tシャツ

通常盤LP

限定盤LP