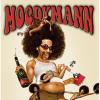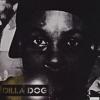MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Andres- II
アンドレス――この名義ではムーディーマンの〈KDJ〉からデビューして2003年には最初のアルバムを発表(あるいは3チェアーズやセオ・パリッシュ作品への参加、ムーズ&グルーヴスからのリリース)、そしてDJデズの名義ではUR傘下の〈ヒプノテック〉からのリリースやスラム・ヴィレッジへの参加などなど、地味ながらキーパーソンたちとしっかり仕事をしているのがアンドレスで――なにせジェイ・ディラからケニー・ディクソン・ジュニア、マイク・バンクスまでなのだから――彼のセカンド・アルバム『II』は、そうした彼の見事な活動領域が鮮やかな形で表出した、まったく素晴らしい作品となった。ハウス、テクノ、ヒップホップ、あるいはジャズやソウル、あるいはアフロやラテン、それらがミックスされたアンダーグラウンド・ブラック・ダンス・ミュージックにおける蜂蜜のようなアルバムである。
ブラック・ミュージック特有の、都会で暮らす人間の日々の感覚とエモーション――温かい午後の会話から孤独な夜の空しさ、街への愛憎、夢と生活、家族と恋人、人生の歓喜と絶望、それらのデリケートな起伏......そういったものから生まれる音を好む耳とハートを持っている人は、この音楽に逆らえないだろう。アメリカにおける過酷な格差社会と日本の殺伐としたそれとはまた趣が違っているように思うのだけれど、持たざる者による美学という言い方がもし許されるなら、僕はこの音楽にそれを見る。僕はいまでもこういう音楽を聴いているといろんなことを思い出すことができるのだ。貧困ではあるがなんとか互いに助け合おうとして成り立っている社会(コミュニティ)というもののことを。
喋るだけ、ないしは喋って踊るだけ(まったくラップとダンス)。夕暮れになると家の玄関先の階段にみんな出てきて、子供や母親や老人たちは喋っているだけなのだ。そこに男がいるとしたら職のない男で、冷やかされながら笑っているだけで、それはモダニズムの名残であるとかポスト・フォーディズムの犠牲者とかそんなものではなく、僕は彼らの精神構造のなかに何かそうした経済的な逆境のなかでも笑っていられる"逞しいゆとり"のようなものを感じ取ってきたのだ。日本で言うところの"ゆるい"という言葉とは違った、もっと深いところの"ゆるさ"。それを強いて意訳するなら、「私たちはたまたま仕方なく、諸事情があって、こうして資本主義とつき合ってやっているだけなのだ」という感覚のようにも思える。それがディアスポラってものだろう。
田中宗一郎によれば『SNOOZER』のコンセプトは「こんがらがった少年少女のため」だそうだが、ブラック・ミュージックは娘も父親も一緒に聴く音楽だ。スタイルがいくら変わっても"変わってゆく同じもの"がそこにはある。"同じもの"とは言うもまでもなく、マイケル・ジャクソンにもケニー・ディクソン・ジュニアにもフライング・ロータスにも偏在するものである。アフリカ・バンバータがパパとママのレコード棚から音楽を作ったことは、決して偶然ではない。だいたい......ラジオからスラム・ヴィレッジの"テインティッド"が流れると、オヤジも子供もみんな歌い出すあの瞬間に居合わせてしまうと......。話がどんどん大きくなりそうなので、このあたりで止めておこう。アンドレスの音楽には自分が経験してきたデトロイトの最良の部分が凝縮されている。
アルバムはアフリカン・パーカッションで幕を開ける。2曲目は素晴らしいベースラインを持つファンキーなハウス(キーボードはアンプ・フィドラーの)、そしてドープでソウフルなダウンテンポへと展開。4曲目のディープ・ハウスではケニー・ディクソン・ジュニアが煙を吸い込んだ声をナメクジのような絡みを加える。女性DJであるミンクスのターンテーブルさばきを挟んで6曲目以降は甘美なブラック・ソウルの時間がはじまる。スキットがあり、DJデズ(アンドレス)がその素晴らしいスクラッチのスキルを披露する曲もある。ラッパーも登場する。エレクトロもアフロもラテンも、ぜんぶある。なにせCDには30曲が収録されている。長くて4分、だいたい1分から2分、だから細切れに、歯切れ良くアルバムは展開する。
アンダーグラウンドな"大衆音楽"――まるでデトロイトのラジオ番組を聴いているようだ。気分が良い。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE