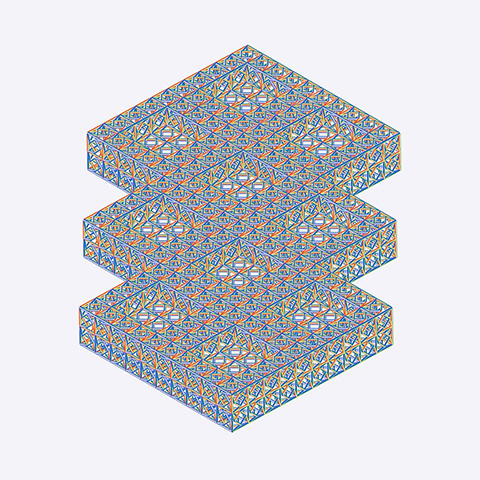MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Sugai Ken- UkabazUmorezU (不浮不埋)
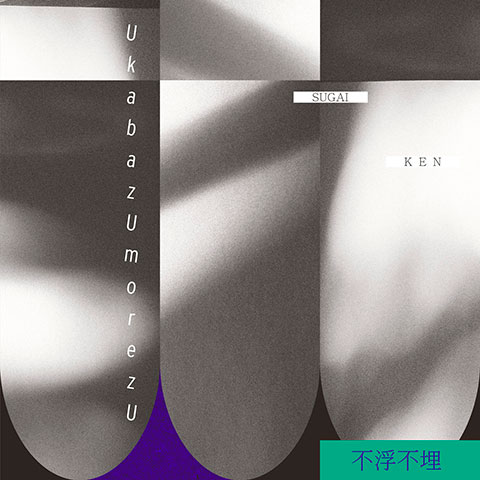
電子音楽家スガイ・ケンの新作はシネマティックなムードを漂わすアンビエント/コンクレートの傑作であった。「シネマティック=映画的なアンビエント」とは何か。それは音楽/音響が、映画のサウンドをイメージさせるかのように「非同期的」(坂本龍一『アシンク(async)』)に構成された音響作品を意味する。「世界」の「豊穣さ」の音響・音楽表現でもある。
『不浮不埋』おいても音楽、環境音、微細なノイズなどが非連続的に構成され、肉体的に慣習づけられた反復的なグル―ヴを解体するようにサウンドのエレメント(それは日本的であり、ミニチュアール/神的なものだ)が非反復的に編集・接続される。音による「光景」が生まれているのだ。
1曲め“湧き祕”で滴り打ち落とされる水滴の音に導かれるようにはじまる2曲め“をちかえりと渦女”を聴けばわかるが、スティーヴ・ライヒ的なミニマリズム(反復性)は解体され、「和的」な具体音が非反復的/ステレオフォニックにコンポジションされている。やがてそれは時計の音へと変貌する。光景は消えて、時間だけが残る。そして、森の中の鳥の声と、その場所の音と、時計の針の音のような音が重なる3曲め“時鳥”への転換も、時間の経過を描写することで、映像作品のシークエンス転換のように耳の遠近法を変えてしまう。続く「「滝宮の念仏踊り」という郷土芸能から着想を得ている」と語る4曲め“桶楽”では、走るような足音と心の芯に響くようなドローン、微かな環境音などが非反復的/非同期的に連鎖し接続され、このアルバムのムードを聴き手の耳に浸透させる。
2016年にオランダの〈ララバイ・フォー・インソムニアック(Lullabies For Insomniacs)〉からリリースされた『鯰上』でも追及されてきた緻密なコンポジションが、〈Rvng Intl.〉から送り出された『不浮不埋』ではより「深い」領域で表現されているように感じた。「深い」とは、スガイ・ケンは日本の伝統的な音楽や風習などをフィールドワークしつつ自身の曲を創作しているのだが、まずもって「音」と「世界」の方が先にあるのではないかと感じられたからだ。
「音」が先にあること。「音と世界」を聴くこと。そのような世界=音への意識・態度が『不浮不埋』のシネマティックな音響空間の生成・構成に大きな影響を与えているように思えてならない。それゆえにスガイ・ケンの音楽は豊穣なのではないか、とも。
ちなみに同じく〈Rvng Intl.〉からリリースされたヴィジブル・クロークス『ルアッサンブラージュ(Reassemblage)』も同様の響きと非連続性を感じた。『ルアッサンブラージュ』は80年代の日本産アンビエント/ニューエイジ・ミュージックという宝石を再発見し、それを現代的にコンクレートするアルバムであり、「ニューエイジ再評価の現代的アンビエント・サウンド」を象徴する傑作であった。むろん『ルアッサンブラージュ』とスガイ・ケンの『不浮不埋』では参照点や音楽のタイプは違うが、2作とも過去=未知の音への調査と探求を経たうえで、非連続的(非反復的)なアンビエントに解体/再構成する音楽作品という点では共通点がある。その意味で2017年の〈Rvng Intl.〉のキュレーションは同時代の潮流をとらえていた。
私はスガイ・ケンの音楽を聴くと、ふと映画作家のジャン=リュック・ゴダールのソニマージュ実践や実験音楽家/美術家のクリスチャン・マークレーのターンテーブル・コラージュ作品を思う。コンポジションとエディットが同列に存在しているからだ。スガイ・ケンの楽曲には、どこか「作曲」という意識だけではなく、一種の音と記憶の「トラックメイク」を行っているという意志を強く感じるのである。音の接続による記憶の再構成とでもいうべきもの……。
日本盤をリリースしているレーベル〈メルティング・ボット(melting bot)〉のサイトに、スガイ・ケン自身によるセルフ・ライナーノーツ的なテキストが掲載されているが、これを読むと彼が日本の伝統音楽を調査し体感していく過程で観た/聴いた/体験した「光景」を自身の音楽にフィードバックしていくさまが語られている。なかでも「京都の山中にある月輪寺を訪れた際、道中の林道がとても印象的な光景であった」ため、それをもとに制作された7曲め“堂尻”は、光景的かつ記憶的で、彼の音楽の本質を照らしているように思えた。
調査と体験。体感と記憶。記憶と解体。解体から生成。彼は記憶と体験から「音の光景」を編集するように音楽を生成・構成する。そして、その「音=光景」の果てには「冥界」のイメージを強く感じる。「柳女のイメージ」で制作されたという10曲め“障り柳”に耳を澄ますと、現実の時間空間意識が消失し、冥界の淵に立っているような気分になるのだ。日本のさまざまな伝統音楽(のエレメント)が、21世紀の「耳」を通じて、新しいアンビエントとして生まれ変わったのである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE