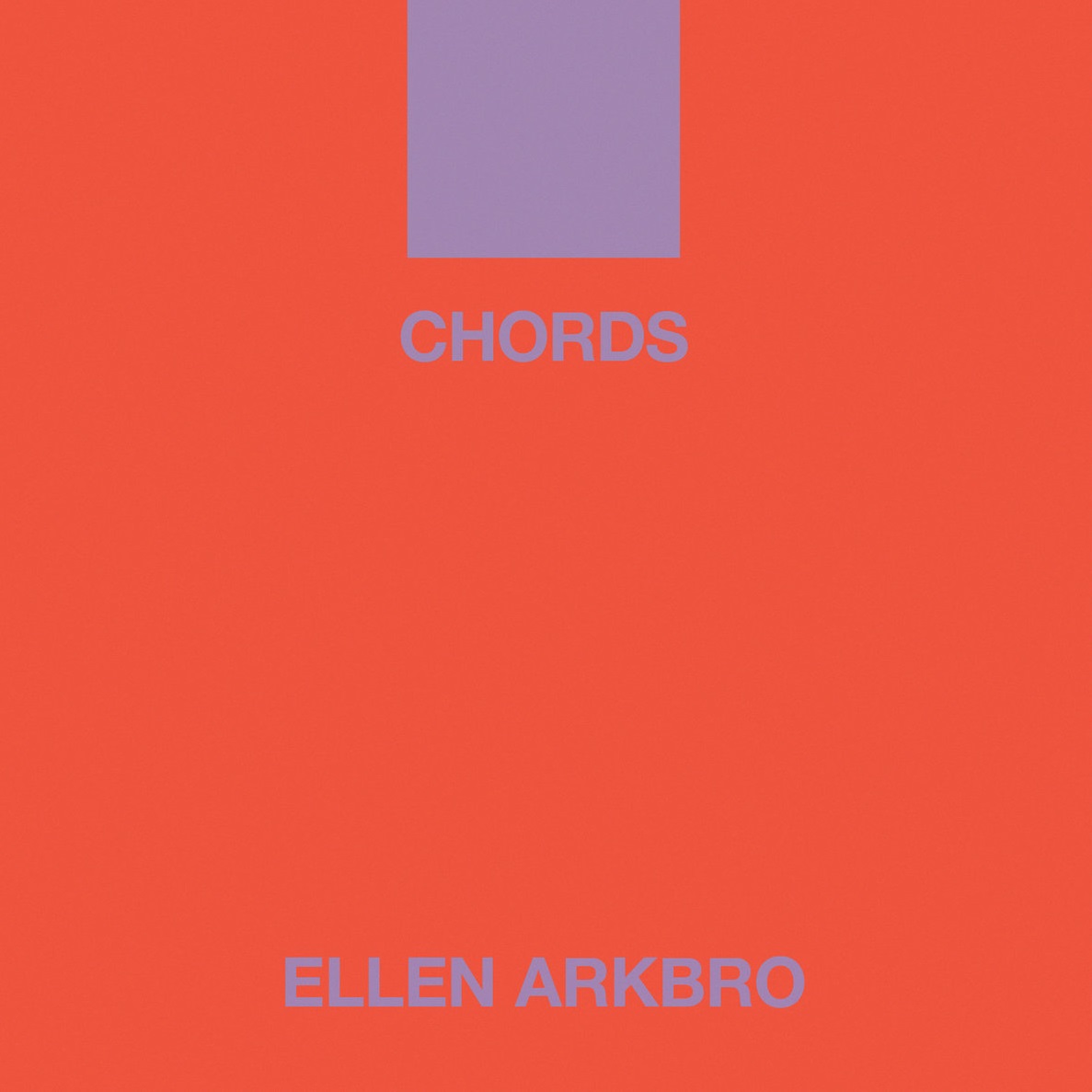MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ellen Arkbro & Johan Graden- I get along without you very wel…

レベッカ・ゲイツの『Ruby Series』を覚えている方はいるだろうか。2001年にリリースされた『Ruby Series』は、トータスのジョン・マッケンタイアのプロデュース・録音のもと、ザ・シー・アンド・ケイクのメンバーが参加したことで知られる静謐で清潔な印象のSSWアルバムである。
『Ruby Series』に限らずだが、90年代末期~00年代初頭に、「シカゴ音響派」の音楽家たちがヴォーカル・アルバムを手掛けていく潮流があった。なかでも一際深く印象に残ったのが、『Ruby Series』であったのだ。透明な歌声と簡素だが繊細でミニマルな演奏/編曲にとても惹きつけられたことを覚えている。
そして2022年。〈Thrill Jockey〉からリリースされた『I get along without you very well』を聴いたとき脳裏に浮かんだのが『Ruby Series』だった。なんというか、極めて曖昧にだが、かつての(後期)「シカゴ音響派」との近似性を強く(勝手に)感じてしまったのである。洗練されたミニマリズムな演奏と歌声のアンサンブルの妙ゆえだろうか。何より実験とポップの領域が溶けていくような風通しの良さが気持ちよかった。
スウェーデン・ストックホルム出身のサウンド・アーティスト/パフォーマーでもあるエレン・アークブロは、〈Subtext〉からリリースされた硬派なドローン・アルバム『For Organ And Brass』(2017)、『Chords』(2019)などでエクスペリメンタル・ミュージック・マニアから知られていた音楽家だが、『I get along without you very well』では楽器演奏はもとより、アークブロはその美しい歌声を披露している。
そしてこの作品にはコラボレーターがいる。スウェーデンのマルチインストゥルメンタリスト、ヨハン・グレイデンである。1991年生まれの彼はどちらかといえばオーセンティックなジャズの領域で活動しているようだが、彼の技巧的な演奏や編曲は、アークブロのクラシカルで実験性と非常に良い対称性を描いていて、素晴らしいコラボレーションだと思う。
彼と共に作り上げた本作は、アーティストとプロデューサーという関係ではないのだろう。アークブロとグレイデンはおそらく対等の立場で曲を作りあげているのだ。ふたりは作曲・編曲のみならずミックスも手がけている。まさに協働作業といえよう。
じっさい一聴してみると分かるが、『I get along without you very well』は、アークブロの滋味に満ちた歌声を聴くことができる「うたもの」としての魅力に加えて、音と音のタペストリーのような演奏と編曲による豊穣な音世界を展開している。
声と音。声と楽器。それらが溶け合っていくことで、慎ましやかで、繊細な音楽が立ち現れる。そのアンサンブルの構築に、グレイデンの技巧的な編曲の構築が非常に重要だったのではないか。聴き込んでいくとわかってくるが、楽器と楽器の層によって生まれる音響には、どこか鳴っていないドローンがうっすらと響いているような錯覚をしてしまう。アークブロは「うたもの」である本作に、そのような鳴っていない「ドローン」の存在を紛れ込ませたのではないか。そんな妄想さえ抱くほどに、このアルバムの演奏/編曲は洗練されている。じじつ、収録されている楽曲は、静謐な響きを持続させながら、静かに、しかし緊張感を持って持続する曲ばかりである。
アークブロの「声」という意味では2015年にリリースされた Hästköttskandalen『Spacegirls』を思い出すマニアの方も多いだろう。いまや人気ドローン作家のひとりでもあるカリ・マローンらとのユニットである Hästköttskandalen は、『I get along without you very well』以前にアークブロの声を記録した貴重なアルバムともいえる。
もちろん『I get along without you very well』の方がよりヴォーカリストとして成長(?)している。少なくとも彼女の声が楽曲の重要な部分を占めているし、ある意味、アルバムに収録された曲の要ともいえるのだから。
全8曲収録されているが、個人的にはアルバムの最初のハイライトは3曲目 “All in bloom” と4曲目 “Never near” だ。特に “All in bloom” に静かにレイヤーされていく管楽器の響き/持続には、どこかジム・オルークの『ユリイカ』を思い出してしまった。この曲だけではないが聴き込むほどに細かな仕掛けやアレンジ、サウンドの妙に気がついくる。たとえばザ・ビーチ・ボーイズ/ブライアン・ウィルソン『ペット・サウンズ』からの引用(ある曲のベースラインだが)にも気が付くだろう。ポップ・ミュージックの歴史への意識(参照)も忘れていない点に、90年代のシカゴ音響派的な歴史意識も強く感じることができた。
ともあれ、このアルバムは素晴らしい。何回でも聴きたくなるし、特に疲れ切った日の深夜に聴くと(耳を傾けると、というべきかもしれない)、本当に心身に染み込む。卓抜だが慎ましやかな演奏が音の層を生み出し、そこにアークブロの素朴にして美しい歌声のアンサンブルが大きな波を描くように響く。聴き手はただその波に身を委ね、音楽の直中を浮遊するように漂っていけばいいだけだ。なんて「贅沢」な音楽体験だろうか。まさにタイムレスなアルバムである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE