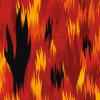MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Bright Eyes- Down in the Weeds, Where the Wor…

アメリカにおいてフォーク(・ロック)が何かしらの説得力を増しているのではないかと感じているのはこの数年のことで、去年辺りからそれが確信に変わりつつある。ひとつにはビッグ・シーフがサウンド的にもコンセプト的にも目を見張るような作品をリリースしメディアに絶賛されたというのもあるし、ひとつにはビル・キャラハンやマウント・イアリのようなヴェテランが力作を発表し若い世代に発見されているということもある。もちろんボン・イヴェールがコミュニティ・ミュージックとしてのフォークを再定義しようとしているのもあるし……さらに大きなところで言っても、ボブ・ディランの17分を超えるシングル、それに久々のオリジナル作がアメリカを激しく問うものであったこともある。あるいはまた、テイラー・スウィフトのようなゴシップと戯れてきたメガ・ポップ・スターがそれこそボン・イヴェール一派の力を借りつつ『Folklore (伝承歌)』というタイトルの、アメリカの人びとの記憶を巡るフォーク・アルバムを制作する事態まで起きている。
それは2016年からの重い問いになっている、「では、そもそもアメリカの民主主義とは何だったのか?」というテーマともリンクしているだろうし、権力と対峙するときの「人びと」のコーラスがいまどれほどの力を持ちうるかの試みでもあるだろう。あるいはまた、個と公がどのような関係を描くのかという問い直しであるだろうし……結局、混乱する時代にあってわたしたちは何度でもそこに立ち返るしかない。
そんななかでいま急速に再注目と再評価を集めているのがコナー・オバースト率いるブライト・アイズである(それと、ボニー・“プリンス”・ビリーも。ウィル・オールダムは『ア・ゴースト・ストーリー』のような若い世代の心を捉えたインディ映画に俳優として出演するなどして、インディ・キッズたちの間でクールなアウトサイダーとして人気を高めている)。ブライト・アイズといえば、多くのひとが思い出すのは音楽的なテンションがピークに達していた『LIFTED or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground』(2002)~『I’m Wide Awake, It’s Morning』(2005)の頃だろう。同時期にはブッシュ政権の傲慢を激しく糾弾したシングルにしてプロテスト・ソング「When the President Talks to God (大統領が神に話すとき)」もある。自分の混乱や不安定さを隠さないままこの社会の不条理を訴えるオバーストの姿を見て、人びとは彼を「若きディラン」と呼んだ。それももう15年前のことだ。
それからブライト・アイズは2010年代頭に向けて批評的にじょじょに失速していく。いま思えば、彼が受けた世の過剰な期待に対応しきれず、ややスピリチュアルな方向に進んだのと関係しているのかもしれない。ライターとしてデビューしたばかりの頃の自分が書いた『The People’s Key』(2011)の拙いレヴューを読み返してみると、はっきりと落胆が記されており、まあ拙いながらも当時の自分の正直な気持ちだったのだろうと思う。ブッシュ時代からオバマ時代へと至り、オバーストは何を歌うべきか、彼自身もリスナーも見失いつつあったのかもしれない。そのことを表すように、『The People’s Key』はフォーク・ロック・アルバムではなかった。
しかしブライト・アイズとしての作品が長く途絶えている間に、次の世代がその存在を参照しはじめる。そこでキーワードになったのがエモだ。リル・ピープやマック・ミラーのようなエモ・ラップがカヴァーやサンプリングで精神性の拠り所にし、また、エモからの影響を公言する新世代のインディ・ロック・スターであるフィービー・ブリジャーズとオバーストのフォーク・ロック・ユニットであるベター・オブリヴィオン・コミュニティ・センターが結成されるなんてこともあった。ビッグ・シーフは自分たちがかつて所属した〈サドル・クリーク〉を「ブライト・アイズがいたレーベル」として認識していたという。初~中期のブライト・アイズにおける思春期性を帯びたエモーショナルさがときを経て、メンタル・ヘルスの問題が取り沙汰される世代に発見されるのは自然な流れだったのかもしれない。時代の混迷とともに、彼の震える声が再び求められたのだ。そして、ブライト・アイズとして9年ぶりのアルバムがリリースされた。
フォークというにはやや作りこまれたロック・アルバムだが、『The People’s Key』よりはるかにフォーク/カントリーが戻ってきているのは間違いない。メンバーであるマイク・モギスとナサニエル・ウォルコットと再び集い、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーやマーズ・ヴォルタのジョン・セオドアのような名プレイヤーの参加もあり、かなり厚みのあるバンド・サウンドとなっている。なかでもウォルコットが手がけたオーケストラはリッチかつドラマティックなもので、初期を思えばずいぶんしっかりしたなと思わせるところがある。骨格としては正統にフォーク・ロック的な “Dance and Sing” の後半でほとんど仰々しく入ってくるストリングス、“Mariana Trench” においてジョン・セオドアの激しいドラミングのなかで縦横に飛び交うブラス、ビターなピアノ・バラッド “Pan and Broom” でよく歌うバグパイプなどを聴いていると、アレンジメントのゴージャスさで聴かせる作品なのだと感じられる。とても力強い。
それでもその中心にあるコナー・オバーストの声と歌、それはいまでも不安を抱えたままで揺らぎ、震えている。このアルバムはオバーストの元妻のスポークン・ワードで幕を開けるのだが、そんな風に人生の様々な経験を経て40代となったいまも消えることのない自身の不安定さがここにはある。そしてオバーストの視線はまた社会や資本主義の欺瞞や不条理に向かっており、しかしそれに対して太刀打ちできない自分自身の弱さや無力感が綴られている。もう彼は「フォークの若き旗手」などではないが、中年になってなお、この世に生きることの過酷さを前に膝を抱える自分を隠そうとしていない。もちろん15年間に比べると歌い方も詞作もぐっと成熟しているし、彼もやはり年を重ねているのだと気づかされる。けれど、清潔な音でピアノが響くバラッド “Hot Car in the Sun” のなかで、「ベイビー、だいじょうぶだよ。愛している」とか弱い声で歌う頼りなさこそオバーストであり、ブライト・アイズなのだ……と思ってしまう。あるいは自分がそんな瞬間を探そうとしているだけなのかもしれないが。
僕はいまでも『LIFTED』のラスト、“Let’s Not Shit Ourselves (To Love and to Be Loved)” で「僕にはブルーズがある! 僕にはブルーズがある! それが僕!!」と絶叫する彼の危うさを耳にすると視界がぼやけてしまうし、自分が過去に持っていたのかもしれない感じやすさを掘り起こされる気分になる。『Down in the Weeds, Where the World Once Was』のクロージング・ナンバーである “Comet Song” は、それを思うとずいぶんコントロールされて安定したアンサンブルが聴けるが、じょじょに壮大になっていくオーケストラのなかで懸命に歌うオバーストの迫力に耳を奪われる。それは彼がいまも等身大の自分自身でこの世界に対峙していることの証だ。このアルバムにあるバンド・サウンドの逞しさとオバーストの不安を滲ませる歌の対比は、個と公の間にある戸惑いのなかで何かを見失いそうな、社会の巨大さや残酷さを前にしたときのちっぽけな自分を、それでも奮い立たせてくれる。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE