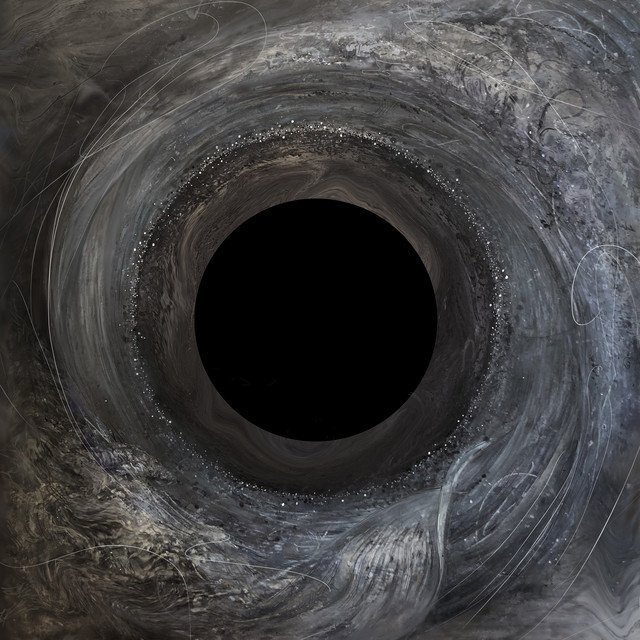MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > PSG- David
東京・板橋区を結成地とするヒップホップ・グループ、PSGのデビュー・アルバム『David』はコミカルなサイエンス・フィクションによる、写実主義、リアリズムへの大いなる挑戦である。PSGの個性は、いまや(とくにこの国では)ヒップホップの至上命題とされているリアリズムを徹底的に突き放している点にある。「全員注目。何者かはわからないが、あの物体は確実に地球を目指して進んでおる」。1曲目"Hello David (Intro)"は、子どもたちによる鼓笛隊の間の抜けた演奏をバックにサンプリングされたこんな言葉からはじまる。また、USサウスのミニマル・ビートと宇宙と交信するようなスペーシーなプロダクションを融合した"きゃつら"にはこんな言葉がサンプリングされている。「ちっとばかし現実社会に飽き飽きしてるんでね」。ラッパー/トラックメイカーで、本作の主要人物のひとりのパンピーは、「地球制服のためにまずは近所のお友だちにお菓子売ってハスラー」とラップする。とくに00年代なかば以降、若い都市生活者の切実なストリート・リアリティとして多くのラッパーがトピックに取り上げてきたハスリング(=ドラッグ・ディール)を、人を食ったような、ナンセンスなリリックで相対化してみせる。こうしたユーモアに彼らの挑戦的な態度が表れている。
PSGの結成は2007年。メンバーはパンピー、彼の実弟スラック(ラッパー/トラックメイカー)、そしてガッパー(ラッパー)といった20代前半の青年たち。ちなみにその前年にパンピーは、MSCが所属するヒップホップ・レーベル〈LIBRA〉主催のフリースタイル・バトル〈ULTIMATE MC BATTLE 〉東京予選で、ハードコア・スタイルのラッパーを頓知の効いたライムで次々に破って優勝している。また2009年に入ってスラックは『My Space』『WHALABOUT』といったオリジナリティ溢れる傑作を発表している。PSGの『David』は、新しい世代の到来を決定付ける作品の1枚だと言える。
多くのハードコア・ラップは、主流社会との距離感、それらに対する嘆きを滲ませることでオリジナリティを獲得する。社会に裏切られたという感覚は音楽化され、あり得たかもしれない幸福な未来、そして暴力とカネに悩まされながらハード・ライフを送るしかない現在という二重性が、ラップのリアリズムに深い陰影を与える。その点、PSGは醒めている。不穏なシンセ音が鳴り響くフューチャリスティックな(ネプチューンズやクリプスからの影響を伺わせる)"M.O.S.I"では、もし金が手に入ったなら、もし夢が叶ったなら、という根拠のない明るい未来を次々に否定し、「申し訳ないけど/元気付ける気はない」(パンピー)と開き直る。
また、孤島となった監獄都市LAを舞台に近未来の管理社会とアウトローの反逆を描くSF映画『エスケープ・フロム・LA』をモチーフにしたであろう"エスケープ from 東京"では、「エスケープ from T・O・K・Y・O」と東京からの脱出をサビでくり返しながら、最後に「てか、無理じゃねぇ」とひっくり返す。アブストラクトなリリックから紡ぎ出されるどこか間の抜けたサイエンス・フィクションは、決してニヒリズムに依拠しているわけではない。むしろP・ファンクを想起させる、痛快なナンセンスと道化的知性を武器に現実を生き抜くしたたかな精神性に支えられている。カラフルなサンプリング・センス、脱力したラップと歌、豊かな諧謔からは、デ・ラ・ソウルの『3 Feet High&Rising』やベックの『Odelay』さえも連想させる。
アフリカ系アメリカンの批評家でミュージシャンのコーネル・ウエストは、ブラック・ミュージックは希望の喪失や意味の不在というニヒリズムの防波堤として機能してきたと語っているが、PSGがヒップホップ、ソウル、ファンク、R&B、レゲエといったブラック・ミュージックのグルーヴから本能的に嗅ぎ取っているのは、(ブラック・コンシャスの生真面目さからは程遠いが)そういう感覚なのだろう。なによりも彼らが、コミカルなサイエンス・フィクションを作り上げることで守りたかったものとは、リアリズムに拘束されることのない音楽的自由だったのだ。そしてそれが2009年、PSGが放つもっとも重要なメッセージのように思える。
二木 信
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE