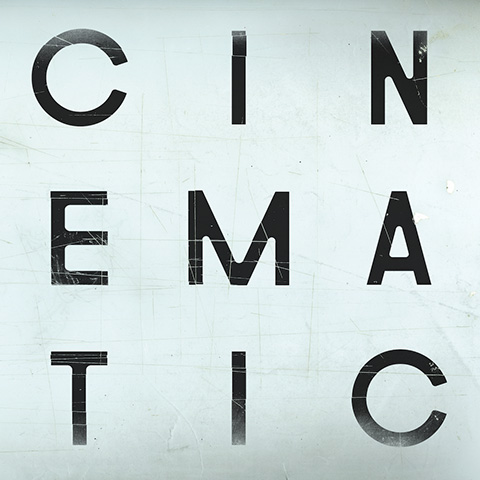MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Dominic J Marshall- Nomad’s Land

現在のUKのジャズではサウス・ロンドン・シーンが注目を集めるが、その中にもいろいろなミュージシャンがいるわけで、すべてをシーンの一言で括ってしまうことはできない。たとえばドミニク・J・マーシャルもロンドンで活動するミュージシャンだが、シャバカ・ハッチングスやモーゼス・ボイドらがいるトゥモローズ・ウォリアーズ周辺のサークルとは異なる出目である。そもそも彼はスコットランドのバンノックバーン出身のピアニスト/キーボード奏者で、2010年にリーズ音楽大学を卒業してプロ・ミュージシャンとなってからは、オランダのアムステルダムで始めたドミニク・J・マーシャル・トリオ(DJMトリオ)で活動してきた。このピアノ・トリオはその後ロンドンへと拠点を移すのだが、ジャズとインストゥルメンタル・ヒップホップの中間的なことをやっていて、『ケイヴ・アート』というシリーズ(2014年と2018年にリリース)ではJディラ、MFドゥーム、マッドヴィラン、フライング・ロータス、スラム・ヴィレッジ、9thワンダーなどのヒップホップ・トラックを人力でジャズへ変換した演奏をおこなっている。こうしたスタイルの作品自体は珍しいものでもないが、ジャズの緻密な演奏力とヒップホップ・センスの高さはなかなかのもので、同世代のアーティストではゴーゴー・ペンギンとかバッドバッドナットグッドあたりに比するものを感じさせた。
ドミニクはソロでもいろいろ作品を作ってきて、そちらでもインストのヒップホップ的なことはやっているが、よりビートメイカーに近い作風となっている。2016年リリースのソロ名義作『ザ・トリオリシック』は、現DJMトリオのサム・ガードナーとサム・ヴィカリー、オランダ時代の旧DJMトリオのメンバーであるジェイミー・ピートとグレン・ガッダム・ジュニアも加わったトリオ編成を踏襲する部分もあるが、アコースティック・ピアノだけでなくシンセやいろいろなキーボード、そしてサンプラーやエレクトロニクスまで駆使し、全体としてはビート・ミュージックやエレクトロニカ的な方向性となっている。ロンドンを拠点とするピアニスト兼ビートメイカーではアルファ・ミストが思い浮かぶが、彼に近いセンスを持っているだろう。さらに2018年のソロ・アルバム『コンパッション・フルーツ』では、アナログ・シンセやビート・マシンを軸としたエレクトリック・サウンドの比重が増しており、ジャズとヒップホップの融合という世界からさらに進化し、1980年代的なエレクトロとフュージョンが結びついたシンセ・ウェイヴ~ヴェイパーウェイヴ的な新たな展開も見せていた。
トリオとソロ活動以外でもドミニクの交流範囲は幅広く、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、ベンジャミン・ハーマン、スチュアート・マッカラム、タウィアーらと共演している。スチュアート・マッカラムとの交流がきっかけになったのだろうか、近年はザ・シネマティック・オーケストラでも演奏していて、最新作の『トゥ・ビリーヴ』(2019年)にも参加していた。そして『コンパッション・フルーツ』から2年ぶりの新作ソロ・アルバムとなるのが『ノマズ・ランド』である。『コンパッション・フルーツ』の世界を発展させた作品と言えるだろうが、前回は元DJMトリオのジェイミー・ピートが1曲にフィーチャーされる程度で、ほぼひとりで作り上げたアルバムだったがゆえの一本調子な面も否めなかったけれど、今回はヴォーカリストや楽器プレイヤーなどいろいろな手助けを借りている。メンバーはジェイミー・ピート(ドラムス)のほか、同じく新旧DJMトリオのハンローザことサム・ヴィカリー(ベース)とグレン・ガッダム・ジュニア(ベース)、エレクトリック・ジャラバやフライング・アイベックスなどのロンドンのバンドで活動するナサニエル・キーン(ギター)、アムステルダムの新進R&Bシンガーのノア・ローリン(ヴォーカル)、ドラムンベースのプロデューサーとしても活動するセプタビート(エレクトリック・ドラムス)で、彼らの参加によってオーガニックなサウンドとエレクトリックなサウンドの融合が増え、音楽的にもより広がりと深みを感じさせるものとなっている。
冒頭の “コールドシャワー(Coldshwr)” から驚かされるのだが、今回のアルバムはドミニク自身が全面的にヴォーカルをとっている。ノア・ローリンもデュエットというよりバック・ヴォーカルに近く、あくまでドミニクの歌が主役という感じだ。どのような理由からドミニクが歌を歌うに至ったかはわからないが、サンダーキャットが単なるベース・プレーヤーから脱却して、近年はシンガーとしても新境地を開拓している姿に重なるものだ。“ハーブ・レディ” での歌はヒップホップのラップからネオ・ソウル調へと遷移するもので、トム・ミッシュとかロイル・カーナーなどロンドンのシンガー・ソングライターにも通じる。全体的にはソウルフルな曲であるが、中盤以降はガラっと様相を変えてフライング・ロータスのように幻想的でコズミックな世界となる。ラップ調のヴォーカルをとる “タイム・アンリメンバード” は、シンセウェイヴとビート・ミュージックが融合したような曲。温もりのあるピアノやキーボードがエレクトロなサウンドやビートとうまく一体化していて、最近の作品ではカッサ・オーヴァーオールのアルバムと同じ感触を持つ。“ライオネス” とかもそうだが、ラップ・スタイルの歌が多い点や、自身の生演奏や歌をサンプリングして変化させたりループさせている点もカッサと重なる。
“DMT” はセプタビートのエレクトリック・ドラムスが織りなす有機的なビート上で、ドミニクが美しいピアノ・ソロを展開する。ヴォーカルのテイストも含め、ジャズとソウルとヒップホップの中間的な作品だ。“フィーリング” はウーリッツァー・ピアノがどこかレトロなムードを奏でるインスト主体の曲で、ハービー・ハンコックやチック・コリアなどの1970年代前半のフュージョンにも通じるが、終盤でヴォーカルが入るあたりではロバート・グラスパー・エクスペリメント風にもなる。そして浮遊感に富むコズミック・ソウルの “オン・タイム” や “イニシエーション”、ティーブスやジェイムスズーなど〈ブレインフィーダー〉勢やLAビート・シーンにも繋がるような “ストーリーライン”、ジャズ・ピアニストとしての神髄を見せるスピリチュアルな “ハイパーノーマライズ”。ロバート・グラスパー、フライング・ロータス、カッサ・オーヴァーオールなどいろいろなアーティストからの影響や通じる部分を感じさせるものの、それらを単なる模倣や物真似でなく自身の音楽にまで高め、オリジナルな世界を作り出した非常に密度の濃いアルバムだ。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE