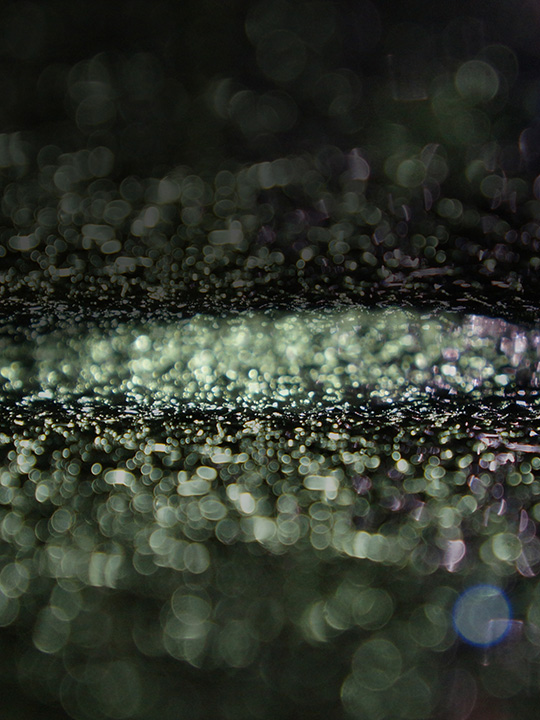6/25に惜しまれながら閉店したアザー・ミュージックは、6/28に最後のインストアライブを行った。バンドは、75ダラービル、リック・オーウェン率いるドローンでジャミングなデュオである。5:30開演だったが、4:30にすでに長い行列が出来ていた。こんな人数が店内に入るのかなとの心配をよそに、時間を少し過ぎて、人はどんどん店の中に誘導されていく。すでにレコード、CDの棚は空っぽ、真ん中に大きな空間が出来ていた。こんながらーんとしたアザー・ミュージックを見るのは初めて。たくさんのテレビカメラやヴィデオが入り、ショーはリック・オーウェンの呼びかけでスタート。デュオではじまり、順々にスー・ガーナーはじめ、たくさんの友だちミュージシャンが参加し、ユニークで心地よいジャムセッションを披露した。たくさんの子供たちも後から後から観客に参加し、前一列は子供たちでいっぱいになった。私は、ジャム・セッションを聴きながら、いろんなアザー・ミュージックでの場面がフラッシュバックし、なきそうになった。インストア・ショーが終わると、彼らはそのままストリートに繰り出し、この後8時から、バワリー・ボールルームで行われる、「アザーミュージック・フォーエヴァー」ショーへ、マタナ・ロバート、75ダラービルなど、この日のショーで演奏するミュージシャンとプラスたくさんのアザー・ミュージックの友だちが、セカンドライン・パレード率い誘導してくれた。アザー・ミュージックの旗を掲げ、サックス、トランペット、ドラム、ギター、ベース、などを演奏しながら、アザー・ミュージックからバワリー・ボールルームまでを練り歩いた。警察の車も、ニコニコしながら見守ってくれていたのが印象的。バワリー・ボールルームの前で、散々演奏したあと、みんなはそのまま会場の中へ。
バワリー会場内もたくさんの人であふれていた。コメディアンのジャネーン・ガロファロがホストを務め、バンドを紹介する(いつの間にか、アザー・ミュージックの共同経営者ジョシュ・マデルに変わっていたのだが)。ジョン・ゾーン、サイキック・イルズ、マタナ・ロバーツ、ビル・カラハン、ヨラ・テンゴ、ヨーコ・オノ、ジュリアナ・バーウィック、シャロン・ヴァン・エッテン、フランキー・コスモス、ヘラド・ネグロ、メネハン・ストリートバンド、ザ・トーレストマン・オン・アースがこの日の出演陣。ドローン、サイケデリック、ジャズ・インプロ、フォーク・ロック、ポップ、ロック、アヴァンギャルド、エレクトロ、インディ・ロック、ファンク、ラテン、ビッグ・バンド、などそれぞれまったくジャンルの違うアーティストを集め、それがとてもアザー・ミュージックらしく、ヘラド・ネグロのボーカルのロバート・カルロスは、「これだけ、さまざまなミュージシャンを集められるなら、アザー・ミュージックでミュージック・フェスティヴァルをやればいいんじゃない」、というアイディアを出していた。オーナーのジョシュが、バンドひとつひとつを思いをこめて紹介していたことや、お客さんへの尊敬も忘れない姿勢がバンドに伝わったのだろう。

Sharon Van etten
サプライズ・ゲストのヨーコ・オノが登場したときは、会場がかなり揺れたが、ヨーコさんのアヴァンギャルドで奇妙なパフォーマンスが、妙にはまっていておかしかった。ヨ・ラ・テンゴとの息もばっちり。個人的に一番好きだったのは、トーレスト・マン・オン・アースとシャロン・ヴァン・エッテン、ふたりとも、個性的な特徴を持ち、いい具合に肩の力が抜け、声が良い。最後に、アザー・ミュージックの昔と今の従業員たちが全員ステージに集合し、最後の別れをオーナーのジョシュとクリスとともに惜しんでいた。スタッフを見ると、なんてバラエティに富んだ人材を揃えていたのか、それがアザー・ミュージックの宝だったんだな、と感心する。スタッフに会いにお店に通っていた人も少なくない(私もその中の一人)。バンド間でかかる曲も、さすがレコード屋、アザー・ミュージックでよく売れたアルバム100枚が発表されたが、その中からの曲がキチンとかかっていた。最後のアクトが終わり、みんなで別れを惜しみながら、写真を取ったり挨拶したり。会場で、最後にかかった曲はコーネリアスの“スター・フルーツ・サーフ・ライダー”だった。21年間、ありがとうアザー・ミュージック。
■Other Musicで売れたアルバム100枚
1. Belle and Sebastian – If You’re Feeling Sinister
2. Air – Moon Safari
3. Boards of Canada – Music Has the Right to Children
4. Kruder and Dorfmeister – K&D Sessions
5. Yo La Tengo – And Then Nothing Turned Itself Inside Out
6. Os Mutantes – Os Mutantes
7. Neutral Milk Hotel – In the Aeroplane Over the Sea
8. Sigur Ros – Agaetis Byrjun
9. Arcade Fire – Funeral
10. Magnetic Fields – 69 Love Songs
11. Belle and Sebastian – Boy with the Arab Strap
12. Cat Power – Moon Pix
13. The Strokes – Is This It
14. Yo La Tengo – I Can Hear the Heart Beating As One
15. Talvin Singh Presents Anokha: Sounds of the Asian Underground
16. Joanna Newsom – Milk-Eyed Mender
17. Interpol – Turn on the Bright Lights
18. Cat Power – Covers Record
19. Cornelius – Fantasma
20. Serge Gainsbourg – Comic Strip
21. Belle and Sebastian – Tigermilk
22. Godspeed You Black Emperor – Lift Your Skinny Fists
23. Amon Tobin – Permutation
24. DJ Shadow – Endtroducing
25. Animal Collective – Sung Tongs
26. Dungen – Ta Det Lugnt
27. Beirut – Gulag Orkestar
28. Belle and Sebastian – Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant
29. Clap Your Hands and Say Yeah – S/T
30. ESG – South Bronx Story
31. Cat Power – You Are Free
32. Broadcast – Noise Made by People
33. The Notwist – Neon Golden
34. Animal Collective – Feels
35. Mum – Finally We Are No One
36. Elliott Smith – Either/Or
37. White Stripes – White Blood Cells
38. Bjorn Olsson – Instrumental Music
39. Boards of Canada – In a Beautiful Place
40. Tortoise – TNT
41. Handsome Boy Modeling School – So How’s Your Girl?
42. Antony and the Johnsons – I Am a Bird Now
43. Zero 7 – Simple Things
44. Broken Social Scene – You Forgot It in People
45. Flaming Lips – Soft Bulletin
46. Devendra Banhart – Rejoicing in the Hands
47. Panda Bear – Person Pitch
48. My Bloody Valentine – Loveless
49. Kiki and Herb – Do You Hear What I Hear?
50. Thievery Corporation – DJ Kicks
51. Boards of Canada – Geogaddi
52. Yeah Yeah Yeahs – S/T EP
53. TV on the Radio – Desperate Youth
54. Yo La Tengo – Sounds of the Sounds of Science
55. Sufjan Stevens – Greetings from Michigan
56. Stereolab – Dots and Loops
57. Tortoise – Millions Now Living Will Never Die
58. Neutral Milk Hotel – On Avery Island
59. Le Tigre – S/T
60. ADULT. – Resuscitation
61. Langley Schools Music Project – Innocence and Despair
62. The Shins – Oh Inverted World
63. Slint – Spiderland
64. Air – Premiers Symptomes
65. Roni Size – New Forms
66. Shuggie Otis – Inspiration Information
67. Nite Jewel – Good Evening
68. Fennesz – Endless Summer
69. Bonnie ‘Prince’ Billy – I See a Darkness
70. Radiohead – Kid A
71. Stereolab – Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night
72. Franz Ferdinand – S/T
73. Amon Tobin – Supermodified
74. Fischerspooner – S/T
75. Stereolab – Emperor Tomato Ketchup
76. Cat Power – What Would the Community Think?
77. Elliott Smith – XO
78. TV on the Radio – Young Liars
79. UNKLE – Psyence Fiction
80. The Clientele – Suburban Light
81. Clinic – Walking with Thee
82. The xx – xx
83. Serge Gainsbourg – Histoire de Melody Nelson
84. Vampire Weekend – S/T
85. J Dilla – Donuts
86. Massive Attack – Mezzanine
87. Joanna Newsom – Ys
88. Sufjan Stevens – Illinoise
89. Portishead – S/T
90. Jim O’Rourke – Eureka
91. Pavement – Terror Twilight
92. Modest Mouse – Lonesome Crowded West
93. Sleater-Kinney – Dig Me Out
94. Tortoise – Standards
95. Sam Prekop – S/T
96. Blonde Redhead – Melody of Certain Damaged Lemons
97. Arthur Russell – Calling Out of Context
98. Aphex Twin – Selected Ambient Works Vol. 2
99. Grizzly Bear – Yellow House
100. Avalanches – Since I Left You
Read More: Other Music’s Top 100 Best-Selling LPs of All Time







 デイヴィッド・シルヴィアン
デイヴィッド・シルヴィアン