先日8年ぶりとなるヘッドライン来日公演を終え、変わらぬ反骨精神を見せつけてくれたオウテカですが、彼らが4月にNTSラジオで披露したロング・セットがCD、ヴァイナル、デジタルの3フォーマットにてリリースされることが決まりました……のですが、ええっと、ちょっと待ってくださいね。彼らのセットは2時間×4日の計8時間あったわけだから……なんと、CDに換算すると8枚組です(絶句)。前々作『Exai』が2枚組の大作で、前作『elseq 1–5』が5枚組相当の超大作で、今回は8枚組……どんどん膨張しております。でもこれ、内容はかなり良いです。これまでのオウテカとこれからのオウテカがみっちり詰まっています。発売日は8月24日。ぼく? もちろん買いますよ。
Autechre.
NTS Sessions.
24 August 2018.

先月6月13日(水)、実に8年振りとなる超待望のヘッドライン公演を行い、平衡感覚すら奪われるような漆黒のライヴ・パフォーマンスで超満員のオーディエンスを沸かせたオウテカから新たなニュースが届けられた。4月、突如始動したオウテカはロンドンのラジオ局「NTS Radio」に4度に渡って出演。DJセットを期待したファンの予想を裏切るように、すべて新曲のみで構成された各日2時間のロング・セットを披露し、リスナーの度肝を抜いた。今回は計8時間にも及ぶその新作『NTS Sessions.』が、CD、アナログ盤、デジタル配信で8月24日(金)にリリースされることが決定! 解説書とデザイナーズ・リパブリックがデザインしたジャケ写ステッカーが封入された国内流通盤は500セット限定となる。
Autechre@恵比寿 LIQUIDROOM ライヴ・レポート
https://www.ele-king.net/review/live/006336/
各種仕様は以下の通り。
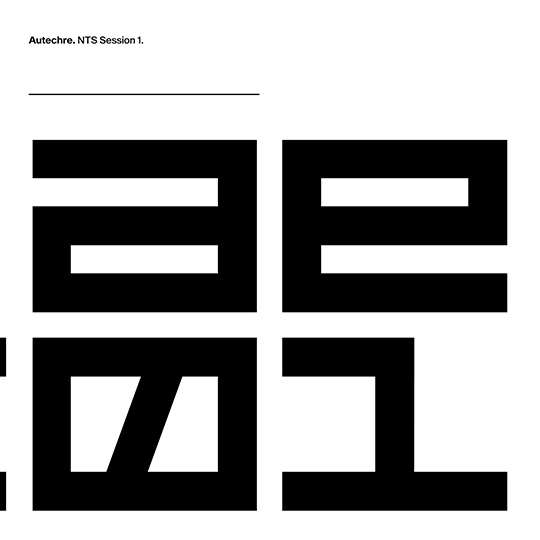
Autechre.
NTS Session 1.
1. t1a1
2. bqbqbq
3. debris_funk
4. I3 ctrl
5. carefree counter dronal
6. north spiral
7. gonk steady one
8. four of seven
9. 32a_reflected
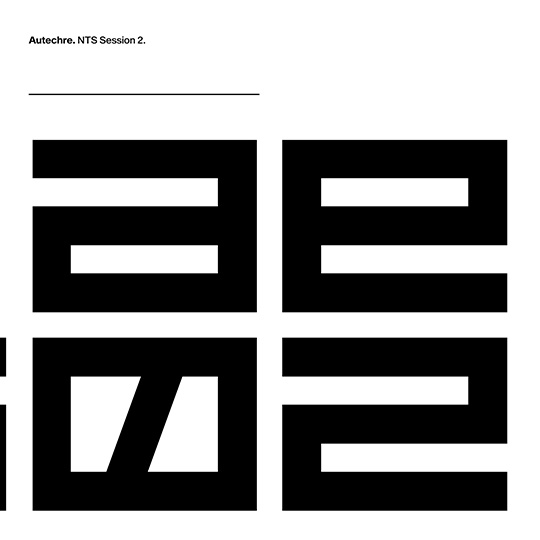
Autechre.
NTS Session 2.
1.elyc9 7hres
2. six of eight (midst)
3. xflood
4. gonk tuf hi
5. dummy casual pt2
6. violvoic
7. sinistrailAB air
8. wetgelis casual interval
9. e0
10.peal MA
11. 9 chr0
12. turbile epic casual, stpl idle
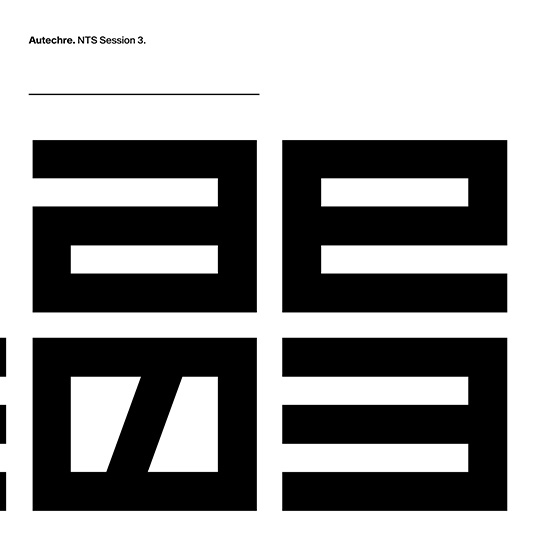
Autechre.
NTS Session 3.
1. clustro casual
2. splesh
3. tt1pd
4. acid mwan idle
5. fLh
6. glos ceramic
7. g 1 e 1
8. nineFly
9. shimripl air
10. icari
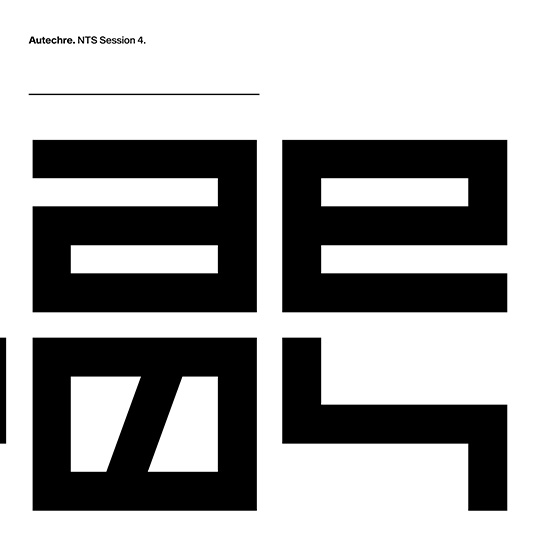
Autechre.
NTS Session 4.
1. frane casual
2. mirrage
3. column thirteen
4. shimripl casual
5. all end
NTS Sessions. LP Complete Box Set.
12枚組LPボックス・セット。特殊ハードケース+インナースリーブ。ダウンロード・カード付。
NTS Sessions. CD Complete Box Set.
8枚組CDボックス・セット。特殊ハードケース+インナースリーブ。500セット限定の国内流通盤には解説書とデザイナーズ・リパブリックがデザインしたジャケ写ステッカーを封入。
NTS Session 1.
NTS Session 2.
NTS Session 3.
NTS Session 4.
3枚組LP。アウタースリーブ+インナースリーブ。ダウンロード・カード付。



