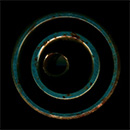あるいはあまりプロモーション展開をしなくとも──名が伏せられ、レコード屋のインディ・コーナーの一隅にひっそりと面出しされているくらいでも、『Hocori』は人々の手に取られるようになるのではないだろうか。ネットレーベル発の才気あふれるプロデューサーやユニット群のひとつとして、あるいは“東京インディ”の新しきピース、と謳われていても違和感がないかもしれない。“Lonely Hearts Club”や“God Vibration Instrumental”などは無名性とともに再生されるとき、もっとも時代性を発揮するように思われる。できることなら期待のデュオの登場だ、その音源がユーチューブで公開されている、とだけ紹介してみたい。そしてどうぞご一聴を。素敵な音楽が聴こえてきます。
“Lonely Hearts Club”Music Video
MONOBRIGHT の桃野陽介(Vo / Gt)とgolf / SLEEPERS FILMで活動する関根卓史のユニット、Hocoriが7月15日(水)にリリースする1st mini album『Hocori』より、リード・トラック「Lonely Hearts Club」のMusic VideoをYouTubeにて解禁した。
このMusic Videoは、Hocoriの持つシティ・ポップやエレクトロ・ポップをベースに置きながらも、ブラックミュージックのスパイスを取り込む作品の方向性にいち早く注目した、NY生まれのファッションマガジン NYLON JAPANのプロデュース及びディレクションによる作品で、モデルの田中シェンと遊屋慎太郎[ユウヤシンタロウ]が起用されている。
田中シェンはモデルとしてNYLON JAPANだけでなく、GINZAや装苑など人気ファッション誌にも多数登場し、「JINS × niko and...」のイメージビジュアルなども務め、Instagramで50,000以上のフォロワーを誇る人気急上昇中のモデル。さらに彼女はイラストレーターとしても注目されており、Music Video内で着用している彼女自身がデザインしたTシャツもNYLON JAPANが手がける作品ならではのポイントだ。また、遊屋慎太郎[ユウヤシンタロウ]もBRUTUSを始めとしたファッション誌やカルチャー誌などでのモデル活動だけでなく、アパレルブランド「sulvam」のコレクションビジュアルにも登場するなど目が離せない。
一目でグイッと引き込む強い視線を持ち、濃厚な空気感を纏う2人のモデルが「Lonely Hearts Club」の楽曲の情景と妄想的要素をNYLON JAPANならではの個性を尊重したスタイルで表現していて、楽曲同様に“新しいセンス”を感じさせる作品となっている。なお、2人のMusic Videoへの出演は本作品が初となる。
さらに、6月にラフォーレ原宿にて行われたポップアップショップや、先日、パリで行われたJAPAN EXPOでも話題となった、新進気鋭のデザイナー 手嶋幸弘氏が手がける「誰かのヒーローになれる服」をコンセプトに展開しているアパレルブランド〈ユキヒーロープロレス〉が今度は大阪・阪急うめだに進出! スペシャルコラボレーションによる限定盤『Tag』[タッグ]も併せてここで発売されることも決定した。これは1st mini album『Hocori』のリリースに先駆けて発表されていた全3曲入りCDで、関根卓史がこの盤のために手がけたオリジナルミックスが収録されていて、収録楽曲の歌詞や世界観からインスピレーションを受けた手嶋幸弘氏がジャケットデザインを手掛けた。遠方のため入手できなかった関西圏の方はMusic Videoを観てからぜひチェックして、それぞれが描き出す世界観を楽しんで欲しい。
■オフィシャルサイト
https://hocori.jp/
Twitter https://twitter.com/info_Hocori(@info_Hocori)
Instagram https://instagram.com/mmnskn/(@mmnskn)
■リリース情報
 『Tag』
『Tag』
発売日:2015年6月18日(木)
品番:CNBN-01
価格:¥1,000(tax out)
収録楽曲:1. Lonely Hearts Club(Tag mix) / 2. Tenkeiteki Na Smoothie(Tag mix) / 3. God Vibration Instrumental
※ユキヒーロープロレスポップアップショップ限定販売
 『Hocori』
『Hocori』
発売日:2015年7月15日(水)
品番:CNBN-02
価格:¥1,500(tax out)
収録楽曲:1. Intro / 2. God Vibration / 3. Lonely Hearts Club / 4. Tenkeiteki Na Smoothie / 5. Alien / 6. Kamone
取扱店:タワーレコード(渋谷、新宿、梅田NU茶屋町、名古屋パルコ、札幌ピヴォ、仙台パルコ、福岡パルコ、広島)、タワーレコードオンライン、音楽処、MUSIC SHOP PICK UP、more records
■ユキヒーロープロレスショップ情報

オフィシャルサイト https://yukihe-ro.jp/
オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/yukihero.prowrestling
※7月29日(水)~8月4日(火)まで、大阪・阪急うめだにてポップアップショップをオープン