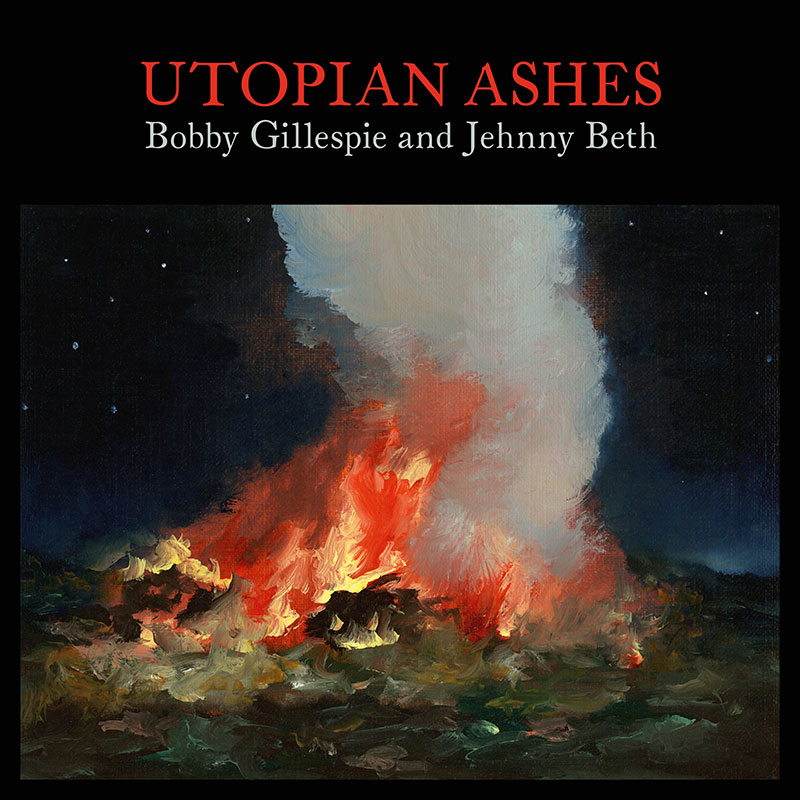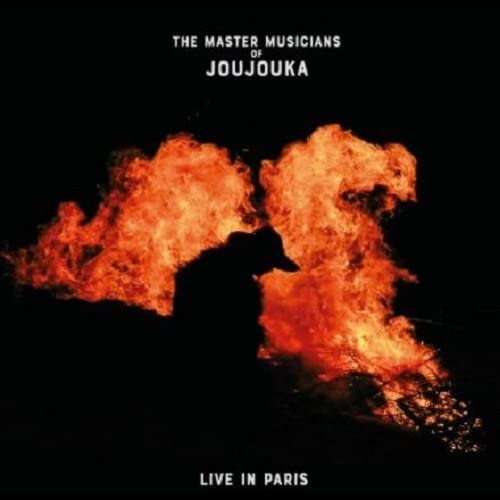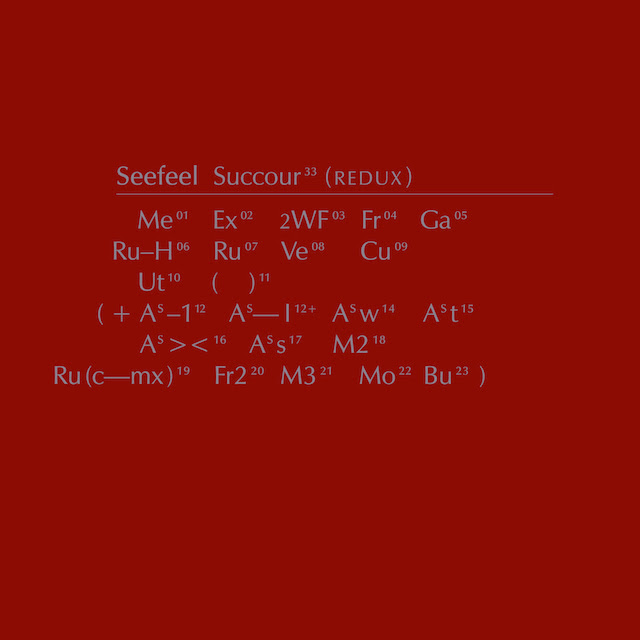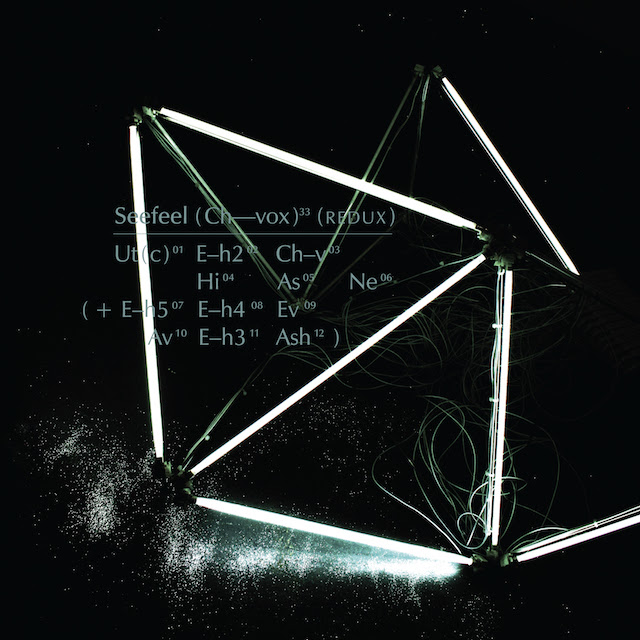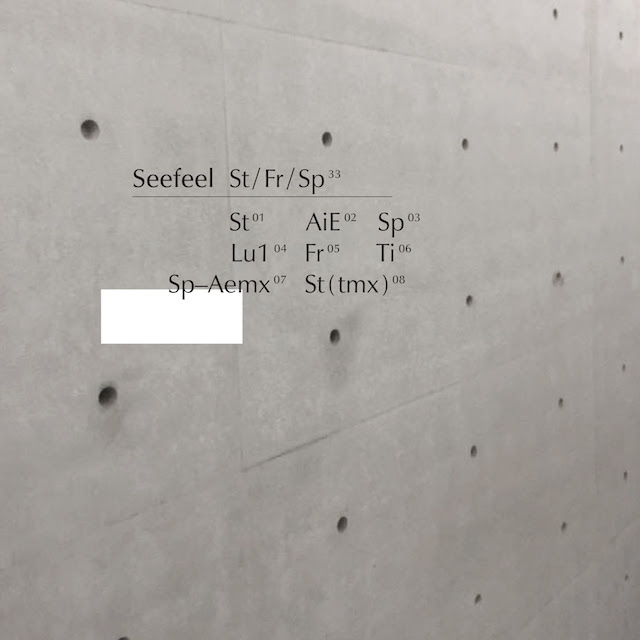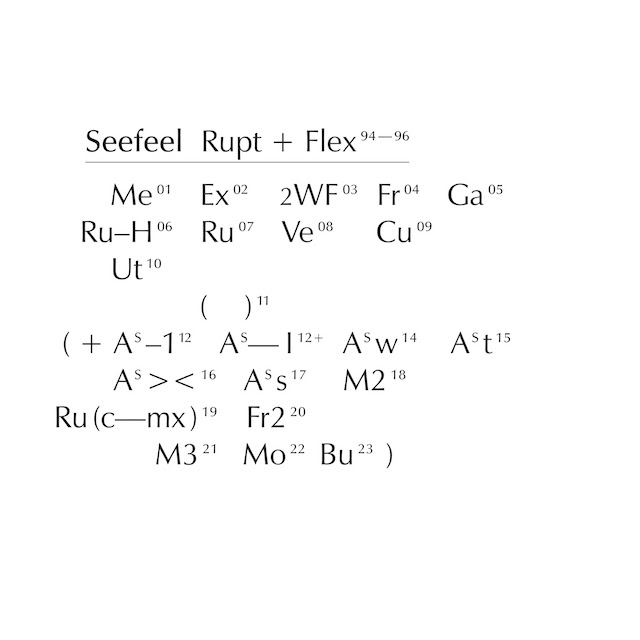恋に落ち、恋に冷め、誰かを愛し、誰かを愛するのをやめる、誰かに愛されなくなる......人間の人生経験は、芸術的経験と同じくらい大切なものだ。
──アンドリュー・ウェザオール
ボビー・ギレスピーとジェニー・ベスによるプロジェクトのテーマが「夫婦の崩壊」だと知ったときに即思い浮かんだのは、上掲したウェザオールの言葉だった。ぼくはこれをもって本作品の解説としたいと思っているわけだが、もう少し言葉を続けてみよう。
まずのっけから世知辛い話をすれば、この無慈悲な資本主義社会で家庭などを持つことは、たいていの夫婦はつねに経済的およびメンタル的な不安定さに晒されるわけで、これがじつにしんどい。さらに家族の意味も20世紀とはだいぶ違ってきている。それに輪をかけて感情のもつれなどもあったりするから、夫婦を継続することの困難さは、年を重ねるに連れてより重くのしかかってくる。ジェンダーをめぐる洗練された議論がかわされている今日において、ボビーもまた、なんとも泥臭いテーマに挑んだものだ。
とはいえ愛の喪失は普遍的なテーマというか、人を愛したことがある人間であれば誰もが経験することでもある。ひいてはポップ・ミュージックの多くは「恋に落ちる」「誰かを愛する」場面を扱い、同時に「誰かを愛するのをやめる」「誰かに愛されなくなる」場面も描いている。オーティス・レディングやスタイリスティックスのようなアーティストのアルバムでは、そのどちらも表現されているように。しかし、「誰かを愛するのをやめる」ことだけに焦点を絞ったものとなると、どうだろうか。それも男女のデュエットによる夫婦の崩壊を描いたものとなると、なかなか思い浮かばない。古風な形態でありテーマかもしれないが、じつはけっこういまどきの話としてのリアリティがある。
マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルが陽光だとしたら、ボビー・ギレスピー&ジェニー・ベスはその影になった部分を引き受けている。70年代のカーティス・メイフィールド風のファンクからはじまる『ユートピアン・アッシュズ』にはブラック・ソウル・ミュージックが注がれているし、ほかにもプライマル・スクリームで言えば『ギヴ・アウト・バット・ドント・ギヴ・アップ』に近いところもなくはないが、60年代風のフォーク・ロックやバラードがほどよいバランスで混ざっている。プライマル・スクリームが持っているアーシーな一面、ボビーのあの甘い歌声によく合うアコースティックな響きが随所にあり、作品の主題ゆえにエモーショナルで、作品の主題に反して音楽は温かい。打ちひしがれ、身につまされもするがそれによって解放もされる、渋い大人のアルバムなのだ。
バックを務めているのは、プライマル・スクリームの面々──アンドリュー・イネス(g)、マーティン・ダフィー(p)、ダレン・ムーニー(d)、そしてベースにサヴェージズのジョニー・ホステル。ほかにチェロやヴァイオリンなどの弦楽器奏者、管楽器奏者も数人参加している。
以下に掲載するのは、日本盤のライナーノーツのためのオフィシャル・インタヴューだが、ふたりはじつに明確にこの作品について説明をしている。とても良い内容のインタヴューなので、ぜひ読んでいただきたい。(野田努)

interview with Bobby Gillespie
僕はただ、普遍的な真実というものを描きたかったんだ。
経験に基づいた実存的な現実というのかな。
──ボビー・ギレスピー、インタヴュー
質問:油納将志 通訳:長谷川友美
人間はとても複雑な生きもので、人生は葛藤の連続だ。人間関係は葛藤そのものだから、このアルバムの命題は、その“葛藤”について描かれたものと言えるだろうね。そして、その葛藤は痛みを伴うんだ。
■ジェニーとは2015年にバービカンで行われたスーサイドのステージで出会ったのが最初のようですね。翌年、ジェニーがプライマルズのステージで“Some Velvet Morning”をデュエットしています。そこからどのようにして今回のコラボレーションが生まれたのでしょうか?
BG:最初にジェニーと腹を割って話したのは、マッシヴ・アタックのフェスティヴァルのときだね。サヴェージズも出演していたんだ。プライマルのギターのアンドリューがジェニーのことをよく知っていて、彼女にゲストシンガーとして歌ってもらったらどうか、と言ってきて。それがすごく良い感じだったから、アンドリューがジェニーと一緒に曲を作ってみたらいいんじゃない? と薦めてくれた。
■あなたはジェニーをどのようなアーティストとして見ていましたか?
BG:彼女のことはサヴェージズの音楽を通してしか知らなかったけど、サヴェージズの1stアルバムを買って聴いてみたんだ。彼女たちの音楽は、とてもミニマルで白黒のコントラストがはっきりしているような印象を受けた。明確な方向性やマニフェストを持っているなという印象だったね。ジェニーは自分の見せ方わかっているし、こう見られたい、こう在りたいというのがとてもはっきりしているところに興味を持った。また、彼女たちの音楽には、たくさんのルールがあるように感じた。ギターソロは入れない、曲はすべて短くまとめる、みたいなね。彼女の音楽を聴いて、批判的思考に基づいた曲作りの世界観、というアイデアが浮かんだんだ。
■サヴェージズの音楽を聴いて、ジェニーとのコラボレーションにあたって曲作りに彼女たちの方程式を取り入れるようなことは考えましたか?
BG:それはまったくなかったね。ただ、“Some Velvet Morning”のリハーサルをしたとき、彼女のプロフェッショナルな姿勢には感銘を受けたよ。
■実際に一緒にスタジオに入ってみて、彼女に対する印象は変わりましたか?
BG:いや、全然変わらなかったね。依然として彼女はとてもプロフェッショナルだったから。絶対に遅刻しなかったし、歌は素晴らしいし、プロジェクトにとても集中していた。ジェニーは詩を書き留めたノートを何冊も持っていて、日記もこまめにつけていたんだ。“Stones of Silence”のヴァースは、彼女のノートの中から歌詞を拝借したんだよ。それから、僕がコーラス部分を書いたんだ。
■基本的にはあなたが曲を書いて、一部の歌詞をジェニーが担当したという感じですか?
BG:曲によって作り方はまちまちだったね。例えば“Sunk in Reverie”や“Living a Lie”は僕が歌詞を全部書いたし、“You Can Trust Me Now”はジェニーが一部を、残りを僕が書いた曲だしね。“English Town”は、「I want to fly away / From this town tonight / So high, so high」の部分だけジェニーが書いて、あとは僕が歌詞を書いた。“Remember We Were Lovers”は僕が書いたヴァースとジェニーが書いたコーラスを組み合わせた曲で、“Chase it Down”はコーラス部分だけジェニーが書いた。“Your Heart Will Always Be Broken”はジェニーがヴァースを、僕がコーラスを書いて、それからセカンドヴァース(Bメロ)も僕が書いたな。
■1曲のなかで、実際に会話しているような感じで歌詞を書いていったんですね。このアルバムを聴いていると、男女の対話が聞こえてくるのにはそういう理由があったんですね。
BG:そんな感じだね。半分は僕が書いて、残り半分はジェニーが書いた曲もあるし、9割を僕が書いた曲もあって。男女の対話がこのアルバムのコンセプトだから、メロディと歌詞の関係もちょっと会話のようになっているかもしれない。
■アルバムにはプライマル・スクリームの主要メンバーも参加しています。アルバムがプライマル・スクリーム&ジェニー・ベスにならなかったのはどうしてでしょうか?
BG:それはこのアルバムのコンセプトが、トラディショナルな男女のデュエットソングだったからだよ。ボビー・ギレスピーとジェニー・ベスのデュエット・アルバムという体裁を取りたかった。男女の会話の持つダイナミズムにとても興味があったからね。それに、ジョン(ジョニー・ホスティル)もアコースティックギターを弾いてくれているし、プライマルのメンバーだけで作ったわけじゃないからね。ジェニーも歌詞のかなりの部分を書いているし、プライマル・スクリームの曲作りとはまったく違うやり方で作ったレコードだという部分も大きいかな。この20年間のプライマル・スクリームのアルバムは、ほとんどコンピュータで曲作りをしてきたんだ。エレクトロニックなサウンドスケープを主軸にした作品を作ってきた。でも、このアルバムの曲のほとんどはアコースティックギターで書いたんだ。初期のプライマル・スクリームに近い曲作りをした感じだね。
■たしかに、このアルバムはプライマル・スクリームの近作に比べてずっとオーガニックな手触りを感じました。
BG:その表現いいね。その通りだよ。
■グラム・パーソンズとエミルー・ハリスの“Grievous Angel”、ジョージ・ジョーンズとタミー・ワイネットの“We Go Together”などのカントリー・ソウルに触発されたともお聞きしましたが。
BG:僕たちは、既存の曲をなぞるようなレコードを作ろうとは思っていなかったんだ。あくまでもオリジナルの音作りを目指していたし。ただ、プレスリリースにそう書いたのは、ジャーナリストにどんなタイプの音楽性を持つアルバムかっていうわかりやすい見本を示したのに過ぎないんだよ。トラディショナルな男女のデュエットアルバム、というコンセプトを理解してもらうためにね。
■以前にも、『Give Out But Don't Give Up』(1994)で、デニス・ジョンソンとの“(I'm Gonna) Cry Myself Blind”“Free”でカントリー・ソウルにアプローチしていますよね。
BG:あのコラボレーションは、今回とはまったく意味合いが異なるものだったんだ。デニースには、ジェニーのようなアーティスティックなクリエイティビティはまったくなかったし。彼女は曲を書いたことも、歌詞を書いたことも、メロディを書いたことも一度もなかったから。『Give Out But Don't Give Up』の曲は全部僕が書いたものだったしね。彼女はシンガーとして、僕の指示通りに歌ったに過ぎないよ。今回のアルバムは、ジェニーも実際に歌詞を書いたり、曲作りにも参加しているからまったく違う性質のものなんだ。
[[SplitPage]]■今回のアルバムは、2人の共作による真の意味でのデュエット・アルバムなんですね。
BG:そうそう。このふたつのアルバムは、まったく異なる性質を持っていると思う。もちろん、楽器の構成とか、演奏の部分では共通点がないこともないよ。“(I'm Gonna) Cry Myself Blind”と“Your Heart Will Always Be Broken”は、言ってみれば同じ枠組みのなかにカテゴライズできると思うけど。とにかく、ジェニーは曲作りも手掛けるアーティストで、デニースはシンガーという大きな違いがある。
■残念ながら急逝したデニスとデュエット・アルバムを作ることは考えたりしなかったということですか?
BG:まったく、全然、一度たりとも考えたことはなかったね。僕とデニースの歌声は、デュエットとしてはまったくかみ合わないというか、成立しなかったと思うよ。

僕たちが信じているもののほとんどは嘘で塗り固められたギミックで、僕たちは嘘を信じて嘘にお金を払って買っている。資本主義社会なんて懐疑的な存在だし、僕たちは疑うべきなんだ。
■アルバム・コンセプトは「slow disintegration of a failing marriage(失敗した結婚のゆっくりとした崩壊)」と聞いています。どうしてこのコンセプトになったのでしょうか?
BG:う~ん。説明が難しいな……僕はただ、普遍的な真実というものを描きたかったんだ。経験に基づいた実存的な現実というのかな。人間同士の相容れない矛盾や、不明瞭な感情といったもの。僕は、人間というのは分断によって結びつけられていると思うんだ。つまり、人間が背負っている痛みの大部分は、他の誰かと繋がりたい、結ばれたいという思いから来ているんじゃないか。そう願っているのに、ぴったりと重なり合うことは永遠にないんだよ。ある一瞬、心が通ってひとつになることはあるし、精神的な結びつきをほんのわずかな間感じることもある。でも、それは永遠には続かないし、完全にひとつになることはない。僕たちはまるで、孤島のようなものだと思う。誰かと地続きのように繋がることはないんだよね。それがあらゆる種類のリレーションシップに対する真実だと思う。だからこそ、僕たちは誰かと繋がることにこれほどの魅力を感じるんだと思うんだよね。人間は孤独で、だからこそ誰かと繋がることで力を得る。それは神の定めたルールに則っているんだろうし、神学的・哲学的な領域の話になるんだろうけど。なぜ人がロマンチックな恋愛関係をこれだけ追い求めるのかと言えば、それは誰かと関係を持つことで自分がより大きな存在の一部になったように感じられるからなんだ。自分の存在がより大きなものになったように感じられるんだよ。でも、それは長くは続かない。永遠に続くものではないんだ。
■それは男女間の恋愛関係に限らず、すべてのリレーションシップについて言えることなんでしょうね。
BG:そう、僕たちは動物と同じなんだ。もしかしたら、無償の愛を注げるだけ動物のほうがマシかもしれない。人間はトリックスター、ペテン師だから。このアルバムは、人間には他の人間のことは理解できないということについて書かれたものなんだよ。もちろん、相手のことは知っているけど、本質まではわからないよね。その人のことを知っているつもりでも、本当のところは全然わかっていないんだ。結局完全に理解することなんてできないから、愛が冷めたらもう全然知らない赤の他人になってしまう。そのとき感じた愛がなんだったかなんて、僕たちにはわからない。愛なんて実体のないものだから。
そう、愛は言ってみれば生命そのものなんだと思う。僕たちの命も、一度死んだら宇宙の塵と消えてしまう。愛も同じだよ。一度その愛が冷めたら、宇宙の藻屑だ。そうやって宇宙のサイクルの一部として、喪失と再生を繰り返していくんだ。僕たちの命もそこに生まれた愛も、宇宙の規模からしたらとんでもなく小さな、取るに足らないことじゃない? 愛やリレーションシップは、本当に小さな一瞬の火花のような存在でしかない。燃え尽きたらそれで終わりだ。
このアルバムは、ある意味とても皮肉だけれど、現実的なことをテーマにしているのかもしれないね。実存的な真実を受容することがこのアルバムで伝えたかったことなんじゃないかな。僕たちはわかり合えない、自分以外の人のことは理解できない。表面的なことはわかるし、見えるものについては深く考察するけれど……太古の昔から、ドラマや芝居や脚本や詩や小説のテーマにもなってきたよね。人間はとても複雑な生きもので、人生は葛藤の連続だ。人間関係は葛藤そのものだから、このアルバムの命題は、その“葛藤”について描かれたものと言えるだろうね。そして、その葛藤は痛みを伴うんだ。「葛藤が生み出す無限の痛み」がテーマになっていると言えるかもしれない。ある意味、とてもブルージーなレコードになっていると思う。
■曲が進むにつれて、内面がさらけ出されていき、痛みも増していくようです。一方で、サウンドそのものは美しく、アップリフティングで時には優しく、癒されるような要素も入っていますよね。
BG:そうなんだ。だから、そこに一筋の希望が見えるんだと思う。
■この痛みを美しいサウンドで表現しようと考えた真意はなんだったのでしょうか。そうした希望の光を込めたかったということでしょうか?
BG:そうそう、その通り。痛みを伴う歌詞を美しい音楽で表現しているというのは良い考察だ。なぜなら、それこそがアートの持つ力だからね。それが聴き手を惹きつけるんだと思う。美しく繊細なサウンドが、ダークな歌詞によって傷つけれた心を引き上げて、包み込んでくれる。言ってみれば、美しさのコクーンのようなものだね。美しい花に見えても、実は君を飲み込んでしまうかもしれない(笑)。毒を持った花みたいなものなのかもね。
言ってみれば、人間だってそうじゃない? 外見は小綺麗にしてるかもしれないけど、中身はダークでドロドロだ。怒りやサディスティックな感情を秘めているんだから。うん、なかなか良い指摘だね。考える良いきっかけになった。本当にどうもありがとう(笑)!
■英国は深刻なコロナ禍を経て、回復へと向かいつつありますが、新型コロナウイルスがアルバムに与えた影響はあったのでしょうか?
BG:いやいや、このアルバムは新型コロナ以前に完成していたから、そうした影響はないよ。曲自体は2017、2018年頃に書いたもので、レコーディングも2018年の夏にやったし、ミックスも2018年中には終わらせていたんだ。本当は昨年リリースされるはずだったんだけど、そのタイミングで新型コロナが流行して、ジェニーのソロアルバムのリリースもあったから、発表をここまで先送りにしていたんだよ。
■そうだったんですね。このアルバムはまるでロックダウン下で物理的な距離を取らざるを得なかったふたりの葛藤を描いているように感じたので。
BG:なるほどね。でも、それは関係なかったかな。それよりも、このアルバムは感情の不明瞭さについて描かれたものなんだ。人間の残酷さと言ってもいいかもしれない。その残酷さというのは僕たちのなかにも、あらゆる場所、あらゆる場面に溢れている。詩人だって脚本家だって小説家だって、本当は不明瞭な感情と闘っているんだ。本当は自身の感情について1ページだって書くことができないのかもしれない。映画や詩を創ってはいるけど、自分自身の感情については不明瞭なまま葛藤を繰り返しているんだと思う。自分の感じ方や生き方、もしかすると結婚生活さえ、自ら正すことはできないんだよ。だって、人間は身勝手で利己的で、ナルシスティックな生きものだから。人間は……そう、混沌としている。すべての人間が、矛盾した存在なんだ。
僕がこのアルバムで本当に描いたことは、そうした人間の持つ矛盾についてなんだろうな。あるときは素晴らしい人物で、ある時は愛情の欠片もない人物で、翌日は誰もがその人のことを憎んでいるかもしれない。ある意味、サディスティックとマゾヒスティックな感情を持ち合わせているということかもしれないね。人間は、何か実体のないものに突き動かされて、しかるべき状況に陥っている気がする。何か得体の知れない、僕たちを突き動かすなにか……人間ていうのは、結局何もわかっちゃいないんだ。僕を含めて、誰もが自分の感情についても、どうあるべきか、どんな行動を取るべきかなんて、まったくわかってないんだと思う。
■そうした音楽に込めた思いや考え方、感じ方というのはやはりあなたのこれまでの経験から来ているのでしょうか。
BG:それはもう、僕の作品はすべて自分自身の経験に基づいているものばかりだよ。
■というのも、このアルバムに登場する男女というのは、明確なキャラクター設定があってのことなのか、それよりももっとパーソナルで自然発生的なものだったのかが気になったんです。
BG:ああ、そうだね。たしかにフィクションの部分もあるから、ある意味架空の登場人物に語らせているところはあるね。でも、そうしたキャラクターの人物設定のベースには僕の経験があって、僕がいろいろな人たちの経験やリレーションシップを観察して考察したものを反映しているから、完全に架空のキャラクターを創り上げたという感じではないかな。僕の視点から見た、さまざまな人たちの、さまざまな“痛み”のコレクションといった感じかな。端から見たら幸せな結婚生活でも、そこに葛藤があるかもしれないと思うんだよね。
1曲目の“Chase it Down”は、生命や宇宙、自然、それに人間にさえ備わっている存在の美しさに対する、ある種の不思議な感動や心理的感覚について歌ったものなんだ。滅私的な優しさや思いやりといった美しさ。でもね、日本もそうだしイングランドも西欧諸国そうだけど、経済的に豊かな国に暮らしていると、生きていることがどんなに幸運で恵まれているかなんて、すぐに忘れてしまうと思う。退廃的になってしまって、どんなに生きづらいかっていう文句ばかり言うようになる。でも、僕は生きていることそのものが素晴らしいことで、奇跡的なことなんだってこの曲で歌いたかった。
「Love while you can / Every woman every man / Everybody is a star / No matter who / Or what you are / And we don’t have too long / Run your race / Sing your song」の部分には、そうした想いが込められているんだよ。人生は短い、僕たちは自分たちに命を授かって、この人生を生きていることを讃えるべきなんだってね。僕たちはこの美しい人生を授かったんだから。でも、人は新しい家が欲しい、新しい車が欲しい、新しい冷蔵庫が欲しいって、不平不満ばかりを言っている。
■貪欲になればなるほど自分の不遇さに絶望してしまって、経済的に豊かな国の方が自殺率が高かったりしますよね。
BG:そうなんだ。結局人は、自分より裕福だったり、成功していたり、美貌を備えていたり、そんな人たちと自分を比較して羨んでばかりいるよね。セクシーでスタイリッシュで大きな家に住んでいるセレブと比較することで自分の価値を決めてしまっている。結局、そうした比較対象を設けて、ある種のゴールみたいな人たちを示すことで、資本主義は機能しているわけだから。フェラーリを乗り回して美人のモデルの奥さんがいて大きな家に住んで、という結論を提示することで、わかりやすくそこに向かっていくことになる。だから人は資本主義社会に疑問を持たずに暮らすことができるんだ。成功者はこんな暮らしを手に入れているという幻想を見せることで、君にもその暮らしを手に入れることができるよ、手に入れたら勝者だよ、手に入れられなかったら敗者だよ、とわかりやすく示すことができるわけだよ。敗者には負けた理由があるんだよ、というのが資本主義社会の根底になっている自由競争からのメッセージなんだ。こんな平等な社会で何も手に入れられなかった君自身に理由があるってね。経済や社会が悪いんじゃない、頭が悪いとか、醜いとか、頑張りが足りなかったとか。成功者はみんな身を粉にして働いているっていうけど、実際の金持ちは、そのほとんどが親から受け継いだものだったりするんだけどね。土地とか不動産とか、両親が築いた財力や先祖代々受け継いだ遺産がほとんどだ。
僕たちが信じているもののほとんどは嘘で塗り固められたギミックで、僕たちは嘘を信じて嘘にお金を払って買っている。資本主義社会なんて懐疑的な存在だし、僕たちは疑うべきなんだ。魅惑的な嘘で塗り固められてる。エルメスのハンドバッグやイブ・サンローランのコートは、消費主義者にとっては魔力を持った魅惑的な存在で、僕たちは幻想に投資してその魔力を持ったフェティッシュな所有物を手に入れている。僕自身だって、他のみんなと同じようにその行為に罪の意識を感じているよ。消費社会の現実は、大衆の奴隷になることなんだ。僕はもちろんその資本主義消費社会の一部だし、ブランドのキャンペーンとかもやってるし、だからこそ罪の意識を感じているよ。でも、この社会の一部だから、その一員として生きていくしかないんだよね(笑)。
■“Sunk in Reverie”を聴いて、そういった消費社会に対する幻滅みたいなものを感じました。
BG:あの曲は、人間に対する最上級の嫌悪感を歌ったものなんだ。人びとの行動を目撃している主人公の語りという体裁を取っているんだけど。人間が持つ、寄生本能とでも言うのかな。それを暴こうという内容なんだ。人はみんなさまざまな仮面を被っていて……この主人公も、俳優としてかつてはそちら側に属していた。だから、自分について歌っている歌でもあるんだよ。最後のコーラスの「The bodies keep on coming / The party never ends」の部分は、パゾリーニの映画『ソドムの市』を観て書いたんだ。ラストシーンで少年少女を次々に虐殺するところを描いたんだけど、人間の死体が累々と重なっている様は、まるで肉屋みたいだな、と思って。人間も、虐待されて使い尽くされてやがて死体となって転がっている。つまりこの曲は、そういう放蕩的なライフスタイルや、そういうライフスタイルを送って吸血鬼のようになってしまった人たちの空虚について書いたものなんだ。繰り返しになるけど、ここで描かれているようなライフスタイルはとても魅力的かもしれないけど、そこに愛はないし、とても空虚だ。でも、そこにいる人たちは気付かないふりをしているんだよ。
■では、少しサウンド面のお話しを聞かせてください。コンセプトの世界を表現するサウンドですが、方向性についてふたりで話し合ったのか、それともあなたが主導していったのかどちらでしょうか?
BG:2017年の1月に僕とアンドリュー(・イネス)がパリに行って、ジェニーと彼女のボーイフレンドのジョニー・ホスティルと一緒にスタジオに入って、本当にごくごく簡単なアイデアを出し合った感じではじまったんだ。当初はかなりエレクトロニックな雰囲気でね。クラフトワークとか、そんな感じの。それでロンドンに戻って来て、頭のなかにあった曲をアコースティック・ギターで弾いてみたんだよ。で、ギターのコードを決めていった。それから少し曲をシェイプして、歌詞を書きはじめた。5曲くらい書いたところで、『ロックのアルバムを作るべきだな』って思ったんだ。アンドリューとデモを作ってみたんだけど、いまのスタイルにすごく近い、ロック・ミュージックになった。もちろん、もっと原始的な感じではあったけどね。それをジェニーに聴いてもらって、「こんな風に作りたいんだけど」って言ったんだ。生演奏でレコーディングしたいことを伝えたら、「いいわ、最高!」って言ってくれて。それでこういうサウンドになったんだよ。
■共作していて思いもよらず、良い方向に向かった曲はありますか?
BG:例えば“Remember We Were Lovers”は、最初はクラフトワークみたいなサウンドだったんだ。ドラムマシーンやストリングマシーン、ピアノが入ってて。でも、自分的にはしっくりこなくて。雰囲気もないし、感情がこもっていない感じがしてね。それで、ギターで曲を書き直してみたんだ。それから、生演奏でレコーディングしたらどうかって提案したんだよ。マーティン・ダフィーとダリン・ムーニーと一緒に。ジョン・レノンの曲みたいなピアノが入れたかったんだよね。(“Mother”を歌う)とかね。“Jealous Guy”とか(“Jealous Guyを歌う)、そんな感じ。アメリカのブラック・ソウル・ミュージックみたいな感じにしたかった。オーティス・レディングとかね。クラフトワークより、ジョン・レノンみたいな曲にしたかった。
■それが、共同プロデューサーとしてブレンダン・リンチを迎えた理由のひとつでしょうか?
BG:ブレンダンは優れたエンジニアであり共同プロデューサーでもあるし、とくにバンドの生演奏をスタジオ録音するのがすごく上手なんだ。だから、このアルバムにぴったりだと思ったのは間違いないね。
■彼を起用したのは『XTRMNTR』以来ですよね?
BG:そうだね。いや、ちょっと待って。2017年にレコード・ストア・デイに合わせてリリースした“Golden Rope”のリミックスをブレンダンにやってもらったな。
■タイトルの『Utopian Ashes』はこれ以上ないほど合ったタイトルだと思いますが、どこから生まれたのでしょうか?
BG:僕の頭のなかから生まれたのさ。アルバムのサウンドとコンセプトを詩的に表現できるタイトルはないかなって考えてて。それでいて、抽象的で聴き手に考える余白を与えるようなものにしたくてね。
■たしかに、このアルバムのライヴは朗読劇でも成立しそうですね。
BG:ああ、本当に? 歌詞が? 嬉しいな、ありがとう。
■実際にこのアルバムを引っ提げてのライヴの予定はありますか?
BG:うん、11月にライヴができないかって考えているところなんだ。キャンドルを灯してライヴをやりたいと思ってて。
■プライマルとしては『Chaosmosis』以来となる新作を期待したいところですが、いかがでしょうか?
BG:『Riot City Blues』の17曲入りアルバムを再発する予定だよ。オリジナルは10曲入りなんだけど、7曲ほど足して17曲入りにしたんだ。
■リミックスなどを含めた構成になるということでしょうか?
BG:いや、全部オリジナル曲なんだけど、シングルのB面を入れることにした。オリジナルがリリースされた15年前は、シングル1、シングル2、7インチシングルという体裁でシングルをリリースしていたから、曲がたくさんあって。レコード会社にとにかくたくさん曲をレコーディングしろって言われていた時代で、アルバムに合わせて17~18曲ほどレコーディングしていたからね。それを全部含めて、セッションでレコーディングしたものを『Riot City Blues Sessions』というタイトルで、曲順も変えてリリースする。4つの章に再構成した感じの作りになってて、第1章はハイエナジーなロック、第2章はバラード、第3章は再びハイエナジーなロック、第4章はよりハイエナジーなロックという感じで、面白い構成になっていると思うよ。
それから、これははっきりとしたことはまだ言えないんだけど、『Screamadelica』もなんらかの形で再発することになりそうだよ。ちょうど今年で発売30周年を迎えるからね。それに、ライヴ・アルバムも出る予定だよ。2015年にオースティンで開催されたサイケデリックのフェスティヴァル、LEVITSTIONに出演したんだけど、その時の音源がライヴ・アルバムとしてリリースされるみたいだね。アハハハ! こんなにいろいろ出るのかって自分でも驚いたよ(笑)。

interview with Jehnny Beth
もう愛していないって言っているけど、それはまだ愛が残っているから言えるセリフなのよ(笑)。
──ジェニー・ベス、インタヴュー
質問:油納将志 通訳:長谷川友美
このアルバムは、リレーションシップの崩壊に焦点を当てているというよりも、その問題に対峙して、なんとか関係を立て直そうと葛藤する男女の姿を描いていると思う。そのために対話を重ねているんじゃないかな。
■いまはロンドンにいらっしゃるんですか?
JB:いいえ、パリよ。4年前にパリに移ったの”
■パリはいまどんな状況ですか?
JB:相変わらず悪夢のようよ。まあ、世界中のどの都市にも言えることかもしれないけど。
■最初にボビーに会ったとき、どんな印象を持ちましたか?
JB:最初にボビーに会ったのは、パリで行われたイブ・サンローランのキャットウォークショーに、彼と私が招かれたときだったの。もちろん彼のことはアーティストとして知っていたけど、個人的に会ったことはそれまでなかったわ。彼も私のことを知ってくれていたから、会話を交わして連絡先を交換したのよ。でも、そのときはそれ以上のことは何も起こらなかったわ。
その後、スーサイドのラスト・ステージとなるA Punk Massっていうイベントがバービカンで行われて、そのときにまた会ったのよ。アラン・ベガが亡くなる直前のことだったんだけど。そこで、スーサイドに“Dream Baby Dream”をボビーと一緒に歌わないかと誘ってもらって。この曲はすでにサヴェージズで歌ったことがあったから、ボビーに「是非やりたいと思ってるけど、一人で歌いたかったら私は遠慮しておくわ」って言ったの。そうしたらボビーが、「いやいや、いいアイデアだからやろうよ」って言ってくれて。なんだかカオスな夜だったわ。ヘンリー・ロリンズが怒ってステージを降りちゃったり(笑)。それで、いつが私たちの出番かさっぱりわからなくて、突然曲がはじまっちゃったの。そうしたら、すぐにボビーがステージに出ていって、こう、客席に向かってかがんだのよ。それが本当にロックスターっぽくて、なんてかっこいいんだろう、って感動したわ。曲の始まりも終わりもわからなくて混乱したけれど、ステージが終わった後は大満足だったし、ハッピーで誇らしい気持ちになって。それでボビーともすっかり意気投合したのよ。
それから、プライマル・スクリームとサヴェージズがブリストルで行われたマッシヴ・アタック・フェスティヴァルで共演する機会があって、アンドリューとボビーが私にプライマルのステージで歌わないかって誘ってくれたの。その後、アンドリューがボビーに2人でレコーディングしてみたらどうかって薦めてくれて。ジェニーとジョニー(・ホスティル)も一緒に曲を書いてみないかって言ってくれて、断る理由なんてひとつもなかったわ。ボビーとの共演は本当に楽しかったし、彼と私の声はデュエットにぴったりだと自分でも感じていたから。それで、ボビーとアンドリューがパリに来てくれて、いま、私がいるこのスタジオで2回ほどセッションしたの。そこで、曲のベースとなるようなものを書きはじめて。
当初は、どんな曲を書いているかはっきりしないような状態だった。ただ、なんとなく曲のアイデアを出す感じだったんだけど、私とジョニーはまるでプライマル・スクリームの曲を書いているような気分だった。ベースとなるサウンドはエレクトロニックで、モノコードで。それで、ボビーはロンドンに戻って歌詞を書きはじめたのよ。パリでは歌詞ではなくて、メロディを書くことに集中していたから。
でも、歌詞がメロディのアイデアにマッチしないと考えたようなのね。それで、「このレコードはエレクトロニックなサウンドのものにはならないと思う」って言われたの。もっと、バラードや、オールドスクールのフォークといった、ソングライティングに重きを置いたアルバムになりそうだって伝えられた。それからアルバムのコンセプトの話になって。“結婚生活の崩壊”というテーマが浮かび上がってきたのよ、ごめんなさい、ちょっと長かったわね。でも、これがボビーと出会った事の顛末なの。
■出会う前は、ボビーをどのようなアーティストとして見ていたのでしょうか。
JB:とても強い個性を持っていて、素晴らしいソングライターだという印象だったわ。プライマル・スクリームの曲はもともと好きだったしね。とくに“I Can Change”がすごく好き。とても良く書かれた曲だと思ったわ。最初に彼を目撃したのは、ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズのアフターショーパーティの会場だったの。もちろんそのときはボビーがどんな人物かまったく知らなかったんだけど、ボビーがニックと談笑しているのを見て、意外と明るくてよく笑う人なんだなって思ったわ。というのも、彼は酷いドラッグ中毒者だって噂を聞いていたから。もちろん、あの時代の人たちは多かれ少なかれそういう印象がつきまとっていると思うけどね。
それが、実際に彼と会って話をしてみたら、そんな悪い印象はすぐに吹き飛んだわ。全然シラフだしクリーンだし。それって、私にとってはとても重要なことなのよ。私はお酒も飲まないし、ドラッグをやるような人たちとつるんだこともない。そういうものは、私が求めているものではないから。ロックンロールミュージックをプレイしているのにね(笑)。ロック界はアンフェタミンと密接に結びついていて、ドラッグまみれという歴史があることもよくわかっているけど、私はもうそういう世代の人間ではないの。サヴェージズは自分自身を律して、自分のやっていること、やるべきことに集中するという考えを共有しているからね。だから、ボビーに会って彼の内面を知ることで誤解が解けて、このプロジェクトは絶対にうまくいくと確信したわ。
■最初に「結婚生活の崩壊」というコンセプトを聴かされた時、どう思いましたか?
JB:電話で突然言われたのでビックリしたけど(笑)、すごく面白いと思ったわ。いろいろな音楽やレコードで語られてきたテーマでもあるしね。このテーマが一体どこから来たのか、少し不思議には思ったけれど。でも、題材としてはいろいろな曲で取り上げられているし、ある種のキャラクターを設定するというコンセプトにはとても興味を持ったわ。もちろん、そうしたキャラクターには私たちの素の部分も大いに反映されてはいるけどね。そうでないと、オーセンティックなサウンドにはならないから。
最初のシングル(“Remember We Were Lovers”)では、一組の男女が彼らの抱えている葛藤と、それをどう乗り越えるのか、その難しさについて歌っているけれど、ある意味伝統的なテーマだと思うのよ。ティーンエイジャーの恋の悩みや失恋とは明らかに異なる胸の痛み。それは、彼らがそれまで一緒に旅してきた軌跡があるからなの。結婚して、生活を共にして、もしかしたら子供もいるかもしれない。責任感の重みも違うし、人生のコミットメントなわけだから。このアルバムは、そうしたリレーションシップの崩壊に焦点を当てているというよりも、その問題に対峙して、なんとか関係を立て直そうと葛藤する男女の姿を描いていると思う。そのために対話を重ねているんじゃないかな。もし話し合うこともなくなってしまったら、関係性は完全に壊れてしまうから。「I don’t love you anymore」なんてとてもヘヴィで辛いフレーズだけど、そうやって自分の心の内を語ることで、なんとか関係性を修復したいと考えているからこそ出て来た言葉じゃないかと思っているの。もう愛していない、って言っているけど、それはまだ愛が残っているから言えるセリフなのよ(笑)。その愛を取り戻したいという心の叫び。まずは自分の相手に対する正直な感情をぶちまけることで、2人の未来を変えたいという気持ちの表れだと思う。私は、このアルバムのコンセプトをそういう風に解釈したけれど。
■たしかに相手に対する感情や情熱が残っていなかったら、もう話しても無駄ですもんね。
JB:その通りよ。情熱が残っているから、なんとかしたいと相手との対話を望むのだと思うわ。もう相手のことがどうでもよくなっていたら、自分の気持ちをぶちまける必要なんかないもの。ただ去って行けばいいだけの話だから。
■アルバムに登場する女性のペルソナは、あなたが創造した架空のキャラクターですか? それとも、自分自身を投影させたもので、キャラクター設定のようなものはなかったのでしょうか。
JB:そのどちらの要素もあると思う。歌詞はすでに書きためていたものがあったし、私が書いた歌詞のほとんどは、アルバムのコンセプトが決まる前に書いたものだから。私の歌詞が、ボビーがアルバムの方向性を決めるプロセスに少なからず影響を与えたところもあるんじゃないかな。コンセプトがはっきりしてから、歌詞を修正したりして曲のテーマや世界観に合うように、無意識のうちにキャラクターを設定していたかもしれないわね。曲のすべてにキャラクターを設定したコンセプトアルバムという発想も悪くはないけど、私は音楽で自分の本当の気持ちや感情を表現したいから、キャラクター設定にはあまりこだわらず、自分の経験を元にして素直な感情を込めたつもりだし、自分が経験していないようなことを歌った歌については、自分だったらどうするかな、どう感じるかなということをつねに念頭に置いて歌詞を書いたのよ。

“Utopia”という希望に満ちた言葉と、“Ashes”という破滅的な言葉とのコントラストがとても面白いと思った。ある意味、さっき話したような、歌詞の持つダークさとサウンドの持つポジティヴさとを的確に表現したタイトルじゃないかしら。
■曲が進むにつれて、内面がさらけ出されいき、痛みも増していくようです。歌詞の一部はある意味、とてもストレートな表現にもなっていますよね。この痛みを男性と女性の両面から描くことが真意だったように思いますがいかがでしょうか?
JB:その通りよ。でも、そこには一筋の光のようなものもあったと思うの。
■たしかに、サウンドそのものはアップリフティングだったり、穏やかだったり、歌詞の内容とのコントラストが鮮明だったように思いました。
JB:私たちは、気の滅入るようなレコードを作りたかったわけじゃないからね(笑)。スタジオで曲作りをしている時は本当に楽しかったし、ジョークを飛ばして笑い合ったり、和気藹々としていたから、そういう心が軽くなるような経験もサウンドに反映されていたんじゃないかしら。それに、さっきも言ったけど、人間関係の真実をこのアルバムに込めたのは、そこに希望の光があるからなの。少なくとも私はそういう風に感じているわ。本音を語るのは、解決の糸口を見つけたいからなのよ。自分たちの素直な感情や考え方を表現するのは、まだ希望が残っているからだと思う。もしかしたらこの状況を変えられるかもしれない、良い方向に舵を取り直せるかもしれないという思いから来ているのだと思うわ。だから、一見真逆に見えるサウンドと歌詞の世界観をひとつにまとめることは、それほど難しいことではなかったのよ。悲しい気持ちや暴力的な感情やトラウマといったものを、全編を通して悲しいサウンドで表現する必要もないし、そこにコミュニケーションが介在する限り、様々な方向へと形を変えていくと思うから。
ボビーが、このアルバムは“表現力の欠如”について描かれていると言ったの。人によっては、会話が苦手で自分の感情や思考をうまく言葉にできないこともあるでしょう。だから、誤解を招くようなきつい言い方になってしまうこともある。でも、このアルバムが最終的に目指すところは、個人や2人の未来を良い方向へと変える力なのよ。カップルとしてすでに機能しなくなっていても、2人とも一緒にいる未来を思い描いている。だから、このアルバムはデュエットとして成立しているのよ。誰かが誰かに属している、そんな感覚を描いていると思うから。
■アルバムで描かれている男性については、どのような印象を抱きましたか? ボビーが自分自身を投影しているように感じる部分はありましたか?
JB:そのことについてはボビーに直接たしかめたことがないからわからないけど、彼が自分のことを歌っているのか、それともフィクションの世界を創り上げたのか、私にとってはどちらでも構わないかな。彼はきっと、この男女のキャラクターを使って自分自身の世界を創ろうとしたんじゃないかと思うから。彼はきっといろいろな経験をしてきて、私たちもメディアを通してしっていることもあるし、彼は結婚もしているしね。でも、そこに彼自身の経験が投影されていたとしても、きっともっと普遍的なものを作ろうと思ったんじゃないかしら。もちろん私は彼ではないし、想像で話しているに過ぎないからもしかしたら正しくないかもしれないけど、これまでのインタヴューで彼が語ったことを総合して考えると、きっとあらゆる人に向けてこうした曲を書いたんだと思うのよ。
人によって受け取り方が違っても良いと思う。多くの人が結婚生活を体験しているわけだし、誰もが最初の頃のときめきや燃え上がるような気持ちを多かれ少なかれ失うのは間違いないと思うから。それで、その頃の思いを取り戻したい、なんとかこの関係を修復したい、って思うのは自然なことよ。だって、リレーションシップって、言ってみれば進化し続けるものなんだから。リレーションシップはレボリューションなのよ。このアルバムの2人も、最後の曲が終わったあとにもしかしたら自分たちの解決策を見つけたかもしれないな、って思うの。
私はいまやボビーとは友だちだと思っているから、友だちが過去について率直に語るのは素敵なことだな、って思って聴いたわ。例えば“You Can Trust Me Now”は、彼が歌うから美しく聞こえるんじゃないかなって思うの。だって、このセリフって、本来なら全然信用ならない感じでしょ? 「僕のことを信じていいよ」って言われたら絶対に信じないわ(笑)。でも、彼がそう歌うことで、なんだかとても美しいフレーズに聞こえるの。だって、ある意味とても脆いでしょ。そう言われてもまた裏切られるかもしれない、信じていいよ、って言った方が裏切られるかもしれない。それを、ドラッグに溺れたこともある、さまざまな経験を積み重ねてきたボビーが言うことに意味があるのよ。彼が言うと、とても心に響くわ。スタジオのなかでこの曲を聴いたとき、感動したのを覚えているわ。
■このアルバムのなかでいちばん好きな曲はどれですか?
JB:やっぱりこの曲かしら。歌詞もサビもとても素敵な曲だと思うから。もう僕は昔の僕じゃないんだ、生まれ変わったんだ、信頼に値する人間になるよ、っていう彼の心の声が聞こえる気がするし、その過程というのはとても美しい軌跡だと思うの。そこに女性キャラクターのヴァースが入ってきて、「You turned into someone / I don’t know」って歌うのは、ある種の拒絶じゃない? それは、彼女のビターな経験から来ている。男は自分を信じてくれっていう。女は信じられないっていう。愛はリスクを伴うもので、だからこそ愛は美しいものだって私は信じているけれど。一方で、リスクを伴うものはもはや愛ではないのかもしれないけれどね。
■あなたは女優としても活動しています。今回のアルバムはとてもドラマチックなストーリーを持っていますが、演じるように歌ったのでしょうか?
JB:(笑)どうかしら。演じることと歌うことは私のなかでは全然違う種類のものだから。もちろん、演じるような表現を用いて歌うこともあるけれど、歌には“真実”がないと心に響かないと思っているの。敢えて穿った表現やシニカルな視点を込めて歌う歌手もいるけれど、そこに自分自身が投影されていなければ、それは聴き手にも伝わってしまうって信じているのよ。信用できないシンガーは好きじゃないの。この人は真実の感情を歌っているなって信じられなかったら、その歌を聴く気にはなれないわ。私は歌に、真実を込めたいと思っている。私はボビーよりも若いし経験も少ないかもしれないけれど、それなりに年を重ねてきたし、ジョニーとは18年間付き合っているから、1人の人と長いリレーションシップを持つことがどういうことかも多少はわかっているつもりよ。だから、自分の知らないことを作り出す必要もないし、身の丈以上の表現を取り入れる必要はないと思っているの。
■サウンド的には、グラム・パーソンズとエミルー・ハリスの“Grievous Angel”、ジョージ・ジョーンズとタミー・ワイネットの“We Go Together”などのカントリー・ソウルに触発されたと読みました。サウンド自体はどのようにしてやり取りしながら完成していったのでしょうか? 男女のデュエットアルバム、というコンセプトには最初から興味があったのでしょうか。
JB:とくにサウンド的なリファレンスについては話をすることはなかったわ。もちろん、多少はこんな感じの雰囲気で、っていう話はしたけれど。ボビーと私の声はすごくマッチしていると感じていたから、デュエット・アルバムというコンセプトは面白いと思ったわ。ボビーと私のハーモニーは、自分でも素晴らしいと思ったの。それがこのアルバムを作った最大の理由なのよ。ハーモニーというのは本当に心地良い体験で、ある意味人間にとって最も原始的なコミュニケーション術だと思うのよ。ふたつの異なる振動がひとつになって、人と人とを結びつける感覚。とても心が温かになる感じがするし、強い力を持っていると思うの。言葉によるコミュニケーションを超えた、本当に原始的な感覚よ。最初のセッションから、2人で歌うのがスムーズにいって、2人の声を重ね合わせた時、本当に驚いたの。ボビーも、アンドリューも、私も、ジョニーも思わず全員で顔を見合わせてしまったわ。“これはアルバム1枚作れちゃうんじゃないの?”って(笑)。2人のハーモニーに無限の可能性を感じたのよ。
■あなた自身は、そうしたハーモニーを取り入れたフォークミュージックやカントリー・ソウルのような音楽には興味がありましたか?
JB:ええ、もちろん。サヴェージズの音楽も、ハーモニーを重視したサウンドを目指しているから。フォークというよりは、もっとリズムが強くてモノコードを使ったサウンドになっているけれどね。ずっとジャズを歌ってきたし、ハーモニーやメロディの美しい曲は大好きよ。私にはこういう歌い方もできるんだって、今回のプロジェクトが再確認させてくれたところもあるの。私にとっては大きな収穫だったわ。このアルバム以来、ちょこちょこ『Utopian Ashes』のときの歌い方を使うようになったから(笑)。
■今回のコラボレーションがあなた自身、またサヴェージズに影響を与えることはありそうでしょうか?
JB:サヴェージズ自体は残念ながらもう何年も活動を休止していて。また活動を再開する可能性はゼロではないんだけど、いまのところは何も今後のことは決まっていない感じなの。でも、ええ、サウンド的なこととは別として、ヴォーカル面では私のソロ・プロジェクトにかなり影響を与えることになると思うわ。歌い方のスタイルの、サヴェージズ時代には閉じていた扉を再び開けてくれたような気がするから。メロディの歌い方や豊潤なハーモニー、それにそうした歌い方への喜びみたいなものを取り戻すことができると思うの。
■新型コロナウイルス禍は、人びとの生活だけではなく、人間関係やリレーションシップの在り方についても大きな変化をもたらしたと思います。あなた自身、影響を受けた部分はありますか?
JB:もちろん、どのミュージシャンやアーティストにも言えることだと思うけれど、完全に私の音楽活動を停滞させてしまったわ。去年、パンデミックの最中にソロ・アルバムをリリースすることになってしまって。本当はアルバムを引っ提げてヨーロッパにツアーに行くはずだったし、アメリカをナイン・インチ・ネイルズと一緒に回る予定だったのに、大きなフェスティヴァルも全部キャンセルになってしまった。私の記念すべきソロ・アルバムが大きな犠牲を強いられた気分だったわ。世界中にファンを持つ安定した人気のポップ・バンドには、いつでも待っていてくれるファンがいるし、他の形でファンと交流する機会もあったと思うからさほど大きな影響はなかったかもしれないけれど、私の場合は、閉じ込められてしまった気分だったの。
でも、良い面ももたらしてくれたのよ。この1年間、フランス国外に出られないからずっとパリにいる必要があって。12年間ロンドンで暮らしていたから、どこにも行けない状況に最初はフラストレーションを感じていたわ。でも地元に戻ってきてみて、自分の周りは才能を持った人たちやインスピレーションの源で溢れているって気が付いたのよ。以前の私はそれに気付いていなかったと思う。それによってまた新しい扉が開かれたし、そのことについてはとても感謝しているの。クリエイティブワークにとって、私にとって大きなターニングポイントになったと思うわ。いまも新しい曲をどんどん書いているし、状況が好転したら、次のソロ・アルバムをリリースしてすぐにでもツアーに出たいわ。
■アルバムの話に戻りますが、タイトルの『Utopian Ashes』はこれ以上ないほど合ったタイトルだと思います。ボビーが決めたそうですが、このタイトルは気に入っていますか?
JB:そうなの。ボビーが提案したんだけど、他にもたくさんタイトルの候補があったのよ。テーマである「結婚生活の崩壊」や、破れた夢を的確に表すとても良いタイトルだと思うわ。そう、夢破れた後の余波というべきかしら。だって、ここで描かれているのははじまりではなく、終わりのその後、すべての出来事を通り過ぎて来たあとの後遺症のようなものだから。燃え尽きたあとに何が残っているのか、ここからどう立て直していくのか。“Utopia”という希望に満ちた言葉と、“Ashes”という破滅的な言葉とのコントラストがとても面白いと思った。ある意味、さっき話したような、歌詞の持つダークさとサウンドの持つポジティヴさとを的確に表現したタイトルじゃないかしら。
■このアルバムのライヴは朗読劇としても成立しそうですが、ライヴの予定は?
JB:わあ、賛成だわ! ボビーの書いた歌詞は、純粋に詩としても優れていると思っていたの。文字で読んでも、読み応えがあるし心情が伝わってくる。スタジオでも、ときどきボビーが大声で歌詞を読誦していたことがあって。私の耳元に囁いてくることもあったわ(笑)。そうやって、みんなが弾いているメロディを聴きながら、歌詞をぶつぶつ唱えることで、曲にぴったり合うようにアジャストしていたみたいなの。それからノートに書き留めて……というのを繰り返していたわ。歌詞のライティングには本当に細心の注意を払っていたと思うから、歌の歌詞というだけではなく、喋り言葉としても成立するかどうかについても細かく考えていたんじゃないかと思う。語彙力の豊かさやイメージの鮮やかな表現力も素晴らしいと思うから、ボビーはこのアルバムで、作詞家としての優れた才能についても遺憾なく発揮していると思うわ。
■サウンド面でも、共作していて思いもよらず、良い方向に向かった曲はありますか?
JB:パリのスタジオに入った当初は、一緒に曲を書き始めたの。それを彼がロンドンに持ち帰って、自分のパートを書いて、曲を綺麗に整えた感じなんだけど、最初はエレクトロニックだったりモノコードを使っていたりした曲も、最終的にはメロディを重視した、真の意味でのソングライティングの力を重視したものになったのね。それをボビーがまたパリに持って来てくれて、私が自分の歌のパートを吹き込んだという感じのプロセスだった。もちろん、一緒にスタジオでやってみて、少し変えた部分もあるけどね。レコーディング自体は本当に楽しかったし、とてもよい経験になったわ。新型コロナウィルスが流行る前にこのアルバムを作っておいて、本当に良かったなって思ってる(笑)。プレッシャーもストレスも心配もなくて、最高のレコーディングだった。ボビーもアンドリューもプライマル・スクリームのメンバーもジョニーもプロフェッショナルだから最高のプレイをしてくれたし、何の心配もなかったし、このアルバムは素晴らしいものになるっていう確信が最初からあったのよ、そう、これこそ“信頼”、信じる力なのよ(笑)!
■(笑)では最後に、あなたのこれからの活動プランを教えてください。
JB:いまは2枚目のソロアルバムの制作でスタジオに入っているところなの。それから今年2本のフランス映画に出て、状況が好転したらソロツアーに出て、このアルバムのライヴも11月くらいに出来たらいいね、っていう話をしているところだし……やることはたくさんあるけど、とにかく来年が今年より良い年になっていればそれでありがたいかしらね(笑)。