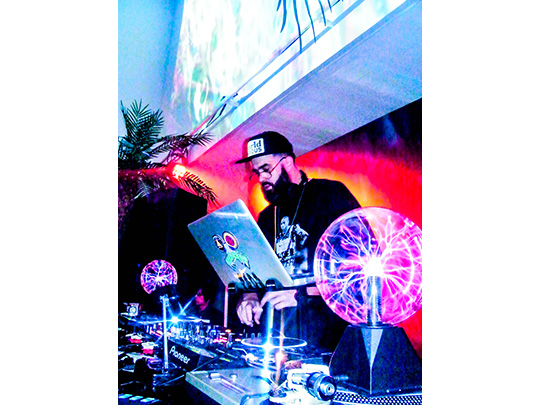2012年に設立されたアーティストコレクティブPROM。国内外のシーンの繋がりを目標に、東京を軸に様々な企画を手がけている。PROM主宰のパーティ「PROM NITE」ではこれまでにNEON INDIAN、LE1F、HEEMS (DAS RACIST)などのアーティストを召還。次の「PROM NITE」は8/2に代官山ユニットでLAのレーベル〈FADE TO MIND〉よりR&BシンガーKELELAとDJ、TOTAL FREEDOMを招いて開催決定。
■PROMオフィシャルWEB
https://www.tokyoprom.com
■ele-king内関連ページ
https://www.ele-king.net/interviews/003100/
https://www.ele-king.net/news/003201/
| Ynfynyt Scroll - Butch Queen (AiR DJ Remix) -#FEELINGS |
| Baauer - Harlem Shake (MikeQ x Jay R Neutron QB Remix) - Queen Beat |
| Rihanna - Diamonds (Dj Sliink Remix) |
| Destiny's CVNT - Nuclear (Cmore Edit by CUNT TR4XXX) |
| Tempa T - Next Hype (50 Carrot's A Day Keeps The Doctor Away Remix) |
| Bok Bok - Silo Pass - Night Slugs |
| Rabit - So Clean (Drippin' Remix) - #FEELINGS |
| Mike Jones feat. Slim Thug and Paul Wall - Still Tippin' - Swishahouse |
| Marcus Price & Carli - Flaska & Bas (Ben Aqua Remix) - #FEELINGS |
| Rizzla - Church - Fade To Mind |
| Fatima Al Qadiri - Hip Hop Spa (Nguzunguzu Remix) - UNO NYC |
| Usher - There goes my baby (Chopped & Screwed by Dj Michael 5000 Watts & Swishahouse) - Swishahouse |
| Hint - Lock The Door (feat. Zed Bias) - Tru Thoughts Records |
| Lil Silva - Venture - White Label |
| French Fries - Space & Smoke (Justin Martin Remix) - DIRTYBIRD |
| Jam City - Her - Night Slugs |
| Tony Quattro & Doctor Jeep - Forth & Seek (feat B. Ames) - Trouble & Bass Recordings |
| KW Griff - Bring in the Katz (feat. Pork Chop) - Night Slugs |
| Cakes Da Killa - Rapid Fire (feat. Dai Burger) - DTM Records |
 ■街のものがたり
■街のものがたり