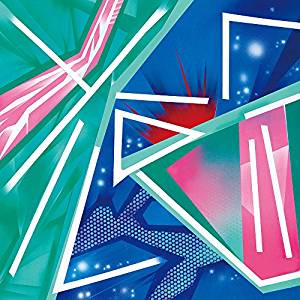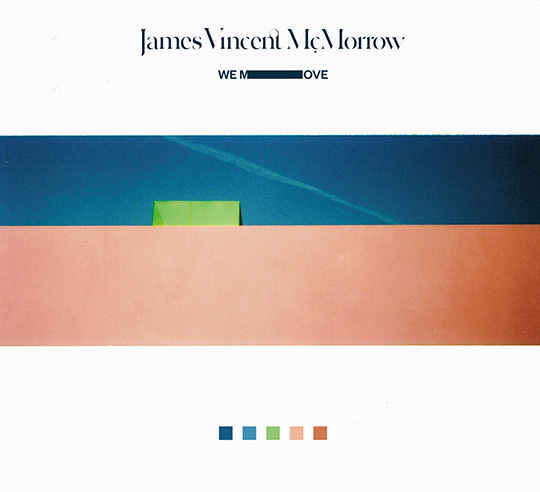Current top 9
 |
Thundercat - A Fan's Mail (Tron Song Suite II) https://www.youtube.com/watch?v=g8f5CtP0nT4 プロデュースはケンドリック・ラマーも所属しているクルー、TDEのプロデューサー「Sounwave」。ケンドリック諸作を聞いていて必ずと言っていい程毎回参加している彼なんですが、常にものすごく質の高いトラックを持って来ていてホントに尊敬しますし、聞いていて「なんだか品があるな」と毎度思います。マニアックな話ですが、サンプリングに”Mountain - Long Red”を使っているのに、トラックがここまでおとなしくなったのが興味深いです。ところで、この間のThundercat来日公演も見に行きましたが、今書いたような「作り込み」とはさらに違った「ライブ/生演奏の良さ」を120%体感できました。ミャウミャウ~ |
|---|---|
 |
Madlib - Shades of Blue https://www.youtube.com/watch?v=apN0AXjJxQE 自分の心の中でとても大きな存在として常に光り輝くアルバムです。最近初期衝動ってなんだっただろうなと思っていろいろ聞き返していて思い当たりました。自分のジャズ観っていうものの根源な気が。ここ数年Brainfeeder等を筆頭に電子音楽にジャズを取り入れる気風があると思うのですが、個人的にはMadlibがこのアルバム以降にやっていた”Yesterdays New Quintet”の存在が大きいのではないか、と推測します。(だったらファンとしては最高~) |
 |
Gold Panda - In My Car https://www.youtube.com/watch?v=MQlAqZvFsbs 昨年の話ですが、Gold Pandaの来日公演が京都でもありまして、その時に自分も出演していました。その時にライブを見てそのライブの良さに今までに無いくらい、大きな感銘を受けました。パッと見ただけではなにか特別なことをしている風には見えなかったのですが、「なにか特別なことが起きている」ということはその場にいてひしひしと感じました。アルバム自体とても素朴なのですが、田舎っぽくなくかっこよくて、味わい深さみたいなものを感じました。決して多くは語らないけど、静かな説得力があり、そこに対して本当に感動しました。(これ書いた後インタビュー読みましたが、めっちゃ大事な良い事言ってました: https://www.ele-king.net/interviews/005159/) |
 |
Group Home - Supa Star https://www.youtube.com/watch?v=OC_aFkfFpSY DJ Premierはかつて教科書のごとく聞いていたトラックメイカーなので思い入れがあるのですが。非ミュージシャンがミュージシャンの演奏し記録した媒体からサンプリングする時にどこを切り取るのか、ということが非常に顕著にわかりやすく現れている例だと思います。プリモは「このレコードのこの1秒間のとこの音。これ!ヤバいやろ」の感覚にとにかく長けている人だと思うので、完成されたトラックというのはミニマルの極み、みたいな構成が多いです、不必要なもの(音)を全て捨てているその決断力は本当にすがすがしいものであります。 |
 |
Cameo - Hangin' Downtown https://www.youtube.com/watch?v=aMvHUkgpnkg 一つ前のGroup Homeの項目で書いた曲のサンプリング元ネタです。これを聞いてもらえば、一体どこをサンプリング&フリップしたか分かると思います(イントロの十数秒のギターとシンセ)。元ネタの曲をアレンジした人たちは、一体どういう思いでその演奏/アレンジにしたのか?みたいなことをいつも勝手に考えたりします。両方の曲が出現すると、聞いているぼくたちはその2つの視点を持つことができます、それってとてもおもしろいことだと思うのです。あと、録音状況等(テープに録音した、とか、スタジオのコンソールが良かった/雑だったとか)も「ヤバさ」につながっていると思うので、その一音にフォーカスするということがどれだけおもしろいかということに改めて気付かされました。 |
 |
坂本龍一 - ZURE https://vimeo.com/212928217 上に書いたような一音一音、ということについて意識的に取り組んだのが坂本氏の最新作「async」だったと思います。僕が選んだこのトラックは再生した瞬間の「うわっ…シンセっぽいシンセの音だ!!ヒョー!」と盛り上がりましたが、よくよく聞いてみるとそれは「音楽」というよりも一つの「音」としてとらえられている意味合いが強く、過去にシンセサイザーの名器「Prophet-5」を「音楽」的にバリバリ使っていた人が作っている、というのを踏まえて聞くとさらに興味深いです。アルバムを通してはっきりとしたメロディやドラムがないですが、僕にはとてもポップに聞こえましたし、人を拒絶しないアルバムだなという感想を持ちました。はい、えらそうなこと言うてすんません。 |
 |
Throbbing Gristle - Persuasion https://www.youtube.com/watch?v=2HMtJWzx6xk 最近彼らのアルバム「20 Jazz Funk Greats」がリマスターで再発されて話題にあがっていたので、教えてもらい知りました。これがとある曲でサンプリングされているのも知れました(Jailib - The Heist)。こういう音楽をなんて言ったらわかりませんけど「ヘンな音楽」っていうのはなぜか強烈に好きです。それが自然になされているのか計算し尽くされて成り立っていようとも、定型にハマらない、っていうのは現代において大事だと思います。 |
 |
HIS - 日本の人 https://itun.es/jp/Lrx8Q?i=720467954 細野晴臣氏、忌野清志郎氏、坂本冬美氏によるスペシャルユニットHISによるアルバム「日本の人」より、タイトルトラックの「日本の人」。なんででしょうか、、清志郎氏の歌詞が強烈に体にすっと入ってきました…あと、坂本冬美さんの歌声のすばらしさにも気付かされました。こんなに説得力がある歌い方は一体何なのでしょうか。元は細野さんが作った曲の改変らしく、すこし聞こえてくるTR-808のドラムマシンっぽい音も最高です。大好きな一曲になりました。 |
 |
山口百恵 - いい日旅立ち https://www.youtube.com/watch?v=V9pyrALvcNQ 去年、よく新幹線に乗っていたのですが、車内で何度も聞くジングル(到着メロディ?)で心を離さなかったのがこの曲です。子供の時によくテレビからJRのCMにで流れていたから印象深いのでしょうかね。で、その車内のバージョンの、キーボードで作ったであろう人工的な鉄琴っぽい打ち込みの音はどんなに眠くても、「ハッ。。。降りねば!」と反応してします(それがもうすぐ駅であるという刷り込みなだけかもしれませんが)。ある種の音の鳴らし方が人間をドキッとさせたり、ビックリさせたりっていうことは曲を作っていてとても参考になります、もちろんですけど、山口百恵さんのオリジナルバージョンがすばらしいです。 |