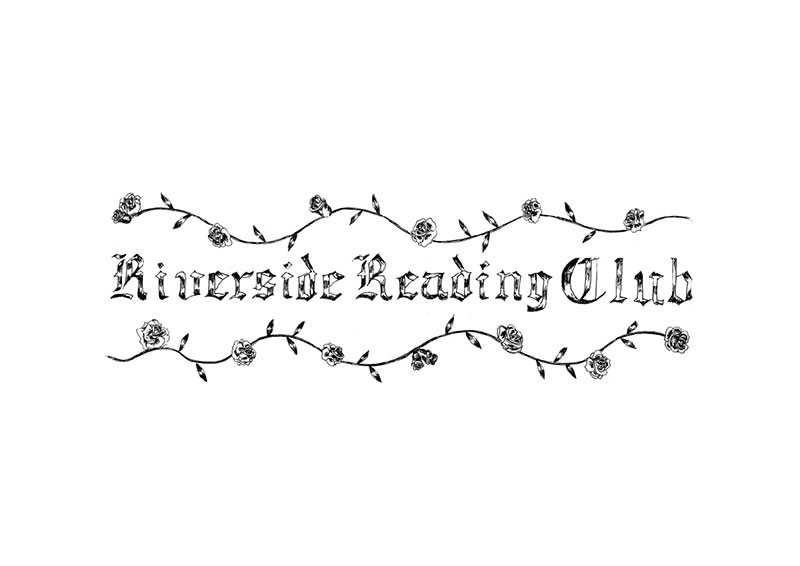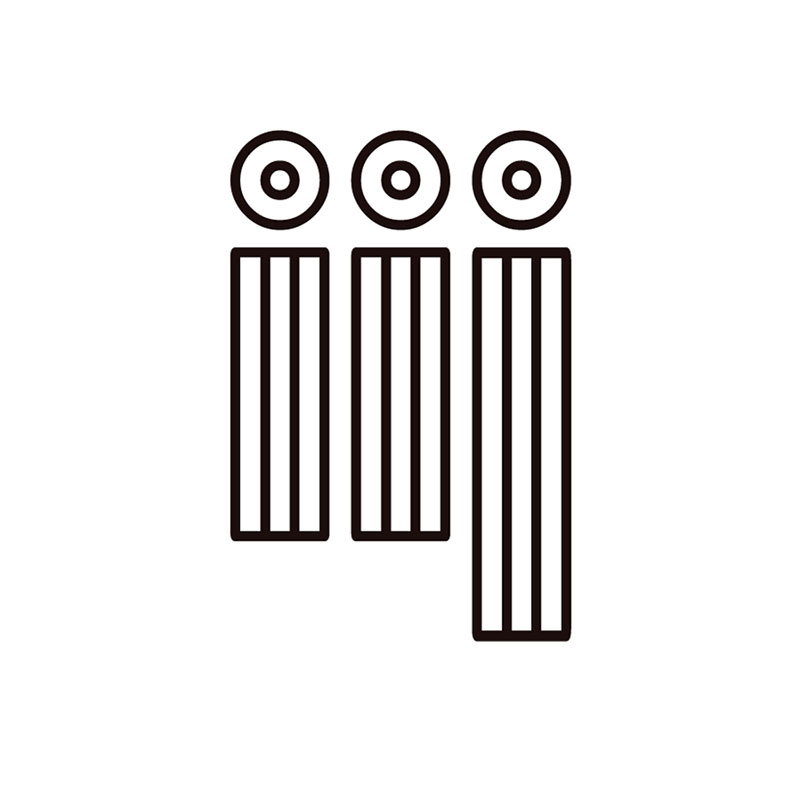シカゴのオルタナ・ラテン・バンド、ドス・サントスの一員でもあるパナマ出身のドラマー/パーカッショニスト、ダニエル・ ヴィジャレアルが初のソロ・アルバムを発売する。シカゴの新たなキーパーソンになっているという彼のアルバムには、ジェフ・パーカーら当地の面々とLAのミュージシャンたちが参加。ラテンのリズムを活かした極上のグルーヴを堪能したい。

ダニエル・ビジャレアル(Daniel Villarreal)
『パナマ77(Panama77)』
発売日:【CD】2022/5/25
大注目!! シカゴのオルタナ・ラテン・ジャズバンド、Dos Santos(ドス・サントス)のメンバーで知られるパナマ出身ドラマー/パーカッショニスト Daniel Villarreal(ダニエル・ ビジャレアル)が待望のソロアルバムを完成させた。ラテンのリズムに導かれるグルーヴ溢れるサウンドは必聴。日本限定盤ハイレゾMQA対応仕様のCDでリリース!! ジェフ・パーカー参加!!
Recorded in Chicago and Los Angeles featuring:
Daniel Villarreal - drums & percussion,
Elliot Bergman - baritone saxophone & kalimba,
Bardo Martinez - bass guitar & synthesizers,
Jeff Parker - guitar,
Kellen Harrison - bass guitar,
Marta Sofia Honer - violin & viola,
Kyle Davis - rhodes piano & synthesizers,
Anna Butterss - double bass & bass guitar,
Aquiles Navarro - trumpet,
Nathan Karagianis - guitar,
Gordon Walters - bass guitar,
Cole DeGenova - farfisa & hammond organs
ダニエル・ビジャレアルは、現在のシカゴのシーンを支える最重要ドラマー/パーカッショニストだ。パナマ出身で、異色のラテン・バンド、ドス・サントスのメンバーであり、DJでもある。ジェフ・パーカーら、シカゴとLAのミュージシャンたちと共に、ラテンのリズムを掘り下げて最上のグルーヴとドリーミーなサウンドスケープに包まれる、真に融和的な音楽を作り上げた。(原 雅明 rings プロデューサー)
アルバムからの先行曲 “Uncanny (Official Video)” のMVが公開されました!
https://www.youtube.com/watch?v=JNUaLAYPURM
アーティスト:Daniel Villarreal(ダニエル・ビジャレアル)
タイトル:Panama77(パナマ77)
発売日:2022/5/25
価格:2,600円+税
レーベル:rings / International Anthem
品番:RINC87
フォーマット:CD(MQA-CD/ボーナストラック収録予定)
* MQA-CDとは?
通常のCDプレーヤーで再生できるCDでありながら、MQAフォーマット対応機器で再生することにより、元となっているマスター・クオリティの音源により近い音をお楽しみいただけるCDです。
Official HP:https://www.ringstokyo.com/danielvillarreal