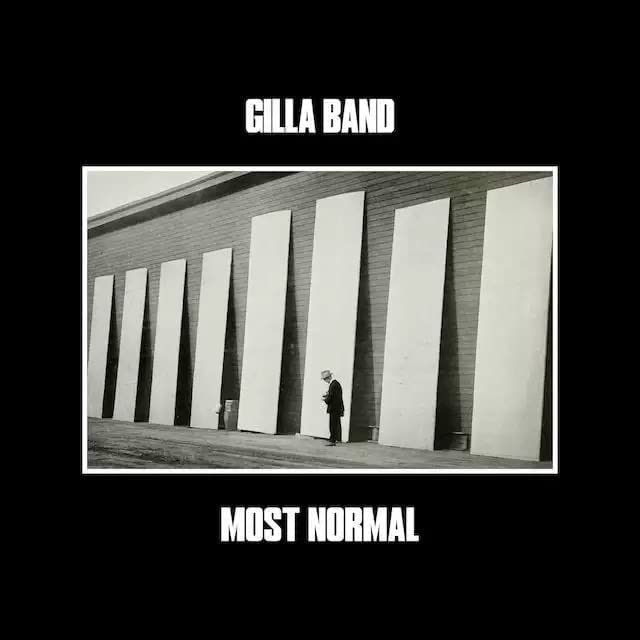去る4月末から1か月半にわたって欧州をツアー中のBoris。今週末マドリードのプリマヴェーラ・サウンドにて掉尾を飾る彼らだが、新たなニュースが届いている。
Borisのキャリアにおいて重要な1枚に位置づけられる2002年の『Heavy Rocks』が、なんとジャック・ホワイト主宰のレーベル〈Third Man Records〉(最近はジーナ・バーチもリリース)よりリイシューされることになった。
またこの再発を記念し、8月から10月にかけ、USオルタナの雄メルヴィンズとのダブル・ヘッドライナーとなるUSツアーも決定している。結成30年を超えて突き進むBoris、依然とどまるところを知らないようだ。

Boris 2002年の名作『Heavy Rocks』がThird Man Recordsからアナログ再発決定!MELVINSとの合同ツアーも開催!
Borisが2002年に発表した『Heavy Rocks』のオリジナル・リリースはBorisの本拠地である日本国内のみで流通し、世界中のリスナーが長らくこのアルバムのフィジカル・コピーを熱望していた。リリース当時、レコードのプレス作業中に工場で火災が発生しスタンパーが消失。そのためアルバムは何年もの間入手不可能となり、世界的なカルト・クラシックとなっていた。
Third Man Recordsから再発は8月18日にデジタル・リリース、9月8日にCDと2枚組LPで発売となる。
またこのリリースを記念し世界のヘヴィー・ロックを共に牽引してきた盟友であるMELVINSとの合同ツアーが開催される。
Borisは『Heavy Rocks』をMELVINSは『BULLHEAD』と共にそのキャリアの重要作を再現する。

Boris + Melvins, on tour:
August 24 Los Angeles, CA @ Belasco Theater
August 25 Pomona, CA @ Glass House
August 26 Fresno, CA @ Strummer’s
August 27 San Francisco, CA @ Great American Music Hall
August 28 San Francisco, CA @ Great American Music Hall
August 29 Petaluma, CA @ Mystic Theatre
August 31 Portland, OR @ Roseland Theater
September 1 Seattle, WA @ The Showbox
September 2 Spokane, WA @ Knitting Factory
September 3 Bozeman, MT @ The ELM
September 5 Fargo, ND @ The Hall at Fargo Brewing Company
September 6 Minneapolis, MN @ Varsity Theater
September 7 Milwaukee, WI @ The Rave II
September 8 Chicago, IL @ The Metro
September 9 St. Louis, MO @ Red Flag
September 11 Indianapolis, IN @ The Vogue
September 12 Grand Rapids, MI @ Pyramid Scheme
September 13 Detroit, MI @ St. Andrews Hall
September 14 Cleveland, OH @ Beachland Ballroom & Tavern
September 15 Pittsburgh, PA @ Roxian
September 16 Maspeth, NY @ DesertFest NYC
September 18 Albany, NY @ Empire Live
September 19 Boston, MA @ Paradise Rock Club
September 20 Bethlehem, PA @ MusicFest Cafe
September 21 Philadelphia, PA @ Brooklyn Bowl Philadelphia
September 22 Washington, DC @ The Howard Theatre
September 23 Virginia Beach, VA @ Elevation 27
September 24 Carrboro, NC @ Cat’s Cradle
September 26 Nashville, TN @ Brooklyn Bowl Nashville
September 27 Atlanta, GA @ Variety Playhouse
September 28 Savannah, GA @ District Live
September 29 Birmingham, AL @ Saturn
September 30 New Orleans, LA @ Tipitina’s
October 2 Houston, TX @ Warehouse Live - Studio
October 3 Austin, TX @ Mohawk
October 4 Dallas, TX @ Granada Theater
October 5 Oklahoma City, OK @ Beer City Music Hall
October 6 Tulsa, OK @ Cain’s Ballroom
October 7 Lawrence, KS @ The Bottleneck
October 9 Denver, CO @ Summit
October 11 Albuquerque, NM @ Sunshine Theater
October 13 Tempe, AZ @ Marquee Theatre
October 14 San Diego, CA @ House of Blues