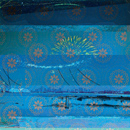Shop Chart
 1 |
THEO PARRISH
Sketches
SOUND SIGNATURE / US
»COMMENT GET MUSIC
|
 2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
 3 |
RYOSUKE & KABUTO
Paste Of Time Vol.2
JPN / CD
»COMMENT GET MUSIC
|
 4 |
|||
 5 |
 6 |
V.A.(BABY FORD,MARGARET DYGAS,FUMIYA TANAKA...)
Superlongevity 5
PERLON / JPN
»COMMENT GET MUSIC
|
|||
 7 |
MOODYMANN / ムーディーマン
Forevernevermore (国内仕様盤)
PEACEFROG / JPN
»COMMENT GET MUSIC
|
 8 |
|||
 9 |
 10 |





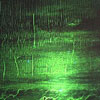






 ノー・ウェイヴ、フリージャズ、ノイズ、ポスト・ミニマリズム、電子音楽、即興演奏等の広大な領域を大胆に横断しながら、肉体的な意味でも精神的な意味でも過激に限界へと挑戦するサウンドが非常に高く評価されている。既存の楽器マニピュレートの域を拡張するユニークな演奏テクニックと、ほとんどテレパシーのようなバンドの呼吸によるコミュニケーションに裏付けられたライヴの強烈さによって叩き出されるその音は、たとえばかつてBattlesの音楽を形容する際に用いられた、「数学と暴力の融合」の発展型にして緻密にリズムを微分するフレーズと限界まで緊張感を高める暴虐性の混交であり、また例えばそれは、ライヒの執拗な反復とフリージャズの覚醒をハードコアへと織り交ぜた激烈なアップデートである。
ノー・ウェイヴ、フリージャズ、ノイズ、ポスト・ミニマリズム、電子音楽、即興演奏等の広大な領域を大胆に横断しながら、肉体的な意味でも精神的な意味でも過激に限界へと挑戦するサウンドが非常に高く評価されている。既存の楽器マニピュレートの域を拡張するユニークな演奏テクニックと、ほとんどテレパシーのようなバンドの呼吸によるコミュニケーションに裏付けられたライヴの強烈さによって叩き出されるその音は、たとえばかつてBattlesの音楽を形容する際に用いられた、「数学と暴力の融合」の発展型にして緻密にリズムを微分するフレーズと限界まで緊張感を高める暴虐性の混交であり、また例えばそれは、ライヒの執拗な反復とフリージャズの覚醒をハードコアへと織り交ぜた激烈なアップデートである。