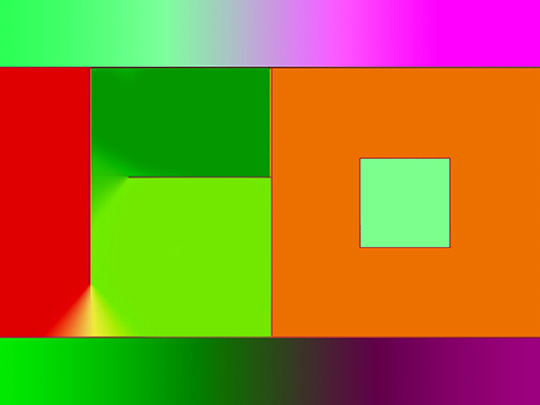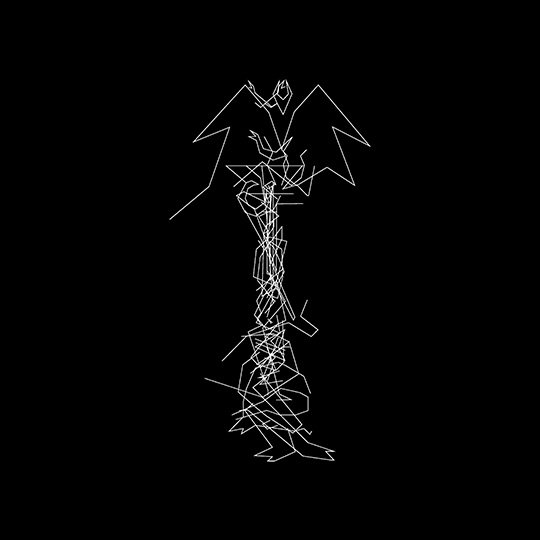これは嬉しいプレゼントです。UKを代表するIDMのベテラン・デュオ、プラッドがフリー・シングル「Bet Nat」をリリースしました。今回のリリースは1月18日よりはじまったかれらの北米ツアーを記念したもので、“Bet”と“Nat”の2曲が公開されています。どちらも無料でダウンロードすることが可能。ダウンロードはこちらから。
PLAID & THE BEE US TOUR DATES 2017
Tickets available at plaid.co.uk
JANUARY
18 – Washington, DC @ U Street Music Hall
19 – Cambridge, MA @ The Sinclair
20 – Montreal, QC @ Fairmount Theater
22 – Philadelphia, PA @ Underground Arts
25 – Toronto, ON @ Velvet Underground
26 – Chicago, IL @ Lincoln Hall
27 – Brooklyn, NY @ Music Hall of Williamsburg
28 – Denver, CO @ Larimer Lounge
31 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom
FEBRUARY
02 – Portland, OR @ Holoscene
03 – San Francisco, CA @ The Independent
04 – Austin, TX @ Empire Garage