ゴミがなくなった。道ばたに紙くずやポリ袋、空き缶やタバコの吸い殻なんかが転がっているのは、10年くらい前まではごくありふれた光景だったはずだけど、最近では街を歩いていてもめっきりゴミを見かけなくなってしまった。滅菌、滅菌、とにかく滅菌。汚いものは視界から全力で一掃。どうやら上層部には人間の痕跡を抹消したくてしかたのない連中が少なからず陣取っているらしい。
伊達伯欣との Illuha で知られるコリー・フラー、彼の〈12k〉からは初となるソロ・アルバムは汚れに満ちている。それはまずアナログ機材に由来する独特のラフな質感に体現されているが、エレクトロニック・ミュージックの作り手でありながらそれほどテッキーでないところは彼の大きな持ち味だろう(元ドラマーである彼は、じっとしたままPCをいじくりまわすよりも、じっさいに身体を動かして機材を操るほうが好きなんだとか)。
冒頭の“Seiche”は「Adrift」「Asunder」「Aground」という三つのパートに分かれている。弦とピアノの間隙に吐息が乱入する序盤、ティム・ヘッカー的な寂寥を演出するノイズの波がメロディアスなシンセの反復を呼び込む中盤、密やかな具体音と重層的なドローンとの協奏を経て穏やかなハーモニーが全体を包み込む終盤──アルバムのあちこちで繰り広げられる種々の試みを一所に集約したようなこの曲は、本作の顔とも呼ぶべきトラックだ。
このアルバムの魅力のひとつは間違いなくそのあまりに美しい旋律にある。Illuha がどちらかといえばフィールド・レコーディングを駆使し、その編集作業に多くの時間を投入するプロジェクトであるのにたいし、コリーは今回のソロ・アルバムの制作にあたってメロディとハーモニー、つまりはコンポジションのほうを強く意識したのだという。その成果は2曲目の“Lamentation”にもっともよく表れていて、出だしのピアノの音を聴いたリスナーはもうそれだけで泣き崩れそうになってしまうことだろう。“Look Into The Heart Of Light, The Silence”のピアノも麗しいが、これらのコンポジションにはもしかしたら『Perpetual』で共演した坂本龍一からの影響が落とし込まれているのかもしれない。いずれにせよ重要なのは、それら美しい旋律を奏でるピアノの音が絶妙に濁っていたり具体音を伴っていたりする点だ。
濁りということにかんしていえば、アイスランド語のタイトルを持つ“Illvi∂ri”がもっとも印象的である。この曲に聞かれるノイズは、コリーがじっさいにアイスランドで遭遇した出来事の結晶化で、深夜に強烈な暴風雨に見舞われた彼はすぐさまレコーダーを回し、風が窓を叩く音を伴奏に、その場にあった楽器で演奏をはじめたのだという。ピアノよりもそのノイズのほうに耳が行くこの曲の造形は、彼がダーティなものに目を向けさせようと奮闘していることの証左だろう。それは彼がアルバム中もっとも具体音にスポットライトの当たる最終曲に“A Handful Of Dust(ひと握りのほこり)”という題を与えていることからも窺える。
汚れたもの、濁ったもの、それは壊れたものでもある。決定的なのは“A Hymn For The Broken”だ。タイトルにあるようにどこか聖歌的なムードを携えたこの曲は、「壊れたもの」にたいする慈愛に満ちあふれている。英語の「break」にはさまざまな意味があって、ひとつはもちろん「壊す」とか「壊れる」ということだけれど、その言葉は「breaking wave(砕波)」のように「波」という言葉と結びついたり、「dawn breaks(夜が明ける)」のように光が差し込むイメージと関連したりもする。コリーいわく、それこそがこの『Break』というアルバムのテーマなのだそうだ。ザ・ブロークン、ようするにそれは壊れそうになったり溺れそうになったりしながらも必死にもがいて光を索める、われわれ人間の姿そのものなのだろう。
このアルバムはあまりに美しいメロディとハーモニーに彩られている。だからこそわれわれリスナーはその音の濁りやノイズにこそ誠実に耳を傾けたくなる。だって、汚れていることもまた人間のたいせつな一側面なのだから。

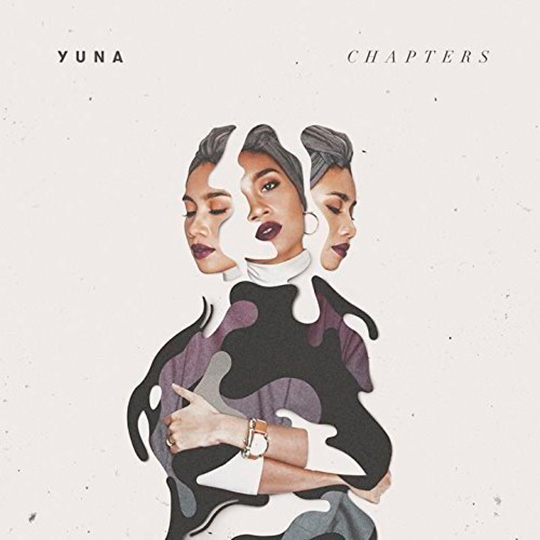








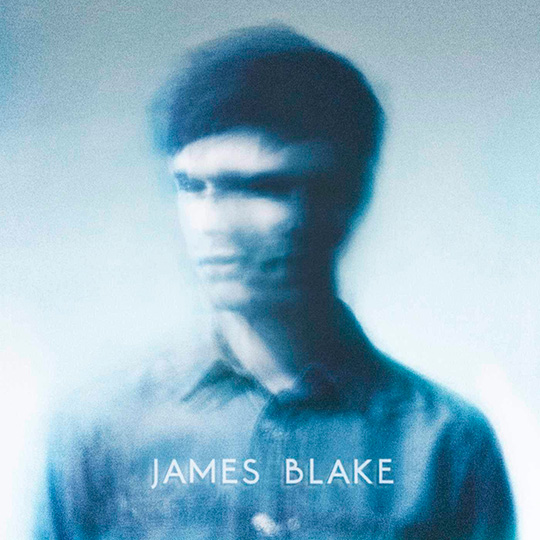




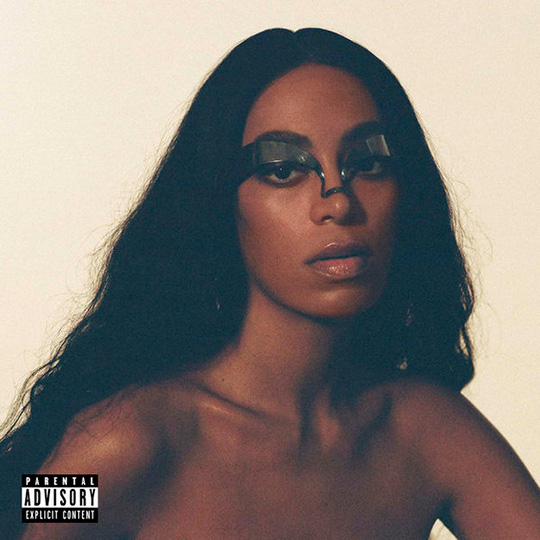

 この時期発掘したCDで、従来の批評的価値の向こう側からやってきた究極の盤は、上述のTBS『アトロク』でも紹介し反響があった、100円ショップダイソーが(おそらく2002年前後)にオリジナルで作成して自社店頭で販売していた〈100円アンビエント〉のCD『アンビエント・リラクゼーション VOL.2』です。当時ダイソーは(今でも一部店舗で展開していますが)、クラシック名曲や落語などを手軽に編んだCDを大量にリリースしていたのですが、その一環として、なんとオリジナルのアンビエント・ミュージックも制作していました。(同シリーズではこのvol.2を含め計2枚リリースされていたよう。好事家によると、vol.1の方はアンビエント的にはたいしたことないらしいけれど…)。
この時期発掘したCDで、従来の批評的価値の向こう側からやってきた究極の盤は、上述のTBS『アトロク』でも紹介し反響があった、100円ショップダイソーが(おそらく2002年前後)にオリジナルで作成して自社店頭で販売していた〈100円アンビエント〉のCD『アンビエント・リラクゼーション VOL.2』です。当時ダイソーは(今でも一部店舗で展開していますが)、クラシック名曲や落語などを手軽に編んだCDを大量にリリースしていたのですが、その一環として、なんとオリジナルのアンビエント・ミュージックも制作していました。(同シリーズではこのvol.2を含め計2枚リリースされていたよう。好事家によると、vol.1の方はアンビエント的にはたいしたことないらしいけれど…)。









