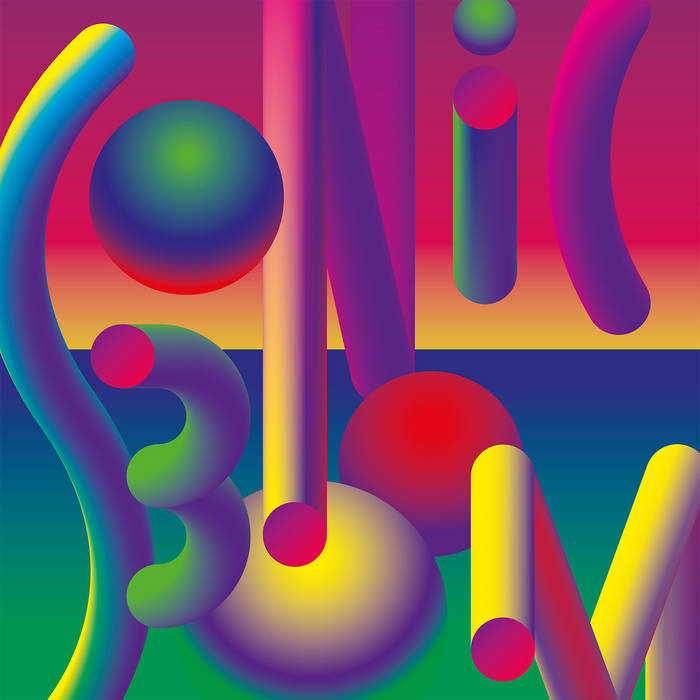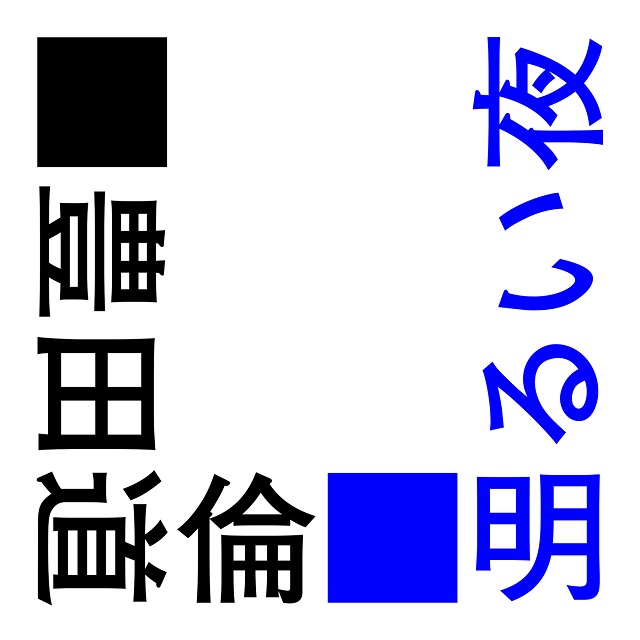ソニック・ブーム。
スペースメン3のふたりのファウンダーのうちのひとりである。イギリスのサイケデリック・バンド、スペースメン3はわずか10年に満たない活動期間(1982年~1991年)の間は一部の熱狂的なファン以外にはあまり知られることはなかったが、特にここ日本でスペースメン3の受容史はまあ、お寒いのひとことではあった。来日公演はもちろん一度もなかったし、そのアルバムがリアルタイムで発売されたのはほとんどバンドが解散状態にあった1991年の4作目にしてラスト・アルバムとなった『Recurring(回帰)』のみというぐあいである。
しかし、実はこの『Recurring』以前にスペースメン3関連のアルバムがひっそりと日本でも発売されていた。それがソニック・ブームのファースト・ソロ・アルバム『Spectrum』だ。
ストーン・ローゼズがデビュー・アルバムを発表し、一躍話題となった〈Silvertone Records〉から1990年にリリースされたソニック・ブームのソロ・アルバムは、ストーン・ローゼズ人気のおかげでまさかの国内盤発売が実現したのである。それがどのくらい売れたのかはまあ、あまり書かないほうがいいだろう。当時の音楽誌などで大きく取り上げられることはなかったし、そもそもそんなに大量に売れるような内容でもなかったのは確かだが。ちなみに国内盤の帯に書かれたキャッチコピーはこうだった。
「ほとんど犯罪的な覚醒サイケ~SPACEMEN3のソニック・ブームによる別プロジェクトアルバム」
「犯罪的な」とまで書かれてしまったこのアルバムは、しかし例えばソニック・ブームを知らない人が「お、ストーン・ローゼズのアルバム出したレーベル? じゃ買ってみようかな」とか言って手を出してはいけないブツだったということは間違いなく言える。
その後、ソニック・ブームはソロ名義ではなく、ソロ・アルバムのタイトルであった Spectrum をユニット名として、同じ〈Silvertone〉からアルバム『SOUL KISS (Glide Divine)』を1992年にリリース。以後はこの Spectrum と、より実験的なユニットとして Experimental Audio Research (E.A.R.)のふたつの名前で活動していくことになる。
近年はメジャーの MGMT のプロデュースなども手掛けるようになった反面、自身の音源のリリースは減っていたのだったが、2020年になって突然ソニック・ブームがアルバムを出すというニュースが舞い込んできた。しかも、それは Spectrum 名義でもなく、E.A.R. 名義でもなく、ソニック・ブーム名義による30年ぶりのソロ・アルバムだというのだからさらに驚きは倍増なのだが、やっと届いた音を聴くとさらに驚きが待っていた。なんだこの明るい曲調は? スペースメン3のラスト・アルバム冒頭のダンス・チューン “Big City” をテンポダウンさせたようなオープニング・トラック “Just Imagine” からやたら多幸感に溢れている。アルバムを貫くオプティミスティックなムードにちょっと戸惑いながら、いまは南欧のポルトガルにいるというソニック・ブームと Skype でつながった。
※本インタヴューは、『All Things Being Equal』のライナーノーツに掲載されているインタヴューと同じタイミングで収録されたものです。両方合わせて読むと、より新作の全貌に迫れます。
分業したほうがいいなんてのは現代の神話みたいなものだと思うよ。ときにはうまいこと分業するというのも必要かもしれないけど、全体を見渡す視点を持つことが大切だと思う。音楽だけじゃなく他のアートも含めてね。
■1990年に〈Silvertone Records〉からリリースした『Spectrum』以来、実に30年ぶりのソニック・ブーム名義のソロ・アルバムということになります。そのアルバムをリリースした後はその名義をご自身の音源制作では使わず、Spectrum、Experimental Audio Research(E.A.R.)というふたつの名義で制作を始めることになったのはどういう理由だったのでしょうか?
ソニック・ブーム(以下、SB):「ソニック・ブーム」は自分ひとりのソロで活動するときに使う名前で、「Spectrum」は他のアーティストやソングライターとバンド形式で曲や歌をメインに活動する名前。「E.A.R.」として作る音楽は楽曲に重きを置くのではなく、サウンドを重視したものにしているんだ。この3つの名前を使いわけることにした主な理由は、区別をつけるためだ。自分だけで作ったソロの作品ではないのに自分の名前をつけるようなことはしたくなかったんだ。そういうのはグループとしての作品であるべきだと思う。もしグループではなくて自分ひとりで作ったのであれば、もちろん自分の名前を使うよ。Spectrumのアルバムは1曲につき最低でもひとりは他のアーティストと一緒に作っていた。当然彼らは楽器を弾いたりするわけでね。そう、Spectrum はコラボレーション・ユニットなんだ。
■Spectrum と E.A.R. というふたつのユニットを使い分けていくなかで、自分のなかでこれらのユニットに対する態度に変化はありましたか? もしかすると、今回のアルバム・タイトル「All Things Being Equal」という言葉が、Spectrum と E.A.R. の境界線が曖昧、というか融合していくということを表しているのかなとも思ったりしますが……。
SB:確かにその境界線というのは曖昧なものではある。名義というものは、最終的に作品をどのようなものにするのかを考えるときに僕が決めなきゃいけないことのうちのひとつなんだ。Spectrum と E.A.R. も自分のなかで区別はつけてはいるけど、本質的にはすべて僕の音楽活動だし、劇的に違ったことをしようとはしていないよ。それぞれのプロジェクトで違うことをしようというよりも、いつもアルバムごとに違ったことをしてみようとしている。だから今回のアルバムもどのようなものにするか、しっかりとした意識的な決定をしたんだ。シンプルな電子音響を核として、そこにパーカッションやヴォーカルを重ねることでよりその要素を際だたせようってね。この作品は俺ひとりで作ることになるだろうとずっと思っていたし、スペースメン3のレコーディングでもよく使っていたようにドラムマシーンを使うだろうなってこともわかっていたんだ。よく言われるんだけど、「ソニック・ブームは元スペースメン3であり、Spectrum よりも世間で認知されている」っていう言葉を信じたほうがいいなっていう気もしたんだ。ただ、それぞれの活動というのは確実にお互いに影響は及ぼし合っているよ。アートワークやビデオといったものから楽曲制作のプロダクションやマスタリングまでね。 それぞれに対して過度に特化していくということは全然信じていない。分業したほうがいいなんてのは現代の神話みたいなものだと思うよ。ときにはうまいこと分業するというのも必要なのかもしれないけど、全体を見渡す視点を持つことが大切だと思う。音楽だけじゃなくて他のアートも含めてね。僕はいつもあるひとつの媒体から学んだことを別の媒体に取り入れたいと思ってる。すべてのものごとは相互に影響をおよぼしあってると思う。そういうのが僕は好きなんだ。
■あなたは2016年に E.A.R. 名義で今回の新作と同じタイトルの「All Things Being Equal」というシングルをリリースしていましたね。このシングル曲は16分にも及ぶ長いインストゥルメンタル・ナンバーです。このシングルが、今回のこのアルバム制作に直接つながっていったのでしょうか?
SB:シングルがアルバムにつながっているかということについてはイエスでもあるしノーでもある。シングルで使った楽器はとても古い CASIO のキーボードなんだけど、アルバムに入っている別の曲でもそれは使っている。でもこのシングルを作ったときにはまだこのアルバムは見えていなかったんだ。そもそも E.A.R. 名義で出したのはアブストラクトなインストゥルメンタルだったからさ。その後この曲をいろいろと弄って、60年代後期か70年代の初めにコンピューターで生成された歌詞をつけて、日本盤にボーナストラックとして収録されるときにタイトルを「Almost Nothing Is Nearly Enough」に変えた。アルバムのタイトルと混同してほしくなかったからね。でも「All Things Being Equal」というタイトルは気に入っていたし、シングルの12インチはかなりレアになっていることもあるから、アルバムのタイトルとしてこれを使ったんだ。アルバムに収録されていない曲のタイトルをアルバム・タイトルにするっていう変な伝統があるんだよね。たとえば Gun Club のデビュー・アルバム『Fire of Love』には “Fire of Love” という曲は入っていない。同様にスペースメン3のデビュー・アルバム『Sound of Confusion』にも “Sound of Confusion” という曲は入っていない(笑)。どんな理由であれ、アルバムに入ることのできなかった曲の名前がアルバム・タイトルになることによってその評価を保ち続けるっていうのはおもしろいと思うんだ。
■そういえばジーザス&メリーチェインのデビュー・アルバム『Psycho Candy』にも同タイトルの曲は入っていませんでしたね(笑)。さて、今回30年ぶりのソロ・アルバムを出すにあたり、ソニック・ブームという個人名義を再度使った理由は?
SB:まずはこの名前をあのクソみたいな SEGA のキャラクターから取り返さなきゃいけなかった。奴が僕の名前を盗んだんだよ! 奴はもともと Sonic The Hedgehog って名前だっただろ。僕は奴が Sonic The Hedgehog だったずっと前からソニック・ブームだった。なのに突然奴は名前をソニック・ブームに変えたんだ。だから僕は立ち上がって僕の名前を守らなきゃって感じだった。
僕がその名前を使うと決めたときは誰もそんな名前を欲しがってなかったよ。すごくいい名前だねっていろんな人が言ってくれた。ソニック・ブームは形を持たないところがすごく好きなんだ。存在していてもそれに手を伸ばして触ったり、家に持って帰ったり、食べたりすることはできないだろう? もしかしたら食べることはできるかもしれないけど(笑)。
とは言っても、特に30年ぶりにこの名前を使うことにしたものすごく強い動機みたいなものは実はないんだ。これは僕のソロのアルバムだから、ソニック・ブームって名前を使うことは正しいと感じられた。パーソナルなアルバムとは思わないけど、確実にソニック・ブームの核があらわれているアルバムだからね。

いま身の回りに起こっている問題は僕たち全員が引き起こしたものだ。もう政治家にそれをなんとかしてもらおうなんて思ってはいけないよ。結局政治なんてビジネスなんだから。僕たち全員がその問題に取り組むべきなんだ。
■この「All Things Being Equal」というタイトルには、あなたの現在のモットー、人生のテーマのようなものが込められていたりしますか?
SB:自分の人生のモットーって言えたらよかったんだけどね。若いときにそう言えるくらい賢かったら、若い頃から地に足がついた性格だったって言えたらいいんだけど、そんなことはないよ。でも、人生や人との出会いを通して自分の行動を省みることはできた。人と一緒に学ぶ機会もまだたくさんある。願わくはみんなには良いことを学んでほしいなと思ってる。僕の経験はいつも良いことばかりではなかったけど、完璧な人なんてどこにもいないし、ほとんどの場合はたとえそれがひどい体験だったとしてもなにか得るものがあるものだよ。
■1990年にあなたがまだスペースメン3に在籍していた時期にソニック・ブーム名義で制作したファースト・ソロ・アルバム『Spectrum』では、ひたすら「現実世界からの逃避」と「何者かによる救済の希求」を描いていました。あの時期はスペースメン3も内部に問題を抱えていて、あなたのフラストレーションはとても大きなものだったと推測します。それがファースト・ソロのムードに現れていると思えます。
しかしそれから30年を経て作られた今回のソロでは、響きの点でも、また歌詞の面でもポジティヴな肯定感、そして抽象的な愛、平等な愛のようなものを感じます。これは普通に考えれば、あなたも歳を重ねて成熟した大人になった、ということなのでしょうが、なにかそれ以上にあなたのなかで自分自身の考え方が大きく変わったというようなことがあるのでしょうか?
SB:実はその当時はスペースメン3はまだ臨界崩壊に至るような状態にまでは行ってはいなかったんだ。だからあのソロ・アルバムではスペースメン3のメンバーが演奏をしてくれているんだ。精神的には機能していなかったのも確かだけどね。スペースメン3は、うまいことやっていくことができない若者が集まったグループだった。だから一緒に沈んでいくような結果になってしまったんだけど、こういうのってある特定の種類のロック・バンドではそんなに珍しい話でもない。セックス・ピストルズやストゥージズ、MC5 なんかを思い出してみてよ。もちろん意識してそうなったわけではないし、僕らだって自分たちの状況に気づいていたとも言えない。そのあと何年もかけて僕たちはお互いうまくやっていけるような人間じゃないって気づいたけど、そういう経験を経ることがものごとの見方を変えてくれたりすることもある。
ものごとの捉え方や考え方は変わったね。2010年だったかな、アニマル・コレクティヴのパンダ・ベアと仕事をすることになったときだった。そのとき僕は50代を目前にしていたんだけど(注:ソニック・ブームは1965年生まれ)、同じ場所や同じ人に囲まれた生活に人生を費やしたくないなと思い始めていた。人間関係がうまくいかない人もたくさんいたし、僕が育ったところ(イギリスの地方都市ラグビー)はいい友達もいるけどすごくフレンドリーな場所というわけでもなかった。そういう環境から出たかったし、商業化された都市にもいたくなかった。同じコーヒーショップ、同じファーストフードショップを見るのも、人々がみんな携帯を見ながら歩いているのを見るのもうんざりだった。
そんなときにポルトガルでパンダ・ベアと一緒に作業をすることになったので、そのあたりに住む場所を探し始めたんだ。リスボンの郊外にある小さなナショナルパークを見つけてさ。美しい山に囲まれた場所なんだ。日本の北部に少し似ているかもしれないな。とにかく美しい場所なんだ。おかげで外でたくさん時間を過ごすようになったし、ガーデニングをするようにもなったんだけど、そういうことをしていると頭の中からノイズやナンセンス、クソみたいなことが消えて空っぽになるんだ。思考も明快になって、考えていたことをもっとリサーチするようになる。バックミンスター・フラー(註:アメリカの思想家。「宇宙船地球号」という言葉で知られる)が地球や人類、経済モデルのとの関わり方、経済資本モデル、その本質の一部である好景気と不景気の繰り返しについて話しているのを見たり聞いたりしてね。もし僕がもう1枚アルバムを作るとしたら、そういう問題についても言及してみたいと思ってる。何が欲しいだとか、もっと欲しい、もっと大きいものが欲しいみたいなこととか、使いまくって捨てまくって消費しまくってやるみたいなことを僕の声を使って届けたくない。
たとえばこれまでの人生で僕が消費してきたプラスチックのことを考えてみる。それらはよく考えると全然必要ではなかったことに気づくんだ。プラスチック製品は好きだったけど、もういまはプラスチックから何かを飲むのも何かをプラスチックで包むのも嫌だ。自分の人生を変えなきゃいけないって思ったんだ。そうしたら突然自分の人生がより良くなった気がするし、いままで自分がしてきたことに対しても気持ちが軽くなったような気がした。すべてのことにつながりを感じることができて、いままでとは比べものにならないくらいハッピーな人間になったよ。それを表現していきたいんだ。いま身の回りに起こっている問題は僕たち全員が引き起こしたものだ。もう政治家にそれをなんとかしてもらおうなんて思ってはいけないよ。結局政治なんてビジネスなんだから。彼らが行動を起こしたとしても牛歩だし、多くの場合政治家自身のビジネス・オペレーションの隠れみのになってしまっている。僕たち全員がその問題に取り組むべきなんだ。もちろん全員がそんなものごとの見方ができるわけではないことはわかっているけど、しっかりとした考えを持っている人はいるわけだしね。最近の気候問題は自分たちに何ができるのかということをより考えさせてくれていると思う。この地球上で起こっている問題について、僕たちはもっと真剣に取り組まなきゃいけない。僕たちは自分たちの人生に起こるノイズに対していっぱいいっぱいになるあまり、たくさんのことに目をつむり続けてきた。説教じみたことは言いたくないけど、いいヴァイブスがあるレコードは作りたいよね。
■ポルトガルに住んだことで、あなたの考え方がそこまで至ったというのは興味深いところです。ポルトガルのなんという街に住んでいらっしゃるのですか?
SB:シントラという街なんだ。ここに限らず、ポルトガルは全然商業化されていない国だから気にいったよ。ここからスペインのマドリードなんて行ったら未来に足を踏み入れたような気持ちになるよ。もちろん東京もね。実際あそこは未来だし(笑)。あまりいい言葉ではないんだけど、ここはオールドファッションなんだ。ここではものごとが急速に発展したりしない。もちろんすべてがってわけじゃないよ。携帯とかラップトップ・コンピューターはちゃんと普及しているし。だけど総じて商業化されたものを見ることは多くなくて、オールドファッションなコミュニティがいたるところにあるんだ。このあたりをドライヴするとき、僕は近所のお年寄りたちに向かって手を振るんだ。そうすると彼らも手を振り返してくれる。おはよう、こんにちは、こんばんは……そんな挨拶も街角で常に交わされている。人が足早に通り過ぎるような都市部ではそんなこと起こらないだろ? そこがすごく好きだ。
生活環境は自分の健康状態や心の健康にすごく影響がある。僕は木や美しい自然、鳥や野生動物、爬虫類、虫に囲まれた、自分が健康でいられる環境にいたかったんだけど、ポルトガルではそれがまだ見つけられるんだ。
音楽もこの生活環境に大きく影響されているよ。このアルバムはまさにシントラの音だと言っていい。童話で有名なハンス・クリスチャン・アンデルセンも家をこの地域に持っていたそうなんだけど、とにかくマジカルな場所なんだ。山に囲まれているけど海も近くにあるからすぐビーチに行ける。その昔ポルトガルの皇室が、毎年夏になると避暑のためにこの山脈に来ていたんだって。リスボンに比べると夏は5度も気温が低いからね。天気も最高で、海から風が吹いてそれが雲を作るんだけどとても美しい。太陽も美しいし、それらのムードはアルバムに取り入れられていると思う。歌詞はほとんどこの土地で書いたけど、ここにいることで感じることを最大限表現したんだ。庭で過ごしたり植物を植えていたりするときの気持ちをね。だからこの地域というのはアルバムにとっての最大の影響源になっていると思うよ。
最良の出来事っていうのは前向きな気持ちで人生を生きて、外に出たり、経験を積んだときに突然起こったりするんだ。
■アートワークにはとにかくあなたが関わってきたたくさんのアーティストの名前がクレジットされていて壮観ですね。
SB:彼らこそがこのアルバムの最大のインスピレーションだからね。たくさんの人たちに感謝しているんだ。覚えている限り300から400のバンドやアーティストと一緒に仕事をしてきたよ。そこまで多くなってくると、さすがにすべてのことを覚えているのは難しいし、その人たち全員をクレジットするのは不可能だ。だからいままで一緒に仕事をした人全員にありがとうという気持ちを込めて「This is dedicated to the ones I love」とクレジットして、特にそのなかでも特別な人たちの名前を載せたんだ。なかには本当に僕の活動の初期から一緒にやっている人もいるし、全然名前が知られていない人もいる。プロデューサーとしての活動の初期に関わったフランスの European Sons というバンドがいるんだけど、彼らが拠点としていたフランスの街に行くたびに「誰かこのバンド知ってる?」って聞くんだけど誰も知らないんだ。プロデュースをしたのは1990年だからすごく前のことなんだけどね。連絡先もなくしてしまって、彼らに関する情報がなにもないんだ。だけどまだCDは持っているよ(笑)。たくさんの名前を載せることで、彼ら全員に僕を助けてくれたことや僕の人生の一部になってくれたこと、そして彼らから学んだすべてのことに対して感謝したんだ。そのときは気づかないかもしれないけど、人は人と出会うことで必ずなにかを学んでいるからね。
こんなにたくさんの人やバンドとレコーディングやミキシング、プロダクションなど、関わり方のかたちは違えども共に音楽を作ってきたなんて信じられないよ! ジャケットを作ったりビデオを作ることで関わったバンドもいる。違うタイプの人と働くのが好きなんだ。ありがたいことにいつも僕はそこから収穫を得ることのできるタイプの人間だから。考えごとをしているときとか、自分の頭のなかでこれは誰がこんなふうに考えろって教えてくれたんだっけ? って思うこともあるよ。それも祝福したかった。彼ら全員が僕の音楽をよりよいものにしてくれたから。
■プロデュースを頼んでくる人たちは、あなたにどんなことを望んで来るのでしょう?
SB:彼らからこちらにアプローチしてくることもあれば、僕のほうからプロデュースさせてくれということもあるよ(笑)。君がライブハウスで来る日も来る日も違うバンドが来て演奏するのを見ていたとする。そうするとだいたいみんな似たようなタイプの人間の集まりだなって思うだろう。でも、スタジオに入って制作を始めてみると、彼らのなかにあるダイナミクスだとか、自分たちの音楽や音楽そのものに対する考え方、音楽の作り方がバンドによって全然違うんだってことに気がつくんだ。プロデュースを始めた初期の頃に気づいたことは、もし自分がスタジオに行ってその場のルールを作って、これが俺たちのやり方だ! なんてことをするのは愚かだということ。僕がプロデュースを始めた理由のひとつは、スペースメン3時代に初めて迎え入れたプロデューサーなんだ(注:おそらくスペースメン3のファースト・アルバムに関わったボブ・ラムのことだと思われる)。彼はとても優しい人だったけど、音楽のことも僕たちのこともちっとも理解していなかった。僕たちの意見よりも彼の意見の方が尊重されたんだ。僕はすぐに彼は間違ってるって気づいたけど、もうああいう人とは働きたくないと思った。少なくとも僕にとってこれはポジティヴなことじゃなかったよ。だから自分でプロデュースもやり始めたんだけど、そのうち他の人が声をかけてくれるようになった。プロデューサーとして関わるけど、決定権は依頼主である彼らにあるべきだと思ってる。僕は彼らがよりよい作品を残せるように、そしてできるだけ早くベストな結果を残せるように正しい方向に導くだけ。最終的には彼らが納得してハッピーになることが大事。僕が納得する結果を残すために他の人を僕のやり方に従わせるっていうのはまったく違うんだ。バンドごとにやり方が違うのを見るのはかなりおもしろいよ。ときにはなによりもまず楽しもうぜってなる場合もあるし……いつだって楽しいんだけどね。すべてが比較することのできない経験になっているよ。とにかく全員違うからさ。人生のなかでも最高の出来事って、いつも予定されて起こることはないだろう? 最良の出来事っていうのは前向きな気持ちで人生を生きて、外に出たり、経験を積んだときに突然起こったりするんだ。
■これまでにプロデュースや共演をしたなかで、印象に残っているアーティストをいくつか挙げてその印象を教えてもらいたいのですが……そうですね、たとえば MGMT、パンダ・ベア、Dean & Britta、Cheval Sombre、No Joy、ビーチ・ハウス、Delia Derbyshire、Silver Apples……
SB:えええ? それはちょっと難しすぎるよ(笑)。たくさんの才能ある人たちと一緒にやってきたんだから! 彼らはゲームのなかでもトップの人たちだよ。ゲームといっても彼らがやりたいことをする彼ら自身のゲームのなかということだけどね。人が自分に人生のリスクを背負わせてまで夢を追いかけるために自分たちのやりたいことをするって最高だと思わない? とにかく……選べないって! それぞれの強みがあるからなあ……みんなイコールにね……All Things Being Equal (笑)。
■今回のソロはあなたもパンダ・ベアやビーチ・ハウスの制作で関わったワシントンDCの〈Carpark Records〉からのリリースです。このレーベルのカラーはあなたの音楽にとてもあっていると思います。このレーベルにはあなたがスペースメン3を始めて以降に生み出した音楽への影響力が継承されている感じがします。
SB:〈Carpark〉と初めて一緒に仕事をしたのはパンダ・ベア絡みで、その後レーベル・オーナーのトッド(・ハイマン)とはたまに連絡を取り合っていたよ。それで〈Carpark〉にいたビーチ・ハウスと一緒にやることになった。だから〈Carpark〉からリリースをすることは自分にとってなんとなく意味があるような気がしたんだ。それと当時僕は、別のレーベルとの問題を抱えていたんだよ。ロイヤリティが払われなかったりとか、アルバムが売れてもそれがちゃんと経理計上されていなかったりとかさ。音楽業界ではありがちなことなんだけど。当時はそういったネガティヴなことと向きあわなきゃいけなかったんだ。彼らはすごくモラルが低くて、非人道的なビジネスをするんだ。彼らのようになって戦ったほうが楽だということはわかっていたけど、それは僕がやりたいこととはまったく逆だし、なにより嫌な感情を振り払いたかった。嫌なものをただ手放したかったんだよ。お金がすごく欲しいんだったらネガティヴなことは付きものなのかもしれないけど、もうそんなものは気にしないって決めたんだ。それよりもその経験をポジティヴなものに昇華すれば、他の人にポジティヴで公平で思いやりのある行動を起こさせるような影響を与えられるかもしれないしね。もうすでにそういう行動を起こしている人もいるけど、まだすごく大きなメジャー・レーベルではまだ信じられないようなことが起こっている。とにかくポジティヴなことに昇華したかったんだ。
トッドには、僕のレーベルに対する気持ちを話したことがあるんだ。彼はとても公平で正直でオープンな人だからね。リリースに関しては最初は全部自分でやろうかなと考えていたんだけど、いろいろな側面からそれを考えてみると、お金は減らないかもしれないけど、作品が届く人の数や作品が広がる可能性も減るんだろうなって思ったんだ。だからパートナーとしては彼らがベストな選択だったよ。いまのところの僕たちの関係性はまさにパートナーシップという感じで、他のレコード会社でたまにあるような契約書で結ばれた奴隷みたいに感じる関係にはまったくなっていない。30年間で学習してきたこともたくさんあるしね。20歳のときにスペースメン3としてレコード会社と契約を結んだときは、なにが起きているかなんてわかってなかったからなあ。

「パイオニアは後追いの人たちにその背中を狙われる」って言葉があるんだ。俺たちがやったことは特別なことではなくて、そのときに俺たちができることのすべてだったけど、もしかしたら背中を狙われていたのかもしれないね(笑)。
■もともとあなたは同時代の音楽シーンに直接的にコミットしてきたタイプではないと思いますが、いまの音楽シーンについて何か思うことがあれば教えてください。
SB:僕はスタジオで一緒に制作をする人に、音楽を作っているんだからある程度はいまこの場所でやっていることを正確に把握しておく必要があるよって言うようにしているんだ。そのとき作っている音楽は何かに影響を与えることもあるからね。未来のことを見据えたときに、この音楽がどんな立ち位置になるのかっていうのはいつも僕が考え続けていること。なぜ、そしてどうやって音楽が定義されてきたのかということにはずっと興味があるけど、シーンというものの大きな一部になったことはないね。スペースメン3はパイオニア的な存在だったのかもしれないけど、パイオニアっていうのは自分の力でどこかに向かって行く人のことを言うだろ? 「You can tell the pioneers by the arrows in their backs (パイオニアは後追いの人たちにその背中を狙われる)」って言葉があるんだ。俺たちがやったことは特別なことではなくて、そのときに俺たちができることのすべてだったけど、もしかしたら背中を狙われていたのかもしれないね(笑)。
このあいだ「もし若手のバンドにひとつだけアドバイスをするとしたらなんと言いますか?」っていう質問をされたんだ。「オーマイガー、若手にアドバイスをする奴って大嫌いなんだよ!」って感じだった。それでも答えてくださいって言われたから「妥協をするな。心からやりたいと思うことをするんだ。友達が好きなシーンの一部になるために音楽をやってはいけない。すぐに友達がライヴを見に来てくれることはないかもしれないけど、やりたいことをやれば報われる」って言ったんだ。心に響く優れた音楽っていうのは、程度は違えど妥協をしない人たちが作ったものなんだよね。彼らは妥協せずに音楽とコミュニケーションをとることが必要だってわかっているんだ、音楽はコミュニケーションがすべてだからさ。それに音楽は素晴らしくパワフルなコミュニケーションの手段のひとつでもある。音楽って自分がそのときに考えていたことや思い出を際限なく呼び起こしてくれるよね。それって10枚のカードセットに入っているカードをある部屋で全部並べて覚えて、その後にもう一度その部屋に戻るとそのカードのすべてを覚えている、みたいなことに近いと思うんだ。もう何年間も聴いていなかったとしても、聴けばほぼ瞬時にその当時の感情や思い出を呼び起こされるという点でね。
■1965年生まれのあなたはあと5年後には60歳になります。そのとき、世界はどうなっていて欲しいと思いますか?
SB:ワオ……僕は現実的だから、もし僕たちがリサイクルをすることや消費活動、長距離移動を削減することに賭けなければ……飢餓や水不足、資源不足、人の超過密といったような他のメカニズムのなかで人口はじょじょに減っていくことになると思うんだ。僕たちが抱えている問題というのは巨大だけど、地球は回復するということはあと2ヶ月くらいでわかると思うんだ。落ち込んでいる日には、「地球は人間がいなければより早く回復していくのでは」なんて考えたりもするけど、いつもは僕たちならできるって感じているよ。海にプラスチックを投げ込むのをやめて、海に浮かんでいるものを取り除いて、石油科学をやめるんだ。石油科学は有毒なものだってわかっているだろ。いまや再生可能エネルギーがあるんだから、それが唯一の回答であるべきだ。
5年後か……夢は大きく持ってみよう……この地球はひとつで人類もひとつであるということを地球上に住む人びと全員が理解して欲しいんだ。お互いのことをレイシストと呼んだり、国家で分断したり、嫌なことやきついことはたくさんあるけど、違いを強調するよりもシェアするべきことのほうがたくさんあるということに気づいてほしい。この地球上で文化的な違いがあることは祝福すべきことだ。だけど一方で全員がこの地球の一部で、ひとりがその他の人のために地球を台無しにするなんてことがあってはいけない。もしひとつ選ぶとしたら、5年後には牛肉の消費量が大幅に減っているといいな……あと国家同士がきちんと手を組んでよりグローバリゼーションが進んでCO2の排出量のコントロールとかができるといいよね。西洋の国が中国を見て「大気汚染が深刻だ! この状況ってクレイジーだよ」って言うけど、いままで自分たちもさんざん大気汚染をしてきたじゃないか。この問題が深刻になる直前にこれはやばいって思ってちょっとだけ賢いやり方に切り替えただけでしょ。そういう問題にもっと目を向けていくべきだと思う。自分たちが「WE」であることを自覚していればいいんだけど、ドナルド・トランプやボリス・ジョンソンが当選するのは……わからないな。彼らは僕たちをつなげるよりも分裂させるだけだから。みんなが一緒になってものごとに取り組むことが大切なんだ。一緒に取り組み始めたら他のことも必然的についてくると思うよ。戦争はなくなって、お互いのことを理解し始めるし、人はそれぞれ違っているのは祝福すべきことで同じである必要はないということもわかる。違いがあることは問題ではないとね。それって両親が言っていたからその子供たちも同じことを言い続けるような、オールドファッションなことなんだよ。いまの人の行動とかものごとのありかたって、いままでずっとそうだったからそうしているだけでさ。そのことに対して疑問を持たないでしょ? 一度でも疑問を持ったら絶対に理にかなってないってわかるからね。