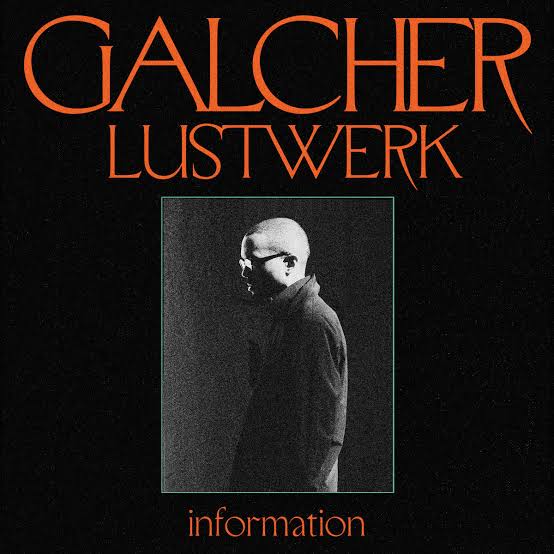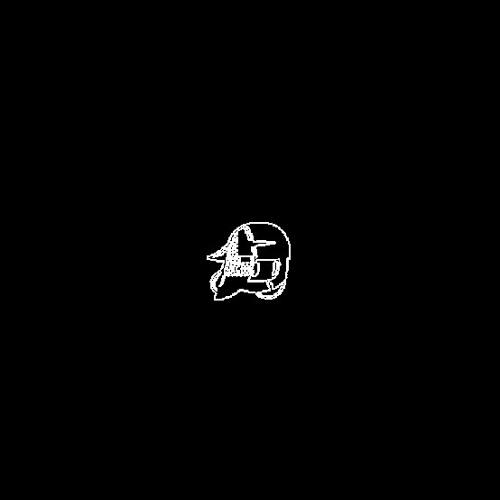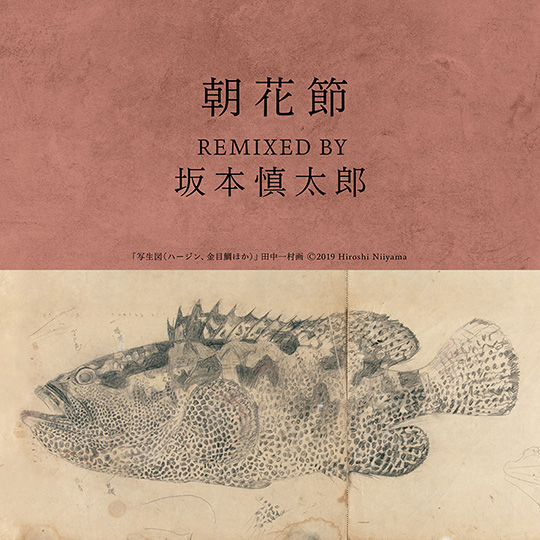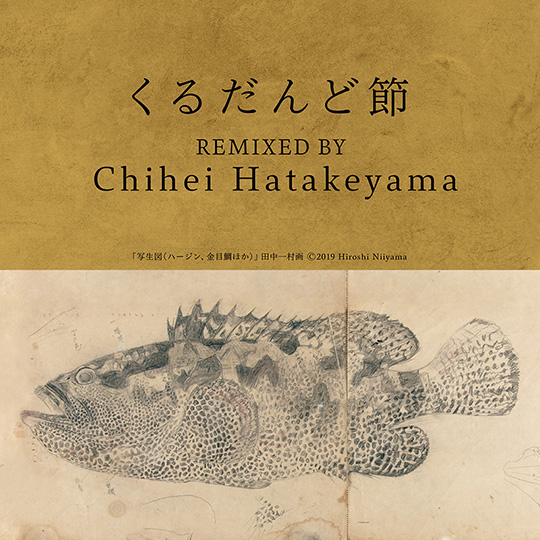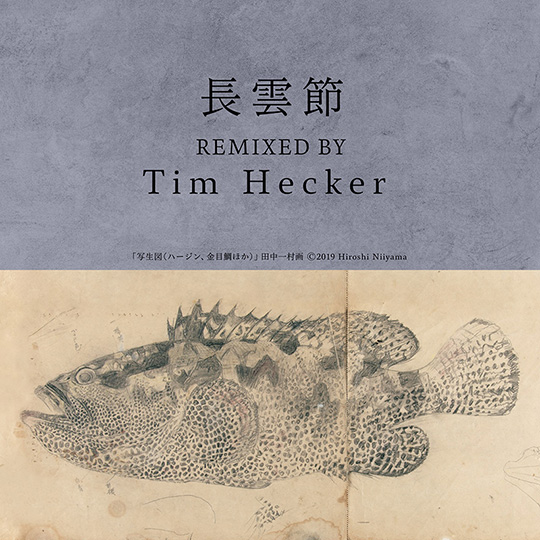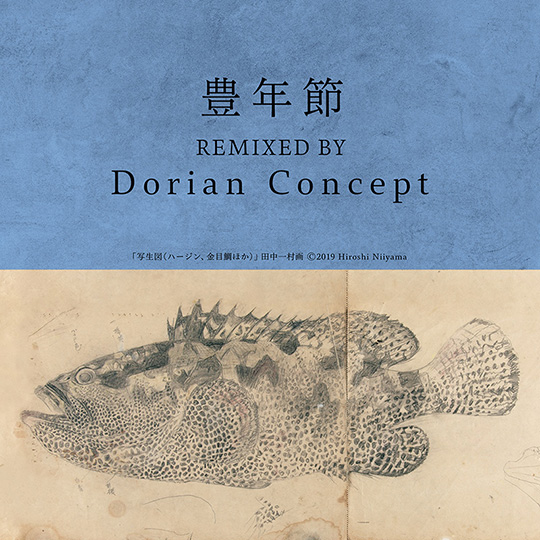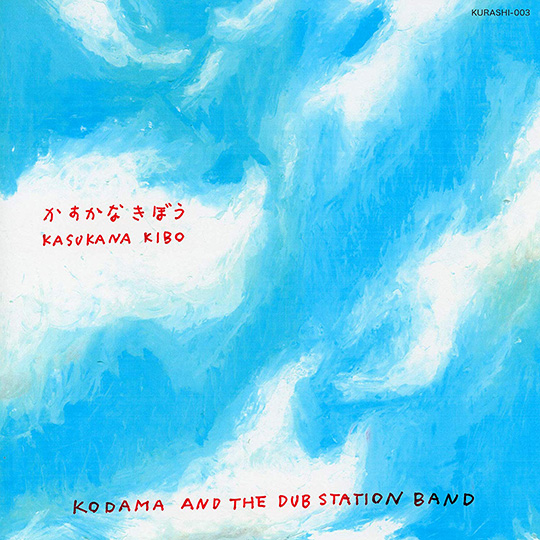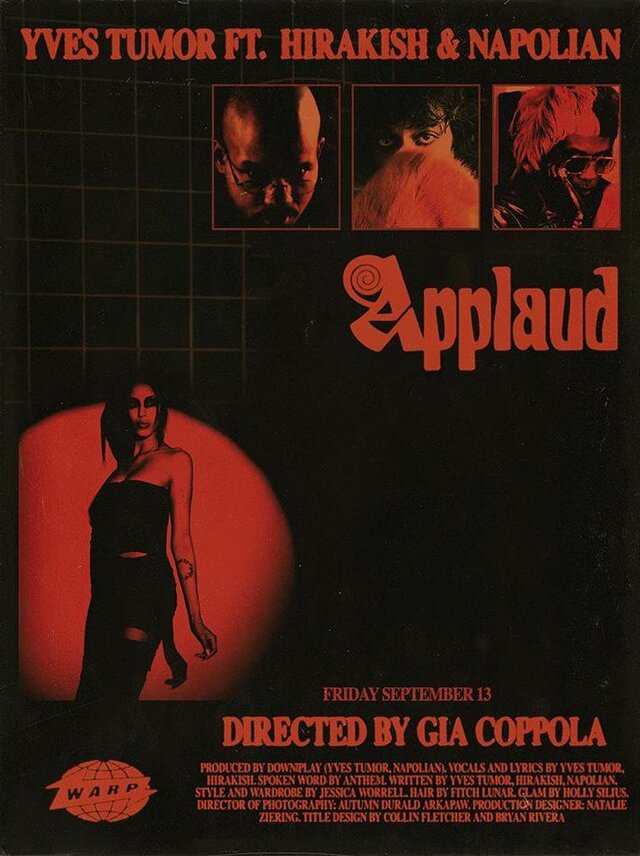京都の電子音楽レーベル〈shrine.jp〉から京都出身の電子音響作家・武田真彦のソロ・アルバムがCD作品としてリリースされた(同レーベルから2年ぶりのCD作品!)。武田は京都市芸術大学ギャラリー、京都芸術センター、十和田市現代美術館、安楽寺、ロームシアター京都などとアート・プロジェクトをおこなってきた気鋭のサウンド・アーティスト。 くわえて Velveljin、Rexikom としても活動をしており、〈shrine.jp〉のサブ・レーベル〈MYTH〉、パリの〈Récit〉、ルーマニアのミニマル・レーベル〈pluie/noir〉などから、EP、楽曲、ミックスなどをリリースしてきたミニマル・シーンの俊英でもある。
『Mitate』はそんな武田真彦名義のファースト・ソロ・アルバムだ。武田がインスタレーションなどで制作・発表したコラボレーション・ワークを中心に全6曲を収録し、「サウンド・アーティスト」としての側面・経歴をパッケージしたノーブルな音響作品に仕上がっている。
コラボレーション・アーテイストは、Virta のメンバーにして京都在住のトランペッター Antti Hevosmaa (M2)、コンテンポラリー・ダンスとして参加した Simon Erin とダンス・建築・美術の領域を越境する Fumi Takenouchi (M3)、1995年生れのフランス人小説家 Théo Casciani (M4)、パイプオルガン/フィールド・レコーディング・サウンドで参加した Vesa Hoikka (M5)など京都のアートシーンと縁のある(関係する)作家/アーティストたち。くわえて1曲め“Expectation”は建築と彫刻、ファッションと音楽、アートとデザインなどの垣根を超えて活動するジルヴィオ・シェラー(Silvio Scheller)とミルコ・ヒンリクス(Mirko Hinrichs)によるベルリンの BIEST のエキシヴィジョンで披露された貴重なパフォーマンスである。
協働によって生まれたサウンドは、まるで清流のような美しさを放っていた。電子音/持続音を基調としつつ、さまざまな環境音などのサウンド・エレメントをミックスした曲(1曲め、2曲め)、密やかなノイズの蠢き琴の音色が交錯する曲(3曲め)、透明な空気を感じさせるアンビエント/ドローンから、Théo Cascian によるテキスト(小説)のリーディング、そして囁くような歌声へと生成変化を遂げる曲(4曲め)、深く響く環境音と柔らかい質感のドローン、細やかなグリッチ・ノイズがミックスされるサウンドスケープがシネマティックな聴取感覚を与えてくれるアンビエント・トラック(5曲め)、環境音からヴォーカル曲が交錯するトラック(6曲め)まで音響作品としてあらゆる手法を存分に投入しながらもスタティックなムードで統一されているのだ。まさに「ソロ・アルバム」としての気品と風格を兼ね備えた作品といえよう。
本アルバムを特徴付けるもうひとつの重要な要素がCD盤を包み込むジャケットにある。素材を提供し、クリエーターの協働をめざす「MTRL KYOTO」は、伝統的な布地にCDを収めるという新しいパッケージ・フォームを生み出した。ジャケット素材の風のような軽さと柔らかさに、硬質な銀盤の共存は本作のサウンドそのものであり、ぜひともCDを手にとってその質感を味わって頂きたい。私見だがこの「触れる/聴く」の共存性は、ストリーミング時代における「CDのあり方」をリ・プレゼンテーションするプロダクトにすら思えたほど。
『Mitate』は、音と素材の「見立て」によって生れた実にエレガント/エクスペリメンタルな音響作品であり、音を用いた芸術と音楽の境界線を思考する上で重要な問いを発している批評的な作品でもある。何より「場」の空気をアート・インスタレーションに変えてしまうほどに美麗さと存在感のある音の粒子を放つ音響作品なのである。このアルバムが2019年の終わりにリリースされたことは10年代の電子音響/サウンドアートにおいて僥倖に思えてならない。2020年も繰り返し聴取したいCD作品のひとつである。