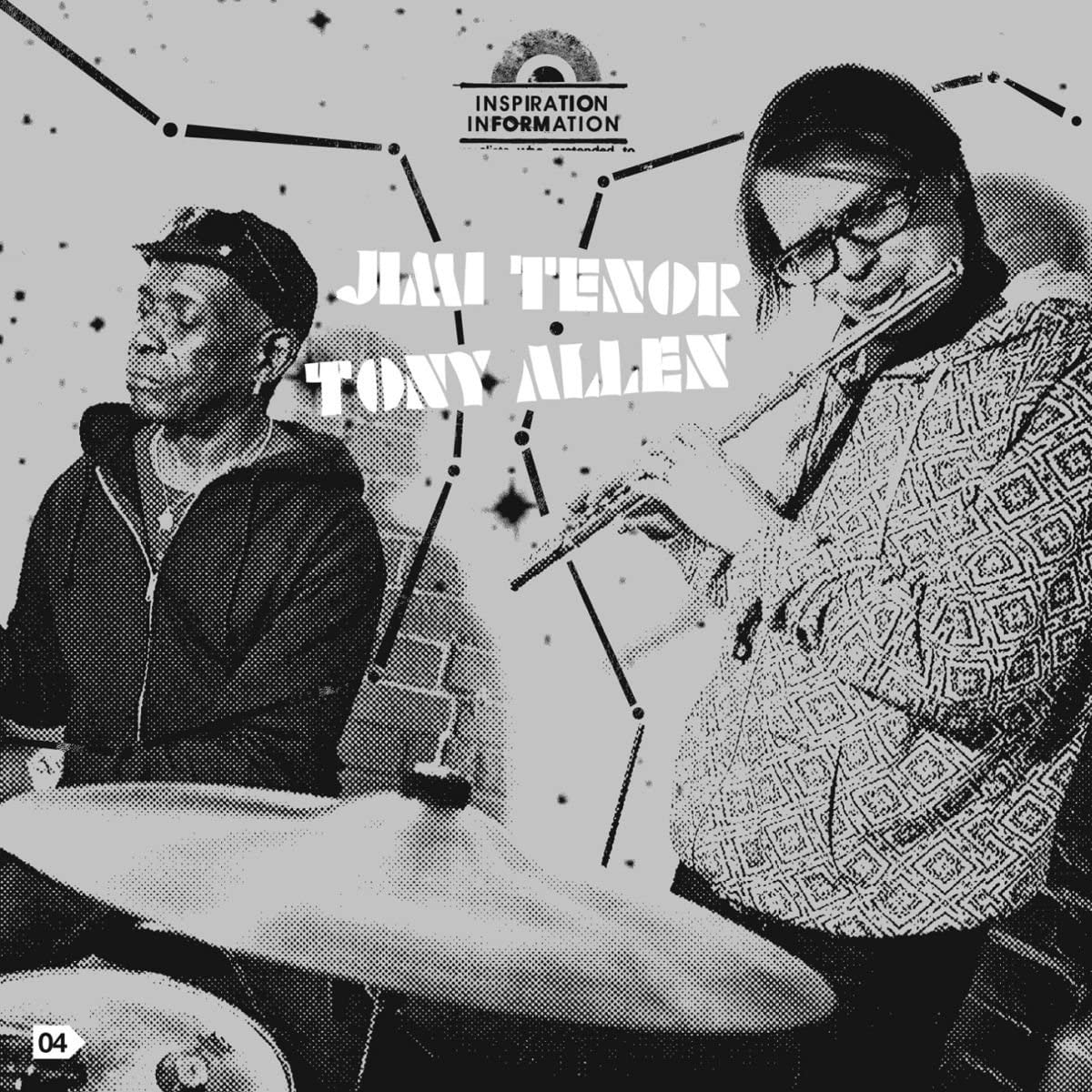MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Idris Ackamoor & The Pyramids- Shaman!
シャバカ・ハッチングスや彼の参加するサンズ・オブ・ケメット、ヌビア・ガルシア(ヌバイア・ガルシア)、モーゼス・ボイドら、ザラ・マクファーレンらの作品には、アフロ、カリビアン、ラテン、レゲエなど第3世界の音楽とスピリチュアルなジャズが結びついたモチーフが頻繁に登場する。こうしたディアスポラなアイデンティティとアフロ・フューチャリズム的な方向性が、彼らサウス・ロンドンのジャズの柱にあると言えるのだが、そうした活動を1970年代からおこなっているのがアイドリス・アカムーアと彼の率いるザ・ピラミッズである。以前『アン・エンジェル・フェル』(2018年)がリリースされたときに彼らのプロフィールや活動の軌跡については触れているので今回は省略するが、カマシ・ワシントンやサウス・ロンドン勢の近年の活躍に触発され、アイドリス・アカムーアのようなスピリチュアル・ジャズのレジェンドやベテランが、彼らが1970年代にやっていたような音楽をいまの時代に再び更新するような動きを見せている。ゲイリー・バーツとマイシャの共演、アーチー・シェップとダム・ザ・ファッジマンクの共演、エイドリアン・ヤングとアリ・シャヒード・ムハマドの『ジャズ・イズ・デッド』シリーズもそうした流れから生まれたものだし、最近では1970年代にニューヨークのロフト・ジャズの一翼を担ったアラン・ブラウフマンが、なんと45年ぶりの新作を発表した。
『アン・エンジェル・フェル』に関しては、アイドリス・アカムーアの共同プロデューサーにマルコム・カット(ヒーリオセントリックス)がつき、彼のミキシングを生かしたアフロ・ダブ的な手法が印象的だった。また、2014年に起こったマイケル・ブラウン射殺事件を取り上げた楽曲も収録するなどブラック・ライヴズ・マターとも結びついた作品だったが、今年もジョージ・フロイド事件など白人警官による黒人市民の射殺事件がアメリカで起こり、世界中で抗議運動が広まるなかでアイドリス・アカムーア&ザ・ピラミッズの新作『シャーマン!(祈祷師)』が発表された。
今回もマルコム・カットがプロデュースを担当したロンドン録音で、ピラミッズのオリジナル・メンバーであるマルゴー・シモンズ(マーゴ・アカムーア)や前作にも参加したサンドラ・ポインデクスターは参加するものの、そのほかはピラミッズを刷新した編成となっている。ヒーリオセントリックスのメンバーのジャック・イグレシアスほか、ルベン・ラモス・メディーナ、ジオエル・パグリアッツィアなど、ラテンやヒスパニック系のミュージシャンが多く参加していて、やはりラテンやアフロ的なリズムが肝となっている点は変わらない。そうしたラテン・リズムという点では “タンゴ・オブ・ラヴ(愛のタンゴ)” のようにアルゼンチン・タンゴを用いた楽曲があり、ここでは往年の『ラスト・タンゴ・イン・パリ』のガトー・バルビエリを彷彿とさせるアイドリス・アカムーアのサックス・ソロが聴けるほか、サンドラ・ポインデクスターのヴァイオリンやマルゴー・シモンズのフルートが印象に残る演奏を繰り広げる。
アルバムは4部構成で、それぞれ「懺悔の火の儀式」「永遠の片鱗」「我々を支える肩(大地)の上で」「クロティルダ号の400年」というサブ・タイトルが付けられる。宗教的で観念的なタイトルだが、このうちクロティルダ号とは19世紀の南北戦争直前に使われた最後の奴隷船である。このパートには “ザ・ラスト・スレイヴ・シップ(最後の奴隷船)” や “ドゴン・ミステリー(ドゴン族の神秘)” とアメリカの奴隷制度について言及した曲があり、自身のルーツであるアフリカに思いを馳せ、現在の人種差別反対運動へとリンクしている。“ヴァージン” とはアフリカの処女なる大地のことを示しているのだろうが、これぞピラミッズと言うべき土着的で雄大なアフロ・ジャズとなっている。現在のマリ共和国の先住民族についての “ドゴン・ミステリー” もアフリカ民謡を下敷きとした楽曲で、ボビー・コッブによるムビラやマルゴー・シモンズによるバンブー・フルートが素朴な音色を奏でる。“ザ・ラスト・スレイヴ・シップ” は瞑想的でサイケデリックな味わいで、クルアンビンあたりの音楽性に通じるものもある。
表題曲の “シャーマン!” は自然による治癒について述べられており、フォーキーなサウンドにアイドリス・アカムーアによるポエトリー・リーディングが交わるイントロダクションを経て、ジャズ・ファンクへと突入していく12分超えの大作である。中間はアフロビートに合わせてヴォーカルとバック・コーラスのコール&レスポンスが繰り返される展開で、ギル・スコット・ヘロンのようなフォークとスピリチュアル・ジャズ、フェラ・クティのようなアフロビートが融合したような楽曲である。この “シャーマン!” と “タンゴ・オブ・ラヴ” による「懺悔の火の儀式」を経て、「永遠の片鱗」は “エタニティ(永遠)” と “ホエン・ウィル・アイ・シー・ユー?(いつ君に再会できるの?)” の2曲で構成される。“エタニティ” は古代文明をイメージさせる荘重かつエキゾティックな楽曲で、フォーク・ロック調の “ホエン・ウィル・アイ・シー・ユー?” は世界中を旅するジプシー・バンドのピラミッズの歌である。「我々を支える肩(大地)の上で」は “サルヴェーション(救済)” と “テーマ・フォー・セシル” から成る。アイドリス・アカムーアによるフリーキーで重量感のあるテナー・サックス・ソロが展開される “サルヴェーション” では祖先への敬意を示し、“テーマ・フォー・セシル” はアイドリスがメンターとして慕うセシル・テイラーに捧げられている。
なお、『アン・エンジェル・フェル』のアルバムのアートワークも非常に秀逸だったが、今回のアルバムはジョージア・アン・マルドロウやシャフィーク・フセイン、マーク・ド・クライヴ・ロー、ユナイティング・オブ・オポジッツなどを手掛けるトキオ・アオヤマによるもので、これまた素晴らしいペインティングとなっている。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE