 agraph / equal Ki/oon |
ゴールド・パンダから〈ラスター・ノートン〉の名前を聞いて、そしてアグラフの『イコール』にはアルヴァ・ノトが参加していることを知る。同じ時期にふたりの新世代の、背景も音楽性も異なるアーティストから、同じように、しかも久しぶりにカールステン・ニコライの名を耳にして、ひっかからないほうが不自然というものだろう。エレクトロニック・ミュージックの新局面はじつに忙しなく、かつて〈ミル・プラトー〉が宣言したようにいろんなものが絡み合いながら脱中心的に動いているように感じられる。
クラブ・ミュージックに関して言えば、多くの論者が指摘するように、ジェームス・ブレイクが新しいところに向かっている。ドイツ語で"ピアノ作品"を意味する「クラヴィアヴェルクEP」を聴いていると、彼が単なるブリアル・フォロワーではないことを知る。ピアノの心得があることを、彼は5枚目のシングルで披露しているのだが、おかしなことにアグラフもまた、『イコール』において彼のピアノ演奏を打ち出している。なんというか、気兼ねなく自由に弾いている。彼のセカンド・アルバムを特徴づけているのは、ピアノとミニマリズムである。
アグラフの音楽は清潔感があり、叙情的だ。きわめて詩的な広がりを持っている音楽だが、その制作過程は論理的で秩序がある。作者の牛尾憲輔と話していると、彼ができる限り物事を順序立てて思考するタイプの人間であることがよくわかる。その多くが感覚的な行為に委ねられるエレクトロニック・ミュージックの世界においては、彼のそれはどちらかと言えば少数派に属するアティチュードである。そして思索の果てに辿り着いた『イコール』は、いまIDMスタイルの最前線に躍り出ようとしている。
リスナーが、スティーヴ・ライヒ・リヴァイヴァルとカールステン・ニコライを経ながら生まれたこの音楽の前から離れられなくなるのは時間の問題だ。アグラフの、傷ひとつないピアノの旋律を聴いてしまえば、多くの耳は立ち止まるだろう。息を立てるのもはばかれるほどの、控えめでありながら、どこまでもロマンティックな響きの前に。
実家が音楽教室でピアノをやっていたので、坂本龍一さんの曲は弾いてました。それは手癖として残っていると思います。坂本龍一さんの手癖にライヒがのっかているんです(笑)。だから混ざっているように聴こえるんでしょうね。
■日常生活ではよく音楽を聴くほうですか?
牛尾:最近は聴かなくなりましたね。本ばっか読んでいます。ぜんぜん聴いてないわけじゃいんですけどね。
■音楽が仕事である以上、当然仕事の耳で音楽を聴かなくてはならないと思うんですけど、自分の快楽として聴く場合の音楽はどんな音楽になるんですか?
牛尾:基本的にはすべて電子音楽かクラシックです。
■どんな傾向の?
牛尾:一筆書きで描かれた、勢いのあるものよりかは、家で聴いて奥深くなっていける細かく打ち込まれたもの。アパラットみたいな、エレクトロニカとテクノのあいだにあるようなもの。ファーストを作っているときからそうだったんですけど、そういう音楽家、(スティーヴ・)ライヒ的な現代音楽......ミニマルであったりとか、そういう音像の作られ方をしているものをよく聴きますね。
■いまの言葉はアグラフの音楽をそっくり説明していますね。
牛尾:そうかもしれません。僕の音楽はそういう影響を僕というフィルターを通して変換しているのかなと思うときもあります。
■最初は鍵盤から?
牛尾:はい。
■今回のアルバムの特徴のひとつとしては、鍵盤の音、メロディ、旋律といったものが挙げられますよね。
牛尾:そうですね。
■自分の音楽をジャンル名で呼ぶとしたら何になると思います?
牛尾:さっき言った、エレクトロニカとテクノのあいだかな。
■アンビエントはない?
牛尾:その考え方はないです。
■ない?
牛尾:アンビエントをそれほど聴いてきたわけではないんですよ。ファーストを作ったときに「良いアンビエントだね」と言われたりして、それで制作の途中でグローバル・コミュニケーションを教えてもらって初めて聴いたりとか、ブライアン・イーノを聴いてみたりとか......。
■イーノでさえも聴いてなかった?
牛尾:意識的に作品を聴いたのはファーストを出したあとです。
■カールステン・ニコライ(アルヴァ・ノト)みたい人は、エレクトロニカを聴いている過程で出会ったんだ。
牛尾:そうです。東京工科大学のメディア学部で学んだんですけど、まわりにICC周辺、というかメディア・アートをやられている先輩や先生だったりとかいたんですね。そういう人たちに教えてもらったり、いっしょにライヴに行ったりとか、スノッブな言い方になりますが、アカデミックな延長として聴いていました。
■なるほど。アンビエント......という話ではないんだけど、まあ、エレクトロニカを、たとえばこういう説明もできると思たことがあったんですよね。ひとつにはまずエリック・サティのようなクラシック音楽の崩しみたいなところから来ている流れがある。もうひとつには戦後マルチトラック・レコーディングの普及によって多重録音が可能になってからの、ジョージ・マーティンやジョー・ミークやフィル・スペクターみたいな人たち以降の、レコーディングの現場が記憶の現場ではなく創造の現場になってからの流れ、このふたつの流れのなかにエレクトロニカを置くことができるんじゃないかと。アグラフの音楽はまさにそこにあるのかなと、早い話、坂本龍一と『E2-E4』があるんじゃないかと思ったんです(笑)。
牛尾:なるほど(笑)。でも『E2-E4』はそこまで聴いてないんですよ。
■やはりライヒのほうが大きい?
牛尾:大きい。『テヒリーム』(1981)みたいにリリカルなものより、彼の出世作が出る前の、テー プ・ミュージックであったりとか、あるいは『ミュージック・フォー・18ミュージシャンズ』(1974)であったりとか、当時のライヒがテープを使って重ねていたようなことをシーケンサーで再現できるように打ち込んだりはよくやりますけどね。
■なるほど。
牛尾:坂本龍一さんはたしかにあります。実家が音楽教室でピアノをやっていたので、坂本龍一さんの曲は弾いてました。それは手癖として残っていると思います。坂本龍一さんの手癖にライヒがのっかているんです(笑)。だから混ざっているように聴こえるんでしょうね。
■しかも坂本龍一っぽさは、ファーストでは出していないでしょ。
牛尾:出ていないですね。
■今回はそれを自由に出している。ファーストの『ア・デイ、フェイズ』よりも自由にやっているよね。
牛尾:ピアノを弾けるんだから弾こうと思ったんですよ。
■僕は3曲目(nothing else)がいちばん好きなんですよ。
牛尾:ありがとうございます(笑)。
■あの曲は今回のアルバムを象徴するような曲ですよね。
牛尾:そうですね。
■ファーストはやっぱ、クラブ・ミュージックに片足を突っ込んでいる感じがあったんだけど。
牛尾:そうです、今回は好きにやっている。ファーストも実は、制作の段階では4つ打ちが入っていたり、エレクトロのビートが入っていたりして、だけど途中で「要らないかな」と思ったんです。それで音量を下げたり、カットしたりしたんですけど、基本的に作り方がダンス・ミュージックだったんですね。展開の仕方もすべて、ダンス・ミュージック・マナーにのってできているんです。今回はクラシカルな要素、アンサンブル的な要素を取り入れていたんです。
■まったくそうだね。
牛尾:こないだアンダーワールドの前座をやったんですけど、前作の曲は四分が綺麗にのっかるんです。でも、今回の曲ではそれがのらないので、ライヴをやってもみんな落ち着いちゃうんですよね(笑)。
[[SplitPage]]「人がない東京郊外の感じをロマンティックに切り取っているよ」と言われて、それはすごく腑に落ちる言い方だなと。とにかく僕の牧歌的な感覚は、そっから来ていると思います。
 agraph / equal Ki/oon |
■今回自分の世界を思い切り出そうと思ったきっかけは何だったんですか?
牛尾:新しいことをやりかったというのがまずあります。前作ではやらなかったこと、まだ自分が出してないものを出そうと。それと、オランダ人で、シメオン・テン・ホルト(Simeon Ten Holt)というミニマルの作家がいて、その人の『カント・オスティナート(Canto Ostinato)』という作品があって、フル・ヴァージョンだとピアノ6台、簡略化された聴きやすいヴァージョンではピアノ4台なんですけど、そのCDのピアノの響きというか、サスティンの音に含まれる空気感みたいなものにとても気づくところがあって、まあ、具体的なものではないんですけど、その空気感に触発されというのはありますね。
■ちょっとのいま言った、えー、シメオネ?
牛尾:シメオン・テン・ホルトです。
■スペルを教えてもらっていいですか?
牛尾:はい。(といって名前と作品名を書く)
■僕もスティーヴ・ライヒは行きましたよ(笑)。90年代に来たときですね。あれは生で聴くと本当に最高ですよ。
牛尾:僕は昨年の来日のときに2回行きました。質疑応答までいました(笑)。
■この10年で、スティーヴ・ライヒは見事にリヴァイヴァルしましたよね。
牛尾:僕は技法的にはすごく影響受けましたね。
■ミニマル・ミュージックには反復と非連続性であったりとか、ライヒの技法にもいろいろあると思いますが、とくにどこに影響を受けたんですか?
牛尾:フェイジングという技法があって、ずらして重ねていくという技法なんですけど、それを根底においてあとは好きなように作っていく。そうすると反復性と非連続性が、重ねた方であるとか響きの聴かせ方で、再現とまではいかないまでも自分のなかに取り込めるのかなという意識がありました。テクニカルな要素ですけどね。
■それはやっぱ、アグラフがピアノを弾けるというのが大きいんだろうね。
牛尾:そうかもしれないですね。とにかくピアノを弾こうというのが今回はあったので。
■楽器ができる人はそういうときに強い。ダブみたいな音楽でも、感覚的にディレイをかける人と、ディレイした音とそのとき鳴っている音との調和と不調和までわかる人とでは作品が違ってくるからね。
牛尾:僕はそこまで音感が良いほうではないんですけどね。音楽の理論も多少は学んだけど、ちゃんと理解しているわけでもないし、すごく複雑な転調ができるわけでもないし、ワーグナーみたいな方向の和声展開が豊富にできるわけでもないので、その中途半端さがコンプレックスでもあるんです。ただ、その中途半端さは自分のメロディの描き方にも出ているんですよね。だから、それが欠点なのか、自分の味なのか計りかねているんですよね。
■なるほど。
牛尾:このまま勉強していいものなのか、どうなのか......好きなようにやるのがいいと思うんですけど。だからいま、菊地(成孔)さんのバークリー・メソッドの本を置いて、「どうしようかな」と思っているところなんです(笑)。
■ハハハハ。まあ、音楽理論が必ずしも作品をコントロールできるわけではないという芸術の面白さもあるからね。それこそ、さっき「一筆書き」と言ったけど、ハウスとかテクノなんていうのは、多くが一筆書きでパンクなわけでしょ。感覚だけでやっていることの限界もあるんだけど、そのなかから面白いものが生まれるのも事実なわけだし。
牛尾:そうですね。そこをどうスウィッチングするのかは僕も考えていかなくてはならないことですしね。
■きっと牛尾くんみたいな人は曲の構造を聴いてしまわない? 「どういう風に作られているんだろう?」とか。
牛尾:聴いてしまいますね。
■だからエレクトロニカを聴いていても、曲の作り方がわかってしまった時点でつまらくなってしまうという。
牛尾:それはあるかもしれませんね。あと、楽典的な技術ではなくて、音響的な技術に関しては僕はもっとオタクなので、たとえば僕、モーリッツ・フォン・オズワルドのライヴに行っても音響のことばかりが気になってしまうんですね(笑)。だから、内容よりも音像の作り方のほうに耳がいってしまうんですね。
■そういう意味でも、アルヴァ・ノトはやっぱ大きかったんですかね。最近、ゴールド・パンダという人に取材したらやっぱその名前が出てきたし、今回のアグラフの作品にもその名前があって、ひょっとしていまこの人も再評価されているのかなと。
牛尾:エポックメイキングな人ですね。
■〈ラスター・ノートン〉もいま脚光を浴びているみたいですよ。
牛尾:それは嬉しいですね。僕が好きになったのは大学時代だったんですけど、とにかくやっぱどうやって作っているのかわからない(笑)。すごいなーと。そういえば、こないだミカ・ヴァニオのライヴに行ったら、グリッジを......ホットタッチと言って、むき出しになったケーブルを触ることでパツパツと出していて、僕はもっと知的に作っていたかと思っていたので、すごいパンクだなと思ったんです(笑)。
■フィジカルだし、まるでボアダムスですね(笑)。
牛尾:しかもコンピュータを使わずにサンプラーだけでやっている。しかもエレクトライブみたいな安いヤツでやってて。スゲーなと思った(笑)。エイブルトン・ライヴであるとか、monomeというソフトがあって、そういうアメリカ人が手製で作っているハードウェアとソフトのセット、Max/MSPのパッチのセットであるとか、スノッブなエレクトロニカ界隈でよく取り立たされるようなソフトウェアって、実は適当に扱うようにできているんですね。僕からはそういう見えていて、僕はCubaseというソフトを使っているんですけど、すごく拡大して、できるだけ厳密に、顕微鏡的に作ることが多いんです。つまり(ミカ・ヴァニオみたに)そういう風にはできていなくて、ああいう音楽がフィジカルに生まれる環境が実はヨーロッパにはすごくあって......、で、そういう指の動きによる細かさが、ループだけでは終わっていない細かさに繋がっているのかなと。
■なるほど。
牛尾:僕は典型的なA型なんで(笑)。
■たしかに(笑)。そこまで厳密に思考していくと、どこで曲を手放すのか、大変そうだね。
牛尾:それはもう、そろそろ出さないと忘れられちゃうなとか(笑)。そういうカセがないと、本当にワーク・イン・プログレスしちゃうんで。
■それは大変だ。
牛尾:でも、「あ、できた」と思える瞬間があったりもするんです。
■ちょっと話が前後しちゃうんだけど、ダンスフロアから離れようという考えはあったんですか?
牛尾:それはないですね。ただ、自由にピアノを弾こうと思っただけで。フロアから離れようとは思っていなかったです。追い込まれた何かがあるわけではないですね。
■音楽的な契機は、さっき言った......えー、イタリア人だっけ?
牛尾:いや、オランダ人のシメオン・テン・ホルト。ファーストのときはハラカミ(・レイ)さんへの憧れがすごく強かったんですね。高周波数帯域が出ていない、こもっているような、ああいう作りにものすごい共感があったんです。それでファーストにはその影響が出ている。だから、次の課題としてはその高い周波数をどうするのかというのがあった。それを思ったときも、ピアノのキラキラした感じならその辺ができるなと思って。ピアノの、たとえば高い方の音でトリルと言われる動きをしたときとか、感覚的に言えばハイハットぐらいの響きになるんですね。だから高周波数の扱いを処理すれば、新しいところに行けるかなと思ったんです。
■ピアノは何歳からやっていたんですか?
牛尾:6歳です。でも、適当にやってました。
■じゃ、ご両親が?
牛尾:いやいや、家が団地の真んなかにあったので、「それじゃ牛尾さん家に集まろうよ」という話になって、そのあと引っ越してから一軒家になってからもそのまま続いているってだけで、親が音楽をやっていたわけではないんですよね。
■出身はどこなんですか?
牛尾:東京の多摩のほうです。だから、多摩川をぷらぷら散歩するのが好きで、ファーストは散歩ミュージックとして作っていたので。
■牛尾くんの作品の牧歌性みたいなのもそこから来ているのかな?
牛尾:そうだと思いますね。ディレクターから「人がない東京郊外の感じをロマンティックに切り取っているよ」と言われて、それはすごく腑に落ちる言い方だなと。僕は人は描かないんですけど、橋とか建物とか人工物は描いていると思うので。とにかく僕の牧歌的な感覚は、そっから来ていると思います。ただ、ちょっと斜陽がかっていますよね。
■なるほど。ずっとピアノだったんですか?
牛尾:とはいえ、ドラクエを弾いたり(笑)。
[[SplitPage]]
夜の海を散歩したこと、夜の街を山の上から見たことが大きなヒントになっています。そのとき感じたのは、「そこにあるのに見えていない」ということだったんです。夜の海は真っ暗で海の存在感はあるのに見えない、夜の街も街はあるのに人が見えない。
 agraph / equal Ki/oon |
■音楽体験として大きかったのは?
牛尾:アクセス。
■なんですかそれは?
牛尾:浅倉 大介さんとか、どJ-POPです。僕はそれをテレビで見て、「将来ミュージシャンになろう」と。それからTMN、小室哲哉さんを見て、「やらなきゃ」と(笑)。
■はははは。
牛尾:痩せているから運動部はやめようと(笑)。まあ、そういう感じでしたね。
■自分で意識的にCDを買いに行ったのは?
牛尾:クラフトワークですね。中学校まではJ-POPだったんですけど、卒業間際に友だちの家で『ザ・ミックス』を聴いて、もう「すごーい!」と(笑)。"コンピュータ・ラヴ"の「ココココココ......」と短いパルスみたいな音にリヴァーブがかかっているだけというブレイクがあるんですけど、それだけテープに録ってずっと聴いてたっりとか。
■はははは。
牛尾:音フェチみたいなのは、もうその頃からありました。気に入った音色をずっと追い続けていたりとか......ピアノを弾いていると戦メリを弾きたくなってくるので、そこから坂本龍一さんを聴いて、YMOを聴いて、みたいなのがちょうどクラフトワークを聴きはじめたのと同じ時期で。そうこうしているうちに90年代後半で、卓球さんやイシイさんも聴いたり、雑誌を見ると「〈ルーパ〉というパーティがあってそこでは80年代のニューウェイヴもかかっているらしい」とか、で、「あー、行かなきゃ」って(笑)。それからジョルジオ・モロダーを探してみたり。そうやって遡っていってるだけなんです。
■最初から電子音楽には惹かれていたんだね。
牛尾:家にはピアノとエレクトーンがあったんですけど、ずっとエレクトーンに憧れがあったんですよ。それが大きかったかもしれないですね。で、クラフトワークにいって、それから......「卓球さんが衝撃を受けた"ブルー・マンデー"とはどういう曲なのか」とかね。
■そうやって一筆書きの世界に近い付いていったんだね(笑)。
牛尾:そうです(笑)。だから、エレディスコなんです。卓球さんにコンピに入れてもらった曲も、最初に出したデモはオクターヴ・ベースがずっと「デンデンデンデン」と鳴っているような(笑)。ちょうど当時はシド・ミードのサウンドトラックを作るんだと自分で勝手に作っていた時期で。
■いまのアグラフの原型は?
牛尾:浪人か大学のときです。でも、ハラカミさんを聴いたのは、高校生のときでしたけどね。だから、エレディスコを作りつつ、そういう、小難しい......。
■IDMスタイル(笑)。
牛尾:そう、IDMスタイルと呼ばれるようなものを作りはじめたんです(笑)。だんだん知恵もついてきて、細かい打ち込みもできるようになったし、アグラフの原型ができていった感じですかね。
■小難しいことを考えているかもしれないけど、ファーストよりも今回の新作のほうが若々しさを感じたんですよ。だって今回のほうが大胆でしょ。ファーストはもちろん悪くはないんだけどわりと型にはまっているというか。
牛尾:ハラカミさんへの憧れですからね。エレディスコをやっていたのも卓球さんやディスコ・ツインズへの憧れでした。それはいまでもあるんですけど、自分のなかで結実できていないんですよね。それよりも自分に素直に自分の味を出すべきだと思ったんですよね。自分がいま夕日を見ながら聴いて泣いちゃう曲とか(笑)、そこに根ざして曲を作りたかったんです。
■なるほど。
牛尾:そうなんです。ファーストは(レイ・ハラカミへの)憧れでしたね。
■この新作は時間がかかったでしょ?
牛尾:かかりましたね。ファーストをマスタリングしているときにはすでに取りかかっていましたから。でも、最初はうまくいかなった。『ア・デイ、フェイズ』の"II"になってしまっていたんですね。
■最初にできたのは?
牛尾:1曲目(lib)と2曲目(blurred border )です。テクニカルな細かい修正を繰り返しながら、だんだん見えてきて、それで、1曲目と2曲目ができましたね。「行けるかも」とようやく思えました。
■アルバムを聴いていてね、ものすごく気持ちよい音楽だと思うんだけど、たとえば1曲目にしても、かならず展開があるというか、だんだん音数が多くなっていくじゃない? ずっとストイックに展開するわけじゃないんだよね。そこらへんに牛尾くんのなかではせめぎ合いがあるんじゃないかなと思ったんですけどね。
牛尾:僕の曲は、後半に盛りあがっていって、ストンと終わる曲が多いんですよ。
■多いよね。
牛尾:小説からの影響なんでしょうね。小説をよく読むんです。小説って、それなりに盛りあがっていって、ストンと終わる。あの感じを自分が紡ぎ出す叙情性の波で作りたいんだと思います。
■なるほど。
牛尾:僕は散歩しながら聴くことが多いんですけど、曲を聴き終わって、いま見ている風景を......、夕焼けでも朝焼けでも夜の街でもいいんですが、曲が終わったときに風景をそのまま鳥肌が立ちながら見ている感覚というか、それをやりたいんです。
■それは面白いね。実際に曲を聴いていて、その終わり方は、きっと考え抜いた挙げ句の結論なんだなというのが伝わってきますね(笑)。
牛尾:ありがとうございます(笑)。
■あと、たしかにヘッドフォンで聴くと良いよね。
牛尾:まあ、やっぱ制作の過程で散歩しながら聴いているので、どうしてもそうなってしまいますね。でも、どの音量で聴いても良いように作ったし、爆音で聴かないとでてこないフレーズもあるんですよ。それはわざと織り込んでいる。
■ちなみに『イコール』というタイトルはどこから来ているんですか?
牛尾:僕の音楽はコンセプトありきなんです。ファーストは日没から夜明けまでのサウンドトラックというコンセプトで作りました。今回は、夜の海を散歩したこと、夜の街を山の上から見たことが大きなヒントになっています。そのとき感じたのは、「そこにあるのに見えていない」ということだったんです。夜の海は真っ暗で海の存在感はあるのに見えない、夜の街も街はあるのに人が見えない。それはひょっとしたら見ている対象物と自分とが均衡が取れている状態なんだなと思ったんです。そのとき、今回のタイトルにもなった"static,void "とか"equal"とか、そういう単語が出てきた。それでは、これを進めてみようと。抽象的だけど、寄りかかれる柱ができたんです。
■なるほど。最後のアルヴァ・ノトのリミックスがまた素晴らしかったですね。
牛尾:そうなんです。今回は10曲作って、最後はもう彼に託そうと。ドイツ人がわけのわからないアンビエントをやって終わるという感じにしたかったんです。そうしたらカールステン(・ニコライ)から「フロア向けにする?」というメールが来て。「あの人も、リミックスのときはフロアを意識するんだ」と驚きましたけどね。
■しかもあれでフロア向けというのが(笑)。
牛尾:でも突出していますよね。マスタリングをやってくれたまりんさんにしても、もう1曲リミックスをしてくれたミトさんにしても、あとブックレットに小説を書いてくれた円城(塔)さんにしても、僕の描いた青写真以上のものを挙げてくれた。だから満足度がすごく高い。
■僕、小説はまだ読んでないですよね。僕も日常で聴いている音楽はインストが多いんですけど、それはやっぱ想像力が掻き立てられるから好きなんですね。同じ曲を妻といっしょに聴いていても、僕と妻とではぜんぜん思っていることが違っていたりする。そこが面白いんです。
牛尾:そこは僕もまったく同じです。たとえばtwitterで曲を発表すると、僕が持っている「この曲はこういう気持ちで作りました」という正解と、ぜんぜん違った感想をみんな返してくれるんですよね。それが面白いんです。
■まさに開かれた解釈というか。だから小説を読んでしまうと、イメージが限定されてしまうようで恐いんです。
牛尾:円城さんは文字を使っているんですけど、ホントに意味わかんないんですよ。言い方は悪いんですけど(笑)。せっかく音楽があるのに、愛だの恋だのと、なんで歌詞で世界観を狭めてしまうんだろうなというのはずっとあるんです。でも、円城さんの言葉は違うんですよ。もっと開かれている言葉なんです。小説を付けたかったわけじゃないんです。円城さんの言葉が欲しかったんです。
■なるほど。
牛尾:さらに勘違いしてもらえると思うんです。
■わかりました。じゃあ、僕も読んでみます。
牛尾:ぜひ(笑)。

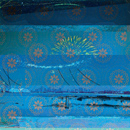

 photo: Maki Mizukoshi
photo: Maki Mizukoshi photo: Maki Mizukoshi
photo: Maki Mizukoshi photo : Tetsuro Sato
photo : Tetsuro Sato photo : Tetsuro Sato
photo : Tetsuro Sato



















![TURN ON THE SUNLIGHT [CARLOS NINO & JESSE PETERSON]](/chart/shop/japonica/images/20100929/09.jpg)












