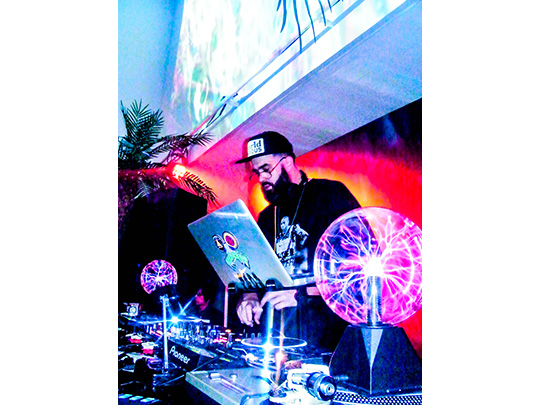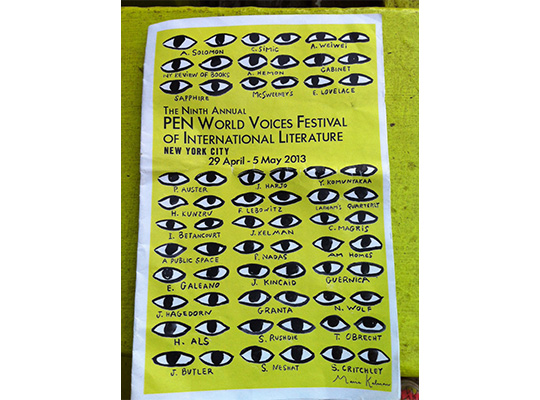Bioshock Infinite テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
皆さまこんにちは、NaBaBaです。今回は『BioShock: Infinite』のレヴュー。前回の『Dishonored』に引き続き、〈Looking Glass Studios〉(以下LGS)特集としていままで勿体ぶってきたわけですが、ついに書くときが来ました。
4月25日の国内発売からここ1ヶ月、メディアからは絶賛の嵐でしたが、僕の身のまわりでも本作は大きな話題になり続けていました。僕自身も2回クリアし、今日まであれこれ考えを巡らせていたのです。それぐらい本作は事件性の強い作品だったのですね。
この『BioShock: Infinite』は、Ken Levine率いる〈Irrational Games〉の最新作。前回ご紹介した『Dishonored』や『Deus Ex: Human Revolution』等と同じく、いまは亡き〈LGS〉の遺伝子を備えた作品ですが、とくに99年に発売された『System Shock 2』との繋がりが深い。『System Shock 2』はKen Levineの実質デビュー作であり、以降のいわば『Shock』シリーズは、〈2K Marin〉が開発した『BioShock 2』を除き、氏が一貫してディレクターを務めています。
彼が手掛けるこの『Shock』シリーズは他の〈LGS〉系の作品とシステム的に共有している部分が多々ありますが、一方で主観視点での没入型のストーリーテリングに重きを置いている点が、他とは異なる特徴になっています。
99年の『System Shock 2』は、当時最新鋭だった『Half-Life』的なサヴァイヴァル演出を基調としつつ、オーディオ・ログや成長システムなどRPG的な要素も盛り込んだ傑作。ここでできあがったゲーム・システムの骨子は後の『Deus Ex』や『Dishonored』にも引き継がれています。
『System Shock 2』はGOGの他、今月からSteamでの再販も開始された。
続く07年の『BioShock』は、ゲーム的には前作と比べより即興重視になり、ストーリーテリングも前作同様、閉鎖空間でのサヴァイヴァルを基本にしつつ、ビデオ・ゲームの一方的な側面とそれを疑わないプレイヤーの関係をメタ的に批判する表現も盛り込んだ、やはり当時を象徴する傑作でした。

『BioShock』は海中都市というケレン味溢れた世界観も特徴で、このコンセプトは『BioShock: Infinite』では空中都市という形で引き継がれている。
こうした流れのなかにあって『BioShock: Infinite』はいままで以上に物語重視の作品となることが予告されていました。彼のいままでの作風と実績、またここ数年の主観視点の表現の停滞感に、何か一石を投じてくれるに違いない、もしかしたら『Half-Life 2』に匹敵する革新性を見せてくれるのではないかという期待感を業界全体に募らせていたと思います。
はたしてその期待は実現したのでしょうか。メディアの評価を見る限りはあちこちで大絶賛ですが、一方で海外のファン・コミュニティの間ではかなりの物議を醸しているという話も聞きます。
じつは僕もファン・コミュニティの反応は納得できてしまう。本作は確かにめちゃくちゃすごい。極まっていると言ってもいいぐらいです。しかし逆に極まっているからこそ、手放しには褒められない今世代のFPS全般にまたがる、宿命的な問題を感じたのです。今回のレヴューではその点を中心に論じていきたいと思います。
[[SplitPage]]■物語の高度化がゲーム・プレイとの間に乖離を起こす
いきなり結論から言ってしまえば、『BioShock: Infinite』は、『Half-Life 2』型FPSの到達点であると同時に限界点でもあると言えます。本作には今世代のFPSが『Half-Life 2』を起点として方々で進化発展させてきた表現手法が、まさに全部入りという感じで濃縮されています。しかしそうであることが、この表現手法が構造的に持っている弱点をいままでになく際立たせてもいるのです。
何より本作は、前評判どおりに物語が非常に強くクローズ・アップされており、『BioShock』以前のサヴァイヴァルを主眼にした内容から、囚われの少女との空中都市からの逃避行という、よりヒロイックで劇的な演出を盛り込んだものに変化しました。なおかつ既存の様式に縛られない、FPSとしてはかなり複雑なシナリオとテーマを描いているのも特徴です。
また物語をプレイヤーに体感させるためのギミック、リアリティを裏打ちするための世界観構築も超一流で、今世代のゲームの一側面である「体験する映画」としては、最上級のものであることに異論の余地はありません。

空想世界の作り込みは圧倒的で他の追随を許さない。
しかしその反面、『Half-Life 2』型のゲーム共通の課題も本作には見られました。そのなかでももっとも深刻に感じたのが、物語が高度になり見た目のリアリティが増すにつれ、実際のゲーム・プレイにおけるリアリティとの乖離が顕著になるという問題です。
本作の主人公のBookerやヒロインのElizabethはFPS史上最大級とも言える緻密な人物造形がされており、リアリティを表現するための演出も幾重にも散りばめられています。そのなかには戦闘で深手を負ったBookerをElizabethが介抱するシーンもあり、そこで巻いてもらった包帯はゲームの最後までつけていくことになるのです。
負った傷は現実ではそうすぐには治らない。そういうことを象徴しているかのような演出ですが、しかしいざ戦闘になるとBookerは結局他のゲームと変わらず、アイテムで何度でも回復し、ひとりで何百という敵を倒す超人になってしまうのです。しかも本作はそのあたりにある食べ物でも回復できるため、状況によってはひたすら拾い食いして回復しまくるというシュールな事態にもなってしまう。せっかくの演出もこれでは興ざめです。
ファンが作ったパロディ・ムーヴィー。本作の仕様を面白おかしく皮肉っているが、問題の本質を鋭く抉ってもいる。
とりわけ本作はインドアの複雑な攻防が主体だった前作から一転し、大量の敵を相手にするアクション重視のゲーム性になっており、これもまた現実離れ感に拍車を掛けています。
こうした現象は本作に限らず、およそ現代のすべてのゲームに見られる問題であります。いままではそれをゲームのお約束として見てみぬふりをしてきたわけですが、『BioShock: Infinite』レヴェルになると物語も見た目も素晴らしいがゆえに、いよいよ見過ごせない違和感が生まれてきたと感じます。
この問題に関連性がある話として、Ken Levineはインタヴューで「FPSにおける戦闘は映画のミュージカル・シーンのようなもの」と語っています。彼のその考えが反映されているのか、本作も中盤までは戦闘時と非戦闘時がかなり明確に分けられています。舞台となるコロンビアの街並を、インタラクティヴな仕掛けとともに眺め歩く時間がしばらく続いたと思ったら、ある瞬間いきなり戦闘になり、それ以降は再び切り替わるまでずっと続くのです。

それまで平和だったのが突然阿鼻叫喚の場面に。こうした転換はたびたび見られる。
ここには敢えてお約束感を強調することで、そういうものとしてプレイヤー側に受け入れさせるような意図を感じました。しかしそれは物語とゲーム・プレイとの一致という点では一種の敗北ではないのでしょうか。
また後半でコロンビアがほぼ戦争状態になり、ゲーム的にも戦闘が占める割合が増えてくることで上記のような不和は若干解消されていきます。しかしそれはそれで、やはりFPSでゲーム・プレイと物語を一致させようと思ったら戦争を描くしかないという事実に、残念な気持ちにもなるのです。
■守るべきなのに守る必要が無いヒロイン
こうした問題点を解決する一発逆転的なものとして、僕はElizabethというコンパニオン・システムにいちばんの期待を寄せていました。うまくいけば彼女の存在が接着剤となり、物語とゲーム・プレイの一致を果たしてくれるのではないかという期待があったのです。
少なくとも彼女は物語的にはとても重要な役割を発揮して深みを与えているし、健気だけど危うさも感じるキャラクター像も魅力的。恐らく洋ゲー史上最も可愛く、ある意味日本の美少女像に近づいたキャラだと思います。要するに守ってあげたい気持ちになるのです。

洋ゲーのヒロインがこんなに可愛いわけがない、と真面目に思ってしまうぐらいElizabethは魅力的。
またAIとして見た場合も、彼女の行動にいっさいの破綻がないのは、これまでのコンパニオンの歴史を考えると感慨深い成果と言えます。広く高低差が激しいマップをプレイヤーが縦横無尽に駆け巡っても、しっかり後についてくる点などは素直に驚きました。FPSで初めてコンパニオン・システムを導入し、歴史に残る大爆死を遂げた『大刀』の登場から苦節13年。コンパニオンはついにここまで成長しました。
しかしここまでは素晴らしいのに非常に残念でならないのは、彼女をゲーム・システムとして見た場合、存在意義が希薄なことです。彼女は無敵なので敵にやられる心配はいっさいなく、なおかつ直接戦闘に加勢してくれるわけでもありません。かわりに戦況に応じてアイテムをくれたり、プレイヤーの指示で別次元から戦闘をサポートするギミックを呼び出してくれるのですが、これがあまりよろしくない。
一見すると有能のようにも感じますが、プレイヤーが彼女の能力発動を完全にコントロールでき、またリスクもまったく無いわけです。これではほとんどプレイヤー自身の能力の一部といった感じで、独立した他者というイメージが弱い。わざわざコンパニオン・システムにしている意味が感じられません。

別次元のものを呼び出す超能力のTearは、便利すぎてElizabethがやってくれることの意味がほとんど無い。
おそらくコンパニオンがプレイヤーの足を引っ張る事態になるのを避けたのでしょう。駄作の代名詞『大刀』を例に挙げずとも、なまじコンパニオンをプレイヤーに近い立場にしたばかりに、すぐ死んだり不用意に戦況を掻き乱したりして、最早コンパニオンのお守りをするのがメインみたいな、破綻したゲームは枚挙に暇がありません。
本作はそんな先人を教訓にして、徹底して面倒が掛からないコンパニオンを目指したのでしょうが、逆にお利口すぎて存在感があまり無いという、何とも皮肉な事態になってしまっています。
じつはここにもまた物語とゲーム・プレイとの乖離が生じているのにお気づきでしょうか。本作の物語でElizabethは守るべき存在であることが何度も強調されます。しかしゲーム・プレイの面では守るどころかまったく気にかける必要がない。この矛盾により物語への感情移入がし難くなり、ゲーム・プレイでの彼女との関わりは淡白なものになってしまっているのです。
僕の意見としては、やはりストレスが生じるリスクを多少踏んででも、Elizabethを守ったりいたわるような要素がゲーム・システム的に必要だったと思います。むしろこんな可愛いキャラならお守りしてあげてもいいと思わせるぐらいの開き直りが見たかった。それができればプレイヤーにより深い感情移入を促し、物語とゲーム・プレイを一致させる文字どおりの革新になり得たかもしれないのです。
結局のところ、僕にとってElizabethにもっとも興奮させられたのは発売前のトレーラーでした。能力の使いすぎで息も絶え絶えになっていたり、敵に連れ去られそうなのを必死に抵抗していたり。そんな危うさをプレイヤーが守ってあげる、それが楽しくできるゲーム・デザインというのが、本作がすべき挑戦だったと思わずにはいられません。
大変驚かされたE3 2011でのゲーム・プレイ・デモ。Elizabethに限らず、このとき見られた要素の多くが製品版では無くなったりスケール・ダウンしてしまったなぁ。
[[SplitPage]]■まとめ
ゲームを含めたコンテンツへの評価軸は、完成度と革新性の2種類があると思います。『BioShock: Infinite』は、完成度の観点から見ると非常に高く評価できる作品です。それはまさに今世代の集大成と言っていい仕上がりであり、これまでのFPSの歩みを感じさせるとともに、その一歩一歩を最高品質で結実させていて感動的。これだけでも本作は傑作の称号を得るにはあり余る成果を上げています。
一方、その輝かしい歩みの陰で、物語とゲーム・プレイとの乖離という問題は、本作の下ではもはや見逃せないばかりに膨らんでおり、目前には暗く厚い雲がたちこめています。僕はこの行き止まりをさらに突き破ってくれることを本作に期待していましたが、しかしそこまでの革新性を示すまでには至らなかった。そこが本当に残念でした。
ある意味、本作はいまの時勢を象徴しているとも言えるでしょう。05年のXbox 360の登場によりはじまった今世代機の歴史は、いままさに終わりを迎える直前で、今年の年末にはいよいよ次世代機がリリースされる機運が高まってきています。本作は、そんなハードの事情と歩調を合わせて、今世代のFPSの終焉を告げているような気もします。
次世代のFPSはどうなるのでしょうか。誰しもが予想できるのが、よりグラフィックスや演出が強化されていく方向性だと思いますが、そんな単純な拡張主義が続く限りは、本作が到達したその先に行くことは本質的に不可能だと思います。必要なのは発想の抜本的な転換であり、それによってゲーム・プレイと物語との乖離が解消されて初めて、FPSの真の次世代がはじまる気がします。
それまでしばらくは、本作を覆う暗く厚い雲が、ゲーム業界全体をも包みつづけることでしょう。