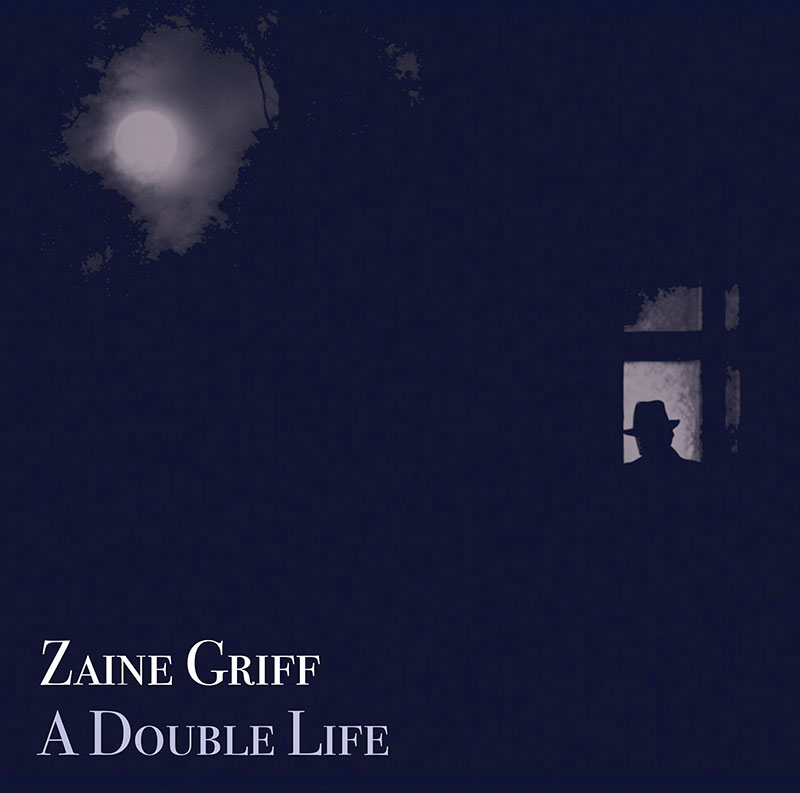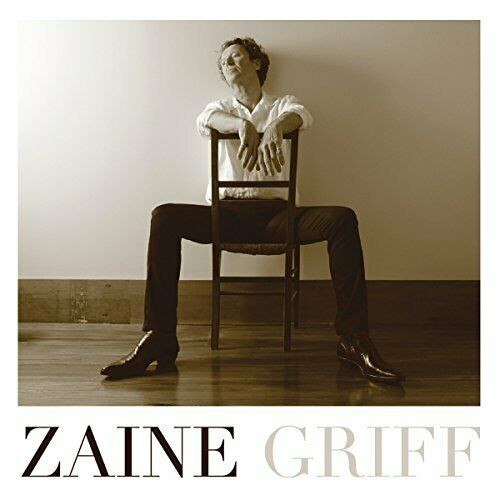2024年1回目のコラムだが、1月は年初でリリースが少なく、紹介すべきものがこれといってない。そこで、2023年を振り返ってリイシューや未発表作品からピックアップしたい。特にアフリカや南米のアーティストで目につく作品が多かった。
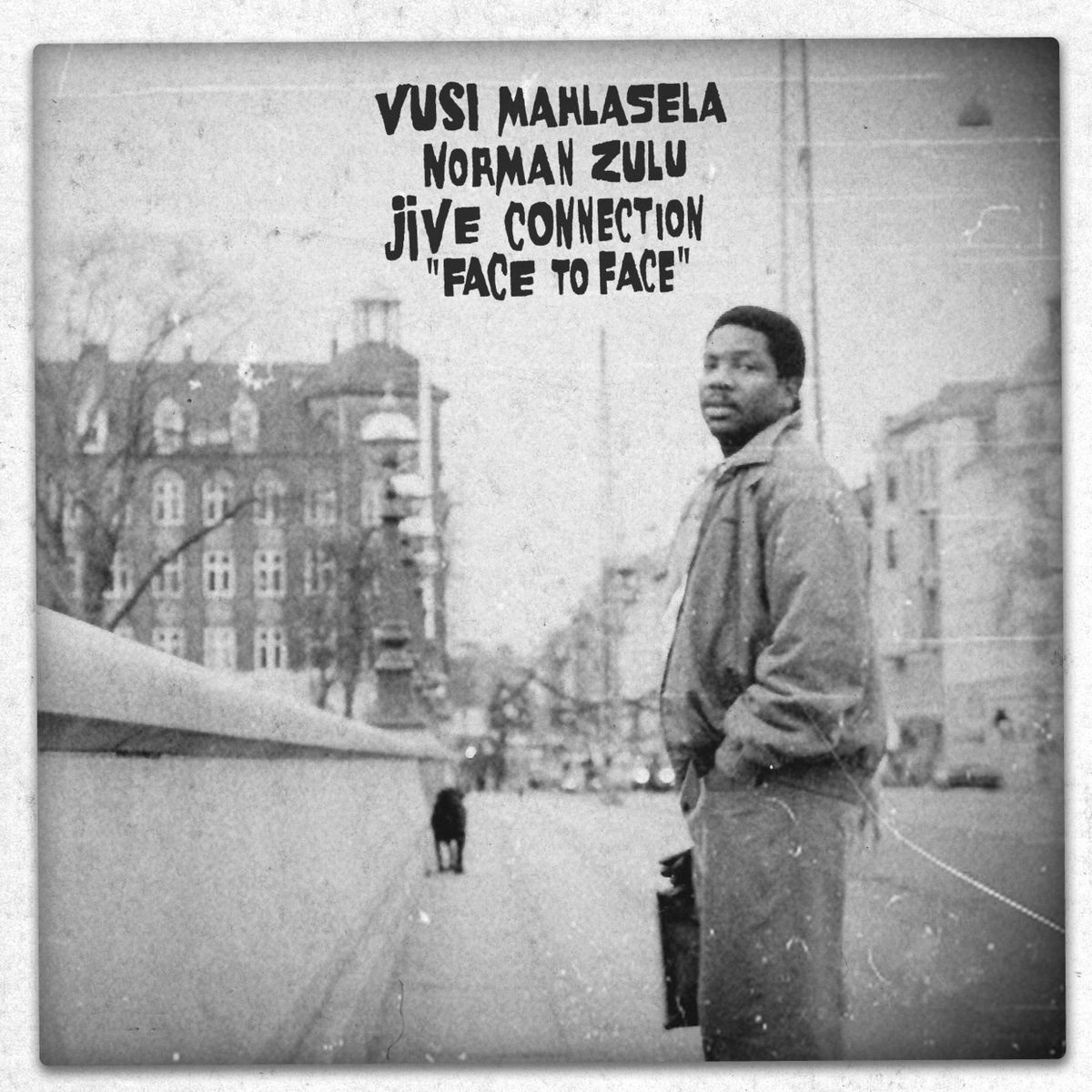
Vusi Mahlasela & Norman Zulu, & Jive Connection
Face To Face
Strut
『フェイス・トゥ・フェイス』は1994年に録音された未発表作品で、スウェーデンの音楽プロデューサーのトルステン・ラーションのアーカイヴから発見された。アフリカ南部のバントゥー系民族であるソト族のフォーク・シンガーのヴーシ・マハラセラ、南アフリカのシンガー・ソングライターのノーマン・ズールーと、スウェーデンのジャズ~ソウル集団のジャイヴ・コネクションが共演した記録である。ちなみにジャイヴ・コネクションにはリトル・ドラゴンのドラマーのエリック・ボディンや、スウェーデン民謡グループのデン・フールなどで演奏するベーシストのステファン・バーグマンらが在籍した。
スウェーデンは昔からジャズが盛んで、ドン・チェリーらアメリカから移住したジャズ・ミュージシャンも少なくない。南アフリカでは元ブルーノーツのジョニー・ディアニが移住している。ジョニー・ディアニなどのジャズ・ミュージシャンはアパルトヘイトから逃れるために他国へ移住したのだが、そうした反アパルトヘイト運動を支援した国のひとつがスウェーデンで、政府はアフリカ民族会議への資金援助をおこなっている。そのANC議長だったネルソン・マンデラが反逆罪で投獄された後、出所して初めて訪れた国がスウェーデンである。1994年のマンデラ大統領就任式で歌を披露したのがヴーシ・マハラセラで、ノーマン・ズールーを含めて彼らと交流を深めていたジャイヴ・コネクションが一緒に録音したのが『フェイス・トゥ・フェイス』である。
ヴーシの歌は自由を求めての闘争に彩られており、南アフリカの伝統的な寓話に基づく『プロディガル・サン(放蕩息子)』や、児童虐待に対する嘆きを歌った『フェイスレス・ピープル』などを力強く歌う。音楽的にはジャズやアフリカ民謡だけでなく、レゲエやダブ、ファンク、ポスト・パンクなどの要素を交えたものとなっており、実に興味深い。“フェイスレス・ピープル” はカーティス・メイフィールド風のニュー・ソウル的な歌や演奏にダビーなエフェクトを交え、まるでガラージ・クラシックと言ってもおかしくないようなものだ。ニューウェイヴとアフロ・ディスコが融合した “プッシュ” はピッグバッグを彷彿とさせ、強烈なダブ・サウンドの “フェイス・トゥ・フェイス” や “ルーツ” はデニス・ボーヴェルがミックスしているかのよう。アフロ・ジャズの “ウマザラ” にしても、楽器の録音やミックスなどダブやレゲエを意識したものとなっている。

Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou Dahomey
Le Sato 2
Acid Jazz
オルケストル・ポリリトモ・デ・コトヌー・ダホメイ(別名T・P・オルケストル・ポリリトモ)は西アフリカにあるベナン共和国のコトヌー出身の楽団で、1968年にシンガー兼ギタリストのメロメ・クレマンによって創設され、1980年代の終わりまで活動した。アフリカ民謡、アフロビート、ハイライフ、アフロ・キューバン・ジャズ、サイケデリック・ファンクなどが融合した音楽を演奏し、地元のヴードゥー教にも繋がりを持つ存在だった。欧米諸国などでは長らく知られざるバンドであったが、2000年代に彼らの音源がUKの〈サウンドウェイ〉から紹介されて広まり、ガーディアン紙は「西アフリカで最高のダンス・バンドのひとつ」と評価している。そうした再評価を受けて2009年にバンドは再結成され、2枚の新録アルバムの発表とワールド・ツアーもおこなうが、創始者のメロメは2012年に亡くなった。
アルバム・リリースは数十枚に及び、原盤はどれもが入手困難なものだが、〈アナログ・アフリカ〉ほか欧米のレーベルもリイシューを手掛けている。1974年作の『レ・サト』は2021年にUKの〈アシッド・ジャズ〉からリイシューされ、その第2弾として同年に録音された『オルケストル・ポリリトモ・デ・ラ・アトランティーク・コトヌー・ダホメイ』が『レ・サト・2』としてリリースされた。原盤は『レ・サト』と全く同じレコード・スリーヴで販売されており、裏面に第1弾と異なるカタログ番号が記載されるという体裁だったため、長らく謎のレコードとされてきたもので、彼らの作中でももっともレアな1枚である。原初的な歌と催眠的なファンク・グルーヴに包まれた10分を超す “ジェネラル・ゴウォン” はじめ、伝統的なヴードゥーの儀式とパーカッションによるポリリズムが結びついた独特の世界を作り出している。

The Yoruba Singers
Ojinga’s Own
Soundway
ヨルバ・シンガーズは1971年に結成された南米のガイアナ共和国のバンドで、アルバムは1974年の『オジナズ・オウン』、1981年の『ファイティング・フォー・サヴァイヴァル』のほか、リーダーのエズ・ロックライフとヨルバ・シンガーズ名義による2009年作『アー・ウィ・ライク・デム・ソング・ディス』などがある。隣国のトリニダード・トバゴのカリプソやスティールパン演奏の影響を受け、ほかにジャマイカから流れてくるロックステディやルーツ・レゲエ、ガイアナ住民の祖先であるアフリカの伝統的な民謡などを育み、プロテスト・ミュージックへと昇華したのがヨルバ・シンガーズの音楽である。ヨルバというアフリカのナイジェリア南西部に住む部族をグループ名に冠している点で、彼らのルーツ的なところが見えてくる。欧米では全く知られた存在ではなかった彼らだが、2018年に『ファイティング・フォー・サヴァイヴァル』がUSの〈カルチャーズ・オブ・ソウル〉からリイシューされ、陽の目を見ることになる。そして2023年には『オジナズ・オウン』がUKの〈サウンドウェイ〉からリイシューされた。
彼らの初期のレパートリーは、農園での労働の合間に歌ったり、または宗教儀式の場で歌われるといったもので、『オジナズ・オウン』はそうした彼らの姿をとらえた素朴な作品集である。演奏は原初的な打楽器やギター、フルートなどによるシンプルなもので、10名ほどのコーラス隊が合唱するというスタイル。“オジナズ・オウン” や “アンコンプレヘンシデンシブル・レディオマティック・ウーマン” など、ガイアナの自然や大地、生活や宗教と密着したプリミティヴな作品集である。

Terri Lyn Carrington
TLC And Friends
Candid / BSMF
現在のUSジャズ界のトップ女性ドラマーであるテリ・リン・キャリントン。1965年生まれの彼女は、ウェイン・ショーターの1988年作『ジョイ・ライダー』への参加で名を上げ、1989年のリーダー・アルバム『リアル・ライフ・ストーリー』でグラミー賞にノミネートされるなど、着実にキャリアを重ねていった。女性アーティストのみで結成されたモザイク・プロジェクトを興すなど、ジャズ界における女性演奏家の地位向上を謳うリーダー的な存在でもある。父親のソニー・キャリントンがサックス奏者だったこともあり、7歳のときからドラムをはじめた彼女は、11歳でバークリー音楽院に奨学金を受けて入学した天才児で、在学中にさまざまなプロ・ミュージシャンとのセッションをはじめ、16歳のときの1981年に自主制作でアルバムを作ってしまった。それが『TLC・アンド・フレンズ』である。一般的に『リアル・ライフ・ストーリー』がファースト・アルバムとされる彼女だが、実は『TLC・アンド・フレンズ』が正真正銘の幻のデビュー・アルバムなのである。
この度リイシューされた『TLC・アンド・フレンズ』は、ケニー・バロン(ピアノ)、バスター・ウィリアムズ(ベース)、ジョージ・コールマン(サックス)という、1960年代より活躍してきた名手たちとの共演となっている。そして、父親のソニー・キャリントンもゲスト参加して1曲サックスを吹いている。バップを中心としたオーソドックスな演奏だが、アレンジも自身でおこなうなどすでに神童ぶりを発揮するものだ。楽曲はコール・ポーターの “恋とはどんなものかしら”、マイルス・デイヴィスの “セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン”、ソニー・ロリンズの “セント・トーマス” と “ソニー・ムーン・フォー・トゥー” など大半がカヴァー曲で、ビリー・ジョエルの “素顔のままで” もやっている。そうしたなか、唯一の自作曲の “ラ・ボニータ” がラテン・タッチのモーダル・ジャズとなっており、とても16歳とは思えない奥深く豊かな表現力を見せる。