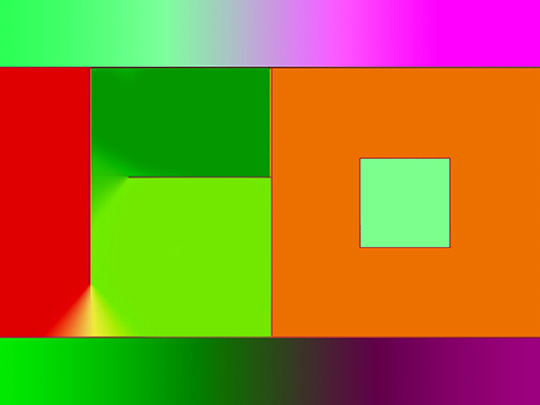覚えているだろうか? 数年前、名門ミックスCDシリーズ『Fabric』がルーマニアン・アンダーグラウンド・シーンにジャックされたことを。『Fabric 72』では Rhadoo が、『Fabric 68』では Petre Inspirescu が、『Fabric 78』では Raresh が立て続けに起用されていたけれど、この3人はリカルド・ヴィラロボスとならんで世界中の様々なフェスでヘッドライナーを務めるルーマニアの重鎮たちである。
東欧というのはある意味でもっともピュアな形で音楽が実践されているエリアで(先日お伝えした Khidja もその一例)、そのシーンは文字通りアンダーグラウンドなものだ。ルーマニアのシーンを代表するかれら3人は [a:rpia:r] というレーベルの運営者でもあるが、その3人によるユニットが RPR Soundsystem である。滅多におこなわれないこのユニットでの公演だが、来春4月1日、かれらが恵比寿に降り立つことが決定した。じつはかれらの来日公演は2年前にも実現しているのだけれど、今回はオフィシャルVJの Dreamrec も加わった「完全体」としてのパフォーマンスとなる。
また、その直前の3月31日には DOMMUNE にて特別番組が放送されることも決定している。お見逃しなく!
RPR SOUNDSYSTEM with Dreamrec VJ @LIQUIDROOM
あの奇跡の夜は序章だった。世界のミニマル・アンダーグラウンド・シーンのトップコンテンツ、RPR SOUNDSYSTEM (Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh / [a:rpia:r] ) が、今回オフィシャルVJのDREAMRECを伴った完全体での究極公演を実現! 来春LIQUIDROOMにて開催決定!!

近年の世界のアンダーグラウンド・ミュージックを席巻するルーマニアン・シーンのボス、Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh。2015年4月4日に実現したその彼ら3人によるRPR SOUNDSYSTEMのLIQUIDROOM公演は、わが国のクラブ・シーンの歴史に偉大な足跡を残してくれた。お客さんの熱気、場内の雰囲気、彼らのパフォーマンスの内容、どれを取っても最高という言葉では言い尽くせぬ、それまで経験した事のないほどの夢のような素晴らしい一夜であり、その熱狂は日本のシーンに語り継がれる歴史の1ページとしていまも記憶に新しい。
あの興奮から丸2年。彼らがあの同じ場所に帰ってくる。
さらに今回は彼ら [a:rpia:r] のオフィシャルVJであるDreamrecの来日も決定し、彼らがついに完全体となる瞬間が訪れる。2016年2月にここLIQUIDROOMでおこなわれた『Beat In Me feat. Rhadoo with Dreamrec VJ』で見せた彼のヴィジュアル・パフォーマンスは、日本のシーンにおいてかつておよそ目にした事のない斬新なイメージでの露出で、そこに集ったクラバーたち全員に強烈なインパクトを与え、2015のRPR3人による公演にひけを取らぬ最高のパーティであったとの評価を各方面から獲得する事となった。
現在の世界のクラブ・ミュージック・シーンにおける紛れもないトップ・コンテンツであるRPR SOUNDSYSTEMに、このDreamrec VJのヴィジュアルを加えた今回のこのキャスティング。アンダーグラウンド・ミュージック・シーンにおいてこれ以上の表現はない、最上級の音と映像の究極の形を今回初めて日本のファンに見せる貴重な機会となる。
■イベント・タイトル
RPR SOUNDSYSTEM with Dreamrec VJ @LIQUIDROOM
■日時
2017年4月1日 (土) 23:30 OPEN / START
■場所
LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net
■出演者
――1F LIQUIDROOM――
RPR SOUNDSYSTEM (Rhadoo, Petre Inspirescu, Raresh / [a:rpia:r])
Dreamrec VJ
――2F LIQUID LOFT――
KABUTO (DAZE OF PHAZE / LAIR)
PI-GE (TRESVIBES SOUNDSYSTEM / Vis Rev Set)
Junki Inoue (Toi Toi Musik)
■料金
早割:3,800円 (1/16 (月) 発売開始)
前売:4,800円 (2/13 (月) 発売開始)
当日:6,000円
Advance Ticket: clubberia, RA Japan, iFLYER, BANANA, disc union, Technique, Lighthouse Records, LIQUIDROOM
■問い合わせ
LIQUIDROOM 03-5464-0800 https://www.liquidroom.net
■※20歳未満の方のご入場はお断り致します。年齢確認のため、顔写真付きの公的身分証明書をご持参ください。(You must be 20 and over with photo ID.)
■Facebook Event Page
https://www.facebook.com/events/209168746155695/?active_tab=about
■RPR SOUNDSYSTEM
現行のシーンにおけるトップDJのひとりであり同時に現在世界を席巻するルーマニアのシーンの事実上のボスであるRhadoo、卓越したプレイはもとよりその生み出される作品群が世界最高レベルのクオリティの評価を獲得している唯一無二のアーティストPetre Inspirescu、2014年まで所属したCOCOONなどでのワールドワイドな活躍により3人のなかでも特にメジャー・シーンにおいても抜群の名声を確立しているRareshの3人によるスペシャル・ユニット。このRPR SOUNDSYSTEM名義で出演するイベントは世界でも彼らにより選ばれたトップ・イベント・フェスのみで、年に数回しか実現する事はない。
2007年に設立したレーベル [a:rpia:r] は世界中のアンダーグラウンド・シーンでカルト的な支持を集める。2013、14年には、ミックスCDシリーズの世界のトップ・ブランド『Fabric』に3人が立て続けに起用されるなど、不動の人気を誇るシーンのカリスマ的存在。近年においては年を追う毎にますますその人気と地位は高まり続けている。
■Dreamrec VJ (Ro, Sunrise)
Silviu Visan(Dreamrec VJ)は、ビデオ・マッピングからインタラクティブ・デザインまで、様々なプロジェクトを手がけるルーマニアのトップ・ヴィジュアル・アーティストだ。彼は過去数年間に渡り、[a:rpia:r] クルーのヴィジュアル面を担当しており、世界のミニマルミュージックのNo.1フェスティヴァルである Sunwaves(ルーマニア)など多くの重要なフェスティヴァルに出演している。2013年後半には、ロンドン・ヴィクトリア&アルバート博物館に展示されているトラヤヌスの記念柱のレプリカを使用し、モーション・グラフィックスや3Dアニメーションを組み合わせ、壮観なプロジェクション・マッピングをおこなうなど、近年ますます世界の各アートの様々な分野で実績を積み上げている。
https://vimeo.com/113155205