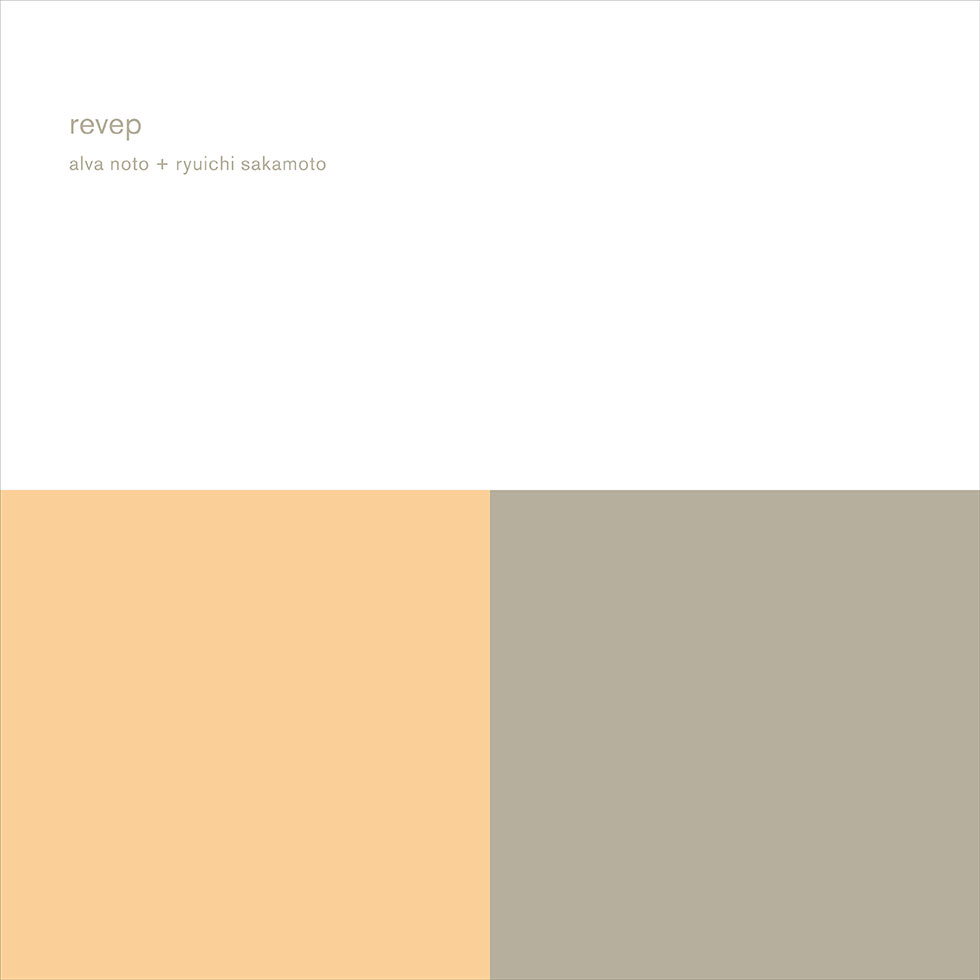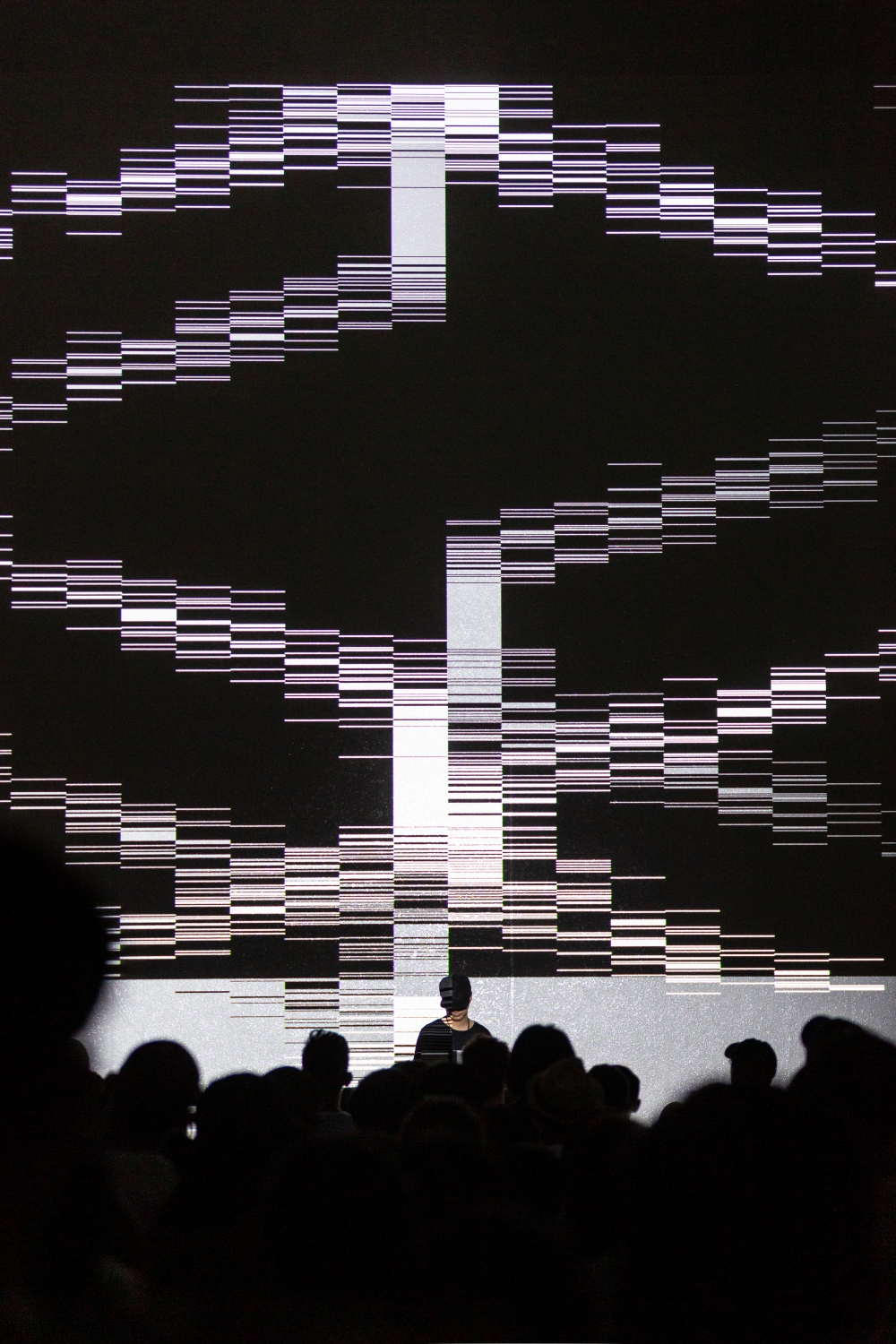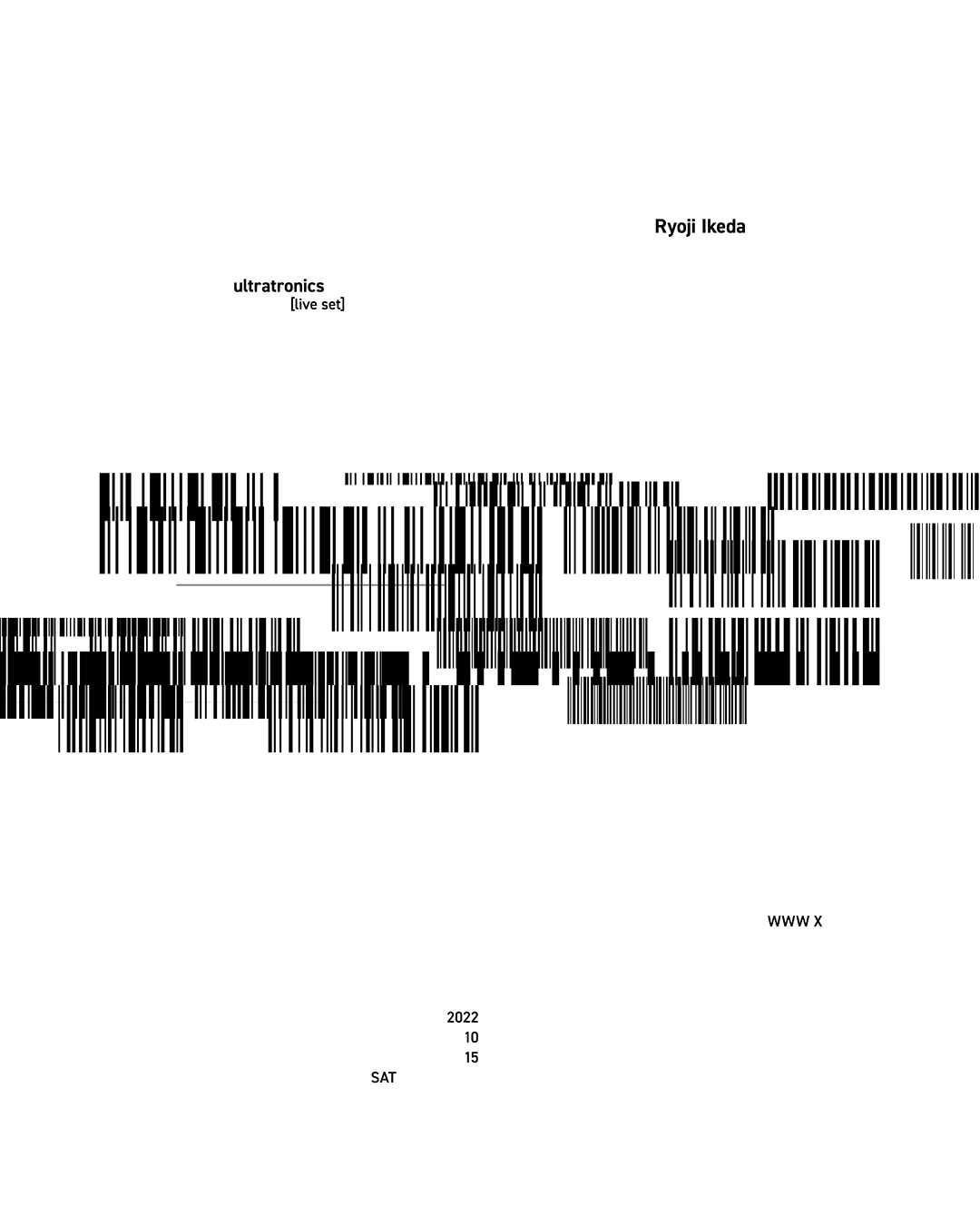Waajeed(ワージード)といえば、デトロイト・ヒップホップを代表するプロデューサーのひとりで、J Dillaとともにスラム・ヴィレッジのメンバーであり、PPP(Platinum Pied Pipers)としての作品も知られている。ワージードが、来る11月、ベルリンの〈トレゾア〉からソロ・アルバム『Memoirs of Hi-Tech Jazz』をリリース。まずはアルバムに先駆けて、シングル曲“Motor City Madness”が発表された。ヒップホップとテクノとジャズがブレンドされた素晴らしい曲だ
以下、資料より抜粋。
『Memoirs of Hi-Tech Jazz』は、デトロイトや世界中の黒人居住区における抑圧的なヘゲモニーに対する革命的な取り組みからインスピレーションを得た、レジスタンスを想起させるサウンドスコアである。このアルバムを抗議運動と並行してプレイすることはできるが、音楽は、抑圧の視線の外側に存在する平凡な瞬間により適している。暴力や不正義がまかり通っているが、それは私たちによっての唯一の物語ではない。私たちは、私たちを抑圧するモノどもよりも遙かに多くのものだ。このアルバムは、黒人の余暇と遊びを称えるもので、枯渇する現実にもかかわらず持続する平凡な喜びを表現している。

Waajeed
Memoirs of Hi-Tech Jazz
Tresor