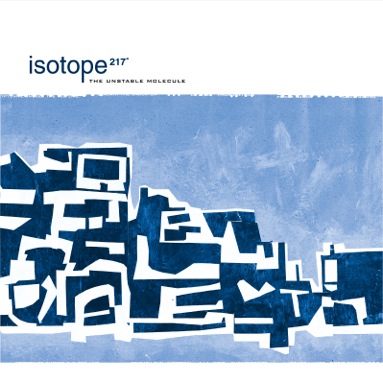Penguin Cafe The Imperfect Sea Erased Tapes / PLANKTON |
音楽の歴史において、「ブライアン・イーノ以前/以降」という区分は大きな意味を持っている。「アンビエント」の発明はもちろんのこと、それ以前に試みられていた〈Obscure〉の運営も重要で、そこから放たれた10枚のアルバムによって、新たな音楽のあり方を思索する下地が用意されたと言っても過言ではない。ペンギン・カフェ・オーケストラを率いるサイモン・ジェフスもその〈Obscure〉から巣立ったアーティストのひとりである。同楽団は「イーノ以降」のクラシック音楽~ミニマル・アンサンブル~アヴァン・ポップのある種の理想像を作り上げ、じつに多くの支持を集めることとなったが、残念なことにサイモンは脳腫瘍が原因で1997年に亡くなってしまう。
それから12年のときを経て、サイモンの息子であるアーサーがペンギン・カフェを「復活」させた。メンバーも一新され(現在はゴリラズのドラマーや元スウェードのキイボーディストも在籍している)、グループ名から「オーケストラ」が取り払われた新生ペンギン・カフェの登場は、ちょうど00年代後半から盛り上がり始めたモダン・クラシカルの潮流とリンクすることとなり、彼らの音楽は今日性を獲得することにも成功したのだった。であるがゆえに、彼らの新作『The Imperfect Sea』がまさにモダン・クラシカルの牽引者と呼ぶべきレーベル〈Erased Tapes〉からリリースされたことは、きわめて象徴的な出来事である。その新作は、これまでのペンギン・カフェの音楽性をしっかりと引き継ぎながら、クラフトワークやシミアン・モバイル・ディスコのカヴァーにも挑戦するなど、貪欲にエレクトロニック/ダンス・ミュージックの成分を取り入れた刺戟的な内容に仕上がっている。
10月に日本での公演を控えるペンギン・カフェだが、それに先駆け来日していたアーサー・ジェフス(ピアノ)とダレン・ベリー(ヴァイオリン)のふたりに、これまでのペンギン・カフェの歩みや新作の意気込みについて話を伺った。
僕の場合、父が亡くなったときはまだ子どもだったということもあって、悲しみよりは、音楽にまつわる父との楽しい思い出やものを引き継いでいく、というような感覚があったんだ。 (アーサー)

Photograph by Ishida Masataka
■1997年にペンギン・カフェ・オーケストラの創設者であるサイモン・ジェフスが亡くなって、2007年に没後10周年のコンサートがおこなわれました。その後2009年にアーサーさんを中心としたペンギン・カフェが始動します。ペンギン・カフェを始めようと思ったのはどのような理由からなのでしょう?
アーサー・ジェフス(Arthur Jeffes、以下AJ):父の没後10周年コンサートは3日間おこなったんだけど、そのときに父の時代のミュージシャンたちが集まってくれて、一緒に演奏することができたんだ。じつは僕にとってはそれが初めて人前で演奏するコンサートだったということもあって、緊張感もあったし、父と同世代のミュージシャンだから当然僕よりも年上で経験値もあって、あっちはあっちでこうあるべきと思っているんだけど、一応僕が父の息子という立場上、何か言わなければいけなくて……それで音楽の持つデリケートなバランスが壊れてしまったようなことがあったんだ。だから、そこから続けてやるというよりは、思い出の扉を閉めるようなつもりでやったんだよね。それから1年後にイタリアの友だちから「家に来て音楽をやってくれないか」って声がかかったんだ。
ダレン・ベリー(Darren Berry、以下DB):家ってもんじゃないな。あそこは城だったよ(笑)。
AJ:そこに呼ばれたので、ダレンとダブル・ベースのアンディ(・ウォーターワース)、ギターの(トム・)CCと行ってみたんだ。ワインを作っている広い農家で、友だちとやるという気楽さが良かったんだろうけど、プレッシャーも感じずにやってみたら、まるで父親の音楽が生き返ったような感覚を味わったんだよ。自分でも何かやってみようと思うようになったのはじつはそこからなんだよね。
■芸能の分野で世襲というケースはよく見られますが、一方で政治的な分野では世襲制は好ましくないものとされますよね。父のあとを継ぐということに関してはどうお考えですか?
AJ:たしかにイギリスの音楽でも世襲でやっているアーティストはたくさんいるからよくわかるけど、僕の場合、父が亡くなったときはまだ子どもだったということもあって、悲しみよりは、音楽にまつわる父との楽しい思い出やものを引き継いでいく、というような感覚があったんだ。難しいことを言えば、その音楽のストーリー性がうんぬんとか、こういうことをするのがはたして正しいのかとか、もし自分が新しくやるのなら名前も「ミュージック・フロム・ペンギン・カフェ」にするべきなのかとか、いろいろなことを考えたけど、それよりももっと感情的な部分というか本能的な部分というか、僕はそういうところで突き進んできたような気がするんだ。あとやっぱり最初の頃は、父が残してきた音楽があって、それを僕らがライヴでやる、というキャラクターが強かったからね。もちろん譜面に書かれたものどおりじゃない、僕らなりのアレンジも自由にできたし、ライヴの場においては自分の解釈でやっていくということがけっして間違いじゃないと思っている。
DB:「ライヴでこれを聴きたい」って人がたくさんいたんだよね。求められているという感覚もあったと思うよ。やっぱりアーサーのお父さんの音楽はたくさんの人に愛されていて、「またあれを聴きたい」という声も多くあったから、それを僕らなりにやっていこうじゃないか、というのがとっかかりだったと思う。あと、バンドだから楽器があって、たとえば“Music For A Found Harmonium”ってタイトルの曲があるんだけど、それは(アーサーの)お父さんがハーモニウムという楽器を見つけたことがきっかけになって書いた曲なんだ。それを、「その楽器はこれですよ」って目の前で弾いてあげるような感覚というのが僕らが提示したかったもののひとつなんじゃないかな。
■ペンギン・カフェ始動の2年後にアルバム『A Matter Of Life...』が出ます(2011年)。このときはどういう思いでアルバムを作ったのでしょうか?
AJ:そこにいたるまでの数年間にライヴ活動をやってきた結果、この先に進むにはまずいまの状態の自分たちを記録する必要があると感じて作ったアルバムだった。2010年にロイヤル・アルバート・ホールでライヴをやる機会があったんだけど、それで一区切りついたということもあって、父親の曲のカヴァーだけじゃなくて、ようするにありものの曲だけをやるミュージアム・バンドじゃないところに進んでいきたいという思いがあったから、あのアルバムははたしてそれが本当にできるのかというテストでもあったんだ。レコーディング自体は4、5ヶ月で終わって、僕らからしてみるとすごく早いペースでできた作品だったからすごく緊張していたね。そういう不安のなかで作っていて、「とにかくやってみよう」ということでやってみたんだけど、とてもいいものができたんじゃないかな。結果には満足しているよ。もちろん演奏のミスとか間違いがあったりもしたんだけど、それが逆におもしろいと思えたらキープして、不完全さを良しとするみたいなことをあのアルバムではやっていたんだよね。
■その後アーサーさんは、現ペンギン・カフェのもうひとりのヴァイオリニストであるオリ・ラングフォードさんとユニットを結成して、サンドッグという名義で『Insofar』(2012年)というアルバムをリリースします。それがペンギン・カフェではない名義で発表されたのにはどのような経緯があったのでしょう?
AJ:僕はたくさん曲を書いているから、なかにはペンギン・カフェっぽくないなと思うものができあがるときもあるんだ。それがどう違うかというのを説明するのは難しいんだけど、僕の感覚としてはそう思うところがあったので、いつも一緒にいたオリとサンドッグというユニットを作ったんだ。『A Matter Of Life...』の最後に“Coriolis”という曲があって、それは僕とオリだけで静かに繊細な音を奏でている曲なんだけど、こういう音をもうちょっと追求してもいいのかなと思ったんだ。でもそれはペンギン・カフェでやることではないと思ったから、オリとふたりのユニットという形でサンドッグが生まれたんだよね。ペンギンでやっているものよりはロマンティックというか、シネマティックというか、そういう方向性を追求したデュオだったね。
■そしてペンギン・カフェとしてのセカンド・アルバム『The Red Book』が2014年にリリースされます。これはどういうコンセプトで作られたのでしょうか? サンドッグの活動からフィードバックされたものもあったのでしょうか?
AJ:オリとふたりで音を作ったあとだったから、あのアルバムの制作に取りかかったときは、自分のなかにヴァイオリンとピアノの音が残っていたのかもしれない。そのふたつの楽器の色合いが強く出たアルバムだったと思う。考え方としては、世界を旅しながら、空想の世界のワールド・ミュージック、フォーク・ミュージックを作ったような感覚があって、前のアルバムに比べたら時間もかけたし、木材にサンド・ペーパーをかけてスムースに仕上げたような、すごく磨かれたアルバムになったんじゃないかなと思っているんだ。実際のレコーディングでは、グループが一同に集まって一緒に録るということをよくやったアルバムだったよ。
僕らにとっては他の人の、しかもいまのアーティストの曲をカヴァーするってこと自体が新しいことで、いままでかぶったことのない帽子をかぶるような感覚なんだ。〔……〕この楽器編成で僕らが演奏すれば絶対に僕らの音になる、という確信があるからこそできたことでもあると思う。 (ダレン)

Photograph by Ishida Masataka
■それらのリリースを経て、この夏、3枚めとなるアルバム『The Imperfect Sea』がリリースされたわけですけれども、これまでの作品とは異なる趣に仕上がっているように感じました。
AJ:前作『The Red Book』とはまったく違うアルバムを作りたかったんだ。一度やったこととは違うことをやりたいという意味だけどね。フォークやチェンバー的な部分は前作でだいぶ探求できたと思ったから、今回はそれとは離れたところにあるものを探求してみようという感覚で作り始めたんだ。それにあたって、前作の活動が一段落したところで1年間くらい活動を控えて、自分たちにあるものを見直してみようというふうに考えてみた。新しいテクスチャーに出会えた気がするよ。
DB:今回はダンス・ミュージック的な要素がかなり出ていると思うんだけど、これも前作の反動なんじゃないかと思う。ようするにリズムやポリリズム、ビートに引っ張られて走っていくような音楽というのはクラシック音楽とは違う要素で、今回はそれを意識的にやってみようと思ったんだよね。それも、一度リセットしたことによって出てきた発想だろうね。
■いまのダレンさんのお話とも繋がると思うのですが、今回のアルバムの9曲目はシミアン・モバイル・ディスコのカヴァーですよね。みなさんはふだんからそういった音楽を聴いているのですか?
AJ:そうだね! よく聴いているよ。いまはダンス・ミュージックの世界でおもしろいものがたくさん出てきているからね。あと僕らはいま〈Erased Tapes〉と組んでいるということもあって、そういうクロスオーヴァーは自然な発展だと思う。僕らからするとクラシカルな世界からエレクトロニックな世界へのクロスオーヴァーってことになるんだけど、エレクトロニックといっても僕らの場合は電子音を使うわけじゃなくて、エレクトロニック的なアプローチって意味でのクロスオーヴァーなんだ。
DB:僕らにとっては他の人の、しかもいまのアーティストの曲をカヴァーするってこと自体が新しいことで、いままでかぶったことのない帽子をかぶるような感覚なんだ。やってみると表現のしかたという意味でも、楽器の演奏のしかたという意味でもいろんな発見があって、自分たちが自分たちのために書いた曲とは違うから、(カヴァーを)やってみて自分を知るような機会にもなったし、すごく楽しかった。勉強になったよ。そういうふうに言えるのも自分たちのアイデンティティがしっかり確立しているからだと思うんだよね。何をどうやっても結局ペンギン・カフェの音になるんだ。この楽器編成で僕らが演奏すれば絶対に僕らの音になる、という確信があるからこそできたことでもあると思う。
■4曲目はクラフトワークのカヴァーですが、これもそういった理由から?
AJ:そうだね。じつを言うとペンギン・カフェ・オーケストラが初めてやった公演はクラフトワークの前座だったんだよ。そういう意味で歴史的にも気の利いた繋がりがあるというのと、あとはやっぱりこの系統の音楽の源泉にあるのはクラフトワークだし、彼らは絶対的な存在だから、やるんだったら源泉まで遡ってやろうということもあったね。
■先ほど〈Erased Tapes〉の話が出ましたが、ペンギン・カフェが始動した頃から「モダン・クラシカル」と呼ばれるような音楽が盛り上がってきて、そのムーヴメントとペンギン・カフェの復活がちょうどリンクしているように思ったのですが、そういうシーンと繋がっているという意識はありますか?
AJ:シーンの一員っていい気分だよね(笑)。でもたしかにそれはあると思う。パラレル的に、同時多発的に、いろんなところからスタートして似たようなことをやっている人たちが惹かれ合ってシーンができていくという感覚は僕もあるよ。〈Erased Tapes〉にはア・ウイングド・ヴィクトリー・フォー・ザ・サルンやニルス・フラームがいるし、そういった人たちがいろんなところから出てきて何かが始まっているという、そういうシーンのなかにいるというのはいいものだね(笑)。
■ペンギン・カフェの音楽にはアンビエント的な要素もあります。ペンギン・カフェ・オーケストラの最初のアルバム(1976年)はブライアン・イーノの〈Obscure〉からリリースされましたが、彼が提唱した「アンビエント」というコンセプトについてはどうお考えですか?
AJ:たとえば布のような、あるいは背景のような存在としての音楽、という考え方だと僕は思っているよ。ようするにストーリーを色濃く語ってくるわけでもないし、パターンが決まっているわけでもないから、アプローチとしてはどうすればいいのだろうと一生懸命考えていて。音楽として取り組むというよりは、たとえば風と対峙するような、壁紙を貼るような、床板を貼るような、あるいは水の流れと対峙するような感じで音楽を作っていくのがアンビエントなんじゃないかと思う。
DB:そうなんだよね。だから自分を取り囲む環境と同じように音楽があるという、そんな質感だと思うんだ。たしかに僕らの音楽にもそういう側面はあって、たとえば僕らのアルバムを3回通して聴いたとして、どこから始まってどこで終わったのかわからなくなるような、そういうところが僕らのアルバムにはあるんだよね。まさにそういう流れがアンビエントなのかなと思うね。
■イーノはここ数年、音楽に取り組む一方で政治的な活動もおこなっています。UKでは昨年ブレグジットがあったり、先日は総選挙があったりしましたが、そういう社会的な出来事はミュージシャンたちにどのような影響を与えると思いますか?
AJ:そういえば先日、バレエのプロジェクトの仕事があってアメリカに行ったんだけど、それがコール・ポーターの1921年の作品(“Within The Quota”)をリヴァイヴするというものだったんだ。それは当時、移民を禁じる新しい法律が布かれることに対するプロテストとして書かれた作品だったんだけど、じつはその仕事を受けた段階ではまだトランプが大統領に決まっていなくて、まさかこんなことになるとは思わずにプロジェクトを進めていたんだ。公演の当日にはすでにトランプが大統領になっていて、それどころか新しい移民法が布かれようとするなかでの公演になってしまった。そういうことを考えると、おそらくミュージシャンに右翼の人はあまりいないと思うんだよね。だいたいの人はリベラルな考えで音楽やアートをやっていると思うんだけれども、だからこそイングランドでもそういった政治的な動きに対するプロテストがすごく多くなっていて、実際にこの前の総選挙のときにチャートのナンバー・ワンになったのが(キャプテン・スカの)“Liar Liar”という曲だったし、音楽と政治の距離感というのはすごく縮まってきているような気がするよ。
DB:まったくそのとおりだね。アーティストで右翼ってそうそういないと思うんだ(笑)。やっぱり心を開いていないと芸術ってできないし、グラストンベリーでジェレミー・コービンが演説をするようなことがあるくらいだから、意識せずにはいられないところまできていると思う。あと、いまは学校から音楽教育が外されてしまっているんだけど、音楽はけっして贅沢品じゃないし、算数などと同じように、教育の場で提供されることによって、魂の部分だけじゃなくて脳の活性化もできるに違いないのにね。そういうことを重んじない政治が進んでいるということに対して、年配の世代だけじゃなく若い世代も敏感になっているんじゃないかな。やっぱり音楽や芸術の存在は年寄りよりも若い人にとってすごく身近なものだと思うからね。
ペンギン・カフェ来日公演2017
●10/05(木) 東京・渋谷クラブクアトロ
18:30 開場/19:30 開演
前売:6,000 円/当日:6,500 円(全自由/税込)
※チケット発売日:07/08(土)より
問:渋谷クラブクアトロ 03-3477-8750
●10/07(土) 東京・すみだトリフォニーホール
special guest:やくしまるえつこ/永井聖一/山口元輝
16:30 開場/17:15 開演
前売S 席:6,800 円/前売A 席:5,800 円(全席指定/税込)
※チケット発売日:07/08(土)より
問:プランクトン 03-3498-2881
●10/09(月・祝) まつもと市民芸術館主ホール
special guest:大貫妙子
14:30 開場/15:00 開演
一般:5,800 円/U25:3,800 円(全席指定/税込)
※チケット発売日:06/24(土)より
問:まつもと市民芸術館チケットセンター 0263-33- 2200
●10/10(火) 大阪・梅田クラブクアトロ
18:30 開場/19:30 開演
前売:6,000 円/当日:6,500 円(全自由/税込)
※チケット発売日:07/08(土)より
問:梅田クラブクアトロ 06-6311-8111
お客様用総合info:プランクトン03-3498-2881

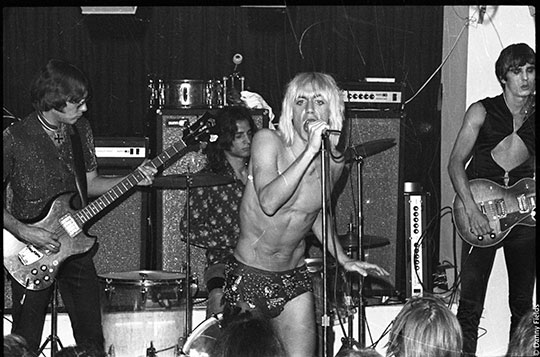




 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
 Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.
Photo by MARY CYBULSKI ©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.