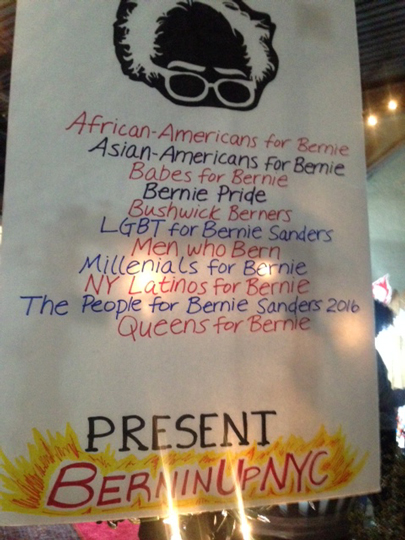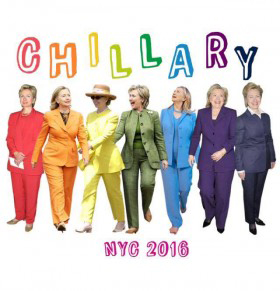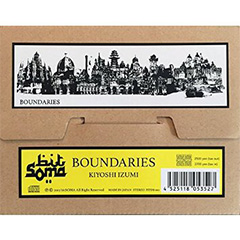なんと厳しくも、美しい音楽だろうか。まさに極寒の音響空間。アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の映画『ザ・レヴェナント 蘇りし者』のサウンド・トラックのことである。
本作を生み出した音楽家は、坂本龍一、アルヴァ・ノト、ブライト・デスナーの3人。坂本龍一ファンでもある監督から坂本個人にオーダーがあり(『バベル』では“美貌の青空”が使われていた)、坂本がアルヴァ・ノト=カールステン・ニコライに協力を求め、さらに監督がオーケストラ的要素としてブライト・デスナーを起用したという。 ここでは中心人物である坂本龍一に焦点を当てて分析してみたい。
坂本龍一の音楽には、大きく分けて2つの系譜がある。ひとつはリリカルで叙情的なメロディと浮遊感のある和声で、20世紀フランス印象派、ドビュッシーの系譜に繋がる作曲家の系譜。もうひとつは、未知の音色と音楽を希求して追求する実験的な音楽家としての系譜である。
このふたつは、坂本龍一という音楽家のなかで分かち難く一体化しており、氏のソロ.・アルバムにおいては、フランス印象派風の響きと電子音楽から無調、未来派によるノイズまで、近代から20世紀以降のあらゆる音楽的な実験のエレメントや、アフリカ音楽から沖縄民謡までの非西欧音楽などが交錯していく。それは初期の『千のナイフ』『B-2ユニット』から近年の『キャズム』『アウト・オブ・ノイズ』まで変わらない。
いわば巨大な音楽メモリ/装置としての存在、それが坂本龍一なのだ。その意味で、氏は言葉の真の意味でポストモダンな音楽家である。氏は自身に「根拠がない」ことを繰り返し語っていた。ゆえに「外部」が必要になるとも。だからこそ坂本龍一にとって「外部」としてのコンピュータが重要であり、それは「電子音楽」への追求でもあった。自己を相対化すること。じじつ坂本龍一の先鋭的な個性はコラボレーションやサウンド・トラックに表出しやすい。『エスペラント』、『愛の悪魔』などなど。
だが「外部」はコンピュータに限らない。真の「外部」は「人」ではないか。それゆえ彼は多くのコラボレーションを実践してきた。カールステン・ニコライやクリスチャン・フェネス、テイラー・デュプリーなど電子音響/エレクトロニカのアーティストとのコラボレーションなどは、コンピュータが「外部」というより、自分の拡張デバイスとなった時代において、当然の帰結であったのだろう。そもそも彼らの音楽は、人との聴覚を拡張するアートであったのだから。
なかでも『Vrioon』以来、10年を超える共闘を続けているカールステン・ニコライ=アルヴァ・ノトとの仕事は重要である。音の建築の中に、微かなポエジーとロマンティシズムを称えるカールステンの作品と、坂本との音楽性との相性は(意外にも)良い。残響の果てに溶けあうノイズへの感性が共通するからだろうか。
そのふたりの新作が本作だ。真冬の、身を切るような、氷の音響。ここでは弦も、電子音響も、音楽の消失点に鳴るような過酷なノイズを生成している。オーケストラとの共演という意味では、2008年の『utp_』を思わせもするが、それよりも遥かに厳しい音のタペストリーだ。
1曲め“ザ・レヴェナント・メインテーマ”のギリギリまで和声が削ぎ落とされた響きが、本作のトーンを決定していく。まるで絶望の中の光のような音楽。背後に微かに鳴る電子音も素晴らしい。2曲め“ホーク・パニッシュ”はアルヴァ・ノトとブライト・デスナーの曲だが、メインテーマの変奏であるのは明確だろう。3曲め“キャリング・グラス”は坂本とアルヴァ・ノトの共作で、微かな記憶の片鱗のような電子音に、硬質な弦、砂塵のような電子ノイズが折り重なる。5曲め“キリング・ホーク”は坂本単独曲で、『愛の悪魔』を思わせる低体温の電子音に、鋭くも厳しい弦楽が鳴り響く。また、坂本単独曲の13曲め“ザ・レヴェンタント・テーマ2”、“ザ゙・レヴェナント・メイン・テーマ・アトモスフェリック”で聴かれる香水のような芳香を放つピアノも美しい。19曲め“キャット&マウス”は坂本龍一、アルヴァ・ノト、ブライト・デスナーの共作で、電子音からオーケストレーション、アフリカン・リズムが交錯し、音楽史と音楽地図と越境するような刺激的なトラックに仕上がっている。3人の共作では、電子ノイズと打楽器と弦楽が拮抗しあう“ファイナル・ファイト”も緊張感も印象的だ。
どの曲もサントラの機能性を保持しながらも、しかし独立した楽曲として素晴らしいものである。オリジナル・アルバムとしてカウントしても良いのではないかと思うほどに(『エスペラント』がそうであるように)。
とはいえ、このような音楽作品に仕上がったのは、やはり「映画」という「外部」が重要に思えるのだ。映画とは監督のものだ(もしくはプロデューサー?)。そこでは音楽家は否が応でも、映画というプロジェクト=「外部」と接することになる。ことイニャリトゥ監督は音楽に拘りを持っている映画作家であり(氏はメキシコでDJもしていたという)、『バードマン』では、アントニオ・サンチェスのドラム・ソロ・トラックを映画音楽のメインに据えるという革新的なことを成し得たほど。つまり音楽への要求は(異様に)高いはず。
じっさい、その音楽制作は度重なる修正などが6ヶ月ほどに渡り続くという過酷なものであったようだ。加えて坂本は重病の治療から復帰したばかりでもあった。いわば映画という「外部」、病という自身の身体に起きた「外部」という二つの状況のなかで、本当に大切な響きを吸い上げるように、音を織り上げていったのではないか。そこにおいて「外部」としてのコラボレーターの存在は、暗闇を照らす光のような存在だったのではないかとも。
じじつ、坂本は素晴らしい共演者と巡り合うことで、自身の音楽の深度をより深めてきた音楽家である。このサウンド・トラックの仕事はたしかに過酷であったのだろうが、しかし、生み出された作品は、氏のディスコグラフィにおいて、ほかにはない「光」を放っている。ギリギリまで和声を削いだ響きに、苦闘の果てのルミナスを聴くような思いがするのだ。それは命への光、のようなものかもしれない。
急いで付け加えておくが、このアルバムにエゴは希薄だ。外部としての映画。外部としてのコラボレーション。相対化し複数化する個。カールステン・ニコライ、ブライト・デスナーらという共演者と音楽は、それぞれの音の層が重なり合い、電子音響でも、アンビエントでも、クラシカルでもない音響を生み出していく。あえていうならばサウンドスケープだ。個がありながらも、個が消え去り、ただ音響が生成すること。
日本盤ライナーでカールステン・ニコライがタルコフスキーの名を出していたが、たしかに本作には「ポスト・タルコフスキー的宇宙」とでも称したい、現実の世界との音響の境界が消えゆくような音楽の未来=サウンドスケープが鳴り響いているように聴こえてならないのだ。