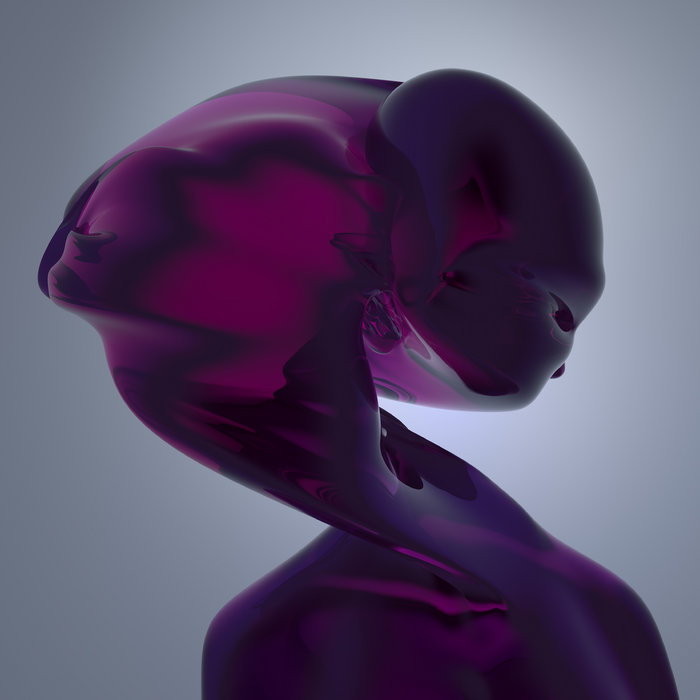先日不失者の2デイズ・ライヴ情報をお伝えしたばかりだが、また新たなニュースの到着だ。
2016年、灰野敬二が若手の実力派たちと結成したロック・バンド「HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS」。同バンドで灰野はヴォーカリストに徹し、自身の原点たるロックンロールやR&B、ソウルやジャズを英語で歌い、精力的にライヴをこなしてきた。その音源は昨年、ロンドンの Cafe Oto からデジタルでリリースされているが、きたる5月11日、待望のスタジオ・アルバムがリリースされる。
また、6月15日には渋谷WWWにて同作のリリース記念ライヴが開催。チケットの販売は明日から。ご購入はお早めに。
灰野敬二率いるリアル・ロック・バンド、HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS待望のスタジオ・アルバム、5/11リリース。6/15に渋谷WWWにてリリース記念ライヴを開催。
これだけがロック。私が言うロックという言語を、古文書の封印が解かれていくように開示する。――灰野敬二
1970年に前衛ロック・バンド、ロスト・アラーフのヴォーカリストとしてデビュー、1978年に不失者を結成、それ以来ソロのほかに滲有無、哀秘謡、Vajra、サンヘドリンなど、多様な形態で活動し、国際的に高い評価を受ける音楽家・灰野敬二。
常に「今」を追求しつづけている灰野が、川口雅巳(Kawaguchi Masami's New Rock Syndicate)をはじめ若手実力派ミュージシャンとともに2016年に結成したロック・バンド、HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKSの待望のスタジオ・アルバム。
録音はアナログ・レコーディングで定評のあるGOK SOUNDにて、エンジニアにバンドが絶大な信頼を寄せる近藤祥昭を迎えて行われた。
灰野がヴォーカリストに徹し、自らの原点といえるロックンロール、R&B、ソウル、ジャズ、そして日本の曲も英語で歌うという明確なコンセプトを打ち出し、精力的にライヴ活動を展開、2021年にイギリスのレーベルから配信でライヴ音源がリリースされ好評を得た。
ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ドアーズ、ボブ・ディラン、ザ・フーなどの名曲が、徹底的に解体・再構築され、曲の“本性”がむき出しになった究極のリアル・ロック。その衝撃は世代を問わず幅広いロック・ファンにアピールするでしょう。
6月15日に渋谷WWWにて本作のリリース記念ライヴを開催。リアル・ロックを体感してほしい。
HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS
灰野敬二 HAINO KEIJI vocal, harp
川口雅巳 KAWAGUCHI MASAMI guitar
なるけしんご NARUKE SHINGO bass
片野利彦 KATANO TOSHIHIKO drums

[リリース情報]
アーティスト:HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS
Title: You’re either standing facing me or next to me
タイトル:きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか
レーベル:P-VINE
フォーマット:CD
商品番号:PCD-28048
価格:定価:¥3,080(税抜¥2,800)
発売日:2022年5月11日(水)
収録曲
01. Down To The Bones
02. Blowin' In The Wind
03. Born To Be Wild
04. Summertime Blues
05. Money (That's What I Want)
06. Two Of Us
07. (I Can't Get No) Satisfaction
08. End Of The Night
09. Black Petal
10. Strange Fruit
11. My Generation
フォーマット:LP
商品番号:PLP-7849
価格:定価:¥4,180(税抜¥3,800)
発売日:2022年9月7日(水)
完全限定生産
収録曲
A1 Down To The Bones
A2 Blowin' In The Wind
A3 Born To Be Wild
A4 Summertime Blues
B1 (I Can't Get No) Satisfaction
B2 End Of The Night
B3 Black Petal
B4 Strange Fruit
B5 My Generation
[ライヴ情報]
HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS
出演:HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS
日程:2022年6月15日(水)
会場:渋谷WWW
時間:開場18:30 開演19:30
料金:前売¥4,000(税込/ドリンク代別/全自由)
チケット一般発売:4月2日(土)10:00 e+にて
問い合わせ:WWW 03-5458-7685
https://www-shibuya.jp
灰野敬二が若手実力派ミュージシャンとともに結成したロック・バンド「HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS」。灰野がヴォーカリストに徹し、自らの原点といえるロックンロール、R&B、ソウル、ジャズ、そして日本の曲も英語で歌うという明確なコンセプトを打ち出す。
2021年にはロンドンのCafe Otoからデジタルリリースし好評を博したそのバンドの待望のスタジオ・アルバム「You’re either standing facing me or next to me」が5月11日P-VINEからリリース、リリース記念ライブを6月15日に開催する。
ロックの衝撃がここにある、本当のロックを聴きたい人は、集まれ。