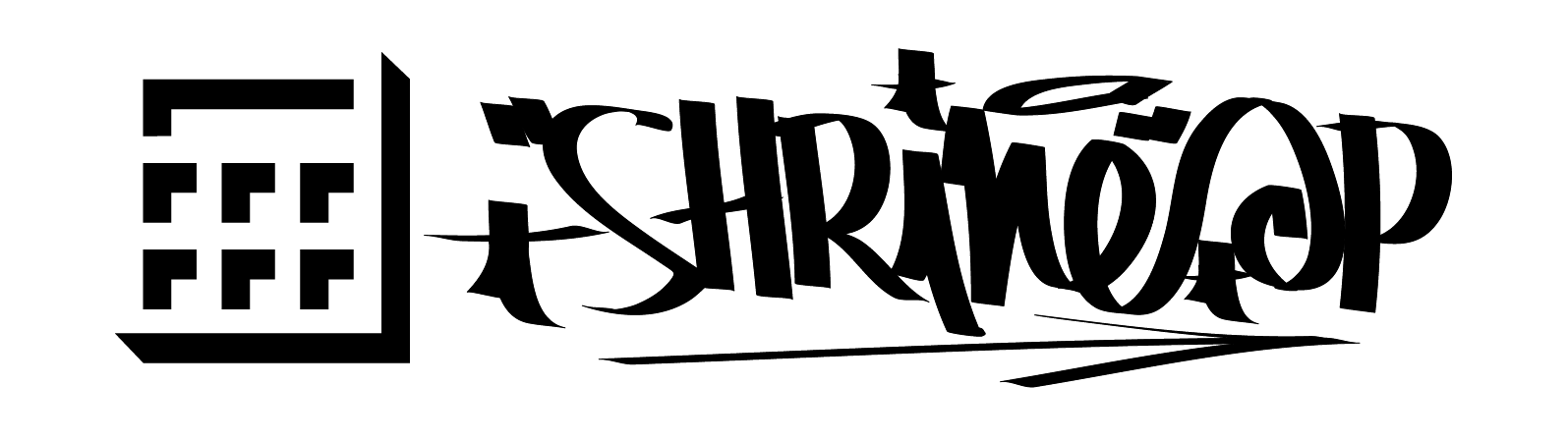ケンドリック・ラマーは今年リリースした新作で、驚くべきことにU2をフィーチャーしている。さらに彼は来年、ジェイムス・ブレイクとともにヨーロッパを回るのだという。いまでも黒人たちの一部は心の底から白人たちを嫌っているという話も聞くが、どうやらケンドリックはそうではないらしい。彼の選択はたぶん、そういう対立を少しでも突き崩していこうという試みなのだろう。それがどこまで成功するのかはわからない。過度な期待はいつだって裏切られる。そう相場は決まっている。
そんなケンドリックの果敢な試みに代表されるように、近年ブラックのサイドが積極的にホワイトのサイドへとアプローチしていく動きが目立っている。その起点となったのはおそらく去年のビヨンセのアルバムだろう。彼女はその力強く気高い作品で、ジャック・ホワイトやジェイムス・ブレイクといった白人のアーティストたちを積極的に起用した。その横断的なチャレンジは、エリオット・スミスやギャング・オブ・フォーをサンプリングしたフランク・オーシャンや、デイヴ・ロングストレスとの共作を試みたソランジュへと受け継がれることになる。そして今春、ついにジェイ・Zまでもが自身のアルバムにジェイムス・ブレイクを招待するに至った。そのトラックでブレイクとともにプロダクションを手掛けていたのが、マウント・キンビーの片割れ、ドミニク・メイカーである。つまり、引く手あまたのブレイクだけでなく、その盟友たるマウント・キンビーもまた、そのような越境ムーヴメントの一端をホワイトの側から支える存在になったということだ。
そんな背景があったので、以下のインタヴューではドミニクにそういう昨今の傾向について尋ねているのだけれど、どうもうまく質問の意図が伝わらなかったようで、「近年はUSのメジャーとUKのアンダーグラウンドが結びついていっているよね」という話になってしまっている。こうして期待は裏切られるのである。
 Mount Kimbie Love What Survives Warp / ビート |
それはさておき、最初にマウント・キンビー4年ぶりのアルバムがリリースされると聞いたときは、それはもう胸が躍った。“We Go Home Together”や“Marilyn”といったトラックが公開される度に、勝手にイメージを膨らませては「今回はぐっとR&B~ソウルに寄った作品になるんじゃないか」「いや、彼ららしいダウンテンポなムードをより洗練させたものになるんじゃないか」などと予想を繰り返していた。そうして迎えた夏の終わり、いざ蓋を開けてみると――これがクラウトロックなのである。冒頭の“Four Years And One Day”からしてそうだ。完全にやられた。アルバム全体が、何やらパンキッシュなエナジーに満ち溢れている。いや、たしかにバンド・サウンドそれ自体は前作『Cold Spring Fault Less Youth』でも試みられていたけれど、それがここまで大胆に展開されるとは思いも寄らなかった。こうして期待は裏切られるのである。
クラウトロックだけではない。マウント・キンビーの新作『Love What Survives』には、さまざまな音楽の断片がかき集められている。本作を聴き込めば聴き込むほど、それらの断片たちが要所要所で効果的な役割を果たしていることに気がつくだろう。そういえば本作をインスパイアした楽曲を集めたという彼らのプレイリストでは、ロックからアフリカ音楽まで多様な楽曲がセレクトされていたし、彼らがやっているNTSのラジオ番組には、ジェイムス・ブレイクやキング・クルールといったお馴染みの面子に加え、ウォーペイントやケイトリン・アウレリア・スミス、アクトレスからウム・サンガレ(!)まで、じつに興味深いアーティストたちがゲストとして招かれていた。つい先日も、アルバム収録曲の“You Look Certain (I'm Not So Sure)”をケリー・リー・オーウェンスがリミックスしたばかりである(彼女はマウント・キンビーの欧州ツアーのサポート・アクトにも抜擢されている)。そんな彼らのレンジの広さや音楽的探究心の断片を、クラウトロック~ポストパンクというムードのなかにさりげなく、だがこの上なく巧みに落とし込んでみせたのが、この『Love What Survives』というアルバムなのだ。
10月9日、この取材の後に渋谷WWWXにておこなわれた彼らのライヴは、荒削りな部分が目立つ場面もあったものの、アルバム以上にエネルギッシュな熱を帯びており、まるで新人ロック・バンドのステージを観覧しているような気分になった(ファーストやセカンドの曲が新たに生まれ変わっている様もじつにスリリングだった)。いや、じっさい、4人編成という点において彼らは新人である。つまり……マウント・キンビーは今回のアルバムやパフォーマンスで、いわゆる「初期衝動」のようなものを演出しようとしているのではないか。そう考えると、なぜ彼らがこの新作に『Love What Survives』という意味深長なタイトルを与えたのか、その動機が浮かび上がってくる。「生き残るもの」とは要するに、かれらが最初に音楽を作り始めたときに抱いていた気持ちや勢い、刺戟のことだったのである。
そんなわけで、「生き残るもの」というのはきっと政治的・社会的に虐げられている人びとを暗示しているのだろう、という小林の浅はかな先入観は見事に覆されることとなった。そして、ファースト・アルバム『Crooks & Lovers』のジャケに映っていたのはおそらくチャヴだろう、という編集部・野田の予想も外れてしまった。こうして期待は裏切られるのである。そんな素敵な裏切り者ふたりの言葉をお届けしよう。
よくわかっていないからこそ、そういう音楽のスペースのなかで、自分たちなりの解釈で何かをやってみるのもおもしろいんじゃないかと思ったんだ。 (カイ)
■マウント・キンビーの音楽について、日本ではいまでも「ポスト・ダブステップ」という言葉が使われることがあるんですが、UKでもまだそう括られることはありますか?
カイ・カンポス(Kai Campos、以下カイ):いまその括りは死につつあるね(笑)。たしかに、僕らが初めてのアルバムを作った2010年当時、その言葉と一緒にその手の音楽がバーッと出てきて、ほんの短期間のうちにダブステップという音楽の概念がガラッと入れ替わった時期があったと思うんだけど、いまはだいぶ死に絶えてきているね。たぶんこのアルバムが出たあとには完全になくなるんじゃないかな(笑)。
■これまでそう括られることにストレスは感じていましたか?
ドミニク・メイカー(Dominic Maker、以下ドム):いや、けっしてその呼び名に納得はしていなかったけど、とくに気にもしていなかったよ。とにかく自分たちの音楽がひとつの箱に収まりきらないようなものであってほしい、ジャンルの境界を跨いでいるようなものであってほしいという意識で音楽を作ってきたし、じっさいいろんなことをやっているから、それが「ポスト・ダブステップ」だろうがなんだろうが、ひとつの言葉で括ってしまうのは僕らの音楽にはふさわしくないんじゃないか、という思いはつねにあったね。
■今回のアルバムからはクラウトロック~ジャーマン・ロックの影響を強く感じました。
カイ:たしかにいままでやっていたエレクトロニック系の音楽よりも、ちょっと前の時代のエレクトロニック・ミュージックに遡ったようなところはあるよね。クラウトロックやジャーマン系の音に聴こえるというのは僕らも認めるところだけれども、僕らはけっしてそのジャンルに詳しいというわけではないんだ。(クラウトロックを)ずっと聴いてきてよくわかっているからそれをいまやってみた、ということではないんだよ。逆に、よくわかっていないからこそ、そういう音楽のスペースのなかで、自分たちなりの解釈で何かをやってみるのもおもしろいんじゃないかと思ったんだ。「セミ・エレクトロニック・ミュージック」とでも言うのかな。過去を振り返って、リズムや楽器の編成といったところからアイデアを引っ張ってきて作ったのが今回のアルバムかな。
■他方で本作からは80年代のポストパンク~ニューウェイヴの匂いも感じられます。そのあたりの音楽も参照されたのでしょうか?
カイ:その手の音楽はUKではかなり広く愛されていたから、僕らも自ずと踏んできてはいると思う。当時はブリティッシュ・ミュージックのなかでもおもしろい時代だったと思うし。ただ僕らの場合、たとえばスクリッティ・ポリッティとか、ああいったバンドは最近になって聴いているんだよね。あの頃の音楽が持っていた、とくにパンクのアティテュードに見られるようなポジティヴな要素を自分たちのアルバムの制作過程に持ち込んだというか、そういうことは今回あったような気がする。あと他にもこのアルバムには、自分たちの音のパレットが幅広くなればと思って、ソウルやディスコみたいなものも組み込んだつもりなんだ。だからいろんな音が聴こえてくると思う。でもけっして後ろばかり振り返っているわけではなくて、あくまで前に進もうとしている作品だと思っているよ。
■昨年リリースされたパウウェルのアルバムはお聴きになりました?
ドム:聴いたと思う。バンドっぽいやつだよね? 僕は好きだったよ。聴いていて楽しかった。
■エレクトロニック畑の人がパンキッシュなサウンドをやるという点で、今回のアルバムと繋がりがあるように思ったんですよね。
カイ:そりゃそうだろうね。だってこういう発想は僕らが思いついたものではないし、大きな流れのなかで、いろんな人が同時発生的にやってみたくなった時期なのかもしれないからね。

Photo by Masanori Naruse
じつを言うとキング・クルールとの曲の歌詞はいまだに意味がわかっていないんだ(笑)。まだ解読中だね(笑)。 (カイ)
■今回のアルバムに影響を与えた楽曲のプレイリストが公開されていますが、そこではロバート・ワイアットやアーサー・ラッセル、スーサイドやソニック・ユース、ウィリアム・バシンスキからアフリカのバンドまで、かなり多様な楽曲がピックアップされていました。それらはおふたりが今回のアルバムを作っていく過程で発見していったものなのでしょうか?
ドム:あれはじつは、僕らはラジオ番組をやっていたんだけど、それ用のプレイリストという側面が大きいんだ。曲をかけるためにいろんなものをチェックして聴いていくなかで幅が広がっていったんだけど、その作業で見つけた曲もプレイリストに入っている。番組をやっていく過程でかなり大量の音楽を吸収して消化したんだ。それは今回のアルバムにも影響を与えていると思う。あと、番組に来てくれたゲストから教えてもらったものもあるね。僕らがリスペクトしている人が来てくれたんだけど、どんなふうに音楽を作っていくのか聞いていくなかでおもしろいものと出会ったりして、そういうこともすべてあのプレイリストには詰め込まれているんだよね。
カイ:そうやって考えるとおもしろいね。そういう流れがあってあのアルバムに至っている、ということがプレイリストからもわかるよね。
■今回のアルバムには4組のゲストが招かれています。キング・クルールは前作にも参加していましたが、4曲目の“Marilyn”にフィーチャーされているミカチューはどのような経緯で参加することになったのでしょう?
カイ:ミカチューは、僕らふたりが音楽を作り始める前からファンだったんだ。知り合ったときに「いつか一緒にやろう」という話をしていたんだけど、それから2年くらい話が続いていて(笑)。今回いよいよ一緒にやる機会に恵まれたわけだけど、作ってみたらあっという間で、すごく相性がいいのかなと思える時間だったよ。だから、僕らにとってはようやく実現できたスペシャルなトラックなんだ。
■その“Marilyn”はアルバムの他の曲と趣が異なっていますが、7曲目の“Poison”や、ジェイムス・ブレイクが参加している8曲目の“We Go Home Together”と11曲目の“How We Got By”の2曲も他の曲と雰囲気が異なっているように感じました。本作をこのような構成にしたのはなぜですか?
ドム:今回のアルバムは全体を通してすごくヴァラエティに富んでいると思う。いま挙げてくれた曲に限らず、個性的な曲ばかりが詰まっていると思うんだけど、それだけにアルバム全体の流れというか、全体で聴いたときの消化具合がうまくいくように、ということをすごく考えて曲順を決めたんだ。ミカチューとの曲もジェイムスとの曲もそうだけど、自分の頭のなかで曲順を組んでみたときに、“Marilyn”は突出しているという印象があって。(この曲は)アーサー・ラッセルの影響がすごく大きいと思うんだけど、とくにユニークな曲だからアルバム全体の流れのなかで活かしたいと考えたんだ。
[[SplitPage]]ジェイ・Zから「ジェイムス(・ブレイク)に歌ってほしい」というオファーがあったんだ。そのときちょうど僕がジェイムスが歌うことを想定して書いていた曲があって、それをやろうかってことになったから、僕も関わることになったんだよ。 (ドム)
 Mount Kimbie Love What Survives Warp / ビート |
■春頃から少しずつアルバムの収録曲が公開されていきましたが、先行公開曲のセレクションに関しては何か意図があったのでしょうか? 公開された曲からぼんやりとアルバムのイメージを膨らませていたのですが、蓋を開けてみると想像していたのとはまったく違い、とてもパンキッシュで驚きました。
カイ:最初に何を公開するかみんなと話し合ったときに意見が一致したのは、ゲスト・ヴォーカルの入っている曲から公開するのが理に適っているんじゃないか、ってことだった。やっぱりヴォーカルが入っているというのはみんなに伝わりやすいだろうし、わかりやすいよね。それを聴いて「アルバムはどんな感じなんだろう」という期待感を煽る狙いで最初の2曲(“We Go Home Together”、“Marilyn”)を選んだんだ。でも、その2曲はみんなが消化するのにちょっと苦労する曲だったかもしれない。それをあらかじめ出しておいて、他の曲より先に聴いてもらうことによって、あとでアルバムを聴いたときに、その曲のあいだにあるどの曲もフィットしたものに聴こえるようになる、という枠組みを提示することができたかもしれないね。
ドム:ジェイムスの曲もミカの曲もそうだけど、僕らはしばらく鳴りを潜めていたから、タイトルのなかにそういう有名な人の名前(ビッグ・ネーム)が入っていることによって注目を集めることができるんじゃないか、という意図もあったね。
■いまヴォーカル曲の話が出ましたが、今回のアルバムにはハードな生活を送っている人たちの登場する曲が多いように感じました。リリックに関して何かコンセプトやテーマのようなものはあったのでしょうか?
カイ:歌詞は、僕らと客演してくれたシンガーとで一緒になって作ったんだけど、基本的には彼らが伝えたいストーリーをそのまま語ってもらえればいいと思っていたんだ。だから僕らが影響を与えたというか、注文をつけたことがあるとすれば、「この曲にはこういうふうに(言葉を)乗せてほしい」という、歌い回しやフレージングに関することだね。「ここに乗せるためには音節はこうじゃないほうがいい」とか、そういう注文はしたけれど、歌詞の内容に関しては自由にやってもらったよ。だから、(それぞれの)曲のメッセージには一貫性がないんだ。でも、そういうふうにやってもらったほうが幅の広さという意味でいいレコードになるんじゃないかと思って。ただ、レコーディングの段階では僕らも完全には歌詞を咀嚼しきれていなくて、じつを言うとキング・クルールとの曲の歌詞はいまだに意味がわかっていないんだ(笑)。まだ解読中だね(笑)。でもライヴでやるときは、あくまでも僕らのものとして消化してやっているから、歌詞の内容もレコードよりももっとフォーカスした内容になっているんじゃないかな。
■ドミニクさんはいまLAに住んでいるんですよね。
ドム:そうだね。
■LAへ移住したのはなぜ?
ドム:ガールフレンドが向こうに住んでいたからだよ。(移住して)もう2年になるね。天気もいいし、楽しんでいるよ。
■ということは、今回のアルバムの制作はカイさんとデータをやり取りする形で進めていったのでしょうか?
ドム:いや、行ったり来たりしながら作ったよ。(UKには)しょっちゅう行くから。ノルウェー航空とかの安い航空券を買ってね(笑)。
■なるほど。ではおふたりはわりと頻繁に会われているんですね。
ドム:そうだね。メインのスタジオはロンドンにあるんだけど、レコーディングの終盤には感覚やリズムを取り戻したいと思ってライヴを始めたんだ。今度のバンド編成はわりかし新しいものだから、アルバムが出る前からライヴに打ち込みたくて、ロンドンでライヴ活動はしていたよ。そういう意味ではLAに住んでいるからどう、ということもないかな。
■ドミニクさんはジェイムス・ブレイクと一緒に、今年出たジェイ・Zの新作『4:44』に参加しています(“MaNyfaCedGod”)。それはどういう経緯で実現したのですか?
ドム:そもそもはジェイ・Zから「ジェイムスに歌ってほしい」というオファーがあったんだ。そのときちょうど僕がジェイムスが歌うことを想定して書いていた曲があって、それをやろうかってことになったから、僕も関わることになったんだよ。結局2曲で参加する形になったけど、作り方が僕らの慣れているやり方とぜんぜん違っていて、でもそれだけ勉強になったね。いい経験だったよ。

Photo by Masanori Naruse
音楽を作るときの刺戟って僕らがファーストを作ったときと何も変わっていないんだよね。そういう気持ちや勢いが「Survive(生き残る)」ってことなんだ。 (カイ)
■ジェイムス・ブレイクは昨年ビヨンセのアルバムに参加していました。また、昨年話題になったフランク・オーシャンのアルバムではエリオット・スミスやギャング・オブ・フォーなど、いわゆる白人の音楽がサンプリングされていて、今回のドミニクさんとジェイ・Zとのコラボもそうなのですが、最近ブラック・ミュージックのビッグなミュージシャンたちが積極的にホワイトの文化を取り入れていっている印象があります。10年前や20年前にはあまりなかったことだと思うのですが、そういう昨今の流れについてはどうお考えですか?
ドム:ドレイクもジャマイカのアクセントを真似して歌ってみたり、グライムが好きで聴いていたりするから、そういう流れはたしかにあるよね。
カイ:カイラの“Do You Mind”(2008年)というUKファンキーの曲があって、むかしUKでビミョーに、ちょっとだけヒットした曲なんだけど、ドレイクの“One Dance”(2016年)ではそれをバックトラックに使っているんだ。もとの曲自体はUKでは大して注目されなかったんだけど、それがいまになってUSの超メインストリームの曲のなかで鳴っているというのはすごくおもしろいことだと思ったよ。そういうのって、(もとの曲に)興味を持ったR&B系のプロデューサーなんかが引っ張ってくるんだろうけど、たとえばビヨンセとかもそうで、メインストリームの人なのにオープンにいろんなものに興味を持ってそれらを取り入れたりしていて、彼女がやればそれに続く人が出てくるし、UKのアンダーグラウンドとUSのメインストリームのあいだにあった大きな壁が、ここ5年、10年くらいのあいだに崩れていっているという実感はあるね。
■今作のタイトル『Love What Survives』は「生き残るものを愛せ」ということで、とても意味深長なのですが、これにはどのような思いが込められているのでしょう?
カイ:今回に限らず、レコードを作っているときに考えすぎてしまうのはよくないと思っているから、いつも感覚でいいと思うものを作っていくんだけど、いざどういうタイトルにするか考える際には、「何がモティヴェイションとなって自分たちはこれを作ったのか」ということを振り返るんだ。今回ふたりでこのアルバムを作りながら話していたのは、とにかく(これまでと)違うことをやりたいということや、変化が訪れたらそれをどんどん受け入れて前に進んでいこうということだった。そういう音楽を作るときの刺戟って僕らがファーストを作ったときと何も変わっていないんだよね。そういう気持ちや勢いが「Survive(生き残る)」ってことなんだ。新しいことをやったり、刺戟を絶やさないことで生き残っていくというか、自分たちのまわりにあるものを受け入れて、ケアをしながら大事に音楽を作っていくというか。そういう気持ちを可能にするには好奇心が必要だったり、変化に対するオープンな気持ちが必要だったり、あとは違うアプローチを恐れないということが必要だったりして、(『Love What Survives』は)そうやって生き残ってきたものを大事にするというような作り方に対する考えなんだ。でもこれは僕の解釈であって、聴いた人がどう解釈しても構わないんだけどね。
ドム:同感だね。
■今回のアルバムはアートワークもユニークですが、被写体の彼は何をしているんでしょう?
ドム:いい質問だね(笑)。
カイ:本当は実際にアートワークを制作してくれたデザイナーのフランク(・レボン)に聞いてもらうのがいいんだけどね(笑)。フランクは今回のヴィデオもほぼすべて手がけることになっているんだ。このジャケットは彼が撮影してくれたものをもとにデザインしたものなんだけど、僕らと彼とではアルバムに対する見方がちょっと違っていて、だからこそおもしろいんだと思う。レコードにあのジャケットが付いたことによって、作品として僕らふたりのアイデア以上の存在になったんじゃないかなと思っている。けっこうインパクトは大きいよね(笑)。見た目もそうだし、フィーリング的にも。僕らだけの作品じゃなくなった気がして好きなんだ。まあ詳しいことはフランクに聞いて(笑)。彼はキャラクターになって何かをやるのが好きなんだ。
■このジャケットを見て、ファースト・アルバムのジャケットを思い出したんですが――
カイ:フランクはファーストのアートワークを手がけたタイロン(・レボン)の弟なんだ。
■へえ!
カイ:ファーストから今回のアルバムまでのあいだに僕らのなかですごくいろんなことが変わったんだけど、そこ(アートワーク)で繋がっているというのはおもしろいよね。
■ファースト・アルバム『Crooks & Lovers』の被写体の女性は、いわゆるチャヴなのでしょうか?
ドム:あの女の子? ぜんぜんわからないな(笑)。
カイ:デザイナーに聞かないとわからないし、たぶんデザイナー本人もわかってないよ(笑)。
■いまはこうして来日されて、ツアーの真っ最中だと思いますが、それが一段落ついたら何かやってみたいことはありますか?
カイ:ここ4年はけっこうおとなしくしていたから(笑)、いまは動きたくて、このツアーができるのが嬉しいよ。もうオフはいいや(笑)。
ドム:僕はこのあとホリデイで、フィリピンに行くんだ。日本ではカイとツアー・メンバーみんなで一緒に京都に行く予定だよ。そうやってちょっと休んで、また動き出したいね。

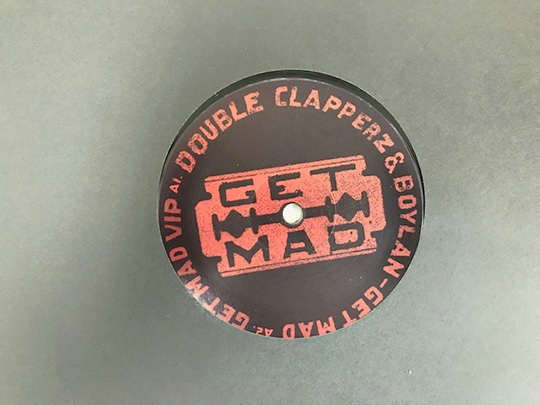

 ブリストルのレーベルから出た、Mars89「Lucid Dream EP」。
ブリストルのレーベルから出た、Mars89「Lucid Dream EP」。 後ろ向きなModern Effectのふたり。
後ろ向きなModern Effectのふたり。 彼らのUSB作品の数々。この怪しげなデザインに注目。
彼らのUSB作品の数々。この怪しげなデザインに注目。