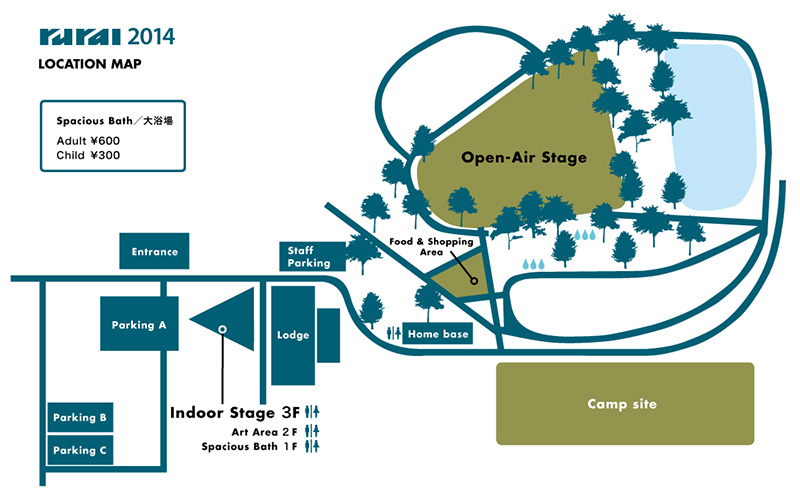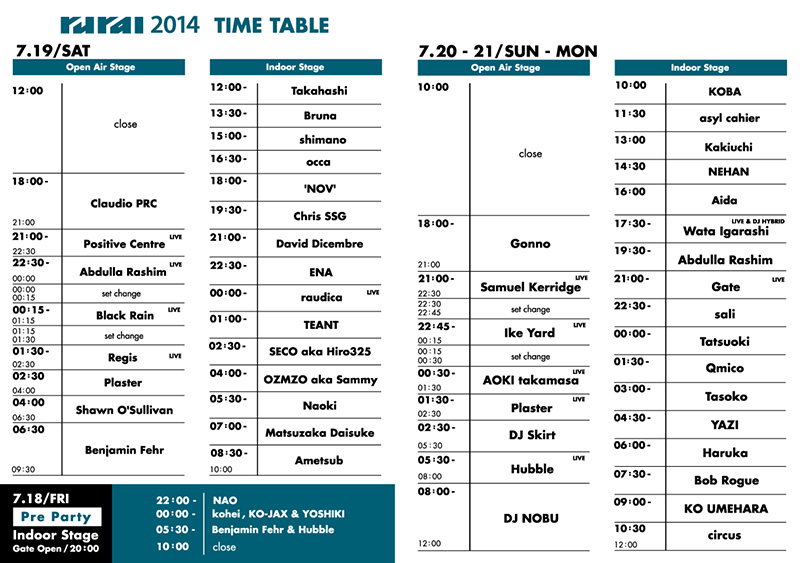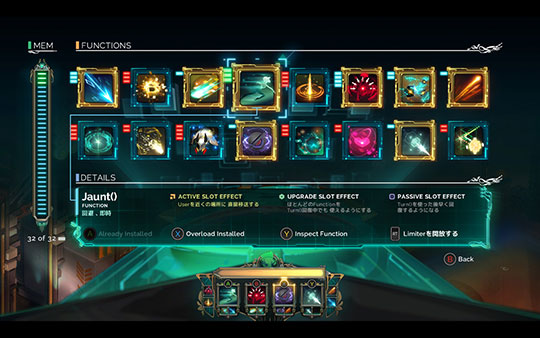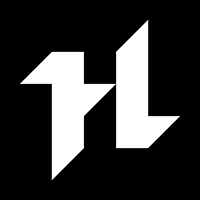パリス・ヒルトンやケイト・モスらが通うセレブなリゾートというよりも、最近は篠田真理子や大島優子が魅せられた休息の島と呼ぶほうが通りがいいだろうか。地中海に浮かぶ、スペイン領のリゾート・アイランド、イビザ島。風と光が戯れ、秘密のビーチに美しいチリンギート(海の家)が佇む最後の楽園。しかし、この島の名をさらに忘れがたいものとして印象づけているのは、あちこちに華やかに構えられたクラブや、そこで昼と言わず夜と言わず繰り広げられているパーティである。
今回、現地体験レポ―トを届けてくれたのは、“ネオ・ドゥーワップ・バンド”として夢と幻想のオールディーズ空間を演出し、ポップスとサイケデリックの可能性をスタイリッシュに追求する注目グループ、JINTANA&EMERALDSのJINTANA氏。軽快な文章をたどっていると、彼がどのような音楽を追求しているのかということとともに、かの島の明媚な風景や、そこに深く根づいたダンス・カルチャーとクラブでの喜びがいきいきと伝わってくる。
それでは8月のスペシャル・コラム、JINTANAのイビザ来訪記をお楽しみあれ。ベッドルームや通勤電車でこの画面を眺めている人にも、願わくはひとたびのヴァカンス・ムードを。 (編集部)

■JINTANA プレ・コメント
 ネオ・ドゥーワップバンドJINTANA&EMERALDSのJINTANAです。
ネオ・ドゥーワップバンドJINTANA&EMERALDSのJINTANAです。
今回、イビザについての旅行記を書かせていただくことになりました。
夏の一日を楽しく過ごすリゾート・エッセイとして、また、ちょっとしたイビザ・ガイドとしての情報も盛り込んでみましたので、イビザに旅行される方もご活用いただければと思います。
それから、Jintana&EmeraldsのサイトがOPENしました。この紀行文といっしょに楽しんでいただくためのJ&E楽曲MIXをサイトにUPしたので、ぜひ音と文でチルアウトなひとときを楽しんでいただけたらと思います。
Jintanaandemeralds.com
JINTANAプロフィール
Paisley ParksやBTBも所属するハマの音楽集団〈Pan Pacific Playa〉(PPP)のスティール・ギタリスト。同じく〈PPP〉のKashifや一十三十一、Crystal、カミカオル、あべまみとともにネオ・ドゥーワップバンドJINTANA&EMERALDSとして『Destiny』をP-VINEよりリリース。オールディーズとチルアウト・ミュージックが融合したスウィート&ドリーミーなサウンドがTiny Mix Tapeなど海外メディアも含め各地で高い評価を得る。この夏は〈JIN ROCK FES〉や〈りんご音楽祭〉などさまざまなフェスに出演予定。


■「悔しさとともに、ヨコハマの夜は更けていく」
ある夏のはじまる前の夜、僕は横浜の飲み屋街、野毛で〈PPP〉のリーダーである脳くんや〈PPP〉の若手のケントらと飲んでいた。〈PPP〉とはPan Pacific Playaという音楽クルーで、LUVRAW&BTBとしても知られるBTBくんやPEISLEY PARKSなどが所属するヨコハマの音楽クルーだ。僕たちは定期的に野毛で、本人らからすると大変に有意義な、他人からするとまったく不毛な飲みをしているのだが、そんないつものノリで蒸し暑い夜に飲んでいた。僕はJINTANA&EMERALDSのファースト・アルバム『DISTINY』をリリースした直後で、ちょっとした達成感とともに心地よくほろ酔いしていたわけだが、そんなところに脳くんが一言を放った。
「でもさ、JINTANA&EMERALDSにおいてさ、JINTANAのスチール・ギターの音、まだまだぜんぜん行けるよね」
「え?」
「いやさ、JINTANAのスチール・ギターはそのヤバさの片鱗の最初の1ページを見せたに過ぎない感じじゃん? まだまだいけるはずなのになー。おかしいなぁ。せっかくスチール・ギターと出会ったのにね~」
と言って脳くんはニヤニヤしている。いつも彼はこうなのだ。家庭教師のように、ほどよく人を悔しがらせ挑発する。本当に人の扱いがうまい男だ。ぼくはとぼけて「そうかなー? すでにけっこういい線いってんじゃない? あ、焼きベーコン追加ね!」とか言いながらも、心のなかではワナワナしていた。脳くんよ、まさにそのとおりなのである。僕の中でも、僕の理想のスチール・ギター像に対して、いまはせいぜい10%達成というレベルなのである。
僕はもともとバンド畑のギタリストだったが、ダンス・ミュージック・クルーの〈PPP〉に10年ほど前に誘われて加入した。トラックメイカーと楽器奏者が共存するこのクルーでの活動のなかで、僕はダンス・ミュージック……それも「シンセのビヨビヨした音色でオーディエンスを飛ばし異世界にいざなう」という音楽の側面に魅せられていった。そして、楽器奏者として僕がたどり着いたのはスチール・ギターという音色だった。この、音色だけで涼感を醸し出し、音階がシームレスだからこそ異空間へトリップさせてしまう楽器を、ダンス・ミュージック/チルアウト・ミュージックという耳のセンスで捉えたら気持ちよすぎてヤバいことになるのではないか? という発想でやりはじめたのだ。いわば、レイドバック空間へ旅立つための装置としての楽器、という役割である。だが、たしかに脳くんの言うようにそのレベルまでまだまだ達していないことは否定できない。そこは2枚めのアルバム以降の大きなチャレンジだと思っていたところであった。
僕は、そんな部分を指摘された悔しい気持ちを隠しながら「あ、焼きベーコン追加ね!」とか言って、その夜は更けていったのであった。
■「伊勢参りならぬ、イビザチルアウト参り」
数時間後、人々が通勤に向かう朝の京浜東北線の中で、ひとりほろ酔いの僕がいた。朝日を反射しまぶしい横浜のビル群を見ながら、僕はひとりつぶやいた。「やはり、チルアウトを極めねば……!」。おそらく朝7時のサラリーマンでごった返す車両の中で、チルアウトについて思索しているのは確実に僕ひとりであったであろう。そんなとき、車窓の向こうに旅行会社の看板をみつけて突然閃いた。「夏だ! 旅だ! 島だ! ってかぁ……、あ、 そうか、イビザ・・・! イビザに何かヒントがあるかも……!」イビザとはダンス・ミュージックが盛んな島として知られ、最近ではEDMのイメージも強いが、一方でそれをクールダウンさえるための音楽、すなわちチルアウト・ミュージックの発信地として広く認識されている。イビザのビーチにある〈カフェ・デル・マー〉は、夕陽が沈むタイミングに合わせてそうした音を用いたDJが聴けるという。それはそれは素晴らしい、波と光と音の完全なる融合を魅せる場としてこの世のものとは思えない美しさがあると伝え聞いている。

僕は江戸時代の「伊勢参り」の気持ちで、イビザにチルアウトを追求する旅にでるのも一興という思いに駆られた。さっそく検索してみると、ヨーロッパまで行ってしまえば、そこからは意外な安さだと知って驚いた。ロンドンからだと片道約2万円だった。あまりに遠い桃源郷に思えていたイビザが、急にリアリティのあるものに思えてきた。2ヵ月後、僕はホクホクした面持ちでイビザの空港に降り立っていた……。
[[SplitPage]]■「パーティは空港からはじまっていた!」
おそらく、イビザ空港は、世界中でもっとも「期待感」に満ち溢れた空港であろう。
飛行機のタラップから降りてくる時点で「ヒャッホーっ」というノリで、みんなちょっと小走りである。イミグレの列に並ぶと、僕の前には「HEN」と書いた揃いのTシャツの15人くらいの女性がいた。先頭にはウェディング・ドレスのヴェールをかぶっている笑顔満開の女性がいる。HENというのは、おそらくバチェラー・パーティ的な意味合いのようで、映画『ハングオーバー』みたいなことをしにきているのであろう。無事に帰って結婚できることを祈らずにおられない。

浜辺で踊る人々を描いてみた
イビザは空港が市街地から近い点も魅力で、タクシー15分で島の中心部であるエイビッサに到着した。僕が泊まったホテルは〈PPP〉と縁のある名前だったために選んだ「IBIZA PLAYA HOTEL」。ちょっとしたプールもあったりする、海辺の庶民派大型ホテルだった。なぜかホテル全体がチューイング・ガムのようにやたら甘い匂いがするのだが、それもイビザと思って気にせず部屋に入ると、窓の外で爆音でダンス・ミュージックが響き渡っていた。外を見ると300人くらいの人が浜辺にDJブースを出して踊りまくっていた。とはいえ、みんなサンダル履きだったり変なTシャツをきていたりして、どうも僕のような観光客ではなく、近所のおじさんおばさんたちがひと踊りしてから寝るべえ的なノリに見える。このダンスの生活への根づき方をみても、この島は、すみからすみまでダンス・ミュージックなんだなと直感した。そんな爆音が鳴り響く一方で、ホテルの廊下には「夜は踊らず静かにね♪ イエーイ!」という可愛いイラストが貼ってあり、そのスペイン的な無邪気さに僕は明日からの日々へ期待感と不安感を抱かずにおられなかった。
■「ダンス・ミュージックを中心点にする世界でも珍しい島」
翌日、僕は街に出た。強い日差しとヤシの木というエイビッサの雑多な街並みは、ヨーロッパというよりアジア的な喧騒に満ちていた。繁華街にたどり着くと、そこには一風変わった光景があった。日本で言うと宝くじ屋のようなノリで、小さなブースで何かを売っている。よくみるとそれはクラブの入場券であり、どの店も大きな看板にその日のパーティ名や出演するDJの名を書いていた。「今日はどのパーティが面白いの?」と僕は訊くと、チケット売りたちは「今日はスティーヴ・アオキのAOKI’S PLAY HOUSEだ!」とか「水曜日ならこのパーティがいちばん素晴らしい!!」などなど口々に自分の持論を展開する。それは心からパーティの楽しさを語っているようでとても和やかな空気だ。まぶしい日差しの中、小さなテーブルを囲んでパーティについて楽しく語るという仕事を目の当たりにして、なんと幸せな光景だろうと思った。

イビザの街の様子も描いてみた
街の中にはそういったチケット売りのほか、クラブ直営のファッション・ブティックやAVICIIなどの写真がデカデカと貼られているパーティ告知の巨大看板など、どこもかしこもダンス・ミュージック一色だ。たとえばアメリカであればgoogleが産業構造の真ん中にあるようなイメージがあったりするが、イビザの場合、産業の中心は完全にクラブである。クラブが真ん中にあり、そこに遊びにきている旅行者がいて、その周りにホテルやレストランがあり、彼らが買い物をするショップが並ぶ。深夜にクラブを行き来する人のために「クラブ・バス」というバスが走る。こんな島は世界中を見渡してもなかなかないだろう。雰囲気としては〈フジロック〉の日の越後湯沢の空気感が365日続いている街というところだろうか。ここまでピュアにダンス・ミュージックを愛する人たちが集まって、それを中心にすえて街が形づくられているという文化のありように驚いた。
■“パーティ・アイランド”イビザの新名所〈USHUAIA〉
イビザには世界的に有名な老舗クラブの〈PACHA(パチャ)〉,泡パーティが開催される〈Amnesia(アムネシア)〉などさまざまなクラブがあるが、チケット売りは俺も行きたくてたまらない! という顔をしながら「いまいちばんイケているのは〈USHUAIA(ウシュアイア)〉だ」と言い切った。
僕は眉毛がつながったスペイン男子の過剰な真顔に説得力を感じ、〈ウシュアイア〉に行くことにした。のどかな町をバスに揺られ〈ウシュアイア〉があるプラヤ・デン・ボッサというビーチについた。そこは他にも〈SPACE〉など巨大クラブが並んでいる、いわば海に面した円山町のようなクラブ・ストリートである。

目が合った瞬間、強烈なハイタッチをされた
〈ウシュアイア〉に入ると、そこは未体験の空間であった。クラブというよりはクラブ付ホテルで、ホテルの中庭に巨大なダンス・フロアがあり、それを取り囲むようにDJブースとホテルのベランダがそびえている構造だ。そして足元には大きなプールと、足だけが浸かれる小さなプールがあり、とても涼しい雰囲気に溢れている。ここはバレアリックなパーティ世界に24時間浸りきって楽しむことのできる滞在型のクラブだったのだ。
クラブにやってきている人々の情熱も素晴らしい。とてもグラマラスなボディにピンクやグリーンの鮮やかな水着を着て、その上に金のネックレスやバングルなどをするというファッションの女性が何人か目につく。これは〈ウシュアイア〉流のパーティ・ファッションなのだろう。彼女らには、とても艶やかではあるがエロティックではない、むしろ人生や若さを最大限楽しみきろうとする健康的なエナジーがほとばしっていた。

車椅子のアイコンも踊っているのが可愛い
さて、この日は元スウェディッシュ・ハウス・マフィア(Swedish house mafia)として知られるAXWELL Λ INGROSSOによるレギュラー・パーティ〈Departures(デパーチャーズ)〉のオープニング・パーティだった。日本より日が落ちるのがずっと遅いイビザだが、21時ごろになってやっと夕闇が落ちてくると、ステージがレーザーなどさまざまな演出で光り輝きだす。フロアも最高潮になりフロアを囲む客室のベランダでもみんなが踊りまくる! この場所は、ダンスを愛する人々がもっともっと楽しいパーティをしたい! という気持ちに忠実に従ってたどり着いた、ひとつの究極形だと思った。頭上には青空から夕景までの美しいグラデーション、足元には涼しいプール、四方には世界から集まってきたパーティ・ピープルの笑顔という最高のシチュエーションに、僕は心の底からの気持ちよさに酔いしれ、両手を広げて、この瞬間にこの場所にいる幸せに浸りきった。
イビザ、そこは弾けるようなパーティ感と、とろけるようなチルアウト感、そしてそれをつなぐピュアな音楽への情熱に溢れている。
次回は、JINTANAが〈カフェ・デル・マー〉に訪れ波と太陽と音が調和した瞬間を味わう編をお届けします。
「JINTANA イビザ紀行~究極のチルアウトを求めて~ 後編」では、JINTANAによるイビザ体験を元にした楽曲も公開予定です。お楽しみに!

P-VINE BOOKSのIBIZAガイドはとても役にたった!