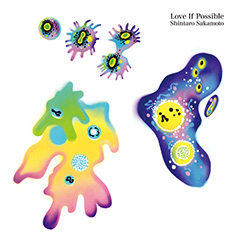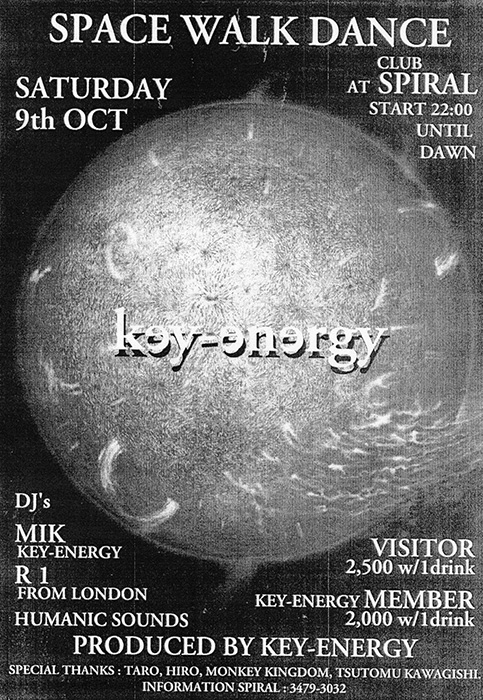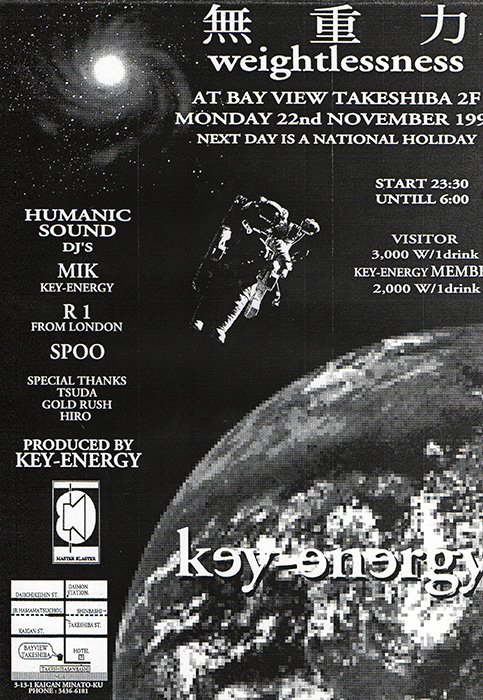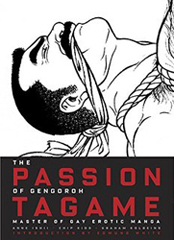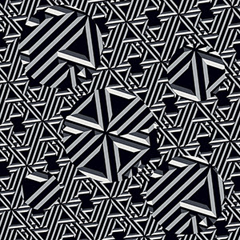 PLAID The Digging Remedy Warp / ビート |
プラッドのアルバムを聴くこと。それはエレクトロニック・ミュージックの快楽そのものだ。電子音の快楽、メロディの美しさ、こだわりまくったトラックメイクなど、エレクトロニック・ミュージックならではの「気持ちよさ」の真髄があるのだ。だから20年以上に及ぶ彼らの軌跡は永遠に色あせない。1997年リリースの『ノット・フォー・スリーズ』もいまだ「未来の音楽」に聴こえるほどである。
前作『リーチー・プリント』から2年の歳月を経て、ついにリリースされた新作『ザ・ディギング・レメディ』も、まったく同様だ。世に出た瞬間からエヴァーグリーンなエレクトロニック・ミュージックなのである(個人的には2000年の『トレーナー』に近い印象を持った)。
そして、とくに肩肘張ることなく自分たちの音楽を自分たちなりに追求していくその姿勢は、とにかく素晴らしい。彼らはいたってマイペースに「普通に、流麗な曲に聴こえるけど、どこか変?」というような、つまりは聴きこめば聴き込むほどにアメイジングな驚きをもたらしてくれるアルバムを生み出しつづけているのだ。たとえば(インタヴュー中でも語っているが)、リズムの拍子なども注意して聴いてほしい。迷宮に入るような気持ちよさがあるはずだ。
今回のインタヴューは、エド・ハンドリーがプラッドを代表して質問に応えてくれた。ユーモアを交えながら、しかし、極めて誠実な返答の数々は、まさにプラッド・サウンドそのもの。これから聴く人も、もう聴いた方も、ぜひとも熟読してほしい。『ザ・ディギング・レメディ』を聴くための素晴らしいガイドになるはずだ。
■Plaid / プラッド
ザ・ブラック・ドッグの結成メンバーとしても知られる、アンディ・ターナーとエド・ハンドリーによるロンドンのデュオ。91年に〈ブラック・ドッグ・プロダクションズ〉より『Mbuki Mvuki』をリリースして以降25年にも及ぶ活動のなかで多数のアルバムを発表、ビョークをゲスト・ヴォーカルに迎えたり、マシュー・ハーバートの作品に参加するなど多数のコラボレーションを行うほか、マイケル・アリアスやボブ・ジャーロックなど映像・映画作品への楽曲提供、日本では劇場アニメ作品『鉄コン筋クリート』のサントラを手掛けるなど多方向にキャリアを展開させ、2000年代には映像と音の融合をはかる取組みにも意欲を見せている。11作めとなるアルバム『ザ・ディギング・レメディ』を2016年6月にリリース予定。
古いローランドの808、101、202なんかを売り払った。(中略)あのサウンドは僕たちも大好きなんだよ。ただ、僕たちとしてもこの機材でこれ以上先に進めないな、と感じてね。
■前作『リーチー・プリント』から約2年を経てのリリースになりますが、本作の制作はいつからはじまったのでしょうか?
EH:このアルバムに本格的に取り組みはじめたのは、おそらくいまから1年前くらいだったと思う。というのも、僕たちは『リーチー・プリント』向けのツアーに実際1年近くを費やしたわけで――、まあ、絶え間なくというわけではないけど、ツアーを消化したら1年ほど経っていた。で、そこからいくつかのプロジェクトもあったんだ。とあるイギリスの映画監督とサントラの仕事をやったりしたね。で、前作ツアーが終わってすぐに今作向けに曲を書きはじめた。もっとも、僕たちはつねに曲は書いているんだ。ただ、アイディアをまとめてトラックに仕上げる、という段階に持っていくのは実際にアルバムをリリースする時期が近くなってからだから、その意味では約1年前からはじまった、ということになるね。
■この2年で制作環境や機材などは変わりましたか?
EH:うん、いくつか新しい機材をエクストラで追加したね。というのも、僕たちは所有していたアナログ機材をかなり売却したんだ。古いローランドの808、101、202なんかを売り払った。あれらの機材は長いことキープしてきたし、さんざん使ってもきた。それくらい愛用してきたし、あのサウンドは僕たちも大好きなんだよ。ただ、僕たちとしてもこの機材でこれ以上先に進めないな、と感じてね。あれらの機材の使い道という意味では、僕たちの側でもアイディアが尽きてしまった。
そんなわけで、古いものは売却して、いくつか新しい機材を購入したんだ。それらはエレクトロンというメーカーの機材で、アナログ・リズムというドラム・マシーンも入手した。これはかなり進歩したマシーンで、プレイするのもおもしろい機材だよ。
ああ、それにデスクトップ・コンピューターもアップグレードした。おかげですごく処理スピードの早いマシーンを使えるようになった。それ以前の僕たちは、長いことラップトップで作業していたんだよ。で、ラップトップでやっているうちに、しょっちゅう電力が切れてダウンしてしまう、そのせいで作業を中止しなくちゃいけない、みたいな状況に陥るのに気づいてね。というわけで(笑)、新しいデスクトップはとても役に立っているよ。なんというか、山ほどのプラグインだのなんだの、いろんなものを放り込んでも大丈夫。けっしてパワー不足になることはない、みたいな。古い型のアップルのデスクトップなんだけど、アップルが最新の黒いデスクトップを売り出しはじめたおかげで旧型が安価で出回るようになってね。おかげで僕たちもそういう古い機種をいくつか格安価格で買い取ることができたんだ。
通訳:そんなふうにテクノロジー面での変化があったことで、『リーチー・プリント』と『ザ・ディギング・レメディ』の間には違いがある?
EH:うん、そうだと思うよ。ただ、それは、本来はもっと複雑に聞こえるはずの『ザ・ディギング・レメディ』がシンプルに聴こえるようになったという意味においてね。この作品は、より音数が少なく、まばらで、もっとアナログな響きになっているんじゃないか、と思う。
というわけで、2枚の間にちょっとした違いはあるけれど、その差は何も巨大なものではない。というのも、どんな機材を使っていても、僕たちは、やっぱりいつだって同じサウンドみたいなものに回帰していくわけだから。
僕たちの音楽の作り方というのは、フィーリング重視というか、もうちょっと「音楽を感じ取る」というものなんじゃないかな。
■本作の制作にあたって、おふたりで決めたルールのようなものはあったのでしょうか?
EH:んー、とくにないかな。まあ、僕たちは毎回「これまで自分たちのやった同じことはあまり繰り返さないようにしよう」と努力してはいるけれど、ある程度は避けられない。やっぱり、僕たちの「テイスト」というものがあるからね。もともと持っている趣向/テイストが、アルバムごとにガラッと変わることはないわけで、少しの差異が生じる程度のものだよ。でも、僕たちの中に常に存在している大いなるアイディアとして、「物事をそぎ落として原点に戻そう」というのがあるんだ。そうやって何もかもを純化して、もっとも重要な要素だけに絞っていく。で、今回のアルバムの何曲かは、いつもの僕たちが作る以上に。よりそぎ落とされ、洗練されたものになっているんじゃないかな。
一方で、そうではないトラックもいくつかあって、そこでは通常どおりの僕たちが聴けるんだけどね。それから、今回はベネット(・ウォルシュ)といっしょに多くの曲を制作した。僕とアンディ(・ターナー)と二人っきりでの作業とは、かなり異なるプロセスだったし、ベネットも含めていっしょにスタジオに1週間くらい詰めて、そこでとにかくいろいろとアイディアを試してみるか、と。まあ、相当に当てずっぽうでダラダラとやっていたんだけど(笑)。
でも、それも含めて、楽しい経験だったよ。ほんと、そうなんだ。そういうのがベストじゃないかと思う。仮に僕たちがもっとアカデミックなタイプのミュージシャンだったとしたら、前もってきっちりとレコーディングの計画を立てなくちゃいけないだろうし、「今回はこれをやる」みたいな明確さで新たなアイディアを試すわけだけども、僕たちの音楽の作り方というのは、ぜんぜんそういうものじゃないからね。それよりももっと、フィーリング重視というか、もうちょっと「音楽を感じ取る」というものなんじゃないかな。
■印象的なアルバム名ですが、どういった意味が込められているのでしょうか?
EH:あのタイトルは、10歳になるアンディの娘さんが思いついたものでね。だから、きっと彼女には彼女なりの意味合いがある言葉なんだろうと思うけど。僕たちからすれば、ただ「The digging is the remedy(何かを掘っていく行為はそのものが治療だ)」。音楽作りにおける重要なパートは、必ずしも生まれる結果ではなく、そこに至るまでのプロセスなんだ。というのも実際の話、音楽作りのその過程こそ、僕たちの生活にもっとも影響するものだからね。いったん作り上げ、完成してしまうと作品はそこで一種の「プロダクト」になってしまうわけだし。というわけで、タイトルの意味にはそれがあると思う。それに「掘り起こす」って言葉は、「宝を探り当てる」という行為のいいメタファーでもあるよね?だからいろいろな解釈の成り立つフレーズだけど、ポジティヴな意味合いなんだよ。
とにかく、グルーヴ群をリリースしよう、みたいな(笑)。まだ「歌」にすらなっていないグルーヴに近い状態のものと、(歌という)複数のセクションに分割されていないものをリリースする、と。
■前作は流麗でメロディアスなエレクトロニクス・ミュージックだったと思うのですが、本作は前作より、やや無骨というかソリッドな印象を持ちました。そのような変化を意識されましたか?
EH:まず、『リーチー・プリント』はアルバムとして短くて、収録トラックの数も新作に較べて少ないよね。それに、いま指摘されたように、もっと洗練されたサウンドだったと思うし。でも今回に関して言えば、あれほど磨きがかかっていないよね。で、それはある意味意図的だった、というのかな。だから、とにかく、グルーヴ群をリリースしよう、みたいな(笑)。まだ「歌」にすらなっていないグルーヴに近い状態のものと、(歌という)複数のセクションに分割されていないものをリリースする、と。
で、それがいわゆる「プラン」として狙ったわけではないにせよ、とにかく最終的にそういうものが生まれたわけだ。というのも、今回の作品での音楽的なアイディアというのは、入り組んだ構成だったり、あるいは過度な洗練だったり、そういったものにあまりそぐわない性質のものだった。むしろこの、シンプルなフォルムでやる方が有効だったから。
■1曲め“ドゥ・マター”の冒頭のベースラインはどこかクラフトワークを連想しました。また、3曲め“クロック”のイントロのコード感にはデトロイド・テクノのエモーショナルな部分を圧縮しているような印象を持ちました。70年代、80年代、そして90年代のエレクトロニック・ミュージックの歴史を圧縮してみようという意識はありましたか?
EH:ああ、僕たちはそういうことをやっているんだろうね。うん、よくやっている。というのも、僕たちは90年代的なサウンドに回帰したり、あるいはクラフトワークみたいな、古代の(苦笑)サウンドに戻っていったりするわけで。何故なら、そうしたさまざまなサウンドというのは、いまや「伝統音楽」みたいなものになっているからじゃないかな。だから、(ロックやポップ勢がやるのと同様に)伝統音楽やフォーク音楽みたいに引用ができるっていうかな。たとえば、ある類いのベースラインを使うと「○×を想起する」といった反応が生まれるのは、そのラインにすでにさまざまな連想が付け加わっているからだしね。そういった歴史的な連想が存在するし、また、映画的な連想というのもあるよね。つまり過去にそのベースラインが用いられてきたさまざまな手法がすべて、聴く人間の耳に作用する、関連するいろんな付随物も聴こえるんだ。
Plaid - Do Matter (Official Video)
で、僕たちは自分たちにそういうことがやれるのはグレイトだなと思った。というのもエレクトロニック・ミュージックはいまや巨大な歴史を誇るようになっているし、それに僕たち自身、その歴史の中の比較的モダンなヴァージョンのいくつかを聴きながら育ってきたんだ。
だからそれらのいろんなアイディアを利用せずにやるっていうのは、ある意味不可能なんじゃないかな。過去に行われたアイディアを引用する、その行為なしにエレクトロニック・ミュージックを作るのはとても難しい。そうはいっても、完全に新しい、まったくオリジナルだってものもあるけれど。ただ、そういうケースは非常に稀だよ。
このアルバムに関しては、そういうフォーク的なものが入ってきていたと思う。そして、それはベネットから発していた。彼は、僕たちに向かってちょっとこう(笑)、「自分はどこから来たのか」を教えてくれたんだ。
■と同時に、4曲め“ジ・ビー”では以前からコラボレーションをされていたベネット・ウォルシュがギターやフルートで参加するなど、エレクトロニック・ミュージックにオーガニックでジャズ的な要素が加えられているように思いましたが、このアルバムに作るにあたり、ほかのジャンルからの影響はありましたか?
EH:うん。それはいつだってそうなんだよ。ほかのジャンルからの影響はある。もちろん、僕たちはエレクトロニック・ミュージシャンだし、僕もアンディも一般的な意味での「楽器」はあまり弾けない。必要とあればピアノをちょっと弾けます、程度だね。僕たちがギターだのフルートだのを自ら演奏することはないわけで。
だから僕たちがベネットみたいな人と作業してみると、彼は彼なりの音楽的な遺産や知識を持ち込んでくれるんだ。彼のバックグラウンドは、フォーク音楽から、いろんな類いのブルーグラスといったものまで、アメリカの伝統音楽みたいなものに根ざしているわけだからね。そういったジャンルのことは正直いって僕たちはよく知らないけれど、いったん彼とスタジオに入り、彼がギターで弾き始めると、僕たちもその音に対して自分たちの知っているものを関連させていってね。たとえば、「ああ、これは僕たちが以前に聴いたことのある、あのアフリカ音楽にちょっと似ているな」とか。
というわけで、このアルバムに関しては、そういうフォーク的なものが入ってきていたと思う。そして、それはベネットから発していた。彼は、僕たちに向かってちょっとこう(笑)、「自分はどこから来たのか」を教えてくれたんだ。
■7曲め“ユー・マウンテン”などはテクノ的なベースラインとコードに加えて、トライバルなビート・プログラミングに驚きました。本作のビート・プログラミングで実践された「新しいこと」は、どういったことでしょうか?
EH:そうだなぁ……どうだろう? 今回のアルバムでは、3/4の拍子が多いよね。3拍子はかなり使っているけど、それはこれまでの作品でも多くやってきた。あと、7/4というのもあるね。あれは僕たちがつねにどこかに紛れ込ませようとしているものだ(笑)。だから、普通のダンス・ミュージックしか聴かないような人が耳にすると、「おや、ヘンだな?」と思えるような拍子が少し混じっているかもしれない。で、今回はアナログ・リズムもちょっと使ったんだよ。それはさっき話した新しいドラム・マシーンのことだけど、あれはすごく優秀でね。ひとつひとつのビートを変えるのに適したマシーンで、細かな変更をどのビートにも加えることができるんだ。
そんなわけでリズム面ではかなり多くのさりげない変化が起きているんだよ。だけど僕たちは、リズムにおいて巧妙なことをやろうとしたわけではないし、グルーヴの多くは基本的に規則的なものだから。ただ、〝ベイビー・ステップ・ギャイアント・ステップ〟なんかでは、かなりいろんなことをリズムでやっているんじゃないかな。あれを聴くとポリリズムに聞こえるだろうし、その意味ではおそらくあの曲がもっとも冒険的なんじゃないかと思う。
僕たちは普通、モロに「民族音楽/ワールド・ミュージック」っぽい方向に向かったりはしないんだけど(笑)、あの曲では「試しにやってみよう」と思ったんだよね。
■さらに8曲め“ラムズウッド”は民族音楽的な雰囲気は、Plaidにおける新機軸ではないかと驚きました。
EH:ああ、うん。
■あのフルートのような音色は、ベネット・ウォルシュによるものでしょうか? とても印象的でした。
EH:その通り。
通訳:あれは彼のアイディアだったんでしょうか。で、それをあなたたちが発展させていった……という? あるいは逆に、すでにベーシックなトラックがあり、そこにベネットが付け足していった?
EH:あの曲はたしか、まずベースラインができていたんじゃないかな。で、そこにベネットが即興で演奏を足していったんだと思う。でも、彼が弾いていたのはフルートではなくて、たぶんペニー・ホィッスル(ティン・ホィッスルのこと)だったんじゃないかな?
でも、そうだよね、あれはかなり中東風な雰囲気のある曲だ。どういうわけか、軽くアラブ風なフィーリングがある。でまあ、僕たちは普通、モロに「民族音楽/ワールド・ミュージック」っぽい方向に向かったりはしないんだけど(笑)、あの曲では「試しにやってみよう」と思ったんだよね。
■今回、ベネット・ウォルシュとまたコラボレーションをした理由を教えてください。今回のアルバムは(とくに中盤以降)、彼のギターは重要な役割を担っているように感じたのですが。
EH:『リーチー・プリント』向けのツアーの際に、僕たちはベネットといっしょに、かなりの数のギグで共演することになってね。あのアルバムで彼が参加しているのは1曲だけとはいえ、あれ以前の昔のトラックで彼が弾いているものはけっこう多いし、そうした楽曲もプレイしたんだ。
で、僕たちは「トリオ」であることをとても楽しんでいたんだ。というのも、僕たちはデュオとして長いこと活動してきたし、だからこそ、たまには新しくフレッシュな要素を注入しなくちゃいけないんだよ。
そんなわけで、ベネットがこのアルバムで、あれだけの数のトラックに参加することになった理由は、とにかく彼といっしょに演奏していて楽しかったから、だろうね。僕たちは以前以上にいっしょに過ごすことになったし、ツアー中もさんざん音楽の話をした。そこからちょっとしたアイディアを思いついたりもした。だからごく自然な成り行きだったんだよ。
とてもトラディショナルでアコースティックに響くものと、エレクトロニックで興味深いサウンド、その「はざ間のライン」を歩こうとしているんだ。
■10曲め“ヘルド”や11曲め“ウェン”はギターのフレーズなどで対になっている印象を持ちました。とくに11曲め“ウェン”はビートレスなアンビエント・トラックで見事なアルバムの締めくくりに思いました。同時に、楽曲全体が生演奏を主体としたオーガニックな曲調で、穏やかながらプラッドにとって挑戦的な楽曲に思えましたが、いかがでしょうか?
EH:なるほどね。たしかに、あの曲はあまりエレクトロニック・ミュージック然と響かないかもしれない――。そうはいいつつ、やっぱりあそこにもエレクトロニックな「層」は存在するんだけども。
通訳:でも、オーガニックなヴァイヴがありますよね。
EH:うん、うん。だから、いっていることは正しいよ。エレクトロニック・ミュージックばかり聴いているようなリスナーには、あまり受けのいい曲じゃないのかもしれない。でも、僕たちの音楽というのは、必ずしも「マジにハードコアなテクノ好き!」な人たちとか、「生楽器のサウンドは一切受け付けない!」みたいな(笑)、そういうクラウドにアピールするものではないと自分たちではそう思っていてね。僕自身、そこまで何を聴くか/聴かないかに関して厳密に線引きしているような、そういう手合いにはあまり多く出くわさないし(笑)。
ともあれ、あの曲のアイディアは、ベネットが主軸になって引っ張ってくれたものだね。で、僕たちがそこにハーモニー的な箇所を被せていったんだ。このアルバムの中で「よりベネットの色が強いもの」といえば、おそらくあのトラックになるんじゃないかな? あの曲はほんと、「ギターありき」ってトラックだからね。
■プラッドの曲を聴いていると、いつもその音色の繊細さに驚きます。本作の音色の選び方、使い方などでもっとも気をつかった点などを教えてください。
EH:んー……。何かサウンドをデザインするときというのは、多くの場合アコースティックな音色との関連から発想するものだし、そういうケースはじつに頻繁なんだ。というか、音色のパレットという点においてはそうならざるを得ない。だから、ちょっとアコースティックっぽく聞こえるサウンドを使う、というのは、エレクトロニック・ミュージックの世界においてもしばしば当てはまる話なんだよ。で、その面を可能な限りまで押し進めつつ、それと同時にハーモニー面でも成り立つもの、音符や変化をうまくコードに変えていくという作業もやっている。そうやって興味深いサウンドを組み立てながら、そこに和声の要素をプラスしているわけだよね。でも、やっぱりそれらのサウンドでメロディを演奏する必要があるし、コードを弾くのが可能じゃなくちゃいけない。で、思うにそういうことが、僕たちが『リーチー・プリント』から、今作にちょっと引き継いできたものなんじゃないかな? これらのサウンドは、ほとんどアコースティックのように使っているけれども、でも、じつは合成された(シンセサイズされた)ものだ、と。
だから、そうしたことをやるおかげで、僕たち自身が興味を抱き、刺激され、ハッピーでいられるんじゃないかな。要するに、「あまりに変わっているために聴き手を疎外する」ことはないけれど、でも、「そこそこ違いがあるから人々を引きつける」というか。うん、そこは微妙なラインだよね。そうはいったって、やっぱり時には全開で「疎外」モードに入りたくなるときだってあるし。エレクトロニック・ミュージックというのは明らかに、それをやるのが得意なわけだよね。
だけど、僕たちにはあんまりそれをやらない傾向があるんだ。それよりも僕たちは、さっき話したぎりぎりの境界線、そこを綱渡りしようとしている。とてもトラディショナルでアコースティックに響くものと、エレクトロニックで興味深いサウンド、その「はざ間のライン」を歩こうとしているんだ。
それって、スポーツ選手が能力を向上させていくのに似ているよね(笑)。
通訳:それはエレクトロニックをベースにしたサウンドを、より自然でアコースティックなサウンドに近づけていこう、という試みなんでしょうか?
EH:そういうことなんだろうね。たとえば最近のもっと新しいタイプのエレクトロニック・ミュージックは、そういうことをやっているのが多いと思う。サウンドはより複雑さを増しているし、もっとずっと豊かなものになっている。音色という意味でも、あるいは時間の経過に伴ってそれがどう変化するかという意味でもね。で、それらはシンセーシスにおける新しいテクニックだし、人々が以前以上にディテールに気を配るようになった、というのもあると思うな。それって、スポーツ選手が能力を向上させていくのに似ているよね(笑)。
だから、エレクトロニック・ミュージックの世界においては――、いまどきの若いアーティストたちの作るベストな新しいエレクトロニック・ミュージックの中には、そこに入り込んで、サウンドをさらに洗練させようとしているってものがいくつかあるからね。これまで行われたことのない、そんなレベルのディテールにまで洗練しよう、と。で、それらは、とても興味深くて、感心させられるようなサウンド・デザインなんだ。そういうサウンドは、相当にナチュラルに聴こえるのに、でも自然な音ではない。それを耳にするのって、かなり落ち着かない気分にさせられるものだよね。「この音はいったいどこから出て来たんだ?」なんて感じるし。それに、サウンドをいろいろと融合させると――それはいまだとソフトウェアを使って、リアルタイムでどんどんやれるようになっているけれど――そこから奇妙に変形したサウンドを手にすることができる。それはまだ人々が耳にしたことのないサウンドであって、実際、とても風変わりな響きなんだ。そこはエレクトロニック・ミュージックにおけるじつにおもしろい側面じゃないか、と僕は思うね。
通訳:なるほど。でも、これはあくまで私個人(通訳)の考えなんですけど、いまの若いリスナーの多くは、携帯電話のチャチなスピーカーやPC、安いヘッドフォンで音楽を聴いていますよね。で、あなたたちのようなアーティストは非常にこだわって時間をかけて音楽を作っているのに、それが理解されない点について、一種のフラストレーションを感じることはないのかな? と思ってしまうのですが。
EH:そうだね、きっとそういう側面もあるんだと思うよ。ただ、僕が思うに、聴き手の側も少しずつ変化しているし、大型のヘッドフォンで聴いている人たちも増えてきたよね(笑)? あの手のヘッドフォンを使うとかなり音がよく聴こえる、というのならいいけどね! そうは言っても彼らの聴いている音源ファイルそのものがMP3なのかもしれないけど……、でも、圧縮をかけないフル・サイズのファイルやロスレスをダウンロードする人たちも増えているわけで。だから、そうした面も変わっていくんだと思う。ってのも、やっぱり高品質なサウンドのほうが、聴く体験としてははるかにいいからね。
僕ももっと、彼の比較的最近の作品を聴くべきなんだろうな。
■音の色彩感覚といえば日本ではこの5月に偉大な電子音楽家/作曲家であった冨田勲氏が――まず、彼のことはご存知ですか?
EH:ああ、うん。知ってる。
■冨田氏は5月に亡くなったんです。
EH:そうなんだ! それは知らなかった……。残念な話だね。
■冨田勲氏もまたテクノロジーと自然を電子音楽の色彩感覚で追求した音楽家でした。冨田勲作品のことはご存知ですか?
EH:うん、彼の作品はクラシック作品を再解釈したものとか、あそこらへんのものはかなり聴いたよ。だから、おそらく彼の晩年の作品はそれほど聴いたことがなくて……。彼の初期の作品、たとえばモーグといった古いシンセを使って作った作品なんかは聴いたと思う。彼がその後もいい作品をいくつか制作したのは知っているけれど、そこらへんはあんまりフォローしていないんだ。そうかぁ、それは悲しい話だな。何歳だったの?
通訳:おそらく80歳ちょっと、あたりかと。
EH:ああ、じゃあ年齢だったんだね……。
通訳:そうですね。日本におけるシンセサイザー音楽のパイオニアかと。
EH:うん、だから僕ももっと、彼の比較的最近の作品を聴くべきなんだろうな。
「流れ/旅」というのは、いつも意識しているんだ。だって、それがなかったらわざわざ「アルバム」をやる意味はあまりないんだし、個別にトラックを発表していけばいいだけの話だからね。
■アルバムはクラフトワークを思わせるエレクトロニック・ミュージック、デトロイト・テクノを思わせるテクノ・トラック、ギターとフルートがレイヤーされるオーガニックなクロスオーヴァーなサウンドへと次々に展開し、最後はアンビエントで幕を閉じる印象を持ちました。また、後半になるに従い、次第にエモーショナルな感情が揺さぶれました。まるでエレクトロニクス・ミュージックによる「旅」をしているような印象でした。アルバム全体で意識された「コンセプト」や「流れ」のようなものがありましたら教えてください。
EH:うん、僕たちはいつもそういう「流れ」を生もうとしている。そうは言っても、全曲を仕上げてひとつにまとめてみるまで、そうした流れが生まれない、ということもたまにあるんだ。だから、つなげてみてやっとわかる。でも今回の作品に関しては並べて聴くべくデザインした、このトラックはあのトラックに続いていく、という具合にデザインしたセクションも含まれているよ。でも、多くの場合は、まず多くのトラックが手元にあって、そこからいい組み合わせになるものを選んでいく……という作業なんだ。だから、音楽的に関連性のあるものを選んでいく。
ただ、今回はその作業にかなり時間がかかったね。難なくストレートに決まるってときもあるんだけど、今回は収録曲をまとめるのに1ヶ月近くかかった。とにかくふたりで聴き返して、曲順をああでもないこうでもないと入れ替えて聴いてみて。だから、どういうわけか、今回は曲順を思いつくのに苦労したんだ。どうしてかといえば、このアルバムには似通った曲がいくつかあるからじゃないか、と僕は思うけど。要するに、近いフィーリングを持った曲がくつかあって、このトラックを入れるべきか?という点まで考えたし、いざそれを収録するとしたら、ではどこに置くのがいいだろう?と迷わされたわけ。
でも、さっきの「流れ/旅」というのは、いつも意識しているんだ。だって、それがなかったらわざわざ「アルバム」をやる意味はあまりないんだし、個別にトラックを発表していけばいいだけの話だからね。
■6月9日(木)より先行販売開始!
PLAID
08/26(FRI)@CIRCUS OSAKA
08/27(SAT)@CIRCUS TOKYO
東京&大阪にて最新オーディオ・ヴィジュアルセットによる完売必至の来日ツアーが決定
8/26(FRI)@CIRCUS OSAKA
出演:PLAID and more
OPEN 23:00 ADV:4000YEN ※別途1ドリンク代金必要(600円)
※18歳未満入場不可
会場: CIRCUS OSAKA
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-8-16中西ビル2F
TEL : 06-6241-3822
https://circus-osaka.com
8/27(SAT)@CIRCUS TOKYO
出演:PLAID / DJ SODEYAMA
OPEN 23:00 ADV:4500yen
※18歳未満入場不可
会場: CIRCUS TOKYO
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-26-16
TEL:03-6419-7520
https://circus-tokyo.jp
チケット発売
☆先行販売:6月10日(金)正午~Beatkartにて受付開始!こちら[https://www.beatink.com]
●一般発売:6月15日~