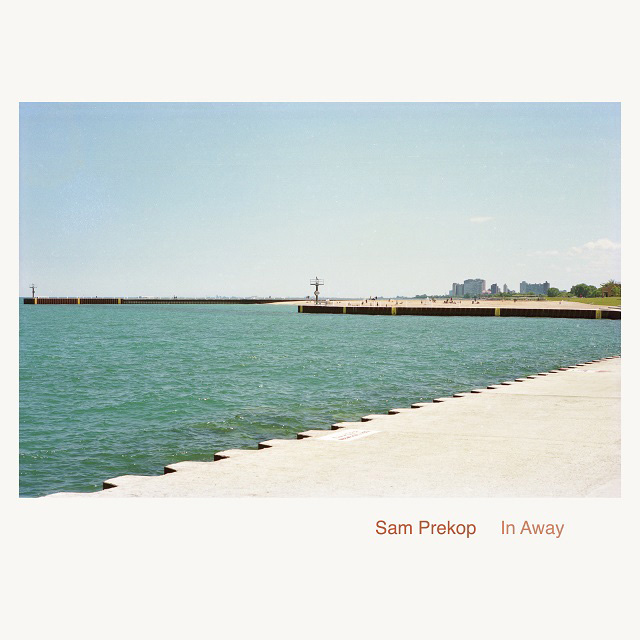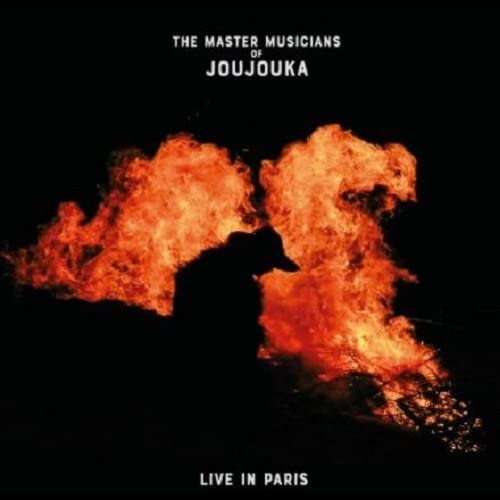〈raster-noton〉が、バイトーン(オラフ・ベンダー)の〈raster〉と、アルヴァ・ノト(カールステン・ニコライ)の〈noton〉に分裂し、それぞれの道を歩みはじめたことは、10年代の先端的な電子音響音楽において重要なトピックだった。電子音響、エレクトロニカを牽引していたレーベルが終わりを迎えたからだ。
その〈raster〉が始動後(再起動後とでもいうべきか)に最初にリリースしたアルバムがアイランド・ピープル『Island people』(2017)である。彼らのアルバムをレーベルのファースト・リリースとしたところに〈raster〉=オラフ・ベンダーの意志を感じたものだ。つまり高品質なエクスペリメンタル・エレクトロニック・ミュージックを送り出していくという意志だ。じじつ〈raster〉は、この4年のあいだ流行に左右されずに、質の高いエレクトロニカをコンスタントに送りだしてした。その原点にアイランド・ピープルがあったのだとは言い過ぎだろうか。しかしわたしが彼らのサウンドが忘れられなかったことは事実だ。折に触れ何度も繰り返し聴き続けた。
アイランド・ピープルはスコットランド・アイルランド出身の4人の音楽家/サウンド・デザイナーによるグループである。ダフト・パンクやジェフ・ミルズ、リカルド・ヴィラロボスやカール・クレイクなどを手掛けた人気のマスタリング・エンジニアのコナー・ダルトン、グラミー賞受賞プロデューサーのデイヴ・ドナルドソン、シリコン・ソウルのグレアム・リーディー、ギタリストのイアン・マクレナンがメンバーである。先にグループと書いたが、「バンド」といってもいいかもしれない。それほどまでに4人の個性が交錯しているサウンドに聴こえるのだ。
プロデューサーとエンジニアが在籍するアイランド・ピープルのサウンドは高品質なアンビエンス/アンビエントを実現していた。まるで映画のサウンドトラックを思わせるようなムードである。その音は緻密かつ繊細に設計され、美しくも深淵な音響空間を実現していた。どこかアンドレイ・タルコフスキーのSF映画『惑星ソラリス』を思わせもする。その意味で同じく2017年リリースの坂本龍一『async』との親和性も感じられた。
前作『Island people』から4年の月日を経て送り出された新作が本作『II』である。待ちに待ったというより、不意に届けられたという印象で、一聴すると基本的に『Island people』のサウンドを継承しているように感じられた。しかしその音は以前よりダークであった。何か世界の変容を捉えようとするように、サウンドの移り変わりは、ゆったりとした映画の長いワンシーン・ワンショットのカメラワークを思わせた。レーベルは「初期のアントニオーニ映画のロング・トラッキング・ショットのように展開され、時間が止まっているようで、その瞬間を巡っている」と書いているが(https://raster-raster.bandcamp.com/album/ii)、まさに言い得て妙である。
つまり前作に比べて、どこか暗く沈んだムードのアルバムなのだ。しかしそれが不快ではない。流行や時間の流れを超越したかのようなサウンドであり、その静かで、不穏で、「人がいない世界」のような音響空間には心を鎮静するような力すらある。特にドラマチックな流れのサウンドを展開する1曲目 “His Illusion” からインナースペースへと沈み込んでいくような3曲目 “Loneliness Has A Purpose” までの展開には孤独のアトモスフィアがうっすらと漂っていた。アルバムはそんなムードを反復するように展開していく。
環境音と電子音が深海と廃墟の中で交錯するような4曲目 “Far From Shore” と5曲目 “Ten Green Bottles”、ギターのアルペジオが映画音楽的なムードを彩る6曲目 “Idyll”、緊張感に満ちたアンビエントを展開する8曲目 “Stillness”、環境音楽的なシンセサイザーに濃厚な音色のギターを聴かせる9曲目 “Luna” まで、まるでひとけのない都市を彷徨するような音世界だ。その映画音楽的なサウンドに聴きいっているとコロナ禍でロックダウンされた都市の音響のように聴こえたほどだ。加えて、ヴォーカリストのアリス・ヒル・ウッズを招いたヴォーカル曲 “Stalling”(10曲目)が収録されたことも重要なトピックだろう。アルバム・ラストの12曲目 “Traffic” では、スペイシーな電子音響アンビエントを展開し、地球を俯瞰するようなムードになり、アルバムは幕を閉じる……。
全12曲、アイランド・ピープルは流行り廃りを超えた普遍的な電子音楽を構築しようとしているのではないか? と感じられた。尖端から深淵へ。流行から普遍へ。モードからスタイルへ。10年代まで切り拓かれてきた電子音響音楽の世界は、いま、聴き手の心に作用するアトモスフィアを得ようとしている。それこそがこのアルバムが獲得した不思議なリアリティの正体なのかもしれない、と思うのだ。