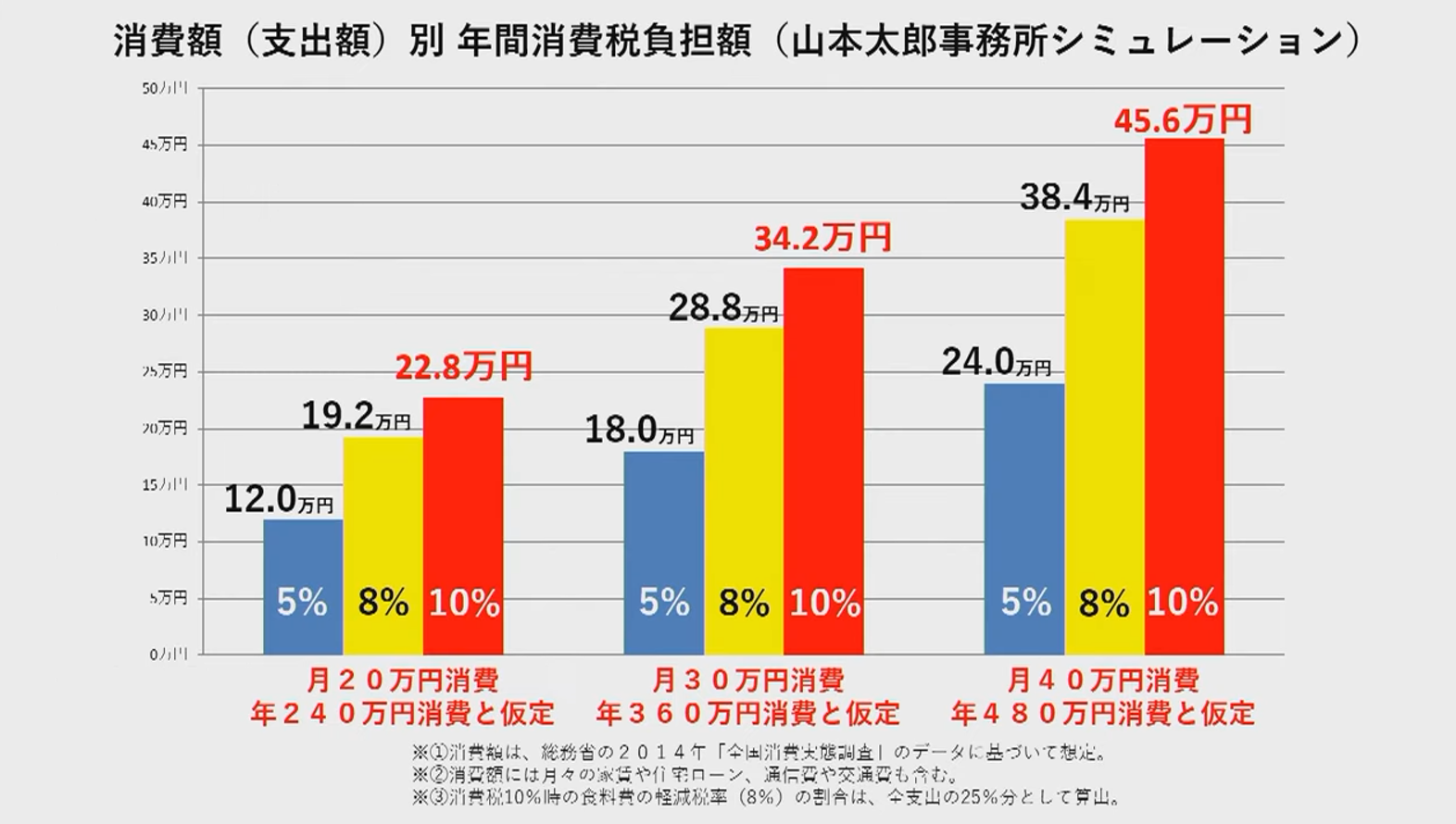プロデューサーであり、ミュージシャンであり、レーベル〈Yoruba〉の主宰者でもあるオスンラデが2年ぶりの来日を果たす。セントルイス出身のこのスピリチュアル・ハウスのヴェテランは、きっと最高にソウルフルでディープな一夜を演出してくれるにちがいない。11月9日は VENT へ。
ハウス界のメシア。
魂を揺さぶるディープ・ハウスの最高峰、 Osunlade
大人気のレーベル〈Yoruba Records〉を率い、アメリカのディープ・ハウス・シーンの最高峰に君臨する OsunladeOfficial が11月9日のVENTに初登場! 存在そのものがアートとも言える重鎮による2年ぶりとなる超待望の来日公演が決定!!
Osunlade ほど多彩なアーティストもなかなかいないだろう。ブラック・ミュージックの代表格であるブルースやジャズが生まれたセントルイスに生まれ育ち、幼少の頃から作曲に興味を持っていたという。17歳でハリウッドへ渡り、プロデューサーとしての才能を開花させてからは、メジャー・レーベルのもとで多くのヒット作を手掛けてきた。
やがてメジャーの音楽スタイルでの音楽制作は自分の音楽への情熱を弱めてしまうと感じ、一念発起してアーティストの道を選択。1999年に〈Yoruba Records〉を設立したのだ。一切の妥協がないディープでソウルフルな作品をコンスタントにリリースすることで Theo Parrish や Dixon をはじめ多くのトップDJたちにサポートされると、レーベルとともに Osunlade はアーティストとしても広く認知され、「ハウス界のメシア」と評されるようになった。
Osunlade の魂を反映したアフロ、スピリチュアル、ソウルフルなディープ・ハウス作品と、彼の繰り出す壮大なDJセットは、オーディエンスのエネルギーとヴァイブスと混ざり合いマジカルな一夜を創り上げるだろう!

- Osunlade -
DATE : 11/09 (SAT)
OPEN : 23:00
DOOR : ¥3,500 / FB discount : ¥3,000
ADVANCED TICKET : ¥2,500
https://jp.residentadvisor.net/events/1317046
=ROOM1=
Osunlade
Motoki a.k.a. Shame (Lose Yourself)
KITKUT (ON and ON)
Atsu (東風 / 三楽)
=ROOM2=
A.M.A. (ON and ON)
Tonydot (TANGLE)
KenNYstyle
Yuri Nagahori
Cozzy
MOMO.
VENT:https://vent-tokyo.net/schedule/osunlade/
Facebookイベントページ:https://jp.residentadvisor.net/events/1317046
※ VENT では、20歳未満の方や、写真付身分証明書をお持ちでない方のご入場はお断りさせて頂いております。ご来場の際は、必ず写真付身分証明書をお持ち下さいます様、宜しくお願い致します。尚、サンダル類でのご入場はお断りさせていただきます。予めご了承下さい。
※ Must be 20 or over with Photo ID to enter. Also, sandals are not accepted in any case. Thank you for your cooperation.
VENT PRESS
MAIL: press@vent-tokyo.net
TEL: 0364389240
ADDRESS: 〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1F
VENT WEB SITE: https://vent-tokyo.net/
Facebook: https://www.facebook.com/vent.omotesando/
Twiter: https://twitter.com/vent_tokyo/
Instagram: https://www.instagram.com/vent.tokyo/

■プロフィール
Osunlade はアートそのものを擬人化したかのような存在だ。彼の音楽は、調和、人生、知性が融合されたメロディーを作り出す。彼の出身はブルースやラグタイム、ジャズなどが生まれたミズーリ州のセントルイスだった。7歳でピアノに運命的に出会った。12歳の頃までには作曲に興味を持っていたという。その後に地元でバンドを結成し、いくつかの楽器も習い、作品に磨きをかけるために学んでいた。
17歳のときの1988年に初めてプロとしてハリウッドへ旅行した。コリオグラファーでパフォーマーでもある Toni “Mickey” Basil にすぐに目をかけられ、セサミ・ストリートなど子供向けテレビ番組を含むいくつかのプロジェクトの音楽担当を任された。彼女の後押しもありロサンゼルスへ移住し、その後の壮大な楽曲制作のキャリアが始まったのだ。数年後に初めてプロデュースしたアルバム作品は、当時はまだインディーだった〈Intersope〉からのものだった。Gerardo というアーティストの作品で、今では友人であり、彼は俳優、ダンサーとしても活躍している。“Rico Suave”というラテン・ポップ初期作とも言えるキャッチーなフレーズの曲を制作した。GQerardo は素晴らしい機会を得た直後に、数作のプラチナ・アルバムと4枚のゴールド・シングルをリリースしている。
その後数年間で20作を超える作品に関わってきたが、Osunlade は音楽ビジネスを学ぶことは、自分の音楽への情熱を弱めてしまうのではないかと考えるようになった。マス向けで供給から成り立つものの元で働くのはやめようと決意したのだ。精神的な癒やしを求め、自分の魂に誇りを持つことを望んでいると、Ifa を知ることになった。それはアフリカのヨルバ民族やアメリカの奴隷達から伝わった自然を元にするの文化的/宗教的な占いのようなものだ。
1999年に Osunlade は夢を叶えるために動き出した。〈Yoruba Records〉を立ち上げたのだ。世界で最も重要なレーベルのひとつと認識されており、魂を昇華させる音楽を作り出している。
レーベルが成長していくと Osunlade の人気も高まっていった。2001年にはデビュー・アルバム『Paradigm』を人気の〈Soul Jazz Records〉 label からリリースした。このアルバムはその年の最も売れたハウス・アルバムの1枚となり、彼は「ハウス界のメシア」と評されるようになった。多くのDJが彼の音楽をサポートし、今ではより多くの人々に聴かれるようになりついには、ミュージシャンであり、コンポーザーであり、プロデューサーであり、そしてアーティストとして認知されたのだ。
DJセット、リミックス、アルバムそして数枚のミックスCDをリリースし Osunlade の唯一無二のクオリティの作品は常に高い評判を得ている。
Osunlade の率いる〈Yoruba Records〉は1999年の最初のリリース以来ダンス・ミュージック・シーンを牽引している。Ifa の教えのもとに立ち上げ、ディープ・ハウスからソウルフルなハウスまで幅広い作品をリリースしてきた。常に素晴らしい作品を心がけ一切の妥協がない。ダンスは昔から重要なものであり、ジャズやソウル、オルタナなエレクトロニックも作品を手掛けてきた。シンプルに良い音楽の事を考え続け、〈Yoruba〉は時代の変化を乗り越えてきた。様々なスタイルのアーティストの作品をリリースしてきた。コンセプトとして精神的な結びつきを最も重要視している。エネルギーとヴァイブスに導かれて、それぞれのアーティストが情熱に従ってクラシックだが誠実な、魂を反映するかのような作品を作り続けている。300を超える作品をリリースし、人々の中にある境界線を広げようとしているのだ
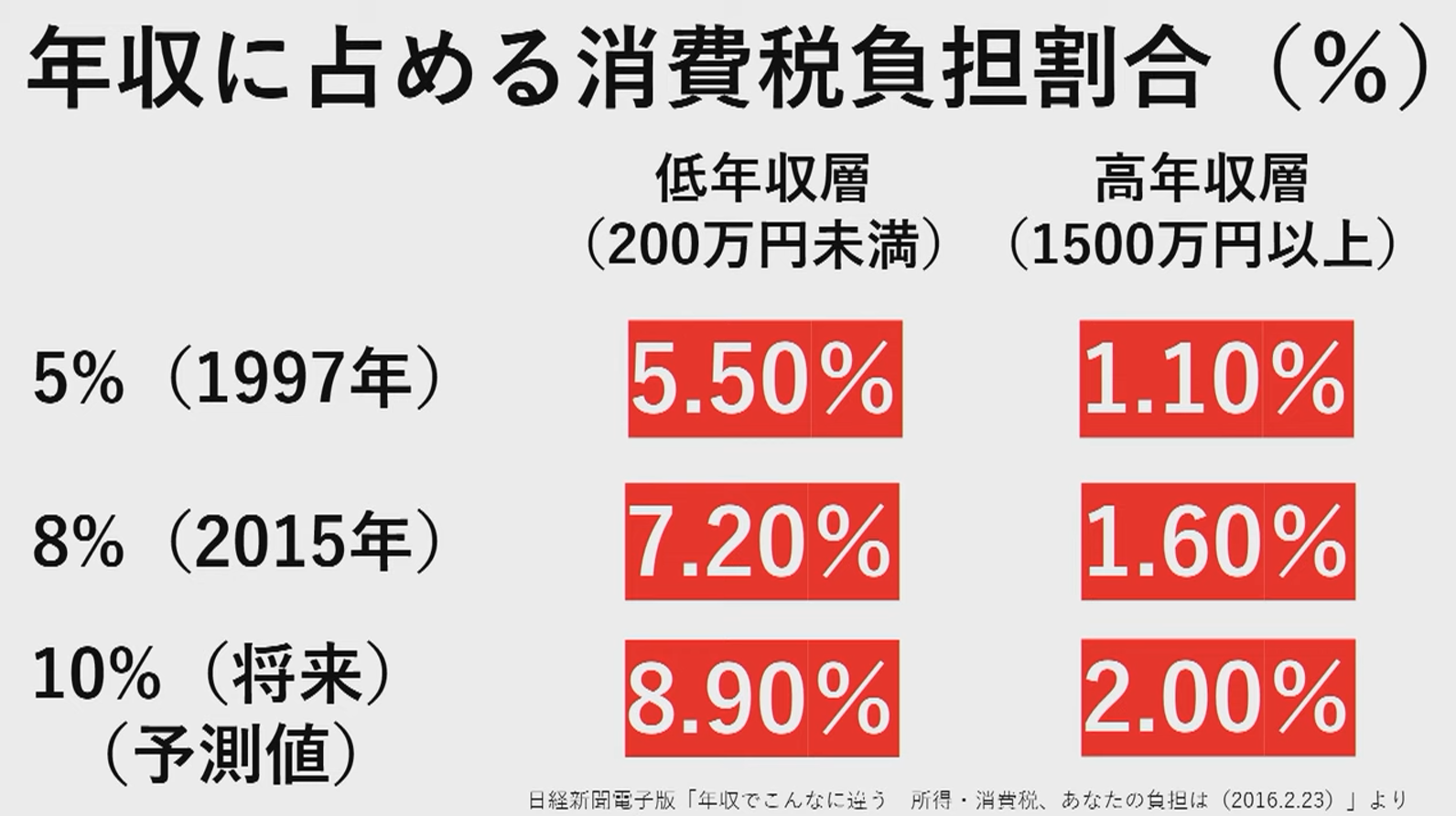





 プログラムA「PLAY through ICONO/MUSICO/CLASH」(撮影:大島拓也)
プログラムA「PLAY through ICONO/MUSICO/CLASH」(撮影:大島拓也) プログラムB「“You are not here” is no use there」(撮影:大島拓也)
プログラムB「“You are not here” is no use there」(撮影:大島拓也) プログラムC「“You are not here” is no use there」(撮影:大島拓也)
プログラムC「“You are not here” is no use there」(撮影:大島拓也)