ジャム・シティことジャック・ラザムが帰ってきた。2015年の『Dream A Garden』から5年、ついに新たなアルバムが送り出される。タイトルは『Pillowland』、発売は来週11月13日で、今回は〈Night Slugs〉ではなく自身のレーベル〈Earthly〉からのリリースとなっている。
プレスリリースによれば、疑念と痛みと混乱と変化に満ちた自らの生活に向きあった結果、アンフェタミン漬けで甘~いポップの夢景色のなかに逃避した内容になっているらしい。ふむ。楽しみに来週を待とう。
 Jam City
Jam City
Pillowland
Earthly
01. Pillowland (2:28)
02. Sweetjoy (2:50)
03. Cartwheel (3:38)
04. Actor (2:01)
05. They Eat The Young (2:30)
06. Baby Desert Nobody (1:32)
07. Climb Back Down (3:26)
08. Cruel Joke (4:50)
09. I Don't Wanna Dream About It Anymore (5:05)
10. Cherry (4:05)
Written & Produced by Jam City
Mixed by Liam Howe and Jam City
Mastered by Precise
All artwork by Jakob Haglof
All photography by Sylwia Wozniak






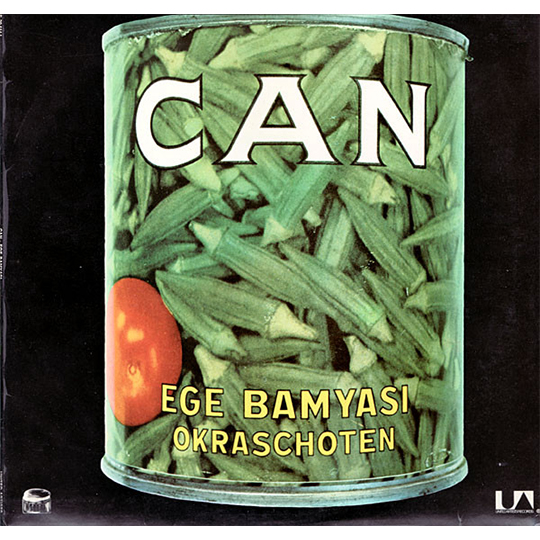
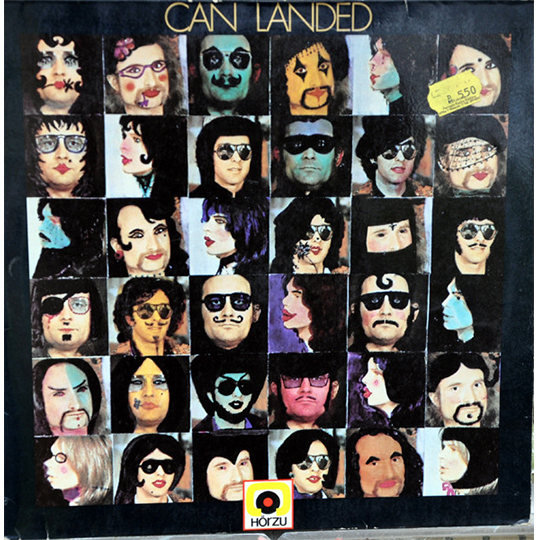













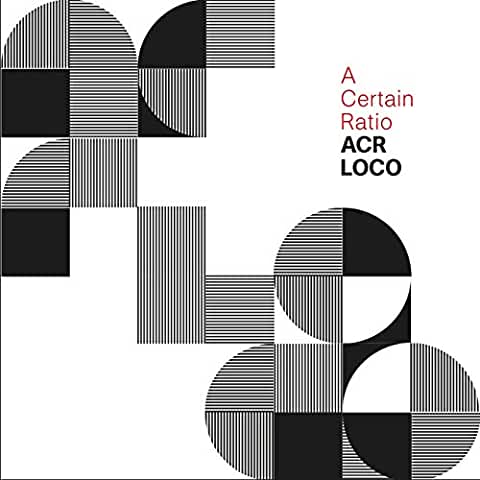
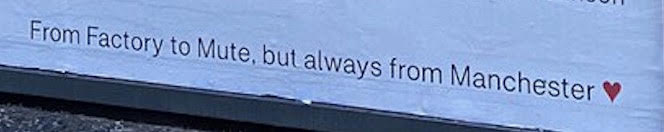


 デニス・ジョンソンとACR。
デニス・ジョンソンとACR。
