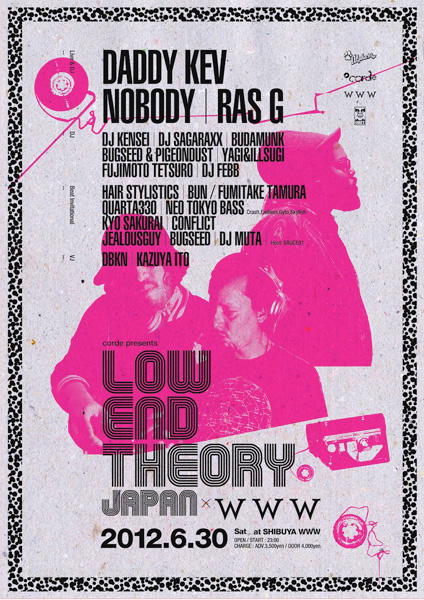ビットとバイトからなる世界に生きている
一緒になれるのはネットの世界だけ
"アイ・ヒューマン"
ジャザノヴァとは、温かきジャズやソウル、そして最新のエレクトロニックの激突だった。たとえば、ジャズなど生楽器によるヴィンテージな音楽、ドラムンベースのような打ち込みによるクラブ・ミュージックを並行して聴いてきた僕にとって、ある時期までそうしたふたつのジャンルは別モノとして接していたが、1997年に登場したジャザノヴァは、生音を好む耳とクラブの耳との交流をうながした。
ジャザノヴァは、もともとはサンプリング主体の音楽だったけれど、たしかにそこには最初からライヴ感と臨場感があった。15年も前にリリースされたデビュー曲「Jazzanova EP」は、生とエレクトロニックの混合、ヴェンテージと最先端を組み合わせがある。ドイツらしくバウハウス調のデザインにパッケージされたそれは、クラブ・ジャズの新境地を切り開いた名盤として知られている。
彼らの初期の影響はアメリカのヒップホップ(ATCQやジャングル・ブラザース)だが──そこがベルリンのテクノ一派とは違っている──、彼らにはセンスがあり、なによりも勤勉さと緻密さとテクニックがあった。やがて、ジャザノヴァはヨーロッパのジャズとマスターズ・アット・ワークやデトロイト・テクノをミキシングした。彼らのレーベル〈コンポスト〉はジャズ・ハウスの引率者となり、他方で彼らは、そして、いわゆるnu jazzの走りともなった(そしてもうひとつの彼らのレーベル〈ソナー・コレクティヴ〉は、その後、新しいヨーロッパ・ハウスの潮流を生んでいる)。
 Jazzanova Funkhaus Studio Sessions Sonar Kollektiv/Pヴァイン |
ベルリンを拠点とするジャザノヴァは、ステファン・ライゼリング、アクセル・ライネマー、ロスコ・クレッチマンのプロデューサー・チーム、そしてユルゲン・フォン・ノブラウシュ、アレクサンダー・バーク、 クラアス・ブリーラーのDJチームからなる。ベルリンにおけるクラブ・ジャズの最重要拠点である。
2002年にリリースされたファースト・アルバム『イン・ビトゥイーン』では、うまさや熱狂だけではなく、彼ら自身の深いエモーショナルな側面も強調しているが、2008年に由緒ある〈ヴァーヴ〉からリリースされた『オブ・オール・シングス』では、アジムス、ドゥウェレ、ホセ・ジェームス、ベン・ウェストビーチなどなど豪華なゲストを招き、それまで以上に生演奏の比重を増やし、よりダイナミックで華麗なサウンドを確立している。ちなみに『オブ・オール・シングス』のクローザー・トラックが、大人に成長することを拒む少年の気持ちを歌っているモリッシーの"ダイアル・ア・クリシェ"(1988)カヴァーだったことは実に興味深い。
そして、先月リリースされた4年ぶりのサード・アルバム、『ファンクハウス・スタジオ・セッションズ』で、ジャザノヴァはまったくの生バンドとなった。デジタル化する世界とは逆行するように、彼らはビットとバイトの世界よりもアナログを選び、サンプリングよりも生演奏に徹し、ジャザノヴァ流のバンド・サウンドの完成へと向かった。アルバムにおける唯一の書き下ろし曲"アイ・ヒューマン"がそうなったことの本心を明かしている。
いずれにせよ、美しい歌、心躍る演奏、それらヒューマンな行為のなかの陶酔する甘美な時間......我々がなぜソウル・ミュージックを必要とするのか、その理由がここにはある。
ジャザノヴァをステファン・ライゼリングとともにオーガナイズしている中心人物のアクセル・ライネマーに話を訊いた。
バックステージでも空港でもemailをチェックしたり、Facebookのコメントをチェックしたりと、これも僕たちの生活の一部になっている。まあ、当たり前なことだと思う。でも隣に座っている人とSkypeで会話をするのではなく、向い合って心のこもった会話をすることは大切なことなんだ。
■まずはアルバム完成おめでとうございます。とても人間味あふれる素晴らしい内容で、いつまでも色褪せないアルバムだと感じました。まず、今回のこのバンド・プロジェクトを試みることになった経緯を教えて下さい。
アクセル:このバンド・プロジェクトのきっかけは2009年にロンドンで開かれたジャイルス・ピーターソンのワールドワイド・アワードだった。ジャザノヴァは今年で結成15年になるんだけど、前作の『オブ・オール・ザ・シングス』では、いままでのプログラミングとサンプリング主体とは違って、ミュージシャンをたくさん使って制作した。だからジャザノヴァのDJは世界中でプレイするたびに各地で「なんでバンドを連れてこないの? DJだけなの?」と質問され続けてきた。だから僕とステファンは「すべてサンプリングで制作された自分たちのエレクトロニック・ミュージックをどうやってステージ上で再現しようか」と話し合ってきた。
最初はやり方がわからなかったけど、『オブ・オール・ザ・シングス』はドラムスだけがプログラミングされたものだったから、もしかしたらいまならバンドで再現することができるかもしれないと思って、そこで以前から一緒に仕事をしてきたミュージシャンを招いた。ミカトーンのポール・クレバーはいつも僕たちの楽曲でベースを弾いてくれていたし、セバスチャン・シュトゥッドゥニツキーは音楽的なディレクターとして楽曲の別アレンジを作る際に協力してくれた。前のアルアバムではオーケストラやストリングス隊など多くのミュージシャンと制作していたから、一緒にステージで演奏するのは難しいと思っていた。でも、セバスチャンが別のアレンジを作ってくれたので9人編成で演奏することができるようになった。
■打ち込み、ダンス・ミュージックに飽きてしまったんでしょうか?
アクセル:飽きたってことはないね。ライヴだってダンス・ミュージックだろう。"フェディムズ・フライト"のようなクラシックから"アイ・ヒューマン"のような最新曲まで演奏するよ。充分にダンサブルな曲だし、パーティ用のセットでもあるからね。クララ・ヒルやラ・ルーの作品をプロデュースしたり、たくさんレコーディングしてきたんで、スタジオでの作業もどんどん良くなっていって、その制作過程を自分たちの楽曲にも活用できると思った。だからステファンはもっと作曲にフォーカスするようになってきたんだ。それでもプログラミングでの制作に飽きたわけじゃないよ。いまでもビートはクレイジーな感じにプログラムしているしね。
■これまでの制作との違いはなんでしょう? こだわりの部分や、苦労したこと、予想もできないハプニングなどがあったら教えて下さい。
アクセル:もっとも変わったことといえばフル・バンドとともにスタジオに3日間入ってレコーディングしたことだね。いままでのジャザノヴァの制作ではホーン隊で1日、次の日にストリングスをレコーディングしたりと、すべてレイヤーになっていて、録音も分けてやっていた。
だけど今回はフル・バンドで一緒にスタジオに入ってレコーディングしたんだ。これは本当に新しいことだったね。しかもかなり上手くいったよ。一緒にツアーをしてきたバンドだから楽曲も知っていたし、演奏も熟知してたからね。このスタジオ・セッション・アルバムはジャザノヴァのスタジオで制作された楽曲とライヴ・ショーとの架け橋だと思っている。ライヴについて言えば、つねにステージの上でジャザノヴァのスペシャルなサウンドが出せるわけでないけどね。ときには20分しか準備時間がないときなんかもあって、9人のバンドでみな違うセッティングだと正しい音が出せないこともある。だけどこのレコーディング・セッションではヴィンテージなマイクをたくさん持ち込んでレコーディングして、自分でミックスをした。だからサウンドがスタジオでのプロダクションとライヴ・バンドの中間なんだ。
■前作から4年間ブランクがありましたね。たとえば、その間、アレクサンダー・バークはクリスチアン・プロマーとのコンビで〈Derwin Recordings〉から積極的に作品をリリースしていましたよね。」他のアーティストは、どのような活動を続けていたのですか?
アクセル:ステファンと僕はバンドと一緒にずっとツアーに付きっきりだった。新しいアルバムはすぐリリースできると思っていたんだけど、ツアーや準備に思った以上に時間がかかってしまった。新しい体験だったからね。でもすごく楽しいことだったよ。それから他のミュージシャンのスタジオ作業やプロデュースでも忙しかった。たとえば〈P-VINE〉からリリースしたフィン・シルヴァーも僕のプロデュースだし。フィン・シルヴァーとはレコーディング、ミックス、ツアーとたくさんの仕事をしてきた。この4年間はこんな感じだったよ。
■各個人が有名なって、なかなか一緒に制作をする時間がないと思いますけど、どのようにやり取りし、制作を進めたのですか? また、衰えることのない制作意欲の源はなんでしょう?
アクセル:ジャザノヴァのメンバー全員がレコーディングに参加したわけではないんだ。オリジナルのメンバーは僕とステファンだけだった。このふたりですべてのプロジェクトをオーガナイズしている。ライヴ・バンドはジャザノヴァのオリジナルのメンバーとはまったく違ってライヴのために結成した新しいものだよ。DJたちは世界中をツアーしたり、コンピレーションを作ったり、自分たちのレーベル、〈ソナー・コレクティヴ〉のことに集中したりとみんな忙しいから、少し休んでからまた制作を再開したんだ。
[[SplitPage]]ジャザノヴァのDJは世界中でプレイするたびに各地で「なんでバンドを連れてこないの? DJだけなの?」と質問され続けてきた。だから僕とステファンは「すべてサンプリングで制作された自分たちのエレクトロニック・ミュージックをどうやってステージ上で再現しようか」と話し合ってきた。
 Jazzanova Funkhaus Studio Sessions Sonar Kollektiv/Pヴァイン |
■手本にしたバンドや、影響を受けたバンドはいましたか?
アクセル:そうだね、たとえばば昨日は僕にとってはダラダラした感じの日曜日だった。ゴロゴロしながらたくさんの音楽を聴いたよ。僕にとってはいろんな音楽のサウンド・スケープに飛び込んでいくような感覚が楽しくて、どうやって曲を作っているのか考える。とても刺激的で、すぐにでもスタジオに入ってレコーディングしたくなる。スタジオで多くの人と働くことも素晴らしいことで、さまざまな人がいるからそれぞれが音楽に何を感じているのか、音楽で何を表現しようとしているのかを理解しようとする。だからみんなの音楽から影響を受けるんだ。
■ジャザノヴァのデビュー当時は、ボサノヴァ色が強かったように思いますが、あの頃に比べ、よりジャズやソウル・ミュージックへ傾倒している理由はなんでしょう?
アクセル:ジャザノヴァが音楽を作りはじめた90年のはめの頃、僕とステファンは、ア・トライブ・コールド・クエストやジャングル・ブラザーズといったヒップホップにどっぷりとはまっていた。それと同じ頃にレコード収集もはじめて、サンプリングに使えそうなものを探していたし、他のアーティストがサンプリングに使っていたものもたくさん聴いた。だからソウル、ファンク、ジャズには大きな影響を受けてきた。時間が経つに連れてロックだったり、カントリーなんかも聴くようにもなったけどね。
音楽を作るときには新しいスタイルを見つけたり、異なったスタイルのなかから類似点を見つけることができる。これが自分のスタイルを確立するのに影響をあたえるんだよ。だから最初にはまったヒップホップやソウルからの影響が大きいんだ。
■デトロイト出身のポール・ランドルフをヴォーカルに起用してますよね。前作でも彼は歌っていますが、どうしてこうなったんですか?
アクセル:自然な流れだったんだ。彼はクールなソウル・シンガーだからね。うまくいったと思っているよ。
■どこでポール・ランドルフとつながったんですか?
アクセル:ジャザノヴァのDJ、ユルゲンがオーストラリアでDJしたときに、ポールはアンプ・フィドラーとツアーしていた。そこで彼らが会った。数年たってからポールがベルリンでライヴをやった際にまた連絡を取って、そのときのアフター・パーティでポールが即興で歌った。彼がマイクを取ったときは本当に驚いた。こんなにすごいシンガーだったとは思ってなかったからね。そこで新しいアルバム(『オブ・オール・ザ・シングス』)で数曲歌ってくれないかと尋ねてね。そして"レット・ミー・ショー・ヤ"と"ラッキー・ガール"、それからモリッシーの"ダイアル・ア・クリシェ"のカヴァーの3曲をレコーディングした。
ライヴ・プロジェクトをはじめる際に「一緒にツアーできるのは誰だろう?」と悩んだ。あのアルバムに参加してくれたホセ・ジェームスとベン・ウェストビーチもツアーで相当忙しかったし、全員で一緒にツアーを回るのは難しかった。そこでポールがいいと思った。ポールならベースも弾けるし、いろんな曲も歌える。ホセが歌った"リトル・バード"もポールの個性で歌えるし。
ポールがマイクを握ると、ジャザノヴァ・バンドのフロントマンにぴったりな感じだった。素晴らしい決断だった思うし、彼もちょうど時間があったからね。いまではジャザノヴァ・バンドの重要な一員になったよ。ライヴ・バンドで制作した曲も、ポールはすべての曲を歌えるからね。
■また、次のシングルでは同じくデトロイトのハウスDJ、マイク・ハッカビーをリミキサーに起用しているようですね。デトロイトへの憧れ、デトロイトからの影響みたいなものはあるのでしょうか?
アクセル:ベルリンとデトロイトはエレクトロニックな音楽で昔から繋がっている。もちろん初期のテクノの時代からDJはデトロイトに影響を受けてきた。僕はそこまでデトロイトの音楽に詳しいわけではないけど、ジャザノヴァのオリジナル・メンバーのユルゲンとアレックスが"アイ・ヒューマン"のリミキサーにマイク・ハッカビーを選んだ。"アイ・ヒューマン"は、僕たちが交流のあるカール・クレイグなどに代表されるデトロイトのエレクトロニックなダンス・ミュージックからの影響ももちろん受けている。
■さらにその次のシングルはウクライナの気鋭ヴァクラのリミックス盤がリリースされそうですが、リミキサー選びの基準は?
アクセル:"アイ・ヒューマン"のテンポやフィーリングはクラップ的なリミックスにぴったりなんだ。歌もヴァクラの音にはまるんだ。クラップな感じのミックスができるDJを探していた際に、僕たちのブッキング担当のダニエルがヴァクラを紹介してくれたんだよ。
■また、ここ数年で友だちのDJやアーティストが数多くベルリンに引っ越してしまいました。あらためて訊きますが、ベルリンの魅力はなんでしょう? 他の都市と違うと感じるところがあったら教えてください。
アクセル:ベルリンはちょうどいい街なんだ。多くの人がベルリンを訪れるよ。ここに住んでDJをはじめたり新しいプロジェクトをはじめたりね。ただ、ある人はベルリンで仕事を見つけるのは難しいとも言うけどね。正しい人と繋がらなければ、シーンが独特なので、仕事を得るのは難しいかもしれないな。イギリスからきたDJレッケムみたいにうまくやっている人もいるけど。また、ベルリンに作曲をしに来るミュージシャンもけっこうまだいるよ。ジョナサン・ジェレマイアーの曲を書いているヘリテイジ・オーケストラのメンバーとも最近出会ったんだけど、彼もロンドンからベルリンに移ってきたんだ。まぁ、手頃な価格で生活できる街なんだよ。
■アルバムには、15年前のデビュー・シングル曲"フェディムズ・フライト"のリメイクも収録されていますが、当時自分たちが作った作品を今再び聴いてみた感想は? また、歳をとったなと感じるところはありますか?
アクセル:"フェディムズ・フライト"は僕たちにとってすべてのはじまりだった。思い出の曲だ。だからこそリメイクを作るべきだと考えたんだ。いまでもライヴで演奏するとき、ベースラインがはじまるとお客さんがすぐに反応してくれる。いまではバンド・メンバーはツアーを通して曲を熟知したから、ソロ・パートを入れたり、レコーディングもリラックスしてできたりと、とてもクールな感じなんだ。昔を振り返ると、すべてをプログラミングするのは時間もかかりすぎたし、考えすぎていた。いまではいろいろな音の個性が見えてくるので、僕自身もこの曲が大好きなんだ。ソロ・パートもかっこいいし、本当にうまくリメイクできたと思っているんだ。
この話を訊いてくるとき、みんな「レジェンド」という言葉を使うんだ。ちょっと怖い言葉だと感じるときがあるよ。自分も歳を取ったのかなーと感じてしまうんだ。もちろん実際に歳は取ったけど、でも気持ちは若いままだよ。すべてが新しくてエキサイティングに感じるしね。毎日が学ぶことの連続でそれが重要なんだ。ライヴでは20代の若者が僕たちをレジェンドのように見ているときがある。でも彼らは"フェディムズ・フライト"を知っている。とても不思議な感じがするんだ。
■昔のように、新譜のガンガンにレコードを買ったり、クラブに遊びに行ったりするんですか?
アクセル:DJとステファンはいまでもたくさんレコードを買っているね。僕は昔ほどではないけど、いまでもクラブには行くよ。僕はそこまでたくさんのレコードを買わないけど、いまはマイクやプリアンプといったスタジオ用の機材をもっと買うようになった。みんなはレコードに夢中で僕は機材に夢中なんだ。
■アルバムで唯一の新曲"アイ・ヒューマン"の歌詞には、人間と人間の「生」のつながりの大切さが歌われていますよね。いまのネット社会に対する危機感が込められてるように思いましたが、いかがでしょうか?
アクセル:仲の良い友人の話なんだけど、みんなで集まって食事に行ったとき、彼女はみんなで話しているあいだもブラックベリー(スマートフォン)を手にとっていま何をしているかをずっとネットにアップしていたんだ。彼女は仲の良いたくさんの友だちに囲まれているのに、本当は楽しんでいないように見えた。ずっと投稿していたんだね。ちょっといき過ぎな感じがして、これを曲にしようと思ったんだよ。でも彼女はこの曲が自分のことだとは知らないけどね。
この話は誰にも当てはまることだよね。バックステージでも空港でもemailをチェックしたり、Facebookのコメントをチェックしたりと、これも僕たちの生活の一部になっている。まあ、当たり前なことだと思う。でも隣に座っている人とSkypeで会話をするのではなく、向い合って心のこもった会話をすることは大切なことなんだ。だからこの曲は楽しい曲にしたかった。「みんなで集まって何かしたり、楽しもうよ!」ということを言いたかった。情熱を込めたかったんだ。これは本当にピースフルな曲なんだよ。
■数年前に比べ、12インチ・シングルのリリース・タイトルは増加している(量は減りましたが......)様に感じますが、あなた達もレコード(盤)に対する愛着、リリースすることに対するこだわりはお持ちですか? また、最近ではデータのみのリリース音源もありますが、どう思いますか?
アクセル:もちろん愛着はあるよ。音質を考えてアルバムをアナログでも作ることにした。これはDJの伝統でもあるしね。しばらくのあいだアナログの人気は下火だったけど、また復活してきた。CDしか売ってなかった店でも、いまではアナログもまた買えるようになってきたんだ。次第に戻ってきた感じがするよ。多くの人はmp3をダウンロードするけどね。でももちろん僕たちはアナログも大切にするよ。DJもみんながアナログだけでプレイするわけではないけど、「ある音楽」にとってはアナログは必要なものなんだ。
やっぱりいまでも手に取れるものが好きなんだ。情報を知ることができる読むことができるブックレットも重要だ。どこでレコーディングしたのか、誰が作曲したのか、バックグラウンドの情報を知ることができるからね。デジタルだと見逃してしまうことだよ。
気持ちは若いままだよ。すべてが新しくてエキサイティングに感じるしね。毎日が学ぶことの連続でそれが重要なんだ。ライヴでは20代の若者が僕たちをレジェンドのように見ているときがある。でも彼らは"フェディムズ・フライト"を知っている。
 Jazzanova Funkhaus Studio Sessions Sonar Kollektiv/Pヴァイン |
■あなたたちにとって音楽は仕事ですか? 趣味ですか?
アクセル:実際には仕事ではないね。ときには簡単なことではないけれど、僕たちにエナジーを与えてくれるんだ。音楽なしでは生きられないよ。ライヴのときは前の方の観客がバンドにあわせて反応するのを見るのは気持ちのいいことで、一体感を感じる。頑張った甲斐があったと感じるんだ。
■制作しているのは売れる音楽? それとも好きな音楽?
アクセル:売れる音楽を作っているとは思っていないよ。たぶんできないね。つねにジャザノヴァは僕たちのなかから出てくるものを制作する。僕たちにはレディ・ガガのような音楽はできないし、彼女にも僕たちの音楽はできないんじゃないかな。これは個性であって真似できるものではないよ。ヒットを作ろうとは思わない。一度ヒットしてしまうと、同じようなものを作ろうと思うんだけど、同じものは作れないよ。それでは成功したとは言えないでしょ。ラナ・デル・レイも一緒。セールスはとてもいいし、他と同様な曲は入っていない。同じようなことを繰り返ししようとは思わないんじゃないかな。
■ある意味、このアルバムでジャザノヴァにとってのひとつの最終地点/完成形を迎えてしまったと思うのですが、次はどこへ向かうのか、次に向かう先はもう明確に見えているのか?
アクセル:休もうとは思っていないよ。次のアルバムを作りたいんだ。向かう先は今作で作った道の延長だろうね。バンドで作曲した曲を増やしたいし、また原点に帰ったインストの曲も入れたいな。そういう曲もジャザノヴァらしい曲だと言えるし、新しいテクニックや、新しいサウンドを見つけたい。
完成形と言われるのが不思議だよ。このアルバムではジャザノヴァは大して変化していないからね。すべての音符をきっちりプログラミングしてきたことから、ライヴ・バンドによってレコーディングするという変化はあったけどね。自分たちでこれ以上コントロール出来ないこともあって、諦めたこともあったけど、いろいろと学ぶことができた。僕とステファンにとってはとても楽しい経験だったよ。もしバンドがいいグルーヴを持っていたら、レコーディングしたものを切り刻んでつなぎ合わせることはしない。ひとつの音が遅れてたり、もしくは走っていたとしても、良い感じに聴こえるのならOKなんだ。昔はすべてをきっちり作ろうとしすぎていたけどね。ポールのヴォーカルもきっちりと正そうとは思わなかった。たとえ音がずれていても、それがライヴ・パフォーマンスなんだ。これは僕たちの主張でもある。すべてを完璧にしようとは思わない。感情に従って、全体像を見る。相互作用を聴くんだよ。でももしかしたらおかしなところがあるかもしれないけどね。
■最後に日本のリスナーにメッセージをお願いします。
アクセル:いつでも日本には行きたいと思っているよ。僕たちの住むベルリンとは全く異なる街だからとても楽しいしね。長く滞在して文化を学べたらいいと思ってるよ。どこへ行ってもライヴに集中して、インタヴューなど受けたりするとその街をじっくり探検することができないからね。みんな日本が大好きで、友人からは日本に行くことを羨ましがられるんだ。素晴らしいファンがいてくれて、素晴らしいコミュニティがあるしね。日本に行けることを本当に楽しみにしているよ!
ゆっくり生きていたときを忘れないで
いっしょにどんちゃん騒ぎをして祝おう
"アイ・ヒューマン"
I Human feat. Paul Randolph
Believer
Let It Go
【ジャザノヴァがバンドセットでの来日決定!】
BROOKLYN PARLOR presents
"GOOD MUSIC PARLOR" LIVE at BLUE NOTE TOKYO
JAZZANOVA LIVE featuring PAUL RANDOLPH
ジャザノヴァ・ライヴ featuring ポール・ランドルフ
DJ : DJ KAWASAKI (7.16mon.)、沖野修也(Kyoto Jazzz Massive) (7.17tue.)
2012 7.16mon.-7.17tue.
7.16mon.
[1st]Open4:30p.m. Start6:00p.m.
[2nd]Open8:00p.m. Start8:45p.m.
★DJ
[1st]4:30p.m.-6:00p.m.
[2nd]8:00p.m.-8:45p.m.
7.17tue.
[1st]Open5:30p.m. Start7:00p.m.
[2nd]Open8:45p.m. Start9:30p.m.
★DJ
[1st]5:30p.m.-7:00p.m.
[2nd]8:45p.m.-9:30p.m.