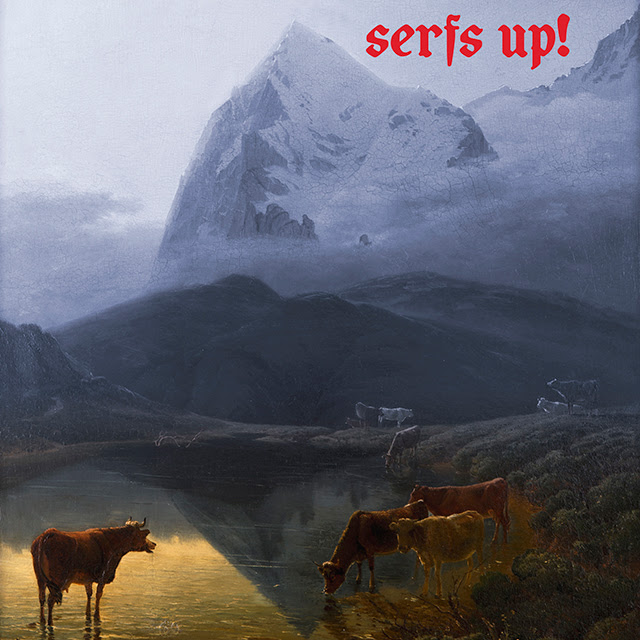先日のモッキーとのライヴも超パンパンだった坂本慎太郎のほやほやニュースです。
(以下、レーベルからの資料のコピペ)
サンパウロのO Ternoのニュー・アルバム『atrás/além』に、坂本慎太郎、デヴェンドラ・バンハート1曲参加。その参加曲「Volta e meia」を、zelone recordsより7inchリリース。
ブラジル・サンパウロを拠点に活動するバンド、O Ternoのニューアルバム「atrás/além」に坂本慎太郎とデヴェンドラ・バンハートが1曲参加し、その参加曲「Volta e meia」の7inch vinylを、5月22日(水)にzelone recordsより発売が決定しました。
坂本慎太郎がソロ初LIVEを行なった、2017年ドイツ・ケルンで開催された”WEEK-END Festival #7”にO Ternoとデヴェンドラ・バンハートも出演。そこでの交流がきっかけとなり、O Ternoからのオファーで実現した今回のコラボレーションです。
共演曲「Volta e meia」は、O Ternoの今までのソウル/ロック路線とはまた違う、淡いサウダージとメロウネスを醸し出す、洗練されたソフトサイケなMPB。c/wの「Tudo que eu não fiz」は、ニューアルバムの冒頭を飾る、ほのかにサイケな珠玉のトロピカリア/ソフト・ロック・チューンで、どちらも新作を代表する2曲です。
zelone版7inchは坂本慎太郎によるアートワーク仕様になります。
この「Volta e meia」は4月16日、ニュー・アルバム『atrás/além』は4月23日にブラジルより世界配信されます。
2019年5月22日(水) zelone recordsより発売!
Volta e meia / O Terno feat. Shintaro Sakamoto & Devendra Banhart
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
SIDE A: Volta e meia / O Terno feat. Shintaro Sakamoto & Devendra Banhart [3:17]
Biel Basile – drums, mpc, percussion
Guilherme D’Almeida – bass
Tim Bernardes – vocals, acoustic and electric guitars, synthesizers
Felipe Pacheco Ventura – violins
Amilcar Rodrigues – flugelhorn, trumpet
Shintaro Sakamoto - vocals
Devendra Banhart - vocals
SIDE AA: Tudo que eu não fiz / O Terno [3:47]
Biel Basile – drums
Guilherme D’Almeida – bass
Tim Bernardes – vocals, electric and acoustic guitars
Felipe Pacheco Ventura – violins
Douglas Antunes – trombone
Amilcar Rodrigues - trumpet
Beto Montag - vibraphone
O terno: Biel Basile, Guilherme D’almeida and Tim Bernardes
Compositions, arrangements and musical production: Tim Bernardes
Co-production: Gui Jesus Toledo, Biel Basile, Guilherme D’almeida
Recording and sound engineering: Gui Jesus Toledo
Mixing: Tim Bernardes
Mastering: Fernando Sanches
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
品番: zel-019 (45rpm)
発売日: 2019年5月22日(水)
形態: 7inch Vinyl (exclusive 7inch)
価格: ¥1,000+税
Distribution: JET SET https://www.jetsetrecords.net
More info: www.zelonerecords.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●O Ternoプロフィール●
Tim Bernardes、Guilherme D’Almeida、Biel Basileによるサンパウロのソウル / ギター・ロックバンドで、新世代ブラジル音楽の重要な担い手として注目を集める。
2012年6月、1stアルバム「66」をリリース。The Globe誌によって”ブラジルのバンドの最も印象的なデビューディスクの1つ”と、Rolling Stone Magazine Brazil による2012年の25枚のベストアルバムに選出された。
2013年、Tom Ze EPのFeicebuqui Courtのために2曲をレコーディングし、EP 「TicTac-Harmonium」リリース。
2014年に、Charlie and the MalletsとLuiza Lianのような7つの他のバンドと共に、レーベル”RISCO”を結成。
同年8月、メンバーによって書かれた12曲を含む2ndアルバム、「 O Terno」をリリース。
2015年3月、バンドの編成が変わり、Victor Chavesが脱退し、現在のBiel Basileがメンバーに加入、そして新生O TernoとしてLollapalooza Festivalに出演。
2016年、RISCOレーベルの最初のコレクション、レコーディングに参加し、 5月下旬から6月上旬にかけて、”Primavera Sound Fes”を含むEUツアーを敢行。
9月には3rdアルバム「Melhor Do Que Parece」をリリース、”トロピカリズム、ロック、ソウル、そしてブラジルの音楽のミックス”、と世界的に評された。
2017年、ドイツケルンで開催された”WEEK-END Fes#7”に出演。そのフェスには、ソロ初のLiveを行なった坂本慎太郎、そしてデヴェンドラも出演。
同年、Vo, GuitarのTim Bernardesは、ソロアルバム「Recomeçar」をリリース。"現代ブラジルのブライアン・ウィルソン"とも評されている。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■