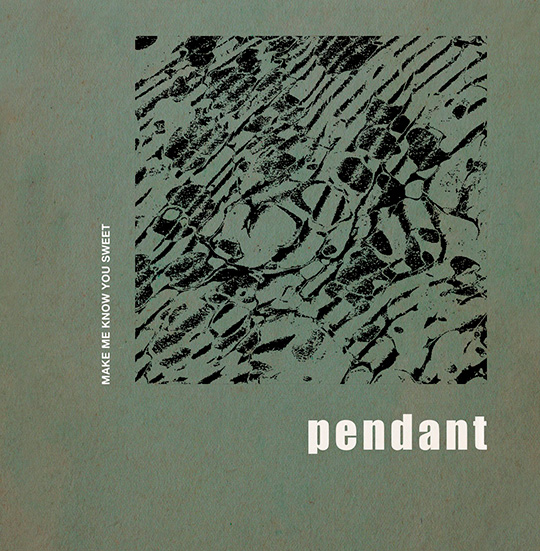Rich The Kid。リッチなキッド。名が特徴を表す。もとい、特徴がそのまま名となる。プリミティヴな、トラップ空間においては。この部族のしきたりは、その名に恥じない歌を編むことだ。だから、提出された。これら13の、富を高らかに宣言する歌が、提出された。
若き男は富をつかんだ。車はマセラッティ。あるいはランボルギーニ。そしてベントレー。時計はオーデマ・ピゲ。そして自身のレーベルも運営する。札束をひけらかすアートワーク。Kendrick Lamar、Future、Lil Wayne、Migos、Rick Rossと錚々たる面子をフューチャー。2014年から数々のミックステープで実績をひけらかしながらもオフィシャル・アルバムをリリースしなかったのは、レーベルとの契約金を最大化する戦略だったのかと訝しんでみる。今回のアルバム契約に際し、もちろん複数のオファーを受けたが、彼は簡単に首を縦に振らなかった。結果、〈インタースコープ〉が競り勝つ形となった。
ニューヨークに生まれNasやBiggieを愛聴する一方で、ハイチにルーツを持ち、フランス語系のクレオール言語を操る。Biggieから学んだことがあるとするなら、「Notorious(悪名高い)」から発想した「名の上げ方」かもしれない。MCとしての成功のためのスキルには、ライミングやフロウ、デリヴァリーだけでなく、当然セルフマーケティングも含まれるからだ。
卵が先か、鶏が先か。最初からRichを名乗る。オフィシャル・アルバムをリリースしないうちから、名を馳せる。もはやアルバムという括りにも、オフィシャルという括りにも縛られる必要はない。そういう時代だ。ただ「Rich」という名を広めることこそが、その名をますます真実にしていく。「Rich」という名が広まるにつれ、その名の真実味が増していく。名乗りそれ自体が目的となる。
トラップ・ミュージックのプレイヤーたちは群れをなし、共同のひとつのプレイグラウンドに何か巨大なモノ/ジャンルを築こうとしているのだろうか。砂場の砂で、どこまでオーバーサイズな楼閣が形作られ得るのか。互いが互いの鏡像と成り合うことで、群れ全体における砂場におけるプレイング・ルールが成形されていく。しかしそこでは個別のスタイルはどのように生まれるのか。彼らは互いの喉仏の形状を確認しながら、舌と唇と声帯で出来たトーキングドラムセットを抱え、TR-808のビートに合わせてそれを乱打する。隣の奴が持つリズムと、ときには競り合うように。そしてときには隣のドラムの響きを引き立てるように。
それは奇しくもヒップホップの黎明期のアティテュードに接近している。まだソロ活動という概念がなかったとき、彼らは徒党を組んで活動した。個ではなく、群れとして。サイファーが基本的なプラットフォームだった。サイファーにおける他のMCたちは、自分の鏡像だ。彼らは鏡の中の自分に向けてスピットする。
だからRichがこれだけの個性的なゲストに囲まれながら、彼ならではのスタイル=個性がどこにも見当たらないとすれば、それは彼の瑕疵ではない。むしろそれは、彼が1970年代と2018年、つまり40年以上を隔てたヒップホップとトラップに通底する本質を体現していることにはならないか。
これもまた「ひとりではない」ソロ・アルバムだ。ゲストをフィーチャーした楽曲群のデザイン。基本的にはまずはRichが最初のヴァースとフックをキメることでグランドデザインを示してから、客演のMCたちがコントラストを最大限に発揮しながら登場する。
たとえば“No Question”では、Futureが「brrt, brrt」と着信音に擬態しながら、荒い目のヤスリで磨いたようなざらついた声色を曝け出す。“Lost It”ではMigosのOffsetとQuavoが俄然パーカッシヴな骨太のトーキングドラムを演奏する。“End of Discussion”では残響の深いパッドと16分で刻まれるハットの上、Lil Wayneが韻先行の高速でうねる狡猾なフロウを披露する。
そしてKendrickをフィーチャーした“New Freezer”。ラッパーの肉声となんらぶつかり合うことのないウワモノ、ベースとドラム。そこではドラムがグリッドを描き、声は裸にされる。ヒップホップ史上(と言って差し支えなければ)、声がもっとも裸にされているのが「いま」なのだ。裸の声を神輿に担ぐ内省的なビートなのだ。Richの滑舌の悪さは白日に晒される。滑舌の悪さは、意図的でないにせよフロウをマンブルに近付ける。それは意味(リリック)であるより先に音色だからだ。
一方のKendrickの舌は剃刀だ。Kendrickはあらゆるフィーチャリング曲で、毎回異なるアプローチを打ち出す。自分の曲でないから余計に自由になる。彼は恐るべきことに、ここで身をもって示してしまう。トラップライクなビートはこうやって乗りこなすんだと、示してしまう。少ない言葉数で、節をつけたフレーズを絞り出す。「6,400万ドル(目もくらむ稼ぎ!)で一体何をショッピングすればいい?」と暗にRichを挑発する。お前らのやり方を、乗っ取ってやると。かつてコンプトン出身の彼が「キング・オブ・ニューヨーク」を名乗った大胆不敵さで。Richは果たして、いかに応答するのか。したのか。
ここでひとつ示されているのは、即物的な言葉を、空間的な音にぶつける手法だ。そこに生まれるのは、世界の歪みだ。奇妙な余韻だ。これは何もRichの専売特許ではなく、共有されている手法(楼閣の建材のひとつ?)だが、「Rich」を名に持つ彼が放つブランド名は、アトモスフェリックなシンセで額装され、抱えきれないほどの空白を撒き散らすのだ。
たとえば前述の“Lost It”のMetro BoominやWheezyによる共同プロデュースのビート。すぐ耳元で弾けるクラップ。それとは対照的に遠くにこだまするシンセのパッド音。両極の間でラッパーの立ち位置はどこか。それは視覚的なヴィジョンとして現れる。トラップの遅いBPMと音数が少ないことで溢れ出した行間が意味するもの。それは音の空間性だ。だから顕現するのはトラップ空間だ。8分から16分、そして32分とその幅を変化させながら縦横のグリッド線が行き交うその空間で、全ての音は座標を意識される。そして言葉も然り。
キックとスネアがグリッドを刻む空間の上で、メロウで、残響音を伴うシンセが滲む。そして投入されるのは、即物的な言葉の数々。見せびらかす、アイスまたはフリーザー。宝石や時計。ルイ・ヴィトンのカーペット。彼にとっては高価でもないベントレー。ドラッグとセックス。内省を促すようなアトモスフェリックな滲みの上で、いまこの瞬間の溢れんばかりの富がドロップされる。その際限のなさが、トラップのスカスカのビート空間にこだまする。そこに虚無を嗅ぎとるのは簡単かもしれない。何れにせよトラップ空間が、モノの異化をもたらす装置であることは疑いようもない。
このアルバムには、ゲストなしにRichひとりがライムする曲も、もちろん存在する。しかし彼は、ひとりではない。メランコリックな逆再生風シンセが手を引く“Plug Walk”。彼のPlug(ドラッグディーラー)との片言のコミュニケーションを宇宙人との会話に擬えるMV。「いまここ」で手に入るブランドを貪り尽くし、「富めること」の想像力は、宇宙へ向かう。未来へ向かう。イーロン・マスクがテスラの自動車をロケットで打ち上げてしまう発想と、火星を思わせる荒野でE.T.とダンスするRichのヴィジョンは共鳴する。Plugを迎えに行くのは、彼がE.T.が乗って来たような宇宙船と呼ぶ車たちだ。“New Freezer”のMVでもRichは、宇宙船のコクピットのようなクーペでKendrickと一緒に未来へ向かうのだ。
そして本人を召喚せずにひとりでふたりの関係を示す“Dead Friends”では、Lil Uzi Vertを壮大なビート(DJ Mustardが音素材サイト「looperman.com」の無料ネタをサンプリングしている!)をもってしてディスる。2015年の“WDYW”ではA$AP Fergを間に挟んで、ふたりのヴァースはシナジーを生んでいた。しかしあれから数年で、一体何が狂ってしまったというのだろう。Richは本曲のヴァースでライムする。「俺は永遠の富を手に入れた。スターになった。大量のアイス。大量の札束。そして大量のトラブルさ」







 photo: Atiba Jefferson
photo: Atiba Jefferson