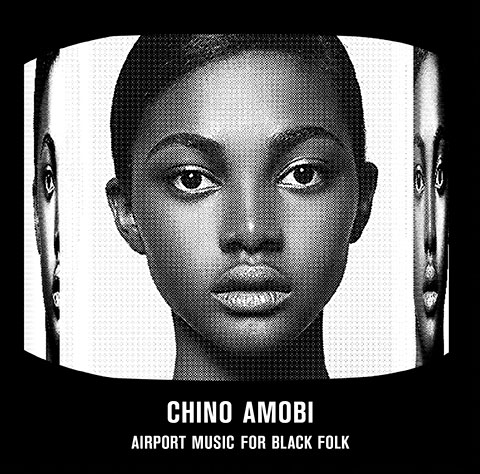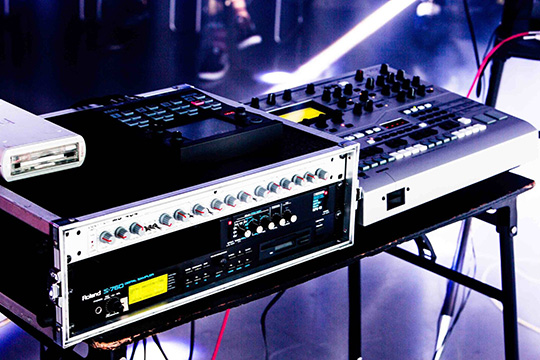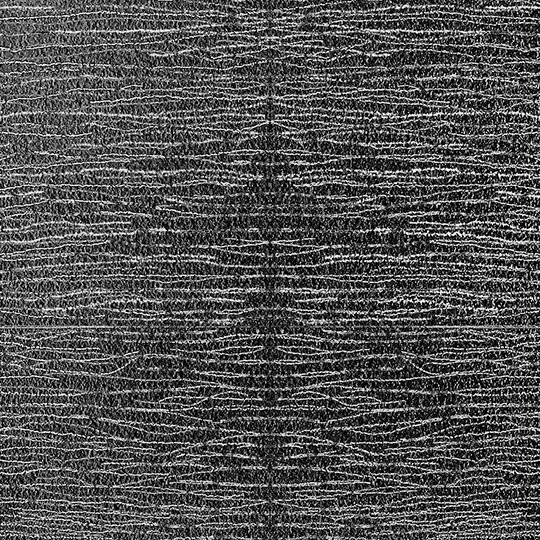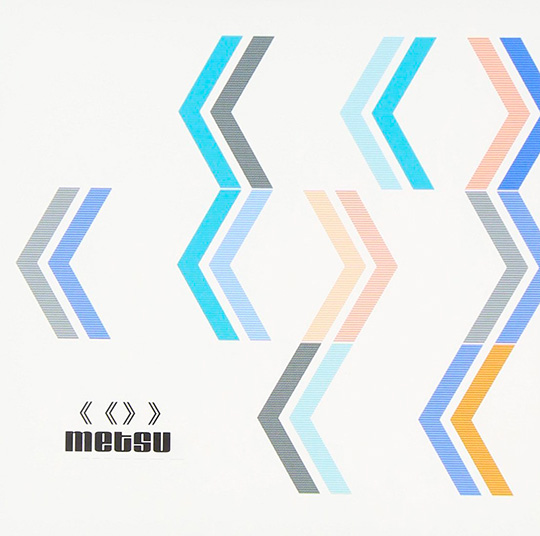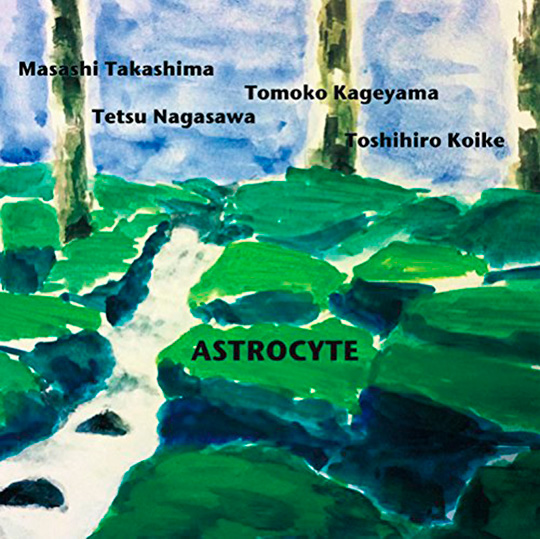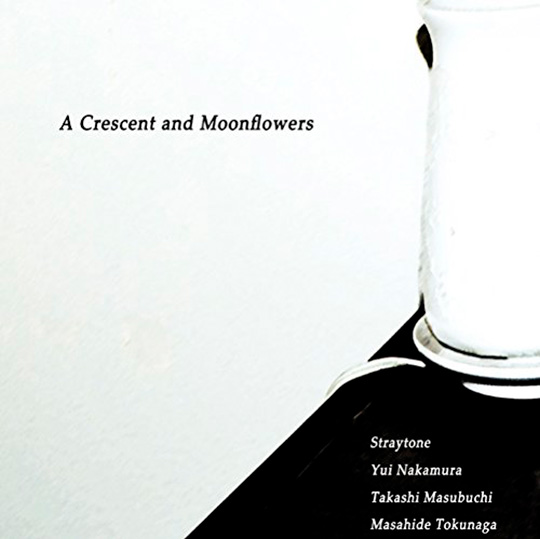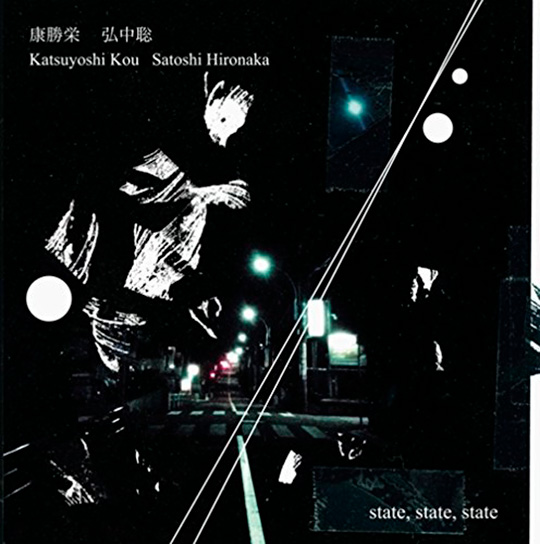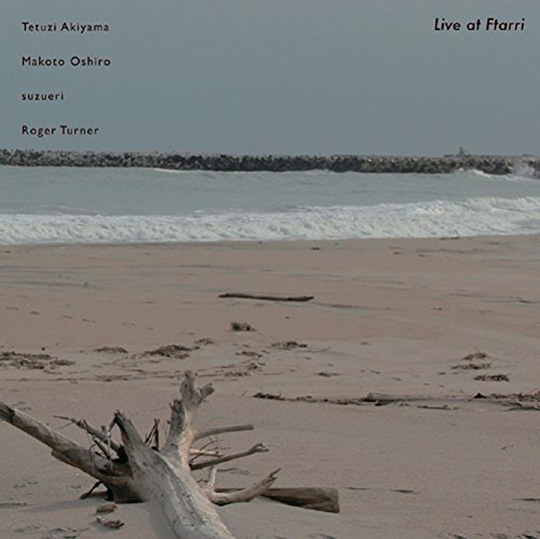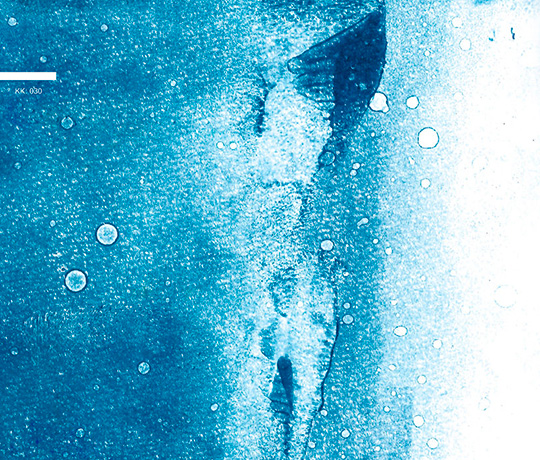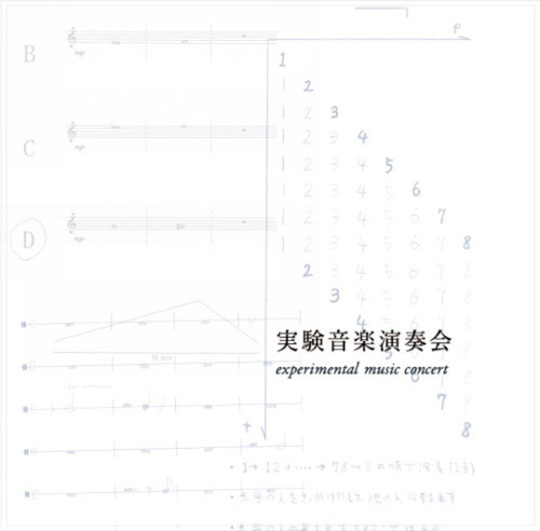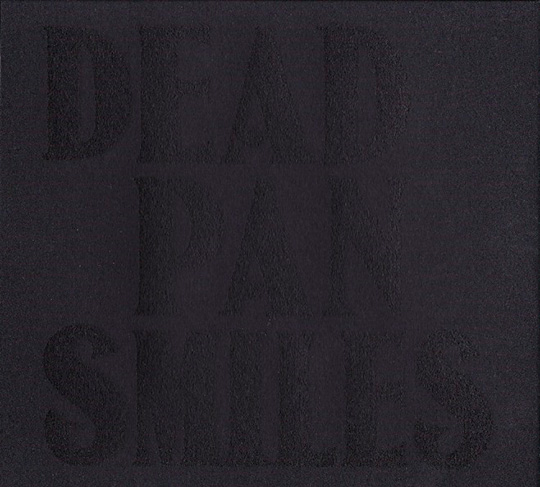ポスト・ダブステップの臨界点を突破した『Crooks & Lovers』から7年、〈Warp〉へと移籍してポスト・ポスト・ダブステップを探究した『Cold Spring Fault Less Youth』から4年……ようやくである。ドミニク・メイカーとカイ・カンポスからなるデュオ、マウント・キンビーが3枚めのアルバムをリリースする。その新作には、かつてマウント・キンビーのライヴ・メンバーであったジェイムス・ブレイクも参加している。00年代末期、マウント・キンビーもジェイムス・ブレイクもそれぞれに固有の方法で、それまでのダブステップを過去のものにしてしまったわけだが、ときの流れは恐ろしいもので、それからもう8年の月日が過ぎ去っている。それはつまり、かつて彼らの音楽に衝撃を受けたティーンネイジャーたちが、新しい音楽の作り手へと成長を遂げているということだ。そんな“いま”マウント・キンビーは、いったいどんなサウンドを届けてくれるのか。リリースは9月8日。
MOUNT KIMBIE
満を持して新作アルバム『Love What Survives』のリリースを発表!
ジェイムス・ブレイク、ミカチューに続き
キング・クルエル参加の新曲“Blue Train Lines”を解禁!
僕たちのニュー・アルバム『Love What Survives』が、9月8日(金)にリリースされることが決まって、とても興奮してるよ。アルバム制作は、バンドとしての僕らを変えてしまったくらい面白いプロセスで、完成した作品に対しても最高に満足してる。早くみんなにこのサード・アルバムを聴いてもらいたいね。
- Mount Kimbie
4月に盟友ジェイムス・ブレイクをフィーチャーした“We Go Home Together”、5月にはアカデミー賞ノミネート・アーティストとしても高く評価されているミカチューをフィーチャーした“Marilyn”と新曲を立て続けに発表し、先月にはyahyel(ヤイエル)をサポートアクトに迎えたジャパン・ツアーも決定。現在話題沸騰中のマウント・キンビーが、今回満を持して最新アルバム『Love What Survives』のリリースを発表! あわせて長年のコラボレーターであるキング・クルエル参加の新曲“Blue Train Lines”を公開した。
Blue Train Lines (feat. King Krule)
https://youtu.be/OMMlPs0O2rw
今作は『Love What Survives』、常に限界を押し広げていく彼らが贈る、自信に満ち溢れた新たなステートメントであると同時に、これまで積み重ねてきたキャリア全ての集大成とも言える作品となっている。今回公開された“Blue Train Lines”は、2013年にリリースされた前作『Cold Spring Fault Less Youth』以降のバンドの進化を凝縮したような楽曲だ。躍動感のあるリズム・セクションにあわせて、キング・クルエルの渋くしゃがれたヴォーカルが炸裂する。
今作は3年間の濃密な創作活動の結晶である。その間、彼らは様々なアイデアをもとに試行錯誤しながら、他に類がないマウント・キンビーの本領を発揮すべく、曲作りを続け、磨きをかけてきた。ジェイムス・ブレイク、ミカチュー、キング・クルエルといった、ともにイギリスの若き才能の一角を占める親しい友人や共同制作者をヴォーカルに取り込み、聴き手を独特な世界に引き込むマウント・キンビーらしいアルバムをまたひとつ完成させた。
Marilyn (feat. Micachu)
https://youtu.be/VjSKEyR2vDo
We Go Home Together (feat. James Blake)
https://youtu.be/Q-7wzb7sRg8
アルバム全体に漂う、より開放的なオーラは、ロンドンとロサンゼルスの両都市にまたがって制作されたという事実も影響している。2016年にドム・メイカーがアメリカの西海岸へ移り住んだ後、彼らはふたつの都市を行き来しながら、ともに精力的なセッションを重ね、アイデアを磨き上げていった。生活拠点を異文化の広大な土地にある都市に置くことは、新鮮な視野とインスピレーションを得る機会をバントに与え、それが飛躍的進化へと繋がった。
また今作では、80年代のUKファッション・シーンに多大なる影響を与えた伝説のファッション集団〈バッファロー〉の一員でもあり、数多くのファッション・マガジンで活躍していた写真家マーク・ルボンとその息子であるフランク・ルボンが、ミュージック・ビデオの制作およびアルバムのアートワーク制作に参加している。
マウント・キンビーの最新アルバム『Love What Survives』は、9月8日(金)に世界同時リリース! 国内盤にはボーナス・トラック“SLP12 Beat (Part 2)”が追加収録され、解説書と歌詞対訳が封入される。iTunesでは「Mastered for iTunes」フォーマットでマスタリングされた高音質音源での配信となり、アルバムを予約すると“We Go Home Together (feat. James Blake)”、“Marilyn (feat. Micachu)”、“Blue Train Lines (feat. King Krule)”の3曲がいち早くダウンロードできる。
 label: BEAT RECORDS / WARP RECORDS
label: BEAT RECORDS / WARP RECORDS
artist: Mount Kimbie
title: Love What Survives
release date: 2017/09/08 ON SALE
BRC-553 ¥2,200(+税)
国内盤特典:ボーナス・トラック追加収録/解説・歌詞対訳付き
beatkart: https://shop.beatink.com/shopdetail/000000002180
amazon: https://amzn.asia/hYzlx5f
iTunes Store: https://apple.co/2uiusNi
Apple Music: https://apple.co/2t3YEeV
Spotify: https://spoti.fi/2uiwx
アルバム詳細はこちら:
https://www.beatink.com/Labels/Warp-Records/Mount-Kimbie/BRC-553
--------------------
マウント・キンビー + ヤイエルという夢の組み合せで実現する完売必至の来日ツアーはチケット好評発売中!
お見逃しなく!
MOUNT KIMBIE - JAPAN TOUR 2017
GUEST: yahyel
大阪 10/6 (FRI) Fanj Twice
東京 10/9 (MON) WWW X - "WWW & WWW X Anniversaries"
OPEN 18:00 / START 19:00
前売TICKET ¥6,000 (税込・1ドリンク別途) ※未就学児童入場不可
INFO: BEATINK 03 5768 1277 [www.beatink.com]
■Mount Kimbie | マウント・キンビー
ドミニク・メイカーとカイ・カンポスによるマウント・キンビー。かつてジェイムス・ブレイクもライヴ・メンバーとして在籍し、「ポスト・ダブステップ」という言葉が広く認知され、ひとつの分岐点を迎えたエレクトロニック・ミュージック・シーンにおいて、中心的な役割を果たしてきた。コーンウォールで育ったカンポス。ブライトンで育ったメイカー。ふたりはロンドンのサウスバンク大学在学中に学生寮で出会い、当時熱中しはじめていたエレクトロニック・ミュージック――とりわけ新興のダブステップ・サウンド――を通じて絆を深めていった。シーンに登場した2009年以来、マウント・キンビーは幾度も予想を裏切りながら、ベッドルーム・スタジオのプロデューサーから、近年最も完成されたエレクトロニック・アルバムのひとつを世に問うたクリエイターへと変貌、ポスト・ダブステップの最右翼として成長を遂げた。満を持して発表された3rdアルバム『Love What Survives』には、ジェイムス・ブレイク、ミカチュー、キング・クルエルといった、ともにイギリスの若き才能の一角を占める親しい友人や共同制作者をヴォーカルに取り込み、聴き手を独特な世界に引き込むマウント・キンビーらしいアルバムをまたひとつ完成させた。
■yahyel | ヤイエル
2015年3月に池貝峻、篠田ミル、杉本亘の3名によって結成。同年5月に自主制作の4曲入りEP『Y』をBandcampで公開。同年8月からライヴ活動を本格化、それに伴い、VJの山田健人、ドラマーの大井一彌をメンバーに加え、現在の5人体制へ。2016年、ロンドンの老舗ROUGH TRADEを含む全5箇所での欧州ツアー、フジロックフェスティバル〈Rookie A Go Go〉ステージへの出演を経て、9月に初CD作品『Once / The Flare』をリリース。11月にはアルバム『Flesh and Blood』を発売、一気に注目を集める。2017年にはWARPAINT来日ツアーでオープニング・アクトを務め、VIVA LA ROCK 2017でのステージが入場規制となるなど、精力的にライヴをおこなっている。
最新ミュージック・ビデオ:「Iron (アイアン)」
https://youtu.be/VrwXQ-JvLis
https://www.1969records.tv/2017/artists/yahyel
label: BEAT RECORDS
artist: yahyel
title: Iron
release date: 2017.06.23 FRI ON SALE
iTunes Store: https://apple.co/2sGMO94
Apple Music: https://apple.co/2sGYJDW
Spotify: https://spoti.fi/2sOhkyr
ototoy:
ハイレゾ版 https://ototoy.jp/_/default/p/76445
通常CD音質 https://ototoy.jp/_/default/p/76444


 アーティスト: shotahirama
アーティスト: shotahirama