ジェフ・ミルズは前へ進み続ける。
去る9月11日、東京フィルハーモニー交響楽団とともに『題名のない音楽会』に出演し、大きな話題を集めたジェフ・ミルズだが、このたび彼の新たな公演が、表参道のイベント・スペースVENTにて開催されることが決定した。11月18日(金)23時、オープン。
今回の公演は、AACTOKYOが手がけるジェフ・ミルズのシネミックス(映像体験作品)最新作の、日本プレミア上映会のアフターパーティーとして開催される。
詳細は以下を。
【テクノの革命家Jeff Mills(ジェフ・ミルズ)、表参道VENTに降臨!】
未来、宇宙のメッセージを込めたテクノ・ミュージックを表現し続け20年強、今年の東京フィルハーモニー交響楽団との共演コンサートや『題名のない音楽界』への出演も衝撃的だったJeff Millsが、別次元の良質なサウンドを提案する、期待のニュースポットVENTで体感できるまたとないチャンス到来!
ハードミニマルテクノというジャンルを確立し、デトロイトから全世界のダンス・ミュージックを革新してきたJeff Mills。テクノのDJやプロデューサーとしての活動は、自身の作品のリリース、クラシック音楽の楽団とのコンサート、宇宙飛行士、毛利衛とのコラボ作品など多岐にわたる。初期Wizard名義のDJ時代にはEMINEMやKID ROCKなど他ジャンルのミュージシャンにまで影響を与えてきたという生きる伝説の存在と言ってもいいだろう。
今回は『AACTOKYO』が手がけるプロジェクト第1弾として、Jeff Millsのシネミックス(映像体験作品)最新作の日本プレミア上映会のアフターパーティーとして行われる。衰えることなく進化を続ける、他の追随を許さない圧巻のDJプレイをVENTの誇るサウンドシステムで体感できる奇跡のパーティー!
《Dekmantel Festival 2016 でのJeff Millsのプレイの映像》
《イベント概要》
" AACTOKYO presents JEFF MILLS “THE TRIP” After Party "
DATE : 11/18 (FRI)
OPEN : 23:00
DOOR : ¥4,000 / FB discount : ¥3,500
=ROOM1=
JEFF MILLS
HARUKA (FUTURE TERROR)
DSITB (RESOPAL SCHALLWARE / SNOWS ON CONIFER)
=ROOM2=
YONENAGA (R406 / SELECT KASHIWA)
NAOKI SHIRAKAWA
SHINING STAR (UTOPIA)
MASA KAAOS (PYROANIA / PHONOPHOBiA)
※VENTでは、20歳未満の方や、写真付身分証明書をお持ちでない方のご入場はお断りさせて頂いております。ご来場の際は、必ず写真付身分証明書をお持ち下さいます様、宜しくお願い致します。尚、サンダル類でのご入場はお断りさせていただきます。予めご了承下さい。
※Must be 20 or over with Photo ID to enter. Also, sandals are not accepted in any case.
Thank you for your cooperation.
Facebookイベントページ
https://www.facebook.com/events/1331989146852699/
《INFO》
VENT
URL: https://vent-tokyo.net/
Facebook: https://www.facebook.com/vent.omotesando/
Twiter: https://twitter.com/vent_tokyo/
Instagram: https://www.instagram.com/vent.tokyo/
Jeff Mills

1963年デトロイト市生まれ。
Jeff Millsがテクノ・プロデューサー/DJとして世界で最も優れた人材であることはすでに説明の必要もない。
高校卒業後、ザ・ウィザードという名称でラジオDJとなりヒップホップとディスコとニューウェイヴを中心にミックスするスタイルは当時のデトロイトの若者に大きな影響を与える。1989年にはマイク・バンクスとともにアンダーグラウンド・レジスタンス(UR)を結成。1992年にURを脱退し、NYの有名 なクラブ「ライムライト」のレジデントDJとしてしばらく活動。その後シカゴへと拠点を移すと、彼自身のレーベル〈アクシス〉を立ち上げる。1996年には、〈パーパス・メイカー〉、1999年には第3のレーベル〈トゥモロー〉を設立。現在もこの3レーベルを中心に精力的に創作活動を行っている。
Jeff Millsのアーティストとしての活動は音楽にとどまらない。2000年、フリッツ・ラングの傑作映画『メトロポリス』に新しいサウンドトラックをつけパリ、ポンピドゥーセンターで初公開して以来、シネマやビジュアルなど近代アートとのコラボレーションを積極的に行ってきている。 2004年には自ら制作したDVD『Exhibitionist』を発表。このDVDはHMV渋谷店で洋楽DVDチャート1位を獲得するなどテクノ、ダンス・ミュージックの枠を超えたヒットとなった。これらの幅広い活動が認められ2007年、フランス政府が日本の文化勲章にあたるChavalier des Arts et des Lettresを授与。
2004年渋谷Wombのレジデンシーから始まったSFシリーズ「Sleeper Wakes」は2016年リリースの『Free Fall Galaxy』で9作目を迎える。
2012年、主宰〈AXIS RECORDS〉の20周年記念として300ページにおよぶブック『SEQUENCE』を出版。2013年には日本独自企画として宇宙飛行士、現日本未来館館長毛利衛氏とのコラボレーション・アルバム『Where Light Ends』をリリース。同時に未来館の新しい館内音楽も手がけた。『Where Light Ends』はオーケストラ化され、2016年3月には文化村オーチャードホールにて東京フィルとの公演を実現させている。
2014年、Jeff Mills初の出演、プロデュース映像作品「Man From Tomorrow」が音楽学者でもあるジャクリーヌ・コーの監督のもとに完成。パリ、ルーブル美術館でのプレミアを皮切りにニューヨーク、ロンドンの美術館などでの上映を積極的に行なう。
第1弾から11年の年月を経て2015年に発表された『Exhibitionist 2』DVDには、DJテクニックのみならずスタジオ・レコーディングの様子やRoland TR909をライヴで即興使用する様子などが収められおり、同じく「即興性」をテーマにゲストミュージシャンを招待して東京と神戸で2015年9月に行われたライヴは「Kobe Session」として12インチでリリースされた。
2016年、初めてオーケストレーションを念頭におき作曲したアルバム『Planets』がポルト交響楽団とのコラボレーションによりリリースされる。








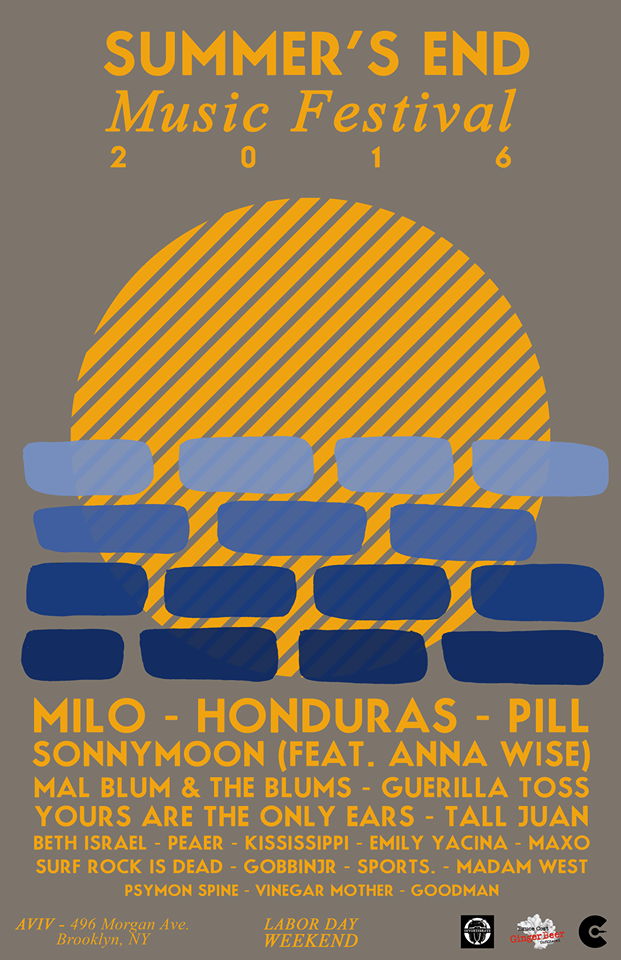




 Guerilla Toss merch
Guerilla Toss merch 



