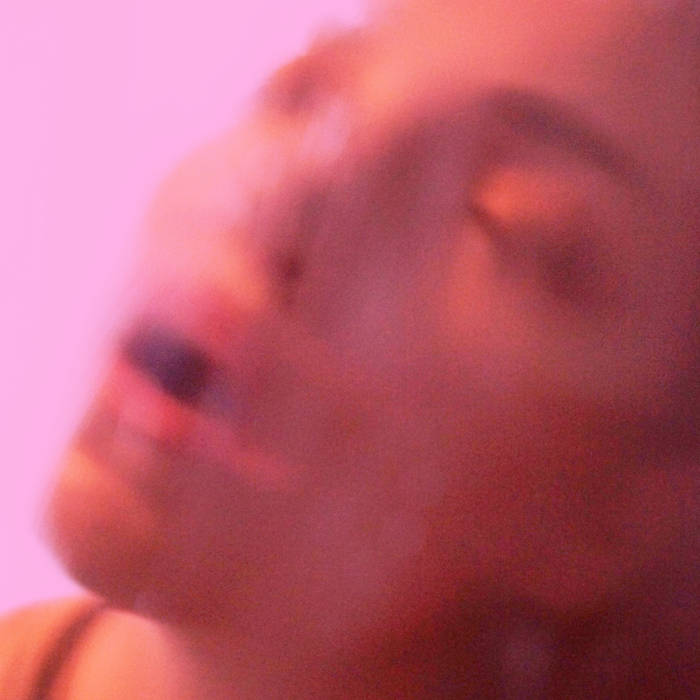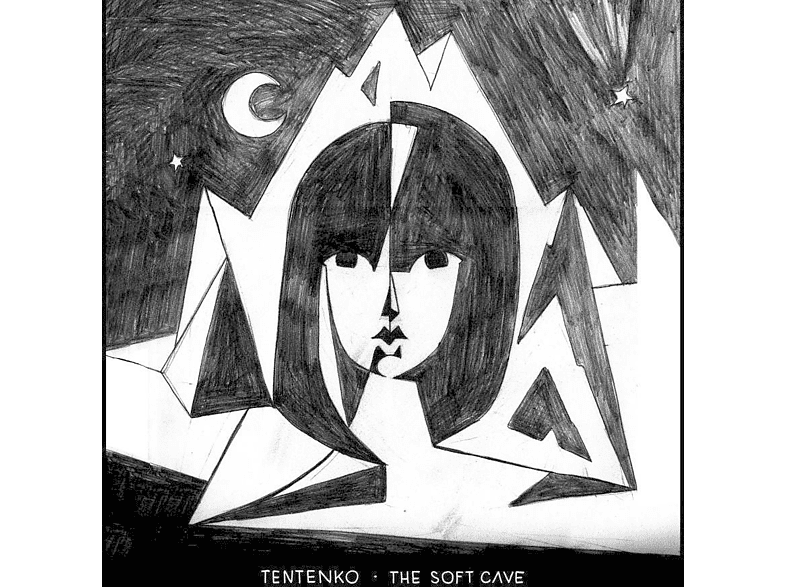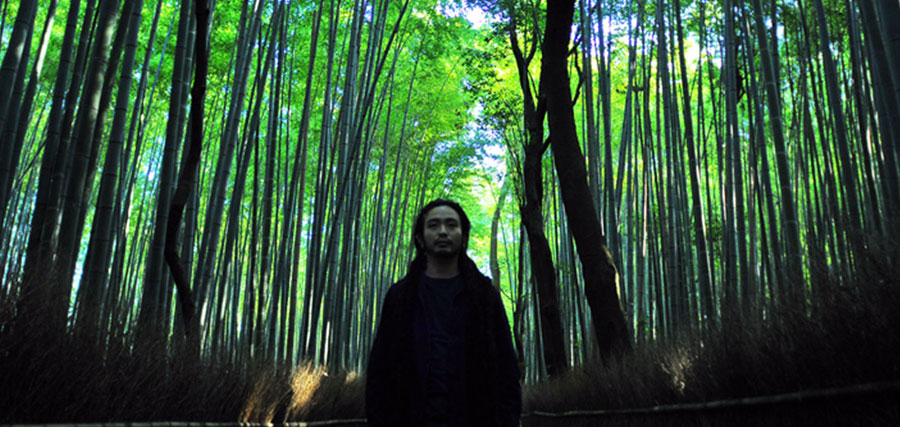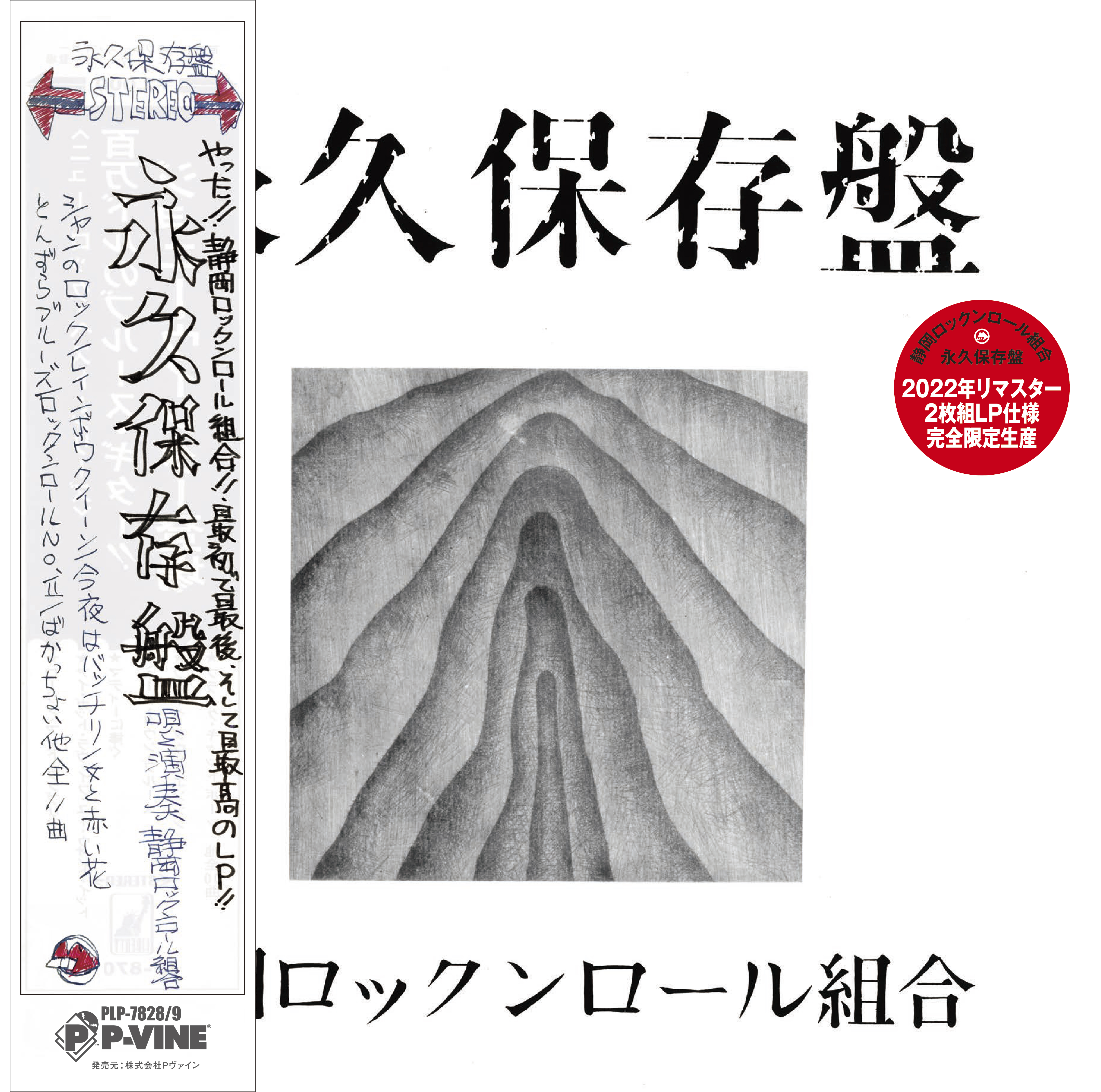つねに尖ったエレクトロニック・ミュージックを送り出しつづけてきたNYのレーベル〈12k〉が25周年を迎える。このアニヴァーサリーを祝しレーベル・ショウケースが開催、主宰のテイラー・デュプリーの来日公演が決定した。今年同レーベルより新作を出した Minamo & Asuna に加え、おなじく〈12k〉から作品を発表している Moskitoo も出演。11月13日(日)@SHIBAURA HOUSE、この貴重な機会を逃すなかれ。
12k主宰、テイラー・デュプリーの来日公演が決定。共演にMinamo &
Asuna、オープニングでMoskitooが出演。

ミニマル、エクスペリメンタル、アンビエント・ミュージックシーンにおける最重要レーベル12kを主宰し、坂本龍一氏とのコラボレーションでも知られるTaylor Deupree(テイラー・デュプリー)の5年振りの来日公演が決定。今年で25周年を迎える12kのアニバーサリーショウケースとして、6月に同レーベルより新作を発表したMinamo & Asunaが共演、 またオープニングアクトとしてMoskitooが出演します。会場はルーヴル美術館ランス別館や金沢21世紀美術館などの設計で知られる建築家、妹島和世氏が手掛けたガラス張りのコミュニティスペースSHIBAURA HOUSE。12kアーティスト3組による一夜限りのスペシャルなライブをお楽しみください。
12k 25th Anniversary - Taylor Deupree / Minamo & Asuna
イベントURL:ttp://12k25th.cubicmusic.com/
チケット予約:https://12k25th.peatix.com/

■日時:11月13日(日) OPEN 15:00 / START 15:30
■会場:SHIBAURA HOUSE 東京都港区芝浦3-15-4
(JR田町駅 芝浦口より徒歩7分、地下鉄都営三田線・浅草線 三田駅A4出口より徒歩10分)
■出演:
Taylor Deupree
Minano & Asuna
opening act:Moskitoo
■料金:前売 3,800円 / 当日4,500円
■チケット予約:https://12k25th.peatix.com/
※ 定員に達した場合は受付を終了いたします。
■音響:Flysound Co.
■運営協力・照明:小柳淳嗣(アリオト)
■宣伝美術:Moskitoo
■協力:p*dis、安永哲郎事務室
■主催:株式会社FUMUF
文化庁「ARTS for the future!2」補助対象事業
■ウェブサイト:https://12k25th.cubicmusic.com/

◆Taylor Deupree プロフィール
テイラー・デュプリー(1971年生)は米NY在住のサウンド・アーティスト、デザイナー、写真家。世界中のレーベルからコンスタントに作品を発表する傍ら1997年にはデジタルミニマリズムに焦点をあてた音楽レーベル〈12K〉を設立し、マイクロスコピックサウンドと呼ばれる電子音響シーンを築く。自身の音楽以外にも、他者とのコラボレーションも大切にしており、坂本龍一やデヴィッド・シルヴィアン、ステファン・マシューなど数々のアーティストと作品を制作。また、YCAMやICCなどの場所でサウンド・インスタレーションや数々の写真展も行っている。アコースティックな音源や最先端の技術を用いながらも、その作品の根底にあるものは自然の不完全さや、エラー、空間性の美学である。
◆Taylor Deupree サイト
https://www.taylordeupree.com/
◆12kレーベル サイト
https://www.12k.com/

◆Minamo プロフィール
1999年、杉本佳一と安永哲郎により結成。これまでに12KやRoom40など多数のレーベルからオリジナル・アルバムを発表するほか、TapeやLawrence Englishとのコラボレーション作品をリリースしてきた。東京を中心に20年に渡り活動を続けながら、アメリカやヨーロッパ、オーストラリアの各
都市でもツアーを行っている。2022年6月にAsunaとのコラボレーションアルバム「Minamo & Asuna - Tail of Diffraction」を発売。minamoとしての活動の他、杉本はFourColor、FilFla、Vegpherとしてソロ活動、劇判、広告音楽等を制作。安永は「安永哲郎事務室」として多方面の企画製作プロジェクトに参画している。
◆Minamo (杉本佳一)サイト
https://frolicfon.com/
◆Minamo(安永哲郎)サイト
https://www.jimushitsu.com/
◆Minamo & Asuna作品ページ
https://www.12k.com/releases/tail-of-diffraction/

◆Asuna プロフィール
石川県出身の日本の電子音楽家。語源から省みる事物の概念とその再考察を主題として「organ」の語源からその原義である「機関・器官」としてオルガンを省みた代表作『Each Organ』(2002)にてデビュー。近年は、干渉音の複雑な分布とモアレ共鳴に着目した作品『100 Keyboards』で、海外の国際芸術祭や現代音楽祭に多数出演、昨年も米ニューヨークの名門・BAM(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック)からの招待を受け単独公演を行う。並行した音楽制作では、10代の頃から東京の実験音楽/即興/音響シーンに関わり、様々なアコースティック楽器や大量のオモチャ楽器、PCベースによる作曲作品から即興演奏まで行いつつ、録音作品では毎回多岐に渡るコンセプトながらも一貫した作品制作を行う。これまで海外25カ国以上で演奏/展示、CDやレコードなどをリリース。
◆Asuna サイト
https://sites.google.com/site/aotoao3inch/

◆Moskitoo プロフィール
2007年ニューヨークのレーベル『12k』より『DRAPE』でソロデビュー。倍音のような広がりを持つ自身の歌声を基点に、様々なオブジェクトや楽器の音、電子音とを交錯させながら、幻想的でアブストラクトな独自のサウンドスケープを構築している。一音一音の音の探求に始まり、歌唱、トラックメイキング、アートワークまで全て彼女自身によって制作されている。作品は世界中から評判を集めこれまでにフランス、オランダなどのヨーロッパ、北米、オーストラリア、デンマーク、韓国のイベントに招待され、各地で海外ツアーや公演を重ねている。最新作はデジタルシングル『nunc』、minamoとの12インチLP、minamo & moskitoo『superstition』。
◆Moskitoo サイト
https://moskitoo.com/