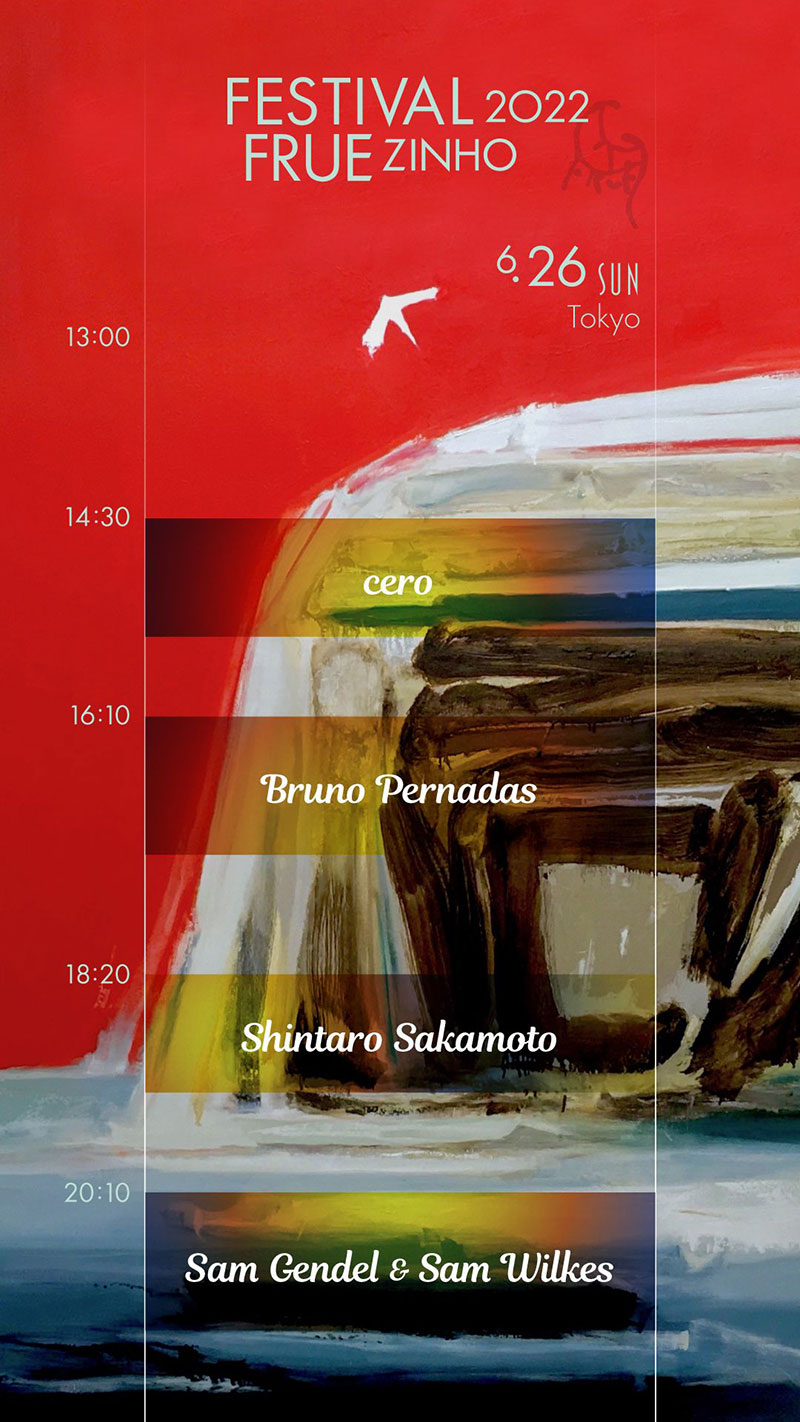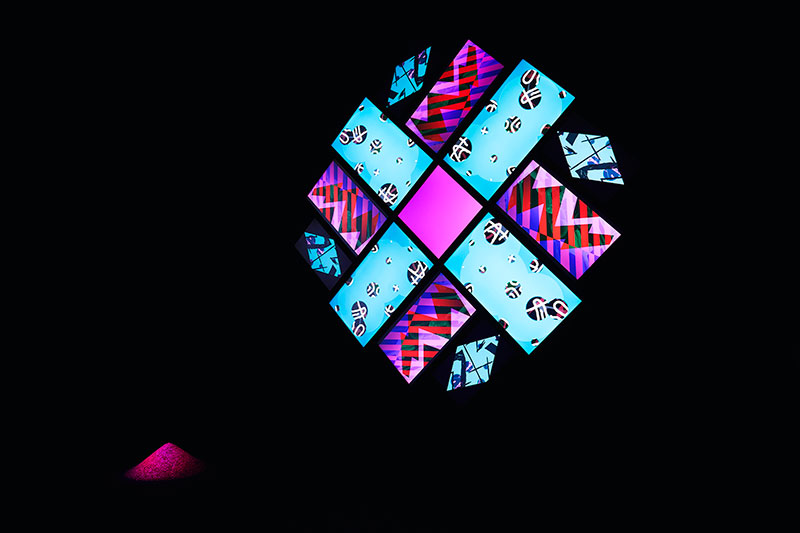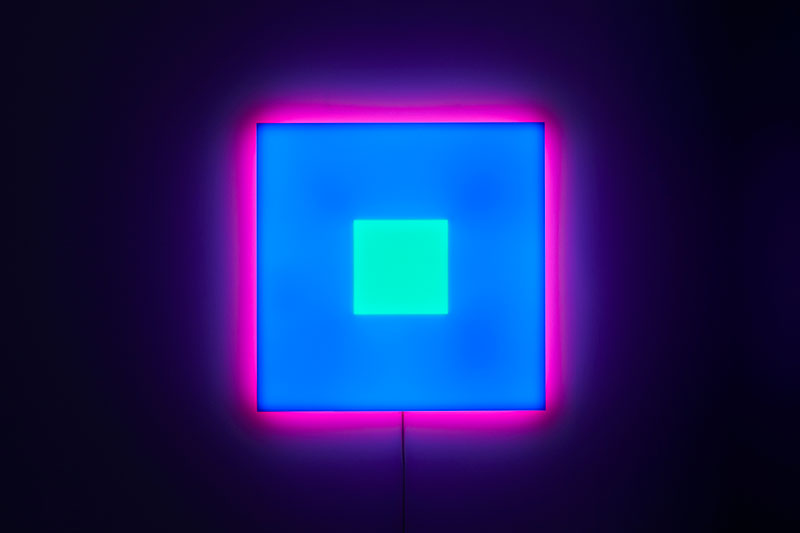パンデミックの影響もあってか昨今はひとつの街に属さず離れて暮らすバンドも増えてきた。だがスーパーオーガニズムのように国境をも超えているバンドは多くはない。そもそもスーパーオーガニズムはそれ以前の世界から、それ以後の世界で当たり前になったような感覚を持って活動していたのだ。ロンドンに暮らすイギリス人のハリー、ニュージーランド出身のトゥーカン、ビー、オーストラリアに住む韓国人ソウル、日本人のオロノ、多国籍なスーパーオーガニズムにどこの国、あるいはどこの街のバンドなのかと尋ねたら果たしてどんな答えが返ってきたのだろう? 答えなんてなくとももうこの状態が物語っている。スーパーオーガニズムはどこからでもアクセス可能な世界の中に存在していて、その場所は手紙を送ろうなんて考えが浮かばないくらいに近くにある。そんな古くてありふれたインターネットの幻想がもう当たり前のものとしてここに存在している。2017年に “Something For Your M.I.N.D.” をひっさげて登場しインターネットの寵児として受け入れられた 1st アルバムからさらに進んでスーパーオーガニズムは気負うことなく拡張したその世界を見せつける。
『World Wide Pop』と名付けられた 2nd アルバムは日本の星野源、CHAI、フランスのSSW ピ・ジャ・マ、イングランド・レッドカー出身のラッパー、ディラン・カートリッジ、アメリカ・ポートランドに暮らすペイヴメントのスティーヴン・マルクマス、世界各国数多くのコラボレーターが参加しながらもそこに強い光が当たるようなことはなく、まるで皆がその場所にいるのが当たり前だというように溶け込んでいてなめらかだ。前作の延長線上にあるような “It’s Raining feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge” の憂いを帯びたカラフルなサウンドの上でラップするディラン・カートリッジ、スティーヴン・マルクマスはいつもと少し違った表情を見せて、その間にいるオロノは自然と世界を繋ぎ合わせる。何かの映画に使われるはずだったという “Flying” は遊び心と少しのいら立ちを併せ持った最高のインディ・ポップで(途中でニュー・オーダーの影さえ見える)アコースティック・ギターの音が鳴り響く “crushed.zip” はSSWが作った孤独な原曲を切り裂いてリミックスしたかのような不思議な感触でそれでいてこのアルバムの世界に見事に馴染んでいる。スーパーオーガニズムの持つこの感覚はベッドルームの扉を開けてそのまま世界を拡大したかのようで(それは音楽以外のものに対してもそうなのだろう。“Teenager” のビデオを思い浮かべて欲しい。上下左右、二次元方向にも三次元方向にも、興味は広がり拡大していく)、境界線が消えたみたいに薄くなりジャンルの枠はぼやけ、ついにはメインストリームとアンダーグラウンドの境目さえも見えなくなる。自由で複雑で繁雑、そんな状態になっているのがいまのスーパーオーガニズムの魅力だろう。世界はひとつだけで完結したりはしない、意識することのない当たり前の『World Wide Pop』がそこにあるのだ。
複数の世界が繋がって世界が作られ拡張していく、スーパーオーガニズムのオロノとハリー、ふたりの話を聞いて頭に浮かんだのはそんな言葉だ。実際に触れあえるようなオンラインと仮想世界を通過したような現実、ひょっとしたら次の世界とはいつの間にかそこに存在しているものなのかもしれない。
Teenager
僕たちはふたりとも複合的な分野のアーティストだってところが似ていると思うんだ。音楽はコアとしてあるけど、オロノはアルバムのアートワークを手がけたりもするわけだし、ビデオをみんなで一緒に作ったりもする。(ハリー)
■スーパーオーガニズムとして日本に来るのはどれくらいぶりになりますか?
ハリー:2019年の1月以来かな? たぶん、それくらいぶりだと思う。
■フジロックの後にあった来日公演ぶりですか?
オロノ:そうですね。来日公演ぶりだから2019年以来です。
■じゃあ3年ぶりくらいなんですね。いまはひとつの国じゃなくてメンバーがそれぞれバラバラに住んでいる感じなんですか?
ハリー:前はみんなで同じ場所に住んでいたときもあったんだけど……、1st アルバムを作り終わったくらいの時期にみんなで同じ家に引っ越して。でもなんていうか「トゥーマッチ」だったんだよね。だから4年くらい前かな? それでみんなバラバラに住むようになって。いまはソウルはオーストラリア、オロノは日本、残りのメンバーはロンドンに住んでる感じかな。
■そうなんですね。でもそれだとメンバー同士でいまどんなモードになっているとかどんなものに興味を持っているとか把握しにくかったりしませんか?
ハリー:そうだね。そういうある種の難しさはあるよ。
オロノ:でももうその段階は通り過ぎたって感じする。
ハリー:そうだね、うん。僕らはもうお互いのことはだいたいわかっているから「いまのモード」はどんななのかっていうのは把握しやすいのかもね。ズームとかでも「いま何に興味を持ってる?」とかよく話すし。もちろん同じ家に住んでたときほどではないんだけど。でもだいたいのことはわかるよ。何かやるときにコンセプトとか素材とかそういうのを話すんだけど、その過程でもみんなが何に興味を持っているのかわかるから。
■そんな感じなんですね。
ハリー:うん。たとえば、ミュージック・ビデオを作るときなんかがそうなんだけど。いまたくさんビデオを作っててさ、二週間くらい前にも新しいビデオに取り掛かったところで、電話で何に影響を受けただとかどう思ったとかたくさん話して。オロノが影響を受けた本の一節から組み立てたりもして。だから、僕たちはいろんなことを共有してアイデアや影響についてお互いに理解できるまでトコトン話すって感じなんだ。
 今回取材に応じてくれたハリー(左)とオロノ(右)
今回取材に応じてくれたハリー(左)とオロノ(右)
■ミュージック・ビデオの話が出たのでここでビデオの話を聞かせていただきたいです。今回は全てのビデオを同じ人が監督しているせいか一貫した雰囲気を感じて、ひょっとしたらアルバムの一部として制作したのかなとも思ったのですが、今回のビデオはどんな風に作られたのですか?
オロノ:そんな風に感じるのはそれが最初に出てきたコア・アイデアだったからかもしれないですね。言ってくれたみたいにビデオをアルバムの一部として作ったってのもあるし。あとはもちろんビデオとしても美しくなるようにって感じに。ダンは私たちのヴァイヴをよくわかってるし、凄くいい感じにリメッシュしてくれて。たぶんあの人こっちの望んでるもの完全にわかってんじゃないかな。私たちにはアイデアはあってもビデオを作る技術はないから。
ハリー:まぁだよね(笑)。
オロノ:うん。だから彼はプロセスの中で重要な役目を担っている。にしてもヴァイヴを理解してくれて細かいディテールを説明しなくていい人を見つけられたっていうのは超良かった。
ハリー:めっちゃ直感的だったよね。なんていうかな、普段は僕たちふたりでアイデア出し合ってときどき他のバンド・メンバーもって感じなんだけど、ビデオの全体のストーリーを描いて、参考になるいろんな写真を組み合わせたりして、ちょっとしたトリートメント・ドキュメントを作るんだ。で、それを今回彼がまとめあげてくれたっていう。だからそれで連続性とか近似性を持ったんじゃないかな。僕たちから生まれた最初のアイデアから全部ドライヴしていって、それを彼が上手く解釈というか翻訳するみたいな形で具現化してくれたわけだから。
■今回はアニメーションが効果的に使われていたと思うんですけど、アニメに関してはどうですか?
ハリー:もちろんアニメは大好きなんだけど、現実的な問題として僕たちはいま同じ場所に住んでいなくて、どこかひとつの場所に集まってビデオを撮影するってことができないっていうのもあったかな。アニメだとみんな一緒にスタジオにいる必要もないし、僕たちが持ってたアイデアも実現しやすかったっていうのがまずあって。で、もうひとつの理由として、伝えたいストーリーをスタジオ撮影の限定的なショットだけで表現したくなかったっていうのもあった。だから自然とアニメを中心に作ろうって方に傾いていったんだ。たとえば “crushed.zip” のビデオは単細胞のアメーバが恋に落ちるってストーリーなんだけど、単なるミュージック・ビデオじゃなくて、ショート・フィルムみたいな感じにしてこの小さなストーリーを伝えたいってアイデアで……。なんていうかさピクサーの映画の前にはいつも短いアニメがあるよね、あれってある種の良さがあって心に残るから、そういう感じにできないかなって考えたんだ。
crushed.zip
 photo: Jack Bridgland
photo: Jack Bridgland
友だちに声をかけて「うん、出たい!」ってなって実際に出てもらったみたいな感じなんで。だからメジャーのアーティストの後にインディの曲がかかるみたいっていうのは特に意識してなかったですね。(オロノ)
■それで思ったのですが、将来的にもうちょっと長めの20分くらいの、音楽と映像を組み合わせた映像作品を作ってみようみたいなアイデアはあったりしませんか?
オロノ:それはマジでいいかも。
ハリー:それアリだね。うん、興味ある。
オロノ:どこかのタイミングでアニメと音楽を組み合わせられたら最高だなって思うんですけど、でもいますぐできるっていうのはなんだろ? ツアー・ドキュメンタリーとかかな。今年の後半にツアーあるし、そっちの方をいまはやりたいかも。
ハリー:僕はそうだな、長いのを作るとなると……僕はSF好きなんだけど、読むのもそうだしSF的なやつを考えるのも好きって感じで。で、そうだな将来的にやるっていうんならそういうSFっぽいやつに関わりたい。ショート・フィルムを作るのもそうだし設定を考えたりするのも凄くやってみたい。実際に “On and On” のビデオのアイデアはSF的なものに触発されて出てきたものなんだけど、予算があればまたそういうビデオが作れるし、そういうのを突き詰めていくのは楽しいって思うんだ。映画を作るだけの予算はないけど、クールなコンセプトとかクールなストーリーを追求していくことはできるから。僕たちはそういうタイプだしさ。うん、だからマジでそうだな。いろんなメディアの可能性はほんと追求していきたい。
オロノ:ビヨンセみたいな感じで映画をプロデュースしたりもしたい。
ハリー:うん。いいね。僕たち(オロノとハリー)はふたりとも複合的な分野のアーティストだってところが似ていると思うんだ。いま言ったみたいな感じのいろんなものに興味がある。音楽は僕たちのコアとしてあるけど、オロノはアルバムのアートワークを手がけたりもするわけだし、ビデオをみんなで一緒に作ったりもする。音楽を作ることはずっとやっていくけど他のことにも同じくらい興味があって、その探究はずっと続けていきたいな。
On & On
(ペイヴメントの曲を)聞いたスティーヴン・マルクマスはそれを最初ローリング・ストーンズの曲だと思ったとかそんな話で。アルゴリズムがその音をクラシック・ロックのサウンドだって認識して~みたいな感じのやつ。〔……〕それって僕たちみたいなバンドにとってちょっと面白いなって。(ハリー)
■音楽がコアとしてあってってそのイメージ凄くわかります。スーパーオーガニズムはベースがあってそこに興味がくっついてどんどん広がっていくみたいなそんなイメージがあったんですけどまさにでした。それは今回のコラボレーターの名前を見てもそうで。国もジャンルもバラバラで垣根がなくて、フラットに好きだという気持ちでみんな繋がっているみたいな。インターネット時代的というか、インディもメインストリームの音楽も次に再生される曲として同じ様に並んでいる曲でしかないというサブスク時代的な感覚というか。スーパーオーガニズムのそういう部分に自由さを感じていて。その辺りの話をもう少し詳しく聞いてみたいです。
オロノ:言ってくれた通りにめちゃくちゃフリーフォームですね。友だちに声をかけて「うん、出たい!」ってなって実際に出てもらったみたいな感じなんで。だからメジャーのアーティストの後にインディの曲がかかるみたいっていうのは特に意識してなかったですね。それはでも、私たちがその両方の音楽が好きで、どっちにも友だちがいてっていうのを表しているんじゃないかって気がします。友だちはいろんなところにいるし、音楽業界のいろんな場所にもいる、それこそ垣根がなくて……。
ハリー:うん。僕たちはそんなバンドと一緒にやることで違う世界に足を踏み入れているんだ。自分たちをインディのバンドだって特に意識をしているってわけでもないんだけど……
オロノ:あとメインストリームのバンドともね!
ハリー:そうそう。メインストリームのバンドでもない。僕らが目指しているのはポップ・ミュージックを作るってことだけで、でもまぁ自分たちのやりたいようにやっているだけだからちょっとヘンな感じになっちゃってるとも思うけど。でも違くて、インディとメインストリーム、どっちかになろうっていうんじゃなくて、ただ自分たちにとって馴染むっていうか自然な形でこうなっているって感じかな。で、それが僕らの好きなインディ・アーティストのテイストにフィットするんだ、荒削りでヘンテコでエッジが立ってる大好きなやつに。で、同時に即効性があってポップでキャッチーって感じなのも好きなわけで。だから、それこそまさに僕らのやっていることだって感じがするよ。そんなわけだから違う世界のアーティストと一緒にやるのは理にかなっているとも思う。それに「そもそも自分たちは何なのか?」っていうところに立ち返る良い機会にもなっているんじゃないかって思うんだ。
■そういう垣根がないという意味で、アルバム・タイトルの『World Wide Pop』はスーパーオーガニズムの音楽性を表していてぴったりだなって感じました。これはある程度狙ってつけたところがあったんですか? それとも偶然にこうなったみたいな?
オロノ:(日本語で)何も狙ってないですよ。
ハリー:そうじゃないけど、でも面白い話でもあるよね。意図的に狙った場合とそうじゃなくて無意識的にやった結果が不思議と同じになるっていうのは。僕は意図的にやっているって思ってたけどでも実は事故だったってそういう話をよくしちゃうんだけど、でも何かを作っているときっていうのは必ずしも何かを意識してやっているわけじゃないと思うんだ。ただその瞬間にひらめいたものにしたがって突き動かされて作っているだけでさ。で、後から自分が作ったものを振り返ってみたときにそこにあるものの意味が全部見えたりして「マジかよ……俺のやりたかったこと実現してんじゃんとか。言いたかったのはマジでこれだよな」みたいな。
それで、アルバム・タイトルだけど、最初はただタイトルが必要だったってことだけだったんだ、おかしな話だけど。で、この曲の名前は、アルバムのタイトルとして理にかなってるし合うんじゃないかってそんな感じでつけたんだよ。衝動的にこれがいいなって感じたからで、特に理由はなく創造性にまかせてつけたって感じで。でもいまこうやって振り返ってみると君の言っていることもよくわかるよ。確かに集約されているかも。テーマもそうだし作り方にゲスト参加している人を見てもそうだしさ。でもアルバム・タイトルを決めたときは全然意識していなかったっていうのもまたポイントだと思うんだ。そのときはそういうのは頭になかった。
オロノ:酷いタイトル案いっぱいあったから。
ハリー:うん、マジで。
オロノ:ほんとヒドいやつ。
ハリー:まったくもってそう。
■でも、ここまでのお話を聞いていても『World Wide Pop』ってタイトルなのはしっくり来るというか、本当ぴったりなタイトルだと思います。
オロノ&ハリー:(日本語で)ありがとうございます。

毎日、家で絵を描いてるみたいな感じで。それってチルで、それだけでも全然良くて。でも YouTube とかそういうのでバンドがプレイしてるのをたまに気が向いたときに見てたりもして。だからいろいろ入り交じったミックス・フィーリング。(オロノ)
■最近は音楽のジャンルがますます混ざり合って複数の要素があるものも当たり前のようにあって、それこそスーパーオーガニズムみたいに「これはなんだろう?」ってなる音楽が増えてきていて、カテゴライズがどんどん難しくなっている気がしています。その一方でSNS映えするというか、「この音楽はこうだ」と限られた一言で言い切るようなこともより求められていて、ちょっと変な状況にもなっていると思うんですけど、そんな中で「スーパーオーガニズムの音楽はポップ・ミュージック」だっていうのは凄く納得がいきました。
ハリー:うん、ちょっとおかしな状況になっているよね。少し前にペイヴメントの曲が Spotify によって発掘されたって記事を読んだんだ。凄い再生されたんだけど、でもその曲は昔の B-Side の曲で、お店か何かで聞いたスティーヴン・マルクマスはそれを最初ローリング・ストーンズの曲だと思ったとかそんな話で。アルゴリズムがその音をクラシック・ロックのサウンドだって認識して~みたいな感じのやつ。で、ストーンズの曲を聞いてその後にランダム再生でペイヴメントの曲がかかるんだ。それって僕たちみたいなバンドにとってちょっと面白いなって。僕はスーパーオーガニズムはどんな感じのプレイリストにもちょっとフィットしないなって思ってて。それはできる限りユニークな音楽をやろうと思っているからなんだけど。で、その音楽はインディ・ロックと言っていいのか、まぁロックじゃなくても全然いいんだけど。インディ・ロックとかエレクトリック・ミュージックとか、エレクトリックって言うにはちょっとラフ過ぎるか。まぁそんな感じで考えていくと、自分たちはカルチャー的にどの箱にもフィットしない、奇妙な場所に行き着くことになるんじゃないかって、そんな風に僕は考えているんだ。アメリカ・ツアーに行ったときなんか実際にそんな感じだったし。アメリカのロック・ミュージックがかかるラジオ局で僕らの曲もかかって、僕らの曲はこのラインナップの中でもOKなくらいロックなんだって思ったんだけど、でも僕たちは伝統的な意味でのロック・バンドじゃないからその中で落ち着かないというか居場所がなかったんだよね。いろんな場所に溶け込めるけど、どの場所にもフィットしないみたいな、そんな変なバンドだったんだよ。
オロノ:それってほんといつも感じてることだよね。
ハリー:うん。マジで。本当にそうなんだよ。
It's Raining
■ライヴの話もお伺いしたいのですが、最近ライヴってやってます?
オロノ:全然やってないです。
■最後にライヴをやったのはいつ以来になるんですか?
オロノ:2019年の夏の終わり頃だったかな。
ハリー:うんそうだね。2019年9月のジャカルタ公演が最後だったはず。
■かなり間が空いているんですね。その間にライヴに関して何か考え方が変わったみたいなところはありますか?
オロノ:ときどき他のミュージシャンの人と話すんですけど、パンデミックとかそれに関して、早くライヴやりたいねとか。でも私は、全然待ちます、むしろもっと待ってたいですみたいな感じで。
ハリー:うん。
オロノ:毎日、家で絵を描いてるみたいな感じで。それってチルで、それだけでも全然良くて。でも YouTube とかそういうのでバンドがプレイしてるのをたまに気が向いたときに見てたりもして。だからいろいろ入り交じったミックス・フィーリングなんですけど。でも実際に、こないだの夜、ハリーと一緒に父親の部屋に行って、自分たちが出たフジロックの映像とか日本でやった他のライヴの映像とかを見たりして、なんか凄く変な感じになって。そのときからほんとに時間が経ったんだなって。
ハリー:そういう部分に関していうと、僕にとってライヴでプレイするのは好きだってことだな。観客の前に立ってもう一回プレイできると思うと本当興奮するし、新しい曲に対してみんながどんな反応を見せてくれるのかって思うと楽しみで仕方がない。でもさ、それとは別にツアーっていうか旅行に関してストレスを感じるわずらわしさみたいなものもあるんだよ。家から離れてる期間がずっと続くのはストレスで。だからその部分に関してはどうしてもナーヴァスになっちゃうな。だけどステージに立つってことに関しては楽しみで仕方がないっていうのも本当だよ。だから、うん、これもミックス・フィーリングだな、こんなに長い時間が経ったんだから。本当変な感じだよ。前みたいなリズムに戻ってどうなるかっていうのはさ。
■今度のフジロックは本当に久しぶりにやるライヴってことになるんですね。
ハリー:そうだね。フジロックの前にUKのレコードストアを回るアコースティックのインストア・イベントはあるんだけど、フルでやるっていうのはフジロックが最初だよ。だからフジロックは今回のアルバム・サイクルの中で最初のショーってことになると思うんだ。ジャカルタ以来の最初のフル・ショー。復帰戦として最初にやるショーとしては大きすぎるってくらい大きい舞台だからうまくできるかやっぱり緊張はするんだけど、でもどうなるか凄く楽しみだよ!
Into The Sun