 Wedding Mistakes Virgin Road |
音楽をやることがけっしてイケてることにはならない時代に、それはむしろ本来的な自由さを取り戻しているともいえるかもしれない。格好よかろうが悪かろうが、カネになろうがなるまいが、やりたいからやるというあり方がデフォルトになった世界のほうが、音楽に多様性を生むという意味ではすぐれている。音楽不況というが、それは旧来的な産業システムにおける話であって、いまインディの層はかつてなく豊かだと言うこともできる。
音楽の自由さを広げている要素はそればかりではない。情報環境の変化もある。ここに登場するような彼らにとって、そもそもアルバムをつくるということは盤をプレスすることではなくなっている。いまとなっては目新しいことではないが、彼らが「ファーストが出て……」などと語るときの「出る」というのは、ネット上にまとまった音源がアップされるというだけのことだ。それが「ジャケ」を持ったアルバム作品として当然のように認識されるようになったのが2000年代なかば、いわゆる「ネットレーベル」の流行以降。なんら資本の影響を受けることなく、かつレーベルというかたちを通してキュレーションされることで、シーンをもつくり得る力を持った作品たちが山のように登場し、主役になる時代の幕開けである。そして、それこそがThe Wedding Mistakesたちが生まれてきた場所でもある。MiiiとLASTorder、それぞれ独立してキャリアを持つふたりのプロデューサーによって結成されたこのユニットの背景には、ネットレーベルの風雲児たる〈Maltine Records(マルチネ・レコーズ)〉などの存在がある。同レーベルの古参であるMiiiはもちろんだが、今作のアートワークを手掛けたおじぎちゃん(セーラーかんな子とのDJユニット、ぇゎモゐとしても活動)を彼らに結びつけたのも〈マルチネ〉のtomadだという。そして、すこし離れたシーンで活動しながらも、それらに寄せるシンパシーはLASTorderも変わらない。社会全体としていい時代かどうか知らないけれど、世知辛くはあっても音楽的には二重に自由な環境を彼らはのびのびと泳いでまわっている。
配信のみで昨年発表されたThe Wedding Mistakesのアルバム『Virgin Road』がフィジカル・リリースされた。そう、商業性のあるステージやフィジカルが流通する場所との行き来も自由である。インタヴュー中、ふたりの口から洩れた「逆にっていうのが嫌い」という考え方が印象的だった。過剰な情報空間において、メタなふるまいによってではなくまっすぐに喜びを得たいという気持ちには、切実に共感を抱く。ポスト・インターネットの感性だからこそつかめる純真さが、そこには顔をのぞかせている。Miiiのギークなブレイクコア、LASTorderの正統派にして抒情系の「ニカ」、音楽的にはさまざまな対照を持っているが、彼らはそうした地平に生まれたドリーミーなミュータントとして、ミューテイトするウエディングとして、明るい音響を築き上げている。
インタヴューのラストでティーザー音源をお聴きいただけます
■The Wedding Mistakes / ウエディング・ミステイクス
MiiiとLASTorderにより2013年に結成されたユニット。2014年11月にリリースされたデビュー作「Midnight Searchlight EP」はiTuensエレクトロニックチャート1位を記録。2015年2月にファースト・アルバム『Virgin Road』をリリース。
https://theweddingmistakes.com/virginroad/
LASTorder
2013年に発表したファースト・アルバム『Bliss in the loss』はタワーレコードでも大きく展開されロングセラーを記録。今年の7月には〈PROGRESSIVE FOrM〉よりセカンド・アルバム『Allure』をリリース。数々のリミックス制作も行う。
Miii
10代から楽曲制作を行い、〈Maltine Records〉の古参としてイベントには毎回出演、2枚のソロ作品を残す。日本屈指のハードコア/ベースミュージック・レーベル〈Murder Channel〉からファースト・アルバムを6月にリリース。東京女子流、夢見ねむ(でんぱ組inc.)等の公式リミックスも手がける。
中学生くらいのときは、ちょうどミクシィとかが出はじめたときだったんですよ。ミクシィはミクシィ・レヴューっていうのがあって。(Miii)
■(『ele-king vol.15』を差し出しながら)お若いおふたりですが、紙の音楽雑誌を読んでいた記憶とかってあったりするんですか?
Miii(以下、M):『DTMマガジン』を買って読むくらいですね。
■おお、本当に実用的な読み方というか。
M:そうですね。音楽専門誌みたいなものを読んでいなくて。
■LASTorderさんはどうですか?
LASTorder(以下、L):『サンレコ(サウンド&レコーディング・マガジン)』。
■やっぱりおふたりとも機材よりなんですね(笑)。
M:機材を眺めて、「コレめっちゃほしい!」みたいなことを、ずっとやっていましたね。
■ははは、いまは「今月このアルバムを聴かなきゃ」ってことを紙で確認するような感じはないですかねー。
M:でも、ディスク・レヴューのコーナーがいちばん好きなんですよね。
■なるほど、それはわかりますね。興味はどっちかというと邦楽よりでした? 洋楽よりでした? ……まあ、そういうふうに括ることの是非はおいといて。
L:俺は邦楽よりだったかな。
M:中学生くらいのときは、ちょうどミクシィとかが出はじめたときだったんですよ。ミクシィはミクシィ・レヴューっていうのがあって、そういうのを見るのが好きでした。
■それはアマゾン・レヴューみたいなものの黎明にあたるようなものですかね?
M:そうですね。新譜情報もインターネットで探していました。
■あー。やっぱりそこは隔世の感が(笑)。だから、隣は何を聴く人ぞってね、「今月聴くべきアルバム」というような認識を、みんなで共有してるわけじゃないですよね。「今月はレディオヘッドの新譜がある」とか(笑)。
M:じゃないですね。
■なるほど。それでは雑談はこのあたりにしまして。おふたりはそれぞれソロ活動がスタートなわけですけれども、そもそも畑違いなアーティストであるという印象があるんですよね。The Wedding Mistakesって名義は、「ふたりのウェディングがミステイクだ」というような意図があるとか?
M:名前は雰囲気というか語感でつけたものなんですが、最終的にそういうものだったのかと思わなくもないですね。ふたりでやろうとなったのも、そもそもは僕がLASTorderに声をかけたんですけど、かたやネット・レーベル、かたやCDをリリースしているという、ぜんぜんちがうところにいたので。
L:あとジャンル的にも。
M:そうそう。だからそこをくっつけたらおもしろいなというのはありましたね。
かたやネット・レーベル、かたやCDをリリースしているという、ぜんぜん違うところにいたので。(Miii)
■「異なったものの出会い」という認識はあったわけですね。LASTorderさんはどうでしょう?
L:エレクトロニカで同い年くらいのトラックメイカーって俺のまわりにすくないので、ネット・レーベル周辺には若いひとが多いから、友だちになってみようという感じで。ツイッターで近づいたりとかイヴェントに行っていたりしていたら、「いっしょに作ろう」って急に言われた感じですかね。
■なるほど。それぞれのジャンルに固有の文法があると思うんですけど、おふたりは互いにそれほど共有してはいないと思うんですよね。それで、自然と制作上の役割もちがってくるような気がするんですが、ふたりの役割分担というと、LASTorderさんがウワモノ、Miiiさんがリズムみたいにすごくザックリで考えていいんですかね?
M:まさにその通りですかね。
■お互いの役割について、何か話し合いみたいなものはあったんですか?
M:デモが送られてきて、それに展開をつけたり、ドラムをこっちで足したり変えたりして返して、それにまたレスポンスがくるみたいな形もある。初めから上とビート、つまり僕がビートを送って、それにメロディを付けて戻してくるみたいなパターンもありますね。最初はデモがあって、ふたりでそれを伸ばしていくことがメインでした。
■それぞれに対して期待した役があると思うんですが。
M:僕は綺麗だけれど割れている……エレクトロニカというか、ノイズよりの音楽がすごく好きでした。それを自分でやるには限界があったので、LASTorderに打ち込みとかウワモノとかで耽美な雰囲気を出してもらって、そこに僕が壊れたビートをのっけたいという願望がありました。それから、LASTorderはちゃんとメロディが書けるひとなので、そういうところも求めていますね。
■メロディね! 特徴ですよね。あと、“ハー・ミステイクス(Her Mistakes)”とかではヴォイス・サンプルがフィーチャーされているじゃないですか? ああいうのってLASTorderさんなんですか?
L:そうですね。
とにかくメロディを作るのが好きなので、メロディをのせることは、毎回、無意識的にしちゃっていますね。(LASTorder)
■へえー。HMVさんの無人島に持っていく俺の10枚、みたいな企画(無人島 ~俺の10枚~)を覚えていらっしゃいます? おふたりがそれぞれアルバムを挙げていらっしゃいますよね。あれをちらっと拝見しまして。LASTorderさんご自身の曲は、全体としてはエレクトロ・アコースティック志向というか。
L:はい、そうですね。
■で、この無人島リストを見ますと、ジュディ・シル(Judee Sill)からはじまって、ベン・フォールズ(Ben Folds)からモリコーネ(Ennio Morricone)、Shing02さんにテリー・ライリー(Terry Riley)まで入っていますね。まずポップ職人的なものに惹かれてるんだなって思ったんですよ。そしてそういうものを志向しつつもミニマルなものに引き裂かれるという。
L:その通りです。全部言われちゃいました(笑)。
■ハハハハ。そのポップ職人というところをもうちょっと訊きたいんですけれども。さっきの、メロディが強いという話とも重なってくると思います。目指しているようなアーティスト像もそのへんに?
L:目指しているアーティスト像はぼんやりしていますが、とにかくメロディを作るのが好きなので、メロディをのせることは、毎回、無意識的にしちゃっていますね。
■無意識的な感覚なんですか?
M:それ、わかる。彼からは、どんな曲にも何かしら主旋律っぽいのがついて返ってくるんですよね。
■なるほど。ポップ・ソングってフォームを、コンポーザーとして作っていきたいという意識なんですか?
L:たぶんそうだと思います。
■そうすると、エレクトロニカという流れのなかだと、また少し変わっているというか。
L:エレクトロニカと言わせていただいているんですけど、そこまでエレクトロニカをやっていることでもないっていうか。
■そういう感じもしますけどね。コキユ(cokiyu)さんとも親和性があるのがわかりますし、活動されている領域もそういうところなんだなっていう。ところで、ジュディ・シルなんて本当に深くて知性的な声だったりしますけど、ここでの“ハー・ミステイクス”のヴォーカル・トラックって、ある意味その真逆みたいな、薄さを持った音だと思うんですね。そういう声や音に対する憧れはあるんですか? ジュディ・シルが好きなら本来逆なような気もしますけど。
L:憧れはたしかにあるんですよね……そういう薄い感じには。でもそういうやり方や、ピッチを上げて散らす感じの音は、やり飽きているというか。ちゃんとした声を入れたいと思っていたりはするんですよ。
■へぇー!
L:けっこう手持ちのものがないというか、機材とかが少なかったりとかしてなかなかできないんですけど……。自分で声をかけて誰かの歌を録るということもあまりないですし。
■肉声ヴォーカルへの、一種のアンチというわけではなく?
L:そうなんです。アンチとかではないですね。
■なるほど、正直でいらっしゃいますね。では、ボカロとかはどうですか?
L:ボカロとかは通らなかったんですけど、もし出会っていたらいまごろはバリバリPな感じになってたかもしれない(笑)。最近はそんな気もしてきた。でも偶然、ぜんぜん聴かなかっただけっていう。
■ははは、素通りしちゃったわけですね。
ボカロとかは通らなかったんですけど、もし出会っていたらいまごろはバリバリPな感じになってたかもしれない(笑)。(LASTorder)
L:どこかで避けていたのかもしれないですけど。
M:僕もボカロはぜんぜん通ってないんですよ。やっぱり、意外と流行っているといえば流行っているけれど、触れないでいいといえば触れないでいいというか。聴かなくても意外となんとかなるという感じですね。
■すごくフラットに考えてみれば、ボーカロイドっていうのはただの音声ソフトというか、シンセサイザーなわけじゃないですか? しかもけっこう魅力的で使いやすい。でも、それを通らないっていうときには、暗にその奥にある何かを否定しているんじゃないですか?
M:ニコニコ動画のボカロPのカルチャーとして、ということですよね、たとえば。
■そうそう(笑)、ちょっと意地悪な質問ですみません。一概には括れませんけれども、彼ら「P」のようなプロデューサーの音やあり方に対するおふたりの感想や評価がどんなものなのか、すごく興味があります。どうでしょう?
僕はもともと音ゲーとかから入って、なんだかんだでネット・レーベルにたどり着いたんですよ。(Miii)
M:いろいろありますけど、僕のイメージ的には、RPGとかで別の大陸に行くともっと強いモンスターがいるという感じですかね。物語を進めて行くと強いモンスターが出てくるという感じ……同人とかボカロの界隈ってそういうイメージがあります。僕はもともと音ゲーとかから入って、なんだかんだでネット・レーベルにたどり着いたんですよ。それぞれが別の島だけど、それぞれに大ボスというか、めちゃくちゃ強い、上手いひとがいて。で、その奥にも上手いひとがたくさんいる。 だけど、自分がそこまでたどり着くために経験値が足りないし、パワーもないという自覚もあって。避けているというとあれなんですけど、あまり交わらないようにしています。だからアーティストとして尊敬しているひとはいます。同年代にかめりあって子がいるんですけど、彼は同人とかボカロとかの流れのひとで、メロディも作れるし、過激でとんがっているもの作れるみたいな。そういう人材が、あっちにはいっぱいいるんですよ。そういうのは向こうのカルチャーにいないと得られないのかな、というのはあります。
■なるほどなあ、“あっち”は分母がでかいし、エネルギーもあると。あと、音っていうよりも歌詞だったりイラストだったりも重要だし、それがいわゆる集合知ってやつでできあがるという、時代性としての鋭さもありますよね。LASTorderさんは、あちらの界隈を音楽というよりもカルチャーとして見ている感じですか? L:僕はそっちの界隈とも繋がりがなくはなくて、初音ミクのリミックスをやってみたりもするんですけど、みんなやっぱり……、言っていいのかわからないけれど……
■言うだけいっときましょう。
L:お手軽に曲がひとつできるじゃないですか? 歌があって歌詞があってって。だからもっと手間をかければよくなるものがいっぱいあると思います。サウンド面ですぐれたひともいれば、ソング・ライティング面で優れているひともいたり、歌詞はそんなに詳しくないですけど上手いひともいるんでしょうね。ソング・ライティングが上手いひとが、サウンドも歌も全部お手軽に自分でできちゃうからそれですぐに作品を出せちゃう。いろんな可能性がいっぱいあります。ニコニコ動画を見たりしていると、ぜんぜん再生数が少ないやつでも歌がよかったりすることもあったりするし。
■聴いているところは「生のヴォイスか」とか、そういう音質みたいなものじゃなくて、メロディとかですか?
L:そうですね。
■だったら必ずしも人格があり、美しい深みを持った人間の声である必要もない、と……ジュディ・シルとか書かれていると、声とか人間の歌礼賛なひとなのかなってちょっと思ってしまうので。
L:聴くぶんにはって感じですね。作っているときに、そうやって意識することはまったくないです。
■なるほど。LASTorderさんとかが、ひとの声をどういうふうに考えているかに興味があったんです。
L:じつはそんなに……。何か考えるようにします。
M:ハハハハ!

子どもがパンク・ミュージックにハマるみたいなものですかね。ちょうどブレイクコアがあって、いまだに生きながらえているのがすごくおもしろくて。(Miii)
■いやいや。逆に興味深かったです! いろんな思いがあって、生の声を避けているのかなと思ってたものですから。しかるに、Miiiさんのほうもおうかがいしたいと思うんですけれども、Miiiさんはもうなんというか、ブレイクビーツですよね(笑)。
M:そうなんですよ。
■おふたりともルーツがはっきりとわかる。そういう意味でもおもしろいです。たとえば、同じようにMiiiさんの「無人島~」のリストを参照させていただくと、ヴェネチアン・スネアズ(Venetian Snares)はもちろんとしてナース(Nurse with Wound)とかworld's end girlfriend(ワールズエンド・ガールフレンド)も入ってましたよね。だからノイズ志向もあるんですけど、かといって、中村一義とか七尾旅人なんかはすぐれたポップ・ソングの作り手でもある。だから、ドリーミーなものやメロディ的なものにも憧れがありそう。
M:そうですね。楽器ができないので、そういうアーティストさんには純粋に憧れがあるし、中村一義とか七尾人は中学高校時代にめっちゃ聴いていたので、普通に大好きなんですよ。やっぱりメロディもすごいし、歌詞もめちゃくちゃいいし。
■そしたら、いかにもバンドとかはじめそうですけれども?
M:あー、なんか……
L:ひと付き合いができないんでしょう?
M:ハハハハ。
■そんな(笑)。ドライなツッコミが入りましたね。
M:その通りです。
■なるほど。ひとりベッドルームでプロデューサーをやることを選んだと。
M:あと、バンドとかをやる以前にパソコンがあって、それで調べてなんとなく曲も作っていたから、「それでよくない?」みたいな感じでしたね。
■なるほど。あと、やっぱり音ゲー的なものってブレイクビーツだったり、ブレイクコアだったりっていうものとの親和性が高いですよね?
M:そうだと思いますよ。曲が1分とか2分とか短いじゃないですか? そのなかで、ひとをどれだけ惹きつけるかという要素を考えなくちゃいけないし、だからこそ展開が突拍子もなくなるというか、変な感じになっていくんだろうなと思います。
■音楽メディアがカバーしている範囲の外に独特のシーンがあって、独特の進化をしていますよね。ところでブレイクビーツってなんであんなに死なないんですかね? ずーっとありますよね。
M:ブレイクコアが全盛期だった2006年くらいってちょうど中学生だったんですけど、日本人でもいいアーティストがたくさん出ていて、そのへんがいちばんおもしろかったです。それこそヴェネチアン・スネアズみたいなちゃんとした音楽というか、レヴューの対象となるようなヤバいアーティストから、著作権完全無視のマッシュアップとか、本当にヒドいアーティストもたくさんいたけど、その全体がかっこいなという感じがあって。とくに〈マルチネ〉の初期も、いまでは「スカム」期みたいに言われるけれど、当時は「すげぇかっこいいことをやってる」と思って聴いていたので。自分にとってはそういうルーツというか、子どもがパンク・ミュージックにハマるみたいなものですかね。ちょうどブレイクコアがあって、いまだに生きながらえているのがすごくおもしろくて。
■そういうカオスみたいなものに若い心が共鳴してシーンが盛り上がっていた感じはよくわかりますけどね。
M:いま聴いてみても、変なドラムンベースを入れていたりとか、BPMが200のものとかを普通にやっているんですよね。なんだかんだカッコいいなと思っていまも見てます。
メロディを信じるしかないという感じだったので。音楽に話せる知り合いができたのも最近なんです。(LASTorder)
■なるほど。LASTorderさんはどうでした?
L:僕はシーンに憧れたりとかっていうことが逆になかったんですよ。
■淡々とひとりで?
L:だからメロディを信じるしかないという感じだったので。音楽に話せる知り合いができたのも最近なんです。小中高なんて、友だちとは音楽の話なんてまったくしていませんでしたからね。自分が不勉強で周りの状況に疎いということもあるので、最近はひとから教えてもらって勉強させてもらってます。
■最近はツイッターのタイムラインで音楽を聴くという感じで、スピードや情報の広がり方・受け取り方が以前とは大きくちがっていると思うんですが、2005年とかってまだそういうものが出てきているわけでもないですよね。当時、情報へはどうやってアクセスしていったんですか?
M:何をやってたかな……。IRCチャットっていう……
■やっぱり、みんなちょっとしたオタクなんですね。
M:そうそう。僕は完全にそっちでした(笑)。
L:そういうのあったよね(笑)。
M:だから、いまでいうラインみたいな感じですかね? チャンネルっていう部屋みたいなものが用意されていて。
L:疎いけど、さすがにチャットはわかるよ!
M:そういうチャットがギークっぽくなったものがあって、周りでチームを組んだりして、たわむれたりって感じでしたね。
■年齢層は若いひとばっかりなんですか?
M:多いのは20代とかでしたよ。
■じゃあ、Miiiさんはちょっと早熟な感じ?
M:そうですね。僕が12、13歳のときでそのなかではいちばん若かったと思います。
■ちなみに部活は(笑)?
M:部活は……、中学のときは吹奏楽部でした(笑)。
■おっと! 楽器ができるじゃないですか!
M:それが、チューバだったんですよ(笑)。
L:ハハハハ!
■それは潰しがきかねぇ(笑)。
M:「チューバをやっていました」って言っても、周りは「チューバ……?」みたいな感じなので(笑)。
■LASTorderさんは何部だったんですか?
L:バスケ部でした。
■そうなんですか? じゃあリアルが充実していらっしゃる?
L:バスケってそんなにイケてないですよ。普通に運動しているくらい。高校は帰宅部でした。
■音楽を作りはじめたのはいつぐらいなんですか?
L:ピアノを4歳くらいのときにはじめて、なんか鍵盤で曲を作っていた記憶はボヤッとあるんですけど、ちゃんとDTMをはじめたのは高2くらいです。
■おお、クラシックの素養もあると。ピアノで弾いて好きなった作曲家というとどんなあたりですか?
L:ピアノを弾いているときはぜんぜんおもしろくなかったんですよ。なんでこんな難しいのを弾かなきゃいけないんだって感じで。“ラ・カンパネラ”(フランツ・リスト)とか練習してたんですよね。そこからあまり好きになれずに、10歳から12歳のときはロック系が好きでした。でも、自分で曲を作るようになってから、あのときに練習していた曲がどんなだけすごかったってわかったんですよ。雰囲気的にはドビュッシーとかサティとかに魅かれますね。
■じゃあ何というか、ギークと……
M:ギークとメインストリームでしょう? だってコピバンとかやってたんでしょう?
L:コピバンやってたね。
M:僕はやってないからさ。
■へぇー! それって素敵なウェディングじゃないですか。ストーリーとしても、いいですね。
M:最初はバックグラウンドとか何も知らなくて、ただ「いい曲だね」って思っているだけだったんですよ。ふたを開けてみて、普段は絶対に出会うことのない遭遇だったんだとわかりました(笑)。 [[SplitPage]]
極端にポップになるか、わかりづらくなっちゃうかばかりで。そうじゃない「ごっちゃ感」を2013年のなかでやりたかった。(Miii)
■ハハハハ。なるほど。いろいろと見えてきたようですごくうれしいんですが、ではこのアルバムについて。今回はフィジカルで出るということですが、バンドキャンプでのリリースが2014年ということでいいですかね?
M:そうですね。
■実際の制作年でいうといつぐらいの曲から入っているんですか?
M:2013年の6月くらいからの音源ですね。
■じゃあ出会ったタイミングくらいにできた曲もあるんですね。以前から温めていたそれぞれのネタみたいなものもあるんですか?
M:それもあるんですけど、最終的にお互いでちょっとずつ手を加えてウェディング~の曲にしました。
■その頃というと、ダンス・ミュージック界隈で盛り上がっていたのは……ジュークとか?
M:そうですね、旬のてっぺんみたいな感じですかね。僕はずっとダブステップとかブローステップとかが好きで、自分でもつくったりしてましたけど、ジュークは進んでやることはなかったです。でも、たとえばウエディングで曲をつくるときに、「試しにジュークっぽいことやってみようか」っていうようなやりとりはありましたし、そのくらいの距離では時流についていっていましたね。
■なんか、自分たちの趣味をひたすらかたちにしましたっていうよりも、ある程度2013年っていう時代性のようなものも意識しているように感じるんですが。このころどんなものを聴いてました? あるいは、このアルバムでこんなことをやりたかったという目的なんかがありましたら教えてください。
M:僕がやりたかったのは、world's end girlfriendがいま僕らの年代だったとしたらどんなことをやるだろう……ってことですかね。あんなバランスのアーティストっていまあまりいないような気がするんですよ。もっと極端にポップになるか、もっとわかりづらくなっちゃうかで。それこそ〈ロムズ(ROMZ)〉系の存在もいないですし。そういう「ごっちゃ感」を2013年のなかでやりたかったということは、なんとなくあるかもしれません。
■へえ、なるほど。
M:なので、当時聴いていたダブステップだったりの要素はちょこちょこ入れていたりしますし、ポストロックっぽいものも入れてみたり──
■おお?
M:当時は下火だったとは思いますけど。
■そう思いますよ。へえー! なんでだろ、ウエディングを紹介する文章で、ときどき「ポストロック」って言葉を見かけるんですけど、わたしそこだけはよくわからないんですよね。
L:それは、君の責任だよね。最初にポストロックみたいなこともやりたいとかって言ってたから、それがプロフィールとかに残っちゃって。
■いや、突っ込んでるんじゃなくて、そんなルーツがあるんならおもしろいなと。だって、この10年もっともダサい音楽だったわけじゃないですか……その、個々のバンドの話じゃなくて、一時代前のものがいつだっていちばんダサいみたいなとこがあるから。
M:ははは! いや、でもたしかにこの10年間下火だったから出してきたかったっていうような気持ちはあったんですよ。
L:でも結局、やってみたらとくにポストロックにならなかった。
■ははは! いや、そうですよ。どこまでをポストロックと呼ぶかですけど、去年は10年選手たちがけっこういい新譜を出してきたり、シガー・ロスも幻のファーストが国内盤で出たりね。また見直されて、カッコよくなるんじゃないかと思いますから。
M:僕はゴッドスピード(Godspeed You! Black Emperor)とか好きだったんです。
■おお、なるほど。復活してますね。
M:2012年の新譜(『'Allelujah! Don't Bend! Ascend!』)はあんまりピンとこなかったですけど……。
L:まあそうやってポストロックだなんだ、って言ってて最初につくったのが、このアルバムの1曲め(“Preface”)なんですけどね。次につくったのが5曲め(“So Hot”)。それで俺は、ポストロック……やんなきゃいけないの? って思って、“Her Mistakes(ハーミステイクス)”のもとを渡したんです。「ぽい」やつを渡そうと思って。で、これで好きにやって、って。
M:そうだねー。
L:それで、無理やりギター入れたりして。
■ああ! ギター入ってますよね。そういうことだったんだ。
M:そういうことじゃないっては思いつつ(笑)、でもポストロックって言葉は入れたくて、でもしばらくして消えていきましたね。僕たちのなかで関係なくなった(笑)。生音でやるという意味でなら、いまでも興味なくはないんですが。
■なるほど(笑)。謎が解けました。ではもとの質問に戻ると、LASTorderさんは2013年に何を聴いていました?
L:僕は坂本慎太郎さんとか──、あれ? 2013年じゃないですかね? ずーっと聴いていました。 (※ソロ1作めは『幻とのつきあい方』2011年、2013年リリース作はシングル「まともがわからない」)
■へえー、そうなんですか。
L:僕自身はまだあまりクラブ・ミュージックに接近してはいない時期でした。
■たとえばTofubeatsさんだったりSeihoさんだったりは「対日本のポップ・シーン」っていうようなわりとデカいスタンスがありますよね。〈マルチネ〉という共通項もあるので、とくにトーフさんなんかはそれほど縁遠いアーティストではないと思うんですが、そういうスタンスはあまりThe Wedding Mistakesにはなさそうですね。この作品はどんなところに向かって放たれたものだと思います?
M:うーん、それこそ、僕が中学生当時エレクトロニカとかを聴いて衝撃を受けた、あのインパクトを持ったものになればいいなと思いました。10年経ったいまでもその頃の影響がみんなにウケたらすごくおもしろい……というか、いまその頃の音とか記憶ってウケるのか? みたいな。
■ははは、リヴァイヴァルっていうより、自分的にはルネッサンスみたいな?
M:はは、そうかもしれないですね(笑)。
彼は彼の世界がすごくあるので、彼から出てきたものは僕はあまり突っつかないんです。(Miii)
■LASTorderさんは? そのへんの感覚はふたりのあいだで共有されているものなんですか?
L:そう……かもしれない。
M:彼は彼の世界がすごくあるので、彼から出てきたものは僕はあまり突っつかないんです。そのほうがおもしろくなるんだろうなって思っていました。
L:できちゃったものを、ずらっと並べていくという感じもやっぱりあったので、どんな相手に向かって投げかけたものかというと、あまり顔は浮かばなくて。
■わりとカジュアルなものなんですね。いつかふたりでつくったものがアルバムになるんだろうなっていう思いはありました?
L:あまり思っていなかったかもしれない。
M:曲がたまったからそろそろ出そうかという部分もあったと思います。そこもアルバムのおもしろさではありますよね。貯まってきたからそろそろ出そうか、といってパッケージしただけでもそれなりのものに見えてしまったりする。だからこそ、CD盤と同じように、ジャケットをおじぎちゃんにお願いしたりとか、リミックスを入れたりとか、しっかりと外枠を固めるようなことはやりました。
■ああ、フィジカルはないけどフィジカルの盤みたいに、っていうのは意識されたわけですね。ところで、曲名は後づけかもしれないですけど、全体をとおして眺めると、なんとなく「ウエディング」ってコンセプトを立てているようにも感じられるんですね。そういうテーマ性はどうです? 意識してました?
L:文字、タイトル部分は僕が担当しました。僕としては、(この作品における)音についての方向性がまだもうひとつ見えてきていない気がしていたので、目に見える部分だけでも統一感を出したいなと思って。
M:アルバム・タイトルはすごく悩んだんです。そのとき「ヴァージン・ロード」ってすごくおもしろくない? って話になって。ウエディング・ミステイクスでヴァージン・ロードって、なかばギャグですよね。
■ははは、ミステイクなのにねーって(笑)。
M:そうそう、そんなノリですよ。
■なるほど、では曲名も、曲ひとつひとつにあらかじめ付与されていたものじゃないんですね。できたあとに加えられた物語というか。
M:そう……ですね。
■「結婚」って、近代以降は自由恋愛とセットで考えられてきたものだったりもするじゃないですか。でも、いま必ずしも憧れるような響きは持っていないというか、そうロマンチックなものではないと思うんですね。「婚活」とか少子化問題とかいろいろ出てきて。だから「The Wedding Mistakes」ってその意味でもちょっと批評的にきこえるというか。なんなんですか、「ウェディング」って?
M:うーん、そうですね。「永遠の愛」とかって、めっちゃ誓いづらいと思うんですよ。結婚式とか神父さんまでいたりして、いちおう儀式的にやったりしますけど、しんどいものでもあると思うんですよね。恋愛は3年しかつづかないとかも言うし。結婚って、僕個人としてはロマンチックなものだと思うし、好きな制度ではあるんですけど、正直、矛盾したものもいっぱい抱えているよなとも感じます。「結婚は人生の墓場」なんていう人もいるわけで。だから、僕的には理想だったりするけど、そううまくはいかないよなっていう皮肉が含まれているかもしれません。
L:……。
■ははは! Miiiさん、質問に対して噛み砕いて考えてくださったんですよね? ありがとうございます。LASTorderさんの沈黙は、Miiiさんの見解への違和感?
L:いえ、そんなに重く考えていたのねという……驚きです。 (一同笑)
L:僕にとっては結婚ってまだまだ遠いことで。
M:それは、そうだけど。
L:「永遠の愛」って口から出てくるとは思わなかった。ノリかなって……。
M:ああ、そう、ほんとには誓えないから、儀式として誓っておいて、じつのところはノリみたいな。でも、まだ当事者じゃないからあんまり言えないけど。だからユニット名に「ウエディング」って単語を入れるのはおもしろいというか意外というか、言葉選びとして気にした部分ではあります。
「逆に」っていうのが嫌い。(LASTorder)
■はい、はい。その、結婚なにかヘンだなってところが一般的に共有されているから気になる名前なんでしょうね。でも最初に名前きいたときは、それこそウエディング・プレゼント(Wedding Present)とかから来てたりするのかなって思って。ギター・ポップ寄りなユニットなのかと思いました。ぜんぜんちがいましたね。
L:そうですね。ギター・ポップ……。あと、それこそ渋谷系みたいなものはあまり知らないというか、聴かないよね?
M:そうだねえ。
L:それから、シティ・ポップとか。
■おお、トレンドじゃないですか。でも、いま渋谷系を標榜する人たちはむしろ90年代のJポップを掘ったりしてるんじゃないですか? まあ、標榜してるわけじゃないかもしれないですけど、それに当たるような人は。
L:僕は90年代のJポップなら大好きですよ。
■あ、そうなんですか?
M:僕も、最近のちょっとアーバンな感じのノリのものとかはあんまり聴かないかもしれません。シティ・ラップとか。
■えっと、「シティ・ポップ」って言葉でどういうものを指してます? そもそもが曖昧な言葉のようですけど、でも荒井由実とか、あるいははっぴいえんどとかを指しているのか、いまのバンドを指しているのか、よくわからなくて。
M:そうですね、最近のバンドとかのことですかね。もともとのシティ・ポップとか、アーバンな感じのものに憧れて、それが音になっているんだろうなって思うんですが、僕自身は東京生まれだけど「アーバン」な生活圏ではなかったので、そのへんの憧れにはそもそも疑いがあるというか。最終的には田舎に住みたい思いもあるし……。僕らくらいの年齢だと、そもそもその時代のこと知らないじゃないですか?
■なるほど。いまの人は、その見たこともないなかば架空の都会性を、逆におもしろがるようなところがあるんだと思いますけどね。昔はもっとベタに憧れたかもしれないですけど。
L:その「逆に」っていうのが嫌い。
■おおっ。
L:ヴェイパーウェイヴとかもそういうところありますよね。「逆におもしろがる」って……それって……なんなの。
M:それは、僕もわかるなあ。「逆に」っていうのは、いっこ上に立とうとしてるわけでしょ? そんなふうに考えなくても、90年代なら90年代で、いいものがあればそれは聴けると思うんですよ。それこそ中村一義とか僕は大好きですし。僕も、そういう感覚を無視した掘り返し方はしたくないですね。
■中村一義は、「逆に」の思考をすべて吹き飛ばしてきた人だと言えるでしょうね。
M:ああ、そうかもしれません。
■「逆に」っていうのは修羅の道で、いちどそれを言いだすとさらに上の「逆に」が際限なく出てくるから、超頭がいいか、それをはね飛ばす強さがないと死んじゃいますね。それでも行ってやろうというのもまたひとつの極道かなって思いますけど。ただ、「逆に」が嫌いだって言えるのは……ちょっと感動しました。
L:僕が普段から90年代の後半のJポップが好きって言っているのは、それは、実際に体験しているからなんです。幼稚園とか小学校の低学年の頃とかに、月に2回レンタル屋さんに連れていってもらって、ランキングの上位10位を借りてきて、それをダビングしてずっと聴くっていう毎日だったんです。本当に心から鈴木亜美とか好きなのに、いま同い年の人とかに「(鈴木亜美)いいよね」って言って、「いいよね」って返してもらったりしても、何かちがう感じがいつもするんです。そう言っている目線が。
同い年の人とかに「(鈴木亜美)いいよね」って言って、「いいよね」って返してもらったりしても、何かちがう感じがいつもするんです。(LASTorder)
M:あー! わかった。言ってることしっくりきた。
■なるほどー。
L:「あー、亜美ね!」って言われるときの……。たぶんそのときに「逆に」の感じが働いているんだと思うんです。
M:あー! うんうん。
L:こっちは逆もなにも……
■ははは! マジだっていう。
L:そう。バカなの、俺? って思っちゃう……。
(一同笑)
L:ちょっと、共有できてるのにできてないみたいなところがすごくあるし。単純に、トラックがよくできてるとかっていうような見方をしてたりもするんだろうけど。それに、……まあ、いいや。
■(笑)いやいや、話しましょうよ。
L:僕、あゆ(浜崎あゆみ)と宇多田(ヒカル)の同時発売の日とか、ちゃんと並んでますから。 (※浜崎あゆみ『A BEST』、宇多田ヒカル『Distance』の同時発売。2001年)
■ああ、えっと……、ふたり同学年ですよね。Miiiさん何歳ですか?
M:13、4年くらい前ですかね? 8歳とかですね。
■おお。そのころ何がいちばん熱かったです?
M:うーん、Jポップとかは聴いてなかったですね。ゲームやってました。
■なるほどね。音ゲーとかも。
M:そうですね、いろいろやりましたけど、『beatmania(ビートマニア)』を買って。それが原体験といえば原体験ですね。
■うーん、Miiさんはじつにルーツがはっきりしてますね。
L:俺は原体験はポケビ(ポケットビスケッツ)だよ。
M:それはさすがに、僕もテレビは観てた。
■ああ、音楽というか芸能というか、テレビから出てきたものですね。そういう記憶は少なからず影響しているんでしょうね。
そのころからコラージュ──いまで言うネットの雑コラ感っていうか──はちょっと流行っていて、でもおじぎちゃんのはちょっとそういうまわりのものとはちがう感じがして。(Miii)
■さて、先ほどもちょっと話題に上がりましたが、ジャケットのデザインがおじぎちゃんさんなんですよね。とても素敵なんですが、おふたりともアニマル・コレクティヴ(Animal Collective)とか好きだったりします?
M:いや、好きっていえるほどはわからないですね。
■なるほど。初期の作品のアートワークをアグネス・モンゴメリ(agnes montgomery)という人がやっているんですが、その人の作品のポスト・ヴェイパーウェイヴ・ヴァージョンって感じがするんですよね、おじぎちゃんさんのジャケは。
M:へえー。
■コラージュなんですが。感性にも似たものがあるなと思うんですよ。
M:当時おじぎちゃんが自分のタンブラー(Tumblr)にどんどん画像を上げていたんですよ。コラージュでした。そのころからコラージュ──いまで言うネットの雑コラ感っていうか──はちょっと流行っていて、でもおじぎちゃんのはちょっとそういうまわりのものとはちがう感じがして。統一感というか、テーマみたいなものがあって、そのなかで色調とかも合わせてくる感じ。そこに自分たちの音に合ったイメージを持っていたんです。〈ROMZ〉のジョゼフ・ナッシング(Joseph Nothing)の、目の切り抜きがたくさん散りばめられているジャケット、あの気持ち悪いけど美しいという感じに衝撃を受けたんですけど、あれを見たときのことを思い出したんですよ。そういう、僕の源流にあったイメージとかインパクトが刺激されたというか……。それでお願いしました。
■へえー。それこそコラージュはメタな編集作業でもあると思うんですけど、おじぎちゃんさんのとかアグネスのとかは、もっと肉そのものというか、そういうものを信じている感性なのかなと思いました。
M:やっぱり、ちゃんと考えられていたり、まとまっているものが好きなので、「できるだけ意味をなくそう」みたいなものとか、そういう感じのコラージュにはピンとこないというのが正直なところですかね。
■なるほど、イルカとか、ヘンな塑像とかね(笑)。
M:あー。シーパンク(Seapunk)は……、嫌いじゃないですけども。
L:俺、髪を青くしてたことある。
■え?
L:なんか、Seihoさんのイヴェントで、髪を青くしていったら安くなるやつがあったから。
(一同笑)
M:あー! あったかも。ウルトラデーモン(ULTRADEMON)のリリパとかかな。
■ははは! 懐かしい。動機が安いなあ。LASTorderさんはジャケットとかアートワークについてディレクションした部分はあるんですか?
L:俺は……、ないかなあ。でも俺は俺でおじぎちゃんを見つけていたんですよ。それで、よくよくきいたらけっこう近いところで活動していて。それで、何かいっしょにできないかなと思っていたら、なんとなくあちらも似たことを思っていたみたいで。
■へえ。
L:だから、だいたいさっきの説明と同じなんですけど、ちゃんと意味のあるものを感じるなと思って、共感するというか。
■ふたりはけっこうバラバラなんだなと思いましたけど、同じようなところもあって、おじぎちゃんというのはそれを理解する補助線のような気もしてきました(笑)。
L:「こうしてください」ってふうにとくに注文していないんです。
M:そう、音源を送ったくらいで。
L:ウエディング・ドレスじゃないけど、そういう雰囲気の花のイメージがきて、あらためて、「ああ、自分たちはThe Wedding Mistakesなんだな」って思いました。
■わたしもこの感じ、とても好きですね。
ソロの音はあまりゆがませたくないので……。だから、どちらかというと自分の音を押しつけている感じです。(LASTorder)
■さて、このユニットは一時的なものなんでしょうか? 期間限定のコラボみたいな。
M:えっと、正直な話、僕らが出会ったのが大学2年か3年のときで、もう卒業になるんですね。だからこの先忙しくなるだろうし、とりあえず1年半くらいやって、1枚2枚作品をつくって、楽しかったねって感じで終わろうと思ってたんです。だけど、こんなふうにリリースしてくれるところも見つかって、いまはちょっと長期的にやろうかというふうに思ってます。
L:俺も……、続けたいし、次はもっと作り込んだものをつくりたい。もっと、さらにいいものをって思える感触がいまのところあるので、まだやっていくつもりですね。
■自分ひとりだとやれない部分が相手の中に見えているということですかね。
L:それがはっきりしたし、それを言いやすくなりました。
■お互い評をもっと訊きたいですね。相手から盗んだ能力とかないんですか?
L:盗んだ能力は……ないですね。
M:(笑)
■でも、データをもらってるわけだから、ある意味では盗み放題ですけども。
L:いや、データはこちらから渡すだけで、それを全部あっちが加工するんで……。
M:でも、たまにあげてんじゃん。こっちのも。
■ははは!
L:でも、わざわざそれを解体したいという感じではないです。ソロの音はあまりゆがませたくないので……。だから、取り入れるということはなくて、どちらかというと自分の音を押しつけている感じです。
■Miiさんは?
M:僕も押しつけられているということに関してはとくに何も、というかもっとやってくれって思ってるし、彼には自分の世界観がしっかりとありますから。僕は知識を体系的に取り入れて、それをどう生かしてブレイクコアとかの方程式で壊すかっていうようなことをやっていたので、LASTorderからもらった素材をどういじるかっていうところに熱量があるんですよね。だから彼から送られてきたものについては全面的に信頼しているし、もし何かやろうとするなら、彼に言うんじゃなくて、自分で解体してどうかしたいって思います。 このアルバムでいえば、2曲め“ドラマティック・ビヘイビア(Dramatic Behavior)”とかは展開が突拍子もないんですけど。これははじめの1分半くらいの音をもらって、それをどう壊したらおもしろいかなって考えて、ジュークぽい低音を入れたりとか、最終的にゆがんだブレイクビーツを突っ込んでみたりとかしました。それはこっちで全部やったことなんですけど、そしたらすごく喜んでくれたし、ライヴでやってもすごくハマる曲になって。
LASTorderからもらった素材をどういじるかっていうところに熱量があるんですよね。(Miii)
■ああー!
M:そのときくらいから、こっちでどうやるかというスタンスができあがっていった気がします。
■たしかに2曲めは、ふたりともの個性がケンカするわけじゃないけどはっきり出てきてぶつかり合ってますよね。ほか、手ごたえのあった曲はどのへんです?
M:“スルー・オール・エタニティ?(Through All Eternity?)”とかもそうですかね。好き勝手やっている感じです。
■ああ! Miiiさんの面目躍如! って感じの曲ですね。
M:そうそう、そうです!
■で、LASTorderさんのメロディ性がより効いてくる。
M:当時はまだサウンドクラウド(SoundCloud)に曲を上げつつ、ライヴもやりつつっていう感じだったので、1曲めがまずサンクラに上がっていて、次に“ハー・ミステイクス(Her Mistakes)”が上がって、次、急にベースが入ったらおもしろいと思って。それで“スルー・オール・エタニティ?(Through All Eternity?)”を作ったんです。だから、特異点でもあります。
■なるほど。では、この中にヴォーカルが入ったりなんて展開は今後考えられますか? すでにふたりともそれぞれのやり方で“歌っている”人たちではありますが。
M:歌は……考えてます(笑)。でも、そっちはまた別の方法論になりますから。デジタルでアルバムを出した後に『ミッドナイト・サーチライト・EP(Midnight Searchlight EP)』っていうEPをつくったんですけど、そっちは1曲だけがっつり歌ものが入ってるんですよ。でもそれはわりと僕らのいつものスタイルじゃなくて、僕が歌詞とかもつくって、編曲をふたりでやったっていう曲なんです。それで、ちょっと色合いとしては今回のアルバムとちがうものになってるんですね。だから歌をやったらまたちがったおもしろさが出てくるかもしれないと思っていて、次はそうなるかもしれないですね。
■歌ものって……R&B寄りなものとか?
L:というよりは、Jポップというか。
M:Jポップだけど、ちょっと毒というか、エグみのあるものを混ぜるので、おもしろい感じになるかとは思います。
L:そうですね……。でも、そういうものもやりつつ、また今度アルバムをやるとなったら、それはそれでちゃんとやりたい。歌ものかどうかというより、もっとちゃんとつくったものをやる。
■ああ、ポジティヴな展開が期待できそうで、素晴らしいです。
歌をやったらまたちがったおもしろさが出てくるかもしれないと思っていて、次はそうなるかもしれないですね。(Miii)
■ライヴはどんなふうにやってます? バースとウワモノで分かれて、けっこう即興的なかたちでふたりがセッションするんですか?
M:そこは僕の力不足もあって……、即興的に合わせるっていうのはまだできていないんですよ。鍛えたいところなんですけど。
■おお、じゃそんなふうにやってきたいなって思いはあるんですね。……チューバ、やったらいいじゃないですか(笑)。
M:チューバかあ……!
(一同笑)
■そこからすでにベースだったんですね。
M:いま思えば(笑)。
■どうですか? ライヴについては。
L:いまライヴで悩んでいるような部分が大きいのはたしかですね。僕ひとりではそれほどライヴをしないので……。
M:月1回くらいがちょうどいいペースかと思いますけどね。
L:月1より、もうちょっとやったほうがいいんじゃない? CDを出したことで、CDを手に取ってくれた人がライヴに来たらいいなと思うし。
■ちなみに、CDはタワレコさん渋谷だったら何階に置かれたいです?
M:いまは4階(クラブ系など)に置いていただいているんですよね。希望するとしたら……そうだなぁ、たとえばJポップのフロアとかにも置かれたいですね。
L:Jポップって、邦楽のロックのバンドとかも同じフロアにある?
M:うん、いっしょなフロア。
L:じゃあ、ちょっと置かれたいです。でも4階に置いてくれるのはうれしい。
■6階(エレクトロニカなど)とかは?
M:ああ、それもうれしいです。多義的なというか、ハードコアっぽい要素すら入っている作品なので、いろんな聴かれ方をしてほしいし、いろんなひとに聴いていただきたいですけどね。
■もちろんそうだと思うんですけども、たとえばインターナショナルな展開は考えていないのかなと思いまして。べつにウエディングは特殊なキャラクターで売っているというわけではなくて、普通に国内外関係ない音楽のつくり方、発信をしてるように感じるので、海外レーベルから出したいみたいな気持ちがないのかなと。
M:海外でも認められればうれしいなというくらいで。あんまり詳しくはないんです。
L:海外でウケるのかどうかっていうのは知りたい。でも、海外の人たちにウケそうなもの、って思って作ってないから……。
■なるほど。今日は意外にドメスティックな一面というか実像を見れてよかったです。なんか、とても自然なスタンスでいまという時代に音楽をつくっているなって思って。
M:そうですね、でも自分で聴いていて、日本人ぽい音楽なんじゃないかって思ってます。うまく言えないけど、日本人っぽい感情の出し方、つくり方。
自分で聴いていて、日本人ぽい音楽なんじゃないかって思ってます。うまく言えないけど、日本人っぽい感情の出し方、つくり方。(Miii)
■ああー。抒情性みたいな部分とか?
M:海外の音楽って、もっと音とかリズムとか一個一個の要素が太くて、それ全体でグルーヴをつくったりするところがあるという感じがします。こっちは、いろんな情報を配置するだけで、あとは聴くほうがその中から何を聴くのかを選んでいるというか……。だから、叙情みたいなものもそこから選んで聴き取るのかもしれないし。そういう意味ではメッセージといえるようなメッセージはないかもしれないというか。そこには多義的な、いろんな情報の層があるだけで。
■ああー、たくさん神様がいる国、みたいな。八百万の。仏様もいっしょくたみたいな。
M:歌詞とかの情報量も多いし、情報の海があるだけって感じ……。つくる側の目線で言えば、自分は「この音だ」っていうのをドーンと出すのは正直なところ得意じゃないし、どんな音を足していったのかということもわりと感覚的で、理屈にもとづいたものではないし。
■なるほど。
M:感覚的な話になってしまいましたが……。
■いえいえ、音楽ですからね。言葉で言えれば音楽である必要もないし。ではリミキサーのHercelot(ハースロット)さんついておうかがいして終わりましょうか。
M:そうですね、もう、すごく好きなアーティストで、高校のころから崇拝していて。この曲(“Marriage for Dance”)については、トイポップみたいな可愛い要素をたくさん入れていただきましたけど、ご自身は「ロムズ・チルドレンだ」って言ってるくらい〈ROMZ〉が好きな方で、このリミックスはそういう人にお願いしなきゃ収まらないっていう思いはありました。
■LASTorderさんは?
L:俺は……、というか、Hercelotさんにお願いしようと言い出したのは俺で。
M:そうですね。それを聴いて、たしかにそうだって思ったんです。
■不思議ですね(笑)、ほんとにふたりは、バラバラで凸凹で、でも妙にシンクロしてる。ヘンなウエディングですよ。



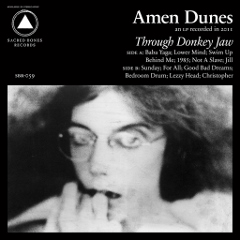
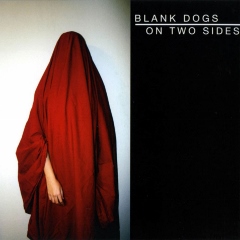

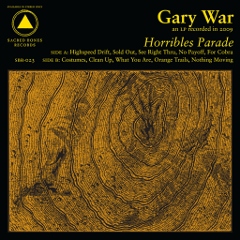


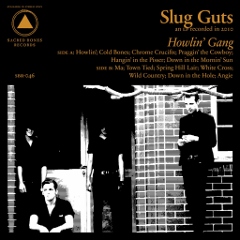



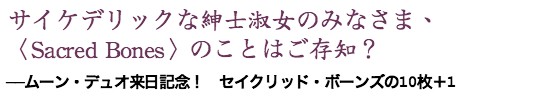
 高校卒業後、ザ・ウィザードという名称でラジオDJとなりヒップホップとディスコとニューウェイヴを中心にミックスするスタイルは当時のデトロイトの若者 に大きな影響を与える。1989年にはマイク・バンクスとともにアンダーグラウンド・レジスタンス(UR)を結成。1992年にURを脱退し、NYの有名 なクラブ「ライムライト」のレジデントDJとしてしばらく活動。その後シカゴへと拠点を移すと、彼自身のレーベル「アクシス」を立ち上げる。1996年に は、「パーパス・メイカー」、1999年には第3のレーベル「トゥモロー」を設立。現在もこの3レーベルを中心に精力的に創作活動を行っている。
高校卒業後、ザ・ウィザードという名称でラジオDJとなりヒップホップとディスコとニューウェイヴを中心にミックスするスタイルは当時のデトロイトの若者 に大きな影響を与える。1989年にはマイク・バンクスとともにアンダーグラウンド・レジスタンス(UR)を結成。1992年にURを脱退し、NYの有名 なクラブ「ライムライト」のレジデントDJとしてしばらく活動。その後シカゴへと拠点を移すと、彼自身のレーベル「アクシス」を立ち上げる。1996年に は、「パーパス・メイカー」、1999年には第3のレーベル「トゥモロー」を設立。現在もこの3レーベルを中心に精力的に創作活動を行っている。

 Terrence Parker
Terrence Parker



