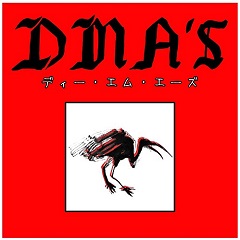1956年にブリクストンで生まれたドン・レッツも今年で60歳。BBCのラジオ6での彼のDJは、いまでは日本で暮らしながら聴けるので、チェックしている方も少なくないでしょう。先月のブリストル特集も良かったですよね。選曲が素晴らしいです。
ドン・レッツは、パンクの時代、パンクロッカーたちからものすごく信用されていたレゲエDJで、以来ずっとDJをやりつつ、映像作家としても活躍しています。UKが誇るファッション・ブランドのフレッド・ペリーのサイトでは、UKサブカルチャー史の映像作品も発表しているので、興味のある方はぜひ見てください。ちなみに神宮前にあらたにオープンしたフレッド・ペリーのお店では、今年はドン・レッツとの共同企画のラインも並ぶそうです。
昨年は井出靖さんのレーベルの10周年を記念してリリースされたミックスCDも話題になりました。日本人によるレゲエ音源をドン・レッツが選曲したものです。
来週はドン・レッツが渋谷のミクロコスモスでDJします。パンキー・レゲエな人はマストです。来て下さい!
【BIG GROOVE feat Don Letts】
日程:3/20 (SUN) *祝前日 OPEN 24:00
料金:ADV ¥2500 (1D) DOOR
会場:MICROCOSMOS
出演:
Don Letts
MURO
COJIE of MIGHTY CROWN
OMI(THE MARROWS)
[REGGAE | DUB ]
MICROCOSMOS
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォティスビル2F
03-5784-5496
https://www.microcosmos-tokyo.com
☆REGGAE/DUBの最重要人物”Don Letts”が登場。MICROCOSMOSに激震が起きる!!
久しぶりのMICROCOSMOSでの開催となる”BIG GROOVE”
今回はUKのレゲエ、ダブシーンを牽引してきたDon Lettsがフューチャーされた。
UKで起きたパンクムーヴメントの拠点と言える”ROXY CLUB”でのDJをしていた彼はパンクとレゲエをつなぐ存在でもあり、THE CLASHのMICK JONESとの”BIG AUDIO DYNAMITE”での活動でも垣間見れる。また、映画監督として顔も持ち2003年にはTHE CLASHのドキュメンタリー『WESTWAY TO THE WORLD』でグラミー賞を受賞する。
彼のクリエティブな才能は現在の音楽シーンに多くの影響を及ぼしてきたことは間違いない。
レジェンドが現れる特別な一夜は逃してはならない。
☆DON LETTS (DUB CARTEL SOUND STSTEM, LONDON)
ジャマイカ移民の一世としてロンドンに生まれる。'76-77年にロンドン・パンクの拠点となった<ROXY CLUB>でDJを務め、集まるパンクスを相手にレゲエをかけていたことから脚光を浴び、パンクとレゲエを繋げたキーパーソンの一人。同時にリアルタイムで当時の映像を撮り、'79年に初のパンク・ドキュメンタリー映画『PUNK ROCK MOVIE』を制作。またブラック・パンクの先駆バンドBASEMENT 5の結成に携わり、THE SLITSのマネージャーもつとめる。'80年代半ばにはTHE CLASHを脱退したMICK JONESのBIG AUDIO DYNAMITEで活動、さらにBADを脱退後の'80年代末にはSCREAMING TARGET(※BIG YOUTHのアルバムより命名)を結成し、"Who Killed King Tuby?"等をヒットさせる。音楽活動と平行して、多くの音楽ヴィデオやBOB MARLEY、GIL SCOTT-HERON、SUN RA、GEORGE CLINTON等のドキュメンタリー・フィルムを制作、’03年にTHE CLASHのドキュメンタリー『WESTWAY TO THE WORLD』でグラミー賞を受賞する。そして'05年にはパンクの核心に迫った『PUNK:ATTITUDE』を制作。DUB CARTEL SOUND SYSTEMとしてスタジオワーク/DJを続け、SCIENTISTの"Step It Up"、CARL DOUGLASの"Kung Fu Fighting"等のリミックスがある他、<ROXY CLUB>期のサウンドトラックとなる『DREAD MEETS PUNK ROCKERS UPTOWN』('01年/Heavenly)、名門TROJAN RECORDSの精髄をコンパイルした『DON LETTS PRESENTS THE MIGHTY TROJAN SOUND』('03年/Trojan)、'81-82年に彼が体験したNY、ブロンクスのヒップホップ・シーンを伝える『DREAD MEETS B-BOYS DOWNTOWN』('04年/Heavenly)の各コンパイルCDを発表している。'07年には自伝「CULTURE CLASH-DREAD MEETS PUNK ROCKERS」を出版。'08年にコンパイル・アルバム『Don Letts Presents Dread Meets Greensleeves: a West Side Revolution』がリリース。'10年にメタモルフォーゼ、'11年にはB.A.Dの再結成でオリジナルメンバーとしてフジロックフェスティバルに出演。'15年7月、井出靖氏が主宰するレーベル、Grand Gallery10周年を記念し、日本人アーティストをメインにセレクトしたMIX CD『Don Letts Presents DREAD MEETS YASUSHI IDE:IN THE LAND OF THE RISING DUB』を発表、日本ダブ史のエッセンスを内外に明示する。
BBC RADIO 6 Musicにて毎週日曜日”Culture Clash Radio"を持つ。
https://www.donletts.com/
https://www.bbc.co.uk/6music/shows/don_letts/
https://twitter.com/@RebelDread
 池野詩織
池野詩織