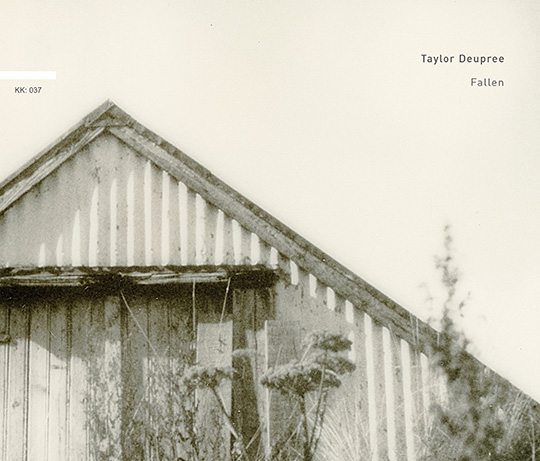いかなる物語にも良いときがあり、悪いときがある。人の人生において喜びに浮かれるときもあれば、悲しみで胸を痛めるときがあるように。家具屋のカタログのようにはいかない。ぼくたちはとにかくそうして生きている。サイレント・ポエツ=下田法晴もそうだ。
サイレント・ポエツは、いわばマッシヴ・アタックへの日本からのアンサーだった。“ダウンテンポ”なるスタイルの継承者である。リーズのナイトメアズ・オン・ワックス、ブリストルのポーティスヘッド、ブライトンのボノボ、ウィーンのクルーダー&ドーフマイスター、パリのザ・マイティ・バップ、DJカム、ラ・ファンク・モブ……そして日本ではサイレント・ポエツ。
昨年はクルーダー&ドーフマイスターも新作を出している。トスカ(ドーフマイスターの別プロジェクトで、Chill好きには必須の“チョコレート・エルヴィス”の作者)の名盤『Suzuki』も再発された。今年に入ってからはナイトメアズ・オン・ワックスも新作をリリースした。いまここにサイレント・ポエツが12年ぶりに新作『dawn』をリリースする……と書けば筋書き通りだが、ぼくたちの人生とはそんなにイージーではないし、そんなに小綺麗でもない。
ぼくは人生に落ちぶれた人たちが集まる酒場にいた。居心地は悪くない。むしろ気分がいいくらいだ。
 Silent Poets dawn Another Trip |
サイレント・ポエツは、最初はミュート・ビートに影響されたインストのレゲエ・バンドだった。それがマッシヴ・アタックを通過して、下田を中心としたよりエクレクティックな音楽性のプロジェクトへと展開するわけだが、根底にあるのはダブであり、こだま和文が絶えず発する“悲しみ”や“痛み”、あるいは小さな“微笑み”かもしれない。ひとつ言えるのは、そこが彼の帰る家だったということである。サイレント・ポエツ印でもあるストリングス・サウンドは以前のように優雅に響いてはいる。が、しかし今作には深い、そう、12年分のエモーションが込められている。
ラッパーの5lackとNIPPS、櫻木大悟(D.A.N.)、レゲエ・シンガーのHollie Cook、イスラエル出身のフィメール・ラッパーのMiss Red、オーガスタス・パブロの息子のAddis Pablo……などなど多彩なフィーチャリングを擁しているが、今作のリリースには制作費を援助するような後ろ盾となるレーベルは存在しない。彼はとにかく人生のいろいろな局面を乗り越えて、なんとかしながら、おそらく這いずるように音楽の世界に戻ってきたと。
どんどん状況悪くなって、けっこうへこんだというか。お金もないし、みたいな感じになってしまって。いままではあんまりそういうことを感じて作っていなかったので、それはけっこうキツかったですね(笑)。
■12年前のことなんてもう覚えていないと思いません?
下田法晴(以下、下田):そうですね。もう消えてますよね(笑)。思い出そうとしたら、いろいろと嫌な思い出も思い出しますけど(笑)。
■この12年間で世の中があまりにも変わったからね。その前の12年よりも変わったでしょう
下田:そうですね。急激に変わりましたね。そういうのもリリースできなかった理由のひとつかもしれないですね(笑)。
■こと音楽を取り巻く状況が変わりすぎたでしょう(笑)?
下田:そうですね。どんどん状況悪くなって、けっこうへこんだというか(笑)。お金もないし、みたいな感じになってしまって。いままではあんまりそういうことを感じて作っていなかったので、それはけっこうキツかったですね(笑)。
■レーベルとの契約があってやっているんだったらともかく、下田くんみたいにインディペンデントで12年ぶりに作品を出すのってそれなりに気持ちが必要だったんじゃないかと思うんですが。
下田:それは相当ありましたね(笑)。出したくてもできないという状況がずっと続いていたんですけど、4年前にエンジニアの渡辺省二郎さんが声をかけてくれて、ダブ・アルバムみたいな作品を出したんですよね。あれをきっかけにその流れでまたやろうと思ったんですけどなんかまたできなくて(笑)。それで沈みかけたんですけど、そのときに(NTTドコモの)CMの話があって、本当に久々に新曲というものを書いたんですよ。
■それが5lackの曲?
下田:そうですね。それが思った以上によくできたというか、評判も良くて。それもあってちょっと自信を取り戻したというか、それでやれるかなというときにちょうど25周年というタイミングだったので、これはいまやるしかないと感じたんですよね。
■デビュー25周年?
下田:そうですね。結成になるともうちょっと長くなるんですけど、最初のCDを出したのが1992年くらいだったかな。もう26年目ですけど(笑)。
■『SUN』からアルバムを出さなくなったけど、下田くんのなかでは「いつかは出そう」という気持ちはあったんですか?
下田:もちろんありました。でもそういう気持ちと出したいけど自信がないというのがずっと交差していて、あとは後ろ盾もなくなって自分でやるにはどうやってやったらいいんだろうというか。お金の問題とか、そういうことを考えているとなかなかできなかったんですね。曲もちょこちょこ作ってはいたんですけど、なんとなく「止めた」という感じになってしまっていて、それを繰り返してかなり燻ぶっていたんです。そういうなかで震災があったり、どんどん良くない状況になっていって、本当にどんどん奥まっていったというか(笑)。
■やっぱり作品を発表していないと、自分が次出しても聴く人がいるのかと思ってしまうと良く聞きますけどね。とくにコンスタントに出していた人はね。
下田:当たり前なんですけど本当にこの10年でぼくのこと知らないって人がすごく増えたので(笑)、若い世代の人とか今回オファーした人で聴いたことない人がいることがけっこうショックで、「あれ?」みたいなことがあって(笑)。それもジワジワ効いてきていて、これは本当にヤバいんじゃないかと(笑)。
■忘れられるんじゃないかと(笑)?
下田:忘れられるし、過去の栄光みたいなものなので。本当に過去の人になっていたなと思いましたね。
■いまではインターネットで昔のものをディグるようなこともあるじゃないですか。そういうことの影響はなかったですか?
下田:なくはなかったですけどね。「ファースト良かったよね」とかそういうことはしょっちゅう言われ続けていたんですけど、いまの作品がなかったから「いまはなにやってんですか?」みたいな質問が怖くて(笑)。「昔はこんないいの作っていたのに、いまはなにをやってるんですか?」みたいなことを訊かれたりして、「やりたいと思っているんですけどね」というような言い訳をするのがすごく辛かったですね(笑)。それを本当に長いことやってきていたから、どんどん消耗していったというか(笑)。
■まさに自分との闘いみたいな(笑)。
下田:それはありますね(笑)。
■制作環境は昔と変わっていないんですか?
下田:もう全然(違いますよ)。昔は事務所を防音したりしてスタジオみたいなところを作っていたりしたんですよね。でもいまは事務所もないし、家のちっちゃい机で最小限の機材でやっているだけなので。だけどやっていたらあんまり関係ないなと思いました(笑)。そんな機材とか防音とかしなくてもできるっちゃできるというか、今回やってみたらなんとかなりましたね。でも逆に狭められたのが良かったのかもしれないです。すごく良い環境であぐらかいて……、はやってなかったですけど(笑)。
■はははは(笑)。
下田:機材もほとんど売りましたけど、全然関係ないと思いました。あったらあったで良いとは思うけど、ないなりのやり方があったというか。
■そういう意味だとニュー・ルーツの人とか(笑)、UKグライムやベース系の若い世代の人たちとかの、PCとソフトウェアだけの最小限の環境に近いというかね。
下田:それが良かったりするんですよね。
[[SplitPage]]今回は作っていてミュート・ビートというものに影響を受けたことをあらためてすごく感じたというか。今回はその影響もモロに出しちゃっていますし、しかもこだまさんにも参加してもらっていますし、自分にとって本当に大きな存在だということを改めて感じましたね。
 Silent Poets dawn Another Trip |
■サイレント・ポエツは元々ミュート・ビートに影響を受けたバンドだったんですよね。
下田:そうですね。初期はぼくがドラムを叩いていたし(笑)。ちゃんとメンバーとしてギターもベースもキーボードもいましたしね。
■いまのリトル・テンポですよね。
下田:リトル・テンポのメンバーの数名はそうですかね。
■今回のアルバムにはこだま(和文)さんが参加されていますよね。
下田:そうなんですよ。
■サイレント・ポエツの歴史を考えると、今回のアルバムにおいて重要な客演の一人じゃないかという気がします。
下田:そうですね。今回は作っていてミュート・ビートというものに影響を受けたことをあらためてすごく感じたというか。今回はその影響もモロに出しちゃっていますし、しかもこだまさんにも参加してもらっていますし、自分にとって本当に大きな存在だということを改めて感じましたね。朝本(浩文)さんが亡くなったということもあって、あの後にまたミュートを聴いていたんですよね。それでやっぱりすごいなと思って。
■ミュートのどこが好きですか?
下田:なんですかね。このシンプルで、重くて強くて……。
■悲しみのこもったメロディーは似てると思います(笑)。
下田:哀愁とか(笑)。そこは本当に好きですね。だからバンドでやろうとしたときにあまりに似ちゃって、どうしようもなかったんですよね。似たものが出来ちゃって「これミュートじゃん」って。暗い曲が多かったから、レゲエにしちゃうと本当に全部ミュートになっちゃうみたいな感じで、これはもうできないなと思ったんですよ(笑)。そこからサンプラーを買って、他の音楽も好きだったのでそっちのほうに移行していって、バンドでやる音楽ではなくなったのでぼくが勝手に分裂させちゃったんですけど。
■当時の印象だと、ミュート・ビートの次に影響が大きかったのはマッシヴ・アタックだったんじゃないかなと思います。
下田:そうですね。そのふたつは完全に二大巨頭としてありますね(笑)。
■だから世代的にミュートの最後期を聴いていて、しばらくしてワイルド・バンチやマシッヴ・アタックが出てくるという感じですよね。
下田:そうですね。その流れでぼくもそっち系のものも聴いていましたね。
■とにかく、今回の新譜の情報を最初にもらったときに、まず「お」と思ったのがこだまさんでした(笑)。ぼくがこう言うのもなんですけど、本当によく声かけてくれたなと思いましたよ(笑)。
下田:(サイレント・ポエツの)初期の頃に一度声をかけたことがあるんですよ。そしたら「俺がやったらミュート・ビートになってしまう。これはやらないほうがいいんじゃない?」って間接的に言われたんですよね。たしかにそうだなと思ってやめたんですけど、そのアルバムには松永(孝義)さんとかは参加していただいたんですよ。という経緯があって、それを(こだまさんと)飲んだときに話したら「そんなことあったっけ?」ってあんまり覚えていらっしゃらなくて(笑)。
(一同笑)
下田:でも今回は「お前よく俺を呼んだな」って喜んでらっしゃいました(笑)。最初にお願いしにいくときに吉祥寺に飲みに行ったんですよ。こだまさんの行きつけのお店に行って頼んだでみたら、「お前偉いなあ」って言われて(笑)。「自分でやるのか。よく俺を選んだな」って(笑)。
■今回こそこだまさんの力を借りたいという?
下田:それもそうですね。あとはやっぱり25周年というアニヴァーサリー感もあって(笑)、本当に好きな人にやってもらいたいと思ったんですよね。
■制作は5lackとの曲から始まっていると思いますが、それ以降はどのようにはじまったんですか?
下田:今回は最初からほとんど全部の曲にフィーチャリングを入れようと思っていたので、アルバム全体の感じというよりも1曲1曲を集中して作ったという感じですね。例えばこれは誰にやって欲しいということを念頭に置いて作りながらオファーして、ダメだった人もいたので、そこからちょっと修正しながら作っていきましたね。
■じゃあ例えばホーリー・クックとやろうと思ったらその1曲を作って、その次の人と一曲作って、って感じなんだ。
下田:本当にそうですね。そうしているあいだに次の曲を作ったりしていて、制作期間は1年くらいでしたけど、実際に曲を作っていたのは半年くらいでしたね。意外とやりだしたらするっとできたというか(笑)。溜まっていたんですかね。あとは最初からフィーチャリングを念頭においてやったというのがけっこうイメージしやすくて良かったのかもしれないですね。
■サウンド的にはどんなコンセプトがあったんですか?
下田:いままで聴いてくれていた方を裏切りたくないというのもあったんですけど、5lack以降はちょっと広がって新しく聴きはじめてくれた方もいたというのも意識して、古くも新しくもないサイレント・ポエツというのをイメージしたかなあ。
■ではとくにひとつテーマを設けたということでもなく?
下田:そうですね。全体のテーマというよりは1曲1曲で作っていったので。あとはとにかく復活とか、そういうキーワードはいっぱいありましたけどね(笑)。
■とにかくかたちにしていくという?
下田:25周年ということで、26年目になっちゃうとダメだという締め切りもあったので(笑)。
■自分でやってみてどうですか? 作るだけじゃないところというか、それこそ制作費とかお金に関するところまで全部自分でやってみて。
下田:そういうことをなんとなくごまかされながらケツを叩かれてやっていたような感じだから、それがわかってやったほうがスッキリできるのかなと思いましたね。めんどくさいこともありますけど、でもいろいろとサポートしてもらったのでわりと(制作に)集中できたと思います。だからやっぱり自分でやるほうがいいのかなと。手伝ってもらわないとできないんですけどね(笑)。
■この櫻木大悟(D.A.N.)も下田くんは好きだったんですか?
下田:好きでしたね。いまの新しい世代で本当にかっこいいと思えるのはD.A.N.くらいじゃないかなと思って(笑)。
■ちゃんと若い世代の音楽を聴いているんですね。
下田:聴きましたね。ただ最初はやっぱり日本語のヴォーカルにちょっと違和感はありましたね。すごく良かったんだけど、いままでの自分にはなかったものだったからちょっと戸惑ったというか。でもだんだん馴染んできいって最終的には良かったと思っていますね。本当に初の試みだったので。
■年齢的には一番離れていますよね。
下田:そうですね。まだ24才くらいですもんね。
■彼はサイレント・ポエツは知っていました?
下田:いや、知らなかったですね。それもけっこうショックでした(笑)。
(一同笑)
■あんな物知りっぽい感じなのにね(笑)。
下田:音とかスタイルとかシンパシーを感じるところがあったので、名前くらいは知っているかなと思ったんですけど知らなかったんですよね。事務所の社長さんがすごく知っていてくれて。だからたぶん説得してくれたのかなと(笑)。でもちゃんと音を聴いての判断だとは思うので、やってくれて良かったですよ。
■ニップスさんはやっぱりって感じですよね(笑)。
下田:そうですね(笑)。
■ニップスさんはある意味サイレント・ポエツとは対極ですよね。
下田:本当にそうですよね。でもやりたがってくれるんですよね。それが本当に嬉しくて。このアルバムでもあの曲はかなり効いていますもんね(笑)。いい意味で変わっていなかったですね。
■そうですよね。意外と90年代にサイレント・ポエツを聴いていた人たちもこういうアルバムが聴きたかったんじゃないのかなと思ったんですよ。
下田:ああ、たしかにね。
■90年代のポエツはもっとスマートな存在で、海外志向が強かったじゃないですか。リミキサーやフィーチャリングのシンガーもだいたい海外勢だったし、あんまり日本のことは考えていなかったでしょう?
下田:そうなんですよ。自分が洋楽で育ったこともあるんですけど CDやレコードを出したときに海外のレコード屋さんの「S」の棚に入っているものを作るというのが当たり前に思ってやっていたので、邦楽とか日本でどうのということは全然考えていなかったというか(笑)。でもいまはもうあっちでも(日本の音楽は)なんでも聴けちゃうじゃないですか。だからそこまで思わなくなりましたけどね。今回はいままで周りで応援してくれていた人とか、「まだ出さないの?」ってずっと言ってくれていた人に向けてというところはけっこうあります。その人たちに「やっとできました」と言えるものを作りたいなという気持ちもけっこうあって、だから人選の幅も広がったのかもしれないですね。
■ご自身でもそこは抜けた感じはありますか?
下田:やっと抜け出せた感じはありますね(笑)。
(一同笑)
下田:やっとちょっと顔を出せたかなと。本当に潜っていましたからね。これからは潜らないようにちょっと顔を出していきたいと思います(笑)。でもなんとなく今回やってみて次のこととかを考えるようになったので、次はこんなことをしようとか、今回やり残したことがあるなとか、いろいろ思っているので次はやれそうな感じがします(笑)。前は出したらしばらくはいいやって感じだったんですけど、あまりにも(出さない期間が)長かったので。ちょっと頑張ります(笑)。
[[SplitPage]]いまの新しい世代で本当にかっこいいと思えるのはD.A.N.くらいじゃないかなと思って。しかし彼はサイレント・ポエツを知らなかった。それもけっこうショックでしたね(笑)。
■ちょっと話は戻りますが、この12年間はずっと仕事をして……
下田:そうですね、仕事はしていましたけど(笑)。普通に仕事をしてダラダラとしていましたね。
■お子さんは?
下田:子どもはいるんですけど、離婚もしまして(笑)。そういうのもあったんですよね。
■それは大変でしたね。
下田:子どもももう高校生ですね。今度2年生になります。
■大きいじゃないですか! 会いますか?
下田:1ヵ月に1回くらいは会ってます。バンドやってベースも弾いてるみたいです。
■『dawn』も聴いているんですか?
下田:聴いてますよ。今回タワーレコードさんの“NO MUSIC, NO LIFE.”のポスターも展開していただいているんですけど、それを子どもが「見に行ったよ」ってメールをくれて。
■へえー!
下田:「この人なにやってんだろう」と思っていただろうから良かったです(笑)。
(一同笑)
■いやあ、みんな苦労してるなぁ。ぼくも他人事じゃない(笑)。
(一同笑)
下田:そうですよねえ。
■いまいくつなんですか?
下田:いまは51才になったんですよ。
■自慢じゃないけど俺なんて54だから……50代キツイっす。
(一同笑)
■てっきり下田くんは順風な人生を歩んでいいるのかと……。
下田:みなさんそういうふうに言ってくださるんですけど、もう全然脱線していっていますからね。いまだにそういうイメージを持たれているんですね(笑)。
■やっぱりヴィジュアルがビシッとしているから(笑)。
下田:デザインだけは絶対カッコよくなきゃいけないと思うんで。
 Silent Poets dawn Another Trip |
■今回のアルバム・ジャケットの写真は砂漠ですか?
下田:これはアメリカにホワイト・サンズという白い砂の大きな砂漠があって、そこで昔から写真を撮ってくれていた内田くんが10年くらい前に撮りに行った写真を使わせていただいたんですよね。
■この砂漠の写真というのは自分のイメージと合ったんですか?
下田:合ってますね。写真を使わせてほしいと相談しに行ったら、「これがいいんじゃない?」って出してきたのがこれだったんですね。でも本当にバッチリだなと思って。
■それは誰もいないイメージみたいなことですか?
下田:そうですね。この写真って見ようによっては夜が明けて人が1人で歩いて帰ってきた、みたいな感じにも見えるじゃないですか(笑)。
■なるほど(笑)。砂漠を歩いてきたというイメージですね。今日はありがとうございました。久しぶりに話せた楽しかったです。
(了)