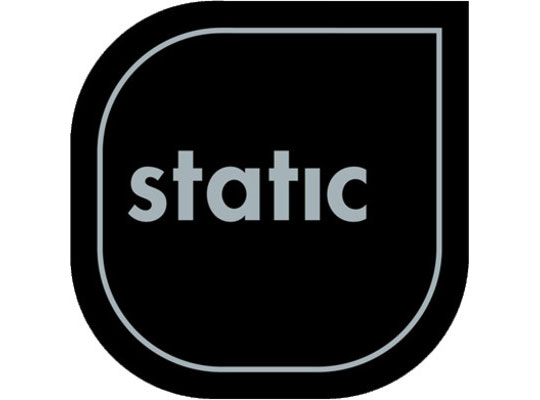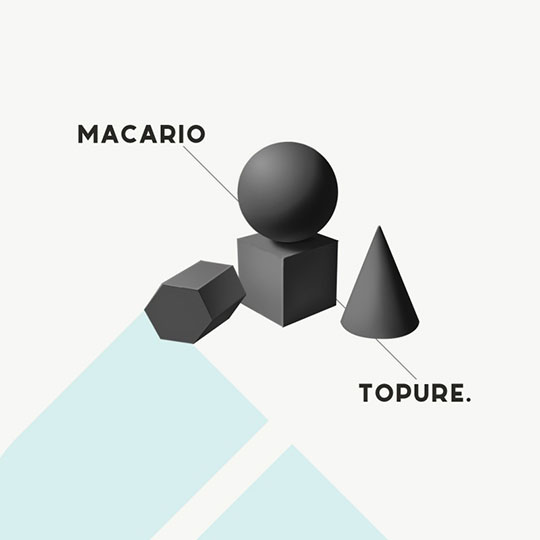アンドリュー・カーシー。無精ひげの男(ミスター・スクラフ)と名乗る男が6年ぶりのアルバム『フレンドリー・バクテリア』を発表する。変わらないというか、そもそも変わる必要もないと言ったほうがいいだろう。ミスター・スクラフは、流行り廃りなどに惑わされることなく、相変わらず我が道を進み続けている。
ミスター・スクラフは、1990年代半ばから作品を出し続けているヴェテランであるが、アルバムに関してはまだ4枚しか出していない。にも関わらず、彼がいまでも人気のあるDJ/プロデューサーであり続ているのは、そのサウンドに経年劣化することのない魅力があるからだ。
ミスター・スクラフのサウンドは単純に言って、楽しい。ソウル、ファンク、ディスコ、ヒップホップ、テクノ、ハウス、エレクトロ……、さまざまな音楽がミックスされている。エクレクティックでオールドスクールなフレーヴァーも彼のサウンドの特徴といえるが、人懐っこさとユーモア、小躍りしたくなる楽しげなメロディとファンキーなグルーヴ。彼自身が手がけるあの可愛らしいドローイングのように、遊び心がある。
 Mr. Scruff Friendly Bacteria Ninja Tune/ビート |
変わらないということは、最新アルバム『フレンドリー・バクテリア』は、つまり相変わらずの傑作ということだ。
もちろん新たな試みも聴くことができる。1曲目の“ステレオ・ブレス”や“フレンドリー・バクテリア”でのアグレッシヴなベースラインはあほくさいEDMを軽々と破壊するだろう。ゲストも人選も良い。シネマティック・オーケストラのベーシストであるフィル・フランス、ディーゴとのプロジェクトで再び注目を集めているカイディ・テイタム、5曲で素晴らしいヴォーカルを披露しているデニス・ジョーンズ、トランペット奏者のマシュー・ハッセル、さらにはハウス界のレジェンド、ロバート・オーウェンスとのコラボも本作の聴きどころだ。
一時期は販売も手がけていほどの大の紅茶好きとしても知られる彼は、いまマンチェスターで〈ティーカップ〉というカフェを運営している。DJ活動も順調に続けている。紅茶と音楽と家族と仲間たちに囲まれた暮らし。『フレンドリー・バクテリア』とは、まさに、そうした場所から響いてくる音楽だ。
多くの人たちにとって、1988年はアシッド・ハウスを発見した年だったかもしれないけれど、僕にとってはいつもと変わらないただの夏だった。僕は16歳で、学校を中退した年だったけどね(笑)。
■この前の2月で42歳になられたかと思います。
ミスター・スクラフ(以下、MS):はははは、そうだよ。
■あなたがDJをはじめたのは12歳の頃だから、もう30年以上も続けていることになりますね。音楽をはじめた当時、30年後も音楽をやり続けているというヴィジョンはありましたか?
MS:うん、その頃から、この先もずっと音楽をやっていくんだろうと思っていたよ。単純な理由だよ。音楽をやっていると心から楽しい。だから歳をとったからって、そんな楽しいことをやめられるわけがないってこと。音楽を止めようと思ったことは、これまで一度もない。
■これまでのご自身の人生を振り返ってみて、最も幸せに感じてることを教えてください。
MS:そうだな、心の底から楽しいと思えること、つまり音楽を仕事にすることができているということ。あと結婚して可愛い娘がいること、それもとても幸せに感じている。
■お子さんを授かったことで、あなた自身に何か変化はありましたか?
MS:もちろん、あったよ。毎日が音楽だけの人生ではなくなり、リアルな生活という観点から物事を見ることができるようになった。そうやって自分に新しい視点が生まれたことは、とてもよいことだと思っている。音楽を作るうえで、音楽以外のものから影響を受けたり、学んだりすることは、大事なことだからね。また〈ニンジャ・チューン〉に所属していることも幸せだ。〈ニンジャ・チューン〉とはもうずいぶん長い付き合いになる。僕にとっての幸せとは、自分の求める生活ができること、仕事やコミュニケーションが上手くいく人を見つけること、またそうした人たちをリスペクトすることだ。そういったベースが固まったら、学び続け、革新し続け、前進すればいい。
■逆にこれまでの人生で後悔していることってありますか?
MS:学校でもっと努力すればよかったと思っている。もっと多くの言語を学べばよかった。この15年間、ツアーで世界中をまわってきたけど、英語圏以外の国では現地の人が僕に合わせて英語を話さなくてはいけないから、いつも申し訳ないと思っている。自分が怠け者のような気になるんだ。もちろん、これからでも学ぶことができるけど、大人になると言語を取得するのが難しくなる。このことにもっと早く気づきたかったな。
■長く音楽をやり続けるための秘訣のようなものがあれば教えてください。
MS:いちばん大切なことは、自分を駆り立てることだ。それから自分の直観を信じること。他人が何を好むか、あるいは自分が何を求められているか、そうしたことを知っていることは悪いことではない。僕の場合、例えばそれは“Get A Move On”のような曲であって、あのようなタイプの曲を好むリスナーが多いということも知っている。が、同じようなことを繰り返しやるべきではない。作曲するとき、パフォーマンスするとき、DJするとき……、それらに共通して必要なのは、まず自分がエキサイトできるかどうかだ。他人の期待に合わせ、自分を作りあげていくと、同じことを繰り返してしまい、エキサイティングでなくなってしまう。エキサイティングでなくなってしまうと、ハッピーでなくなってしまう。だから自分をインスパイアさせ、エキサイトさせ、学び続けることが大切なんだ。
■なるほど。
MS:すべてを知りつくしたと思わないで、学び続ける。人生とは学びの連続だ。それは歳を重ねるごとにわかっていくものだと思う。そして、自分は一生かけてもすべてを知ることはできない、という事実を受け入れられるようになる。完全なものなどない。だから自分自身や自分の性格も受け入れられるようになる。そして、よりオープンになり、さまざまな影響を素直に受けることができ、他人から何を学べるかがわかるようになっていくのさ。

僕にとって大事なのは音楽の趣味を発展させていくことであり、音楽の趣味や知識を増やすのことだ。実際に当時よりも、今のほうが、興味のある音楽の種類が増えた。ある音楽スタイルについて知ると、その先をさらに知りたくなる。
■あなたがDJをはじめた80年代後半、まさに世はセカンド・サマー・オブ・ラヴの狂騒の真っ只中だったのではないかと思うのですが、あなたにとってそれはどのようなものでしたか?
MS:それって1988年のことかい? うーん、よいものだったと思うよ。1988年のマンチェスターといえば、〈ハシエンダ〉やアシッド・ハウスを思い出す人も多いだろうね。でも僕は当時16歳だったから、まだクラブに行ったことがなかったんだ。セカンド・サマー・オブ・ラヴは、パーティに遊びに行き、ドラッグをやって踊りまくるというのがメインだったけど、僕はそのどれもやっていなかった。家でラジオを聴いたり、レコードを買ったり、ミックステープを作ったりすることのほうに夢中だったんだ。
通訳:ではあのシーンは経験していないのですね。
MS:まったくない。8歳まで僕と音楽との接点は、レコード・ショップやラジオや雑誌に限定されていた。最初の10年は誰とも交流を持たず、ひたすら音楽を聴き続けながら、自分のスタイルを確立していったんだ。僕は1986年からアシッド・ハウスを聴いている。地元のレコード店にもシカゴからの輸入レコードがたくさん入荷されていたからね。リヴァプールやマンチェスターなどイギリス北部やスコットランドでは、シカゴ・ハウスやデトロイト・テクノは大きなブームだった。多くの人たちにとって、1988年はアシッド・ハウスを発見した年だったかもしれないけれど、僕にとってアシッド・ハウスはもうそんなに目新しいものではなかった。僕にとってセカンド・サマー・オブ・ラヴはいつもと変わらないただの夏にすぎなかった。僕は16歳で、学校を中退した年だったけどね(笑)。
■1995年のデビュー作「The Hocuspocus EP」を聴くと、いまのサウンドにも通じる部分が多くあり、すでにミスター・スクラフとしての音楽性が確立されているようにも感じます。そうした意味では、かなり早い時期に目指すべき音楽の方向性が固まっていたのではないかと思うのですが、ご自身としては、当時と比べ、音楽の趣味であったり、作るサウンドの方向性などが変わったと思いますか?
MS:いや、あまり変わってないと思う。ファースト・アルバム『ミスター・スクラフ』(1997年)をリリースした時点で、僕は10年くらいDJをやっていたし、レコーディングも8年、9年ほど経験していた。そうした中で、いろいろな音楽をミックスさせ、遊び心のあるサウンドを作りたいって方向性がすでにあった。その部分は当時もいまも変わらない。
ただ、その後も膨大な量の音楽を聴き続けてきた。さっきも話したように、自分を駆り立てながらね。僕にとって大事なのは音楽の趣味を発展させていくことであり、音楽の趣味や知識を増やすのことだ。実際に当時よりも、いまのほうが、興味のある音楽の種類が増えた。ある音楽スタイルについて知ると、その先をさらに知りたくなる。「このミュージシャンはどんな影響を受けたのだろう?」というように。僕の基礎や土台は当時も現在も同じ。ただヴィジョンが広がったということだと思うね。
■あなたが音楽制作をはじめた頃に比べると、音楽制作ツールも大きく変化していると思います。そうした環境や機材の変化があなたの音楽にもたらしたものがあるとすれば、それはどんなものですか?
MS:その点においても、あまり変化はないかな。僕は自分のスタイルを前進させきたけど、オールドスクールやルーツっぽいサウンドが好きだという核の部分は相変わらず変わらない。いろいろなスタイル、テンポ、雰囲気のサウンドを試みたとしても、いつも僕はある一定のサウンドにたどり着く。リスナーが聴いて「これはスクラフの曲だな」とわかるようなサウンドさ。自分でもはっきりとは認識していないけど、何かしらの要素が組み合わさり、バランスが取れて、生まれてくるサウンドなんだろうね。
■あなたらしいサウンドなるものを決定づける要素とは何だと思いますか?
MS:何がどうなってそれが生まれてくるのか、正直なところ、僕にもよくわからない。でも僕がいまラップトップで音楽を作ったとしても、そこにはきっとドラムマシーンを使ったオールドスクールなフレイヴァーを必ず注入するだろう。ラフで攻撃的なプロダクションが好きだからね。僕はいままだに古い機材もたくさん使っている。30年前の機材がまだ使えて、サウンドもいいなら、僕は喜んでそれを使うよ。アナログ・レコードだってかける。いまのところ最新の技術を常に把握する必要性は感じていない。きっとそんな自分の好みや趣向に導かれ、あのサウンドが出てくるんじゃないかな。
[[SplitPage]]マンチェスターのアーティストは海外へ出てショーをやったりするけど、地元を基盤にした活動もしっかりおこなっていて、マンチェスターにもちゃんと活気がある。いまだにたくさんのレジデント・パーティがあるしね。
■SoundCloudにDJミックスを大量にアップしていますよね。相変わらず精力的にDJをされているかと思います。膨大なコレクションをお持ちだと思いますが、レコードは買い続けているのですか?
MS:もちろん。レコードは買い続けている。比率は、新譜を2枚買ったら、中古を1枚買うという感じかな。レコードショップに行くときは、中古を買い求めにいくことが多いかな。
通訳:どういうジャンルのレコードが多いですか?
MS:オール・ジャンルさ(笑)。いまでも週に20枚から30枚のレコードを買っているよ。それらはあらゆるスタイルのものを網羅している。
通訳:ここ最近、新しいレコードであなたを夢中にさせたものは?
MS:何枚かある。〈エグロ・レコーズ(Eglo Records)〉から出たファティマの新しいアルバムは最高に素晴らしい。クアンティックの新しいアルバムもすごくいいね。あとフローティング・ポインツのニュー・シングルも相変わらずいい。カルバタ(Kalbata)とミックスモンスターのアルバムも最高だった。テルアビブの連中がジャマイカに行って、ハードコアなルーツ・レゲエを作った作品なんだけど、本当に素晴らしいよ。
■地元のマンチェスターで多くDJをされているようですが、マンチェスターのクラブ・ミュージック・シーンは現在どんな状況でしょうか?
MS:とてもいい。アーティストやレーベルの状況も健全だと思う。マンチェスターのアーティストは海外へ出てショーをやったりするけど、地元を基盤にした活動もしっかりおこなっていて、マンチェスターにもちゃんと活気がある。いまだにたくさんのレジデント・パーティがあるしね。僕もレジデントをやっている。オススメはイルム・スフィア(Illum Sphere)がレジデントを務める〈ホヤ・ホヤ(Hoya Hoya)〉という人気パーティ、それから〈ソー・フルート(So Flute)〉ってパーティだな。〈ソー・フルート〉は僕のパーティやホヤ・ホヤに影響を受けた若い連中がやっているパーティだ。ベース・ミュージックのパーティやレゲエのパーティ、アンダーグラウンド・ハウスのパーティ、インディ・ロックのパーティ、ニューウェイヴのパーティ……、本当にいろいろあるんだよ!
■マンチェスターのクラブ・シーンが活況であり続けている理由は何だと思いますか?
MS:音楽好きな若者が多いというのは理由のひとつとしてあるかもね。大学生も多いし、音楽が目当てでマンチェスターに来る人もいるし、クラブで騒ぐために集まってくる連中もいる。こうした若い人の中に、自分たちでクラブ・パーティをはじめたり、音楽をリリースしたり、レコード・レーベルを立ち上げたりするやつらがいる。毎年、大学に通う目的でマンチェスターには大勢の若い連中がやってくる。そのおかげで、マンチェスターは若い人が多く、活気に溢れている。若者の中には、マンチェスターが気に入って住み続ける人も少なくないし、音楽で生計を立てているやつらもたくさんいるんだ。
■あなたはマラソン・セットとも呼ばれる6時間近くに及ぶロング・セットを展開することでも知られてますが、あなたがロング・セットを好む理由を教えてください。
MS:理由はふたつある。まずはロング・セットというスタイルがオールドスクールであるから。僕がDJをはじめた頃は、DJはみんなオールナイトでDJし、いろいろなスタイルの音楽をかけていた。僕はいろいろなスタイルの音楽をかけるのが好きだから、短いセットだと窮屈に感じてしまうんだ。たくさんのジャンルを短い時間の中でかけようとすると無理が生まれるだろ。1曲1曲をちょいちょい聴かせるというよりは、ひと晩のDJを通して長い物語のようにプレイしたいんだ。
■もうひとつの理由は?
MS:早い時間に、ウォームアップみたいな感じでプレイするのも好きなんだ。夜の早い時間にメロウな曲をかけるのも好きだし、夜の遅い時間にクレイジーな曲をかけるのも好きさ。どっちもやろうとしたら、ずっとやるのがいちばんいい(笑)。それにロングセットをやると、クラブ・ミュージックだけをかけなくてもいい。ジャズやフォークのようなメロウな音楽をかけたかったら、夜のどこかの時点でその音楽がしっくりくるタイミングがある。僕はいままでずっとオールナイトでDJしてきた。だから僕にとってはそれが普通なことで、特別なこととは思っていない。自分が一番上手くDJできると感じられるのがロングセットなんだ。
通訳:DJをするときに最も大事にしていることは?
MS:よいレコードを正しい順番でかけること。それからクラウドをよく見ていること。
■フローティング・ポインツと一緒にバック・トゥ・バックでプレイされているようですが、彼とはどのような交流があるのですか?
MS:彼に会ったのは5、6年前。彼の音楽がとても気に入ったから、僕からメールしたんだ。彼はまだ若いけど、音楽に対する見方はとても成熟している。多くのジャンルに興味を持っていて、プロデューサー、作曲家としても素晴らしい。DJとしての姿勢も好きだ。彼は変わった音楽や古い音楽をプレイし、人をワクワクさせることができる。一緒にDJをするには最適な人だ。バック・トゥ・バックをするとき、もうひとりのDJがヒット・チューンばかりかけていると、DJ体験としては退屈なものになってしまう。が、彼の場合、かける音楽が実に幅広いから、一緒にやっていて面白いだ。とても刺激されるし、勉強になるよ。
■2009年の話なのでだいぶ前ですが、あなたがBBCの『Essential Mix 2009』をやったときに、トーマス・バンガルターの“On Da Rocks”を入れていましたが、あなたの作るファンキーなグルーヴのヒントがあるような気がして、とても興味深かったです。Rouleに代表されるあの当時のフレンチ・ハウスは好きでしたか?
MS:ああ、好きなものもあったよ。ボブ・サンクラーやモーターベース、ダフトパンク、トーマス・バンガルター、エティエンヌ・ド・クレイシー、ペペ・ブラドックなどのフレンチ・ハウスのレコードは大好きだった。彼らはよい音楽を作った。なかでもトーマス・バンガルターの“オン・ダ・ロックス(On Da Rocks)”は実にユニークな曲だ。シンプルでキャッチーで、それに他のハウスよりも少しテンポがゆっくりだよね。何よりもみんなが聴いて楽しめる曲。僕からすると、ダフトパンクのどの作品よりも“オン・ダ・ロックス”のほうが優れていると思う。1999年にリリースされたときはあのレコードをかけたけど、いまでもかける。僕にとってはスペシャルでクラシックな曲だ。ディスコの要素が強いから、ハウスとミックスしても合うし、アフロビートのレコードやその他のさまざまな音楽とミックスできる。僕にとっては汎用性のある、本当にクラシックな1枚だよ。
紅茶はイギリスではとても大切なものだ。紅茶はイギリス人にとって身近で大切なものであるにも関わらず、多くのイギリス人は紅茶についてあまりよく知らない。だが、カップにティーバッグを入れて紅茶を飲む。それって、何か安心するんだよね。紅茶は気分をほっとさせてくれるし、よい気分にもさせてくれる。
■今回の『フレンドリー・バクテリア』は、オリジナル・アルバムとしては2008年の『ニンジャ・ツナ』以来の作品になるわけですが、その間、主にどのような活動、生活をして過ごされていたのですか?
MS:DJギグをやったり、忙しく過ごしていた。それから3年前、娘が生れた。それもあっていろいろと忙しかった。スタジオで過ごす時間もたくさんあったけど、他のことで忙しいと、大きなプロジェクトを完成させるのに時間がかかってしまう。
1年くらい前かな、〈ニンジャ・チューン〉に言われたんだ。「そろそろアルバムを完成させたらどうだい?」ってね。「オッケー」と即答したよ。〈ニンジャ・チューン〉は僕にいつもメロウに接してくれる。抱えているアーティストが多いからかもしれないけれど、僕に変なプレッシャーをかけてくることなんてなかった。だから、彼らが少しプレッシャーをかけてきたときは「はい、やります」と素直に返事をしたよ。誰かに指示されることは時にはよいことだ。それで僕はスタジオに入ってアルバムを完成させたというわけさ。
■音楽を作るときのインスピレーションはどのようなものから?
MS:アイディアは、サンプル、ドラムループ、ベースライン、メロディをハミングした時、あるいは友だちとの会話から生まれることもある。そうしたひらめきをヒントにして、サウンドを作り、自分がワクワクしてきたら、だいたいいい曲ができあがるものだ。
■あなたの曲名やアルバム名はいつもユニークものが多いですよね。今回のアルバム・タイトルである『フレンドリー・バクテリア』の由来について教えてください。
MS:僕は違うスタイルの音楽や違うサウンド、年代の違うサウンド同士を組み合わせるのが好きなんだ。その組み合わせによって、リスナーを笑顔にさせるという反応を起こすことができる。僕は音楽のこの効果をとても気に入っていてね。これは言葉でも可能なことで、変わった感じの言葉の組み合わせから、詳しい説明はなくても、想像力が働き、ユーモアが感じられ、笑ったりほほ笑んだりしてしまうものがある。僕は曲名でもこういうことをするのが好きなのさ。説明する必要もない、単なる言葉遊び。僕はサウンドで遊ぶのが好きなのと同じように、言葉で遊ぶのも好きなんだ。
■本作には「フレンドリー・バクテリア」のようにゴリゴリのシンセ・ベースを使った曲から、最後の“フィール・フリー”のようなジャジーでメロウな曲まで、さまざまなタイプの楽曲が並んでいますが、今回の『フレンドリー・バクテリア』のサウンドにおいて、何かコンセプトめいたものはあったのでしょうか?
MS:コンセプトというほどのものはとくにないけど、デニス・ジョーンズと一緒に作った曲がアルバム全体の土台になっていると思う。今回のアルバムには彼と作った曲が5曲も入っている。曲単位ではいろいろなタイプのものが収録されているけれど、僕とデニスで一緒に曲を作っていた時、ある特定のサウンドを想定して曲を書いていた。アルバムの他の曲は、そのサウンドに合うものを選んだり、そのサウンドに合うように作られた。もちろんヴァラエティ豊かなアルバムにしたいということも考えていたけど。DJをしているときやアルバムを作るとき、僕が大切にしているのは、たくさんのスタイルを取り入れると同時に、それらが一緒になったときにしっくりときて、一貫性が感じられるということだ。僕はDJしているときは、毎回それをしているから、アルバムを通して、多くのスタイルを網羅するのは、自分にとっては自然なことなんだ。普段からDJしているから、アルバムをまとめるの作業には慣れている。
■本作にはザ・シネマティック・オーケストラの主要メンバーとして知られるフィル・フランスやカイディ・テイタムといった豪華なミュージシャンたちが参加しています。本作で彼らを必要とした理由を教えてください。
MS:僕が共演した人たちのほとんどは、仲の良い友人たちだ。みんなお互いに尊敬し合っている。僕は彼らの音楽がすごく好きだし、彼らは僕の音楽を気に入ってくれている。コラボレーションは、自分のサウンドを発展させるよい機会だと思う。自分とは違う考えを持つ他の人と一緒に作業するから、スタジオでも常に違ったことをトライしてみることになる。サンプルをあまり使わない場合は、ミュージシャンと一緒に仕事をするのがいちばんだね。ひとりですべての作業をしていると、ときに一歩下がって客観的に自分の音楽を見るのが難しくなる。他の人と仕事していると、自分の音楽を新しい視点から見ることができて楽しいね。
■トランペット奏者のマシュー・ハッセル(Matthew Halsall)も素晴らしい演奏を披露していますね。
MS:彼は偉大なトランペット演奏者であり作曲家だ。彼のスピリチャル・ジャズのリリースは本当に素晴らしい。彼とも今後たくさんのコラボレーションをやる予定だ。マシュー・ハッセル、フィル・フランス、デニス・ジョーンズは、お互い面識もあり、マンチェスターのミュージシャン集団として一緒にプレイしている。すでに顔見知りの人たちと一緒に仕事をするのは素敵なことだよ。みんな各自でプロジェクトをやっていて、それが上手くいっているから、みんなが集まると、発想が自由になり、特別で変わったものを作ろうということになる。
■このところ、IGカルチャーとバグズ・イン・ジ・アティック(Bugz in the Attic)のアレックスによるネームブランドサウンド(NameBrandSound)が〈ニンジャ・チューン〉から出たり、フローティング・ポインツのレーベル〈エグロ・レコーズ〉からはディーゴ・アンド・カイディ(Dego And Kaidi)が出したり、かつてブロークンビーツを盛り上げたヴェテラン勢たちの活躍が目立ちますが、このあたりの動きには注目してますか?
MS:もちろんだよ。ブロークンビーツというのは、ソウルやジャズ、ファンク、テクノ、ドラムンベースなど、本当にたくさんの音楽の影響を受けている音楽だ。僕は古い音楽のフレイヴァーを持った新しい音楽が大好きだ。いま名前の挙がった人たち、とくにディーゴなどは、これまでにいろいろな種類の音楽をやってきた。テクノもやったし、ハウスもやった、ドラム&ベースもやったし、ヒップホップやソウルのリリースもあった。ブロークンビーツとは彼が作ってきたいろいろなスタイルの音楽の総称のようなものだ。ディーゴ・アンド・カイディは去年、素晴らしい12インチをリリースしたし、今後はセオ・パリッシュと曲を作り〈サウンド・シグネイチャー〉からリリースする予定になっている。それもきっと素晴らしいものになるはずだ。ディーゴ・アンド・カイディは〈エグロ・レコーズ〉からも作品を発表していて、それも最高だった。カイディはGフォースと新しいレーベルを立ち上げるみたいだしね。
■そのあたりのサウンドはこれからまた面白くなっていきそうですね。
MS:みんな、長年音楽を作ってきた才能ある人たちだ。メロディやリズムを聴きわけるよい耳の持ち主だし、音楽の素晴らしさを知っている連中ばかりだ。だから彼らの動きは僕にとってもとてもエキサイティングなことだよ。ブロークンビーツのシーンがなくなってしまったのは残念だったけどね。ブロークンビーツシーンは、バグス・イン・ジ・アティック(Bugz in the Attic)が〈ヴァージン〉からアルバムをリリースしたときに途絶えてしまったと思っている。それからブロークンビーツの主なディストリビュータであったゴヤが閉鎖してしまって、彼らのような人たちがレコードをリリースするのが難しくなってしまった。だから、ヴェテラン勢が戻ってきて、音楽をたくさん作ってくれるのは素晴らしいことだと思うよ。
■“He Don't”でロバート・オウエンズを起用した理由について教えてください。
MS:ロバートは素晴らしい声の持ち主だ。彼の声を初めて聴いたのは1986年、僕が14歳のときだった。「ブリング・ダウン・ザ・ウォールズ(Bring Down the Walls)」など、当時、彼がラリー・ハードと一緒に音楽を作っていた頃の作品さ。彼のシンプルでエモーショナルなヴォーカルのスタイルが大好きなんだ。彼は僕にとっても伝説的存在だよ。
■一緒にやってみてどうでしたか?
MS:“He Don't”のトラックを作ったとき、僕の頭のなかではもうすでにロバートが歌っていた(笑)。この曲には彼しかいないって感じだった。僕はすぐに彼に連絡を取り、彼自身も“He Don't”を聴いて、自分が歌っている姿を想像できるかどうかってきいたんだ。その後、彼に曲を送ったら、数時間後に返信があって「イエス」と言ってくれた。「自分でも歌っている姿が想像できる」と。それで一緒にスタジオに入ることになった。すべてがスピーディに進んだ。今までロバートには会ったことがなかったんだ。彼のレコードはたくさん持っているけどね。ラリー・ハードと一緒に作ったものやコールドカットとの作品やフォーテックとの作品など。彼は本当に才能豊かなインスピレーションを与えてくれる最高のヴォーカリストだ。
■いまさらですが、あなたが描くあのかわいいキャラクターはどのようにして生まれたのですか?
MS:僕が若いころ、15歳だったかな、いつも落書きをしてた。子供の頃から絵を描くのが好きだった。その絵がじょじょにシンプルさを増していった。そして、今の形、つまり目と口と体と手足が2本ずつ、になった。子供の落書きがそのまま変わらず今も残っているというわけさ。
■あなたは自ら紅茶の販売を手がけるくらい、紅茶に思い入れがあるかと思います。あなたにとって紅茶とはどんなものなのですか?
MS:紅茶はイギリスではとても大切なものだ。自分で作った紅茶の会社はもう手放してしまったけど、いまはマンチェスターでカフェを経営しているよ。「Tea Cup」という名前のカフェで、おいしい紅茶を出している(笑)。紅茶はイギリス人にとって身近で大切なものであるにも関わらず、多くのイギリス人は紅茶についてあまりよく知らない。日本にもお茶のカルチャーがあると思うけど、日本ほどにはイギリス人の飲み方は洗練されていない。だが(日本とは違う種類の情熱だけれども)イギリス人もお茶が好きだ。僕はそういうイギリス人の感じも嫌いじゃなくてね。カップにティーバッグを入れて紅茶を飲む。それって、何か安心するんだよね。紅茶は気分をほっとさせてくれるし、よい気分にもさせてくれる。友だちと一緒に紅茶を飲むときも、仕事中にひとりで飲むときも、紅茶は日常においてスペシャルな時間を提供してくれる。多くのイギリス人がそんな感じで紅茶を愛していると思うよ。
■最後になりますが、次のアルバムはいつ頃の予定でしょうか?
MS:2020年までにはリリースしたいと思っているよ。今回、久しぶりにアルバムを作り、、そのための作業が自分にとってどんなに楽しいことなのか改めて感じることができた。すでにデニス・ジョーンズとも、このアルバムのツアーが終わったら、すぐにまたスタジオに入り、新しい曲を一緒に作りはじめようという話をしている。だから、まあ、今回のリリースにかかった時間によりも早く、次のアルバムは出せると思うな。このアルバムの作業は本当に楽しかった。とくに他の人とのコラボレーションはインスピレーションも得られ、刺激的な仕事だった。今後もコラボレーションはたくさんやっていくと思うよ。楽しみに待っていてくれ。

 ハウス、ブレイクビーツの影響を受け、89年からDJ活動を開始。海賊放送やレイヴで活躍、ハードコア~ジャングル/ドラム&ベースの制作をはじめる。95年にGanjaから"Super Sharp Shooter"の大ヒットを放ち、96年にはDJ HYPE、PASCALと共にレーベル、True Playazを設立、ファンキービーツとバウンシーかつディープなベースラインで独自のスタイルを築く。00年の“138 Trek"は自己のレーベル、Bingo Beatsに発展、ブレイクステップの新領域を開き、2ステップ~グライムやブレイクス・シーンに多大な影響を与える。03年にはPolydorから1st.アルバム『 FASTER』を発表。09年以降、“Crack House”と銘打ったZINC自身が提唱する新型サウンドを布教。“Crack House”はBasslineサウンドを主体として、エレクトロ、ダブステップ、フィジェットハウス、ブレイクス、ジャングル等をミクスチャーした最先鋭のエレクトロ・ダンスミュージック。MS DYNAMITEをフィーチャーした10年の"Wile Out"はアンセムとなる。近年はA-TRAKとの共作をはじめ、自身のSoundcloudで新曲を続々とフリー・ダウンロードで挙げ、多大な支持を得ている。毎週金曜にRinse FMでオンエア。
ハウス、ブレイクビーツの影響を受け、89年からDJ活動を開始。海賊放送やレイヴで活躍、ハードコア~ジャングル/ドラム&ベースの制作をはじめる。95年にGanjaから"Super Sharp Shooter"の大ヒットを放ち、96年にはDJ HYPE、PASCALと共にレーベル、True Playazを設立、ファンキービーツとバウンシーかつディープなベースラインで独自のスタイルを築く。00年の“138 Trek"は自己のレーベル、Bingo Beatsに発展、ブレイクステップの新領域を開き、2ステップ~グライムやブレイクス・シーンに多大な影響を与える。03年にはPolydorから1st.アルバム『 FASTER』を発表。09年以降、“Crack House”と銘打ったZINC自身が提唱する新型サウンドを布教。“Crack House”はBasslineサウンドを主体として、エレクトロ、ダブステップ、フィジェットハウス、ブレイクス、ジャングル等をミクスチャーした最先鋭のエレクトロ・ダンスミュージック。MS DYNAMITEをフィーチャーした10年の"Wile Out"はアンセムとなる。近年はA-TRAKとの共作をはじめ、自身のSoundcloudで新曲を続々とフリー・ダウンロードで挙げ、多大な支持を得ている。毎週金曜にRinse FMでオンエア。 ディープ&ドープな最重量ベース・サウンドでダブステップの真髄を表現する"King of Wobble Bass"、LOEFAH。90年代ロンドンのレイヴ・シーンでハードコア~ジャングル/ドラム&ベースを体感し、4HEROのReinforced、GOLDIEのMetalheadzからの作品群にインスパイアされる。2000年頃には古いダブ、レアグルーヴ、ソウル、ヒップホップを再発見し、音楽的基礎を広げる。やがて友人のDIGITAL MYSTIKZのMALA&COKIと音を作り始め、138bpmでダビーなトラックを作る等、様々な実験を繰り返す。04年にはDIGITAL MYSTIKZとレーベル、DMZを旗揚げし、"Dubsession"、"Twisup"を発表。またBig Appleから"Jungle Infiltrator"、Tempaから"Truly Dread"、Rephlexからのコンピ『GRIME 2』では3曲フィーチャーされる等、彼の存在がダブステップと共に脚光を浴びる。その後もDMZを始め、Tectonic等からフロアーフィラーを連発する。09年からは自己のレーベル、Swamp 81を設立、ポスト・ダブステップの潮流を開き、エレクトロ、ハウス、テクノ、ガラージ、ゲットー等を奔放にmix。BODDIKA、JOY ORBISON、ZED BIASらを擁し、UKベース・シーンの要塞となっている。
ディープ&ドープな最重量ベース・サウンドでダブステップの真髄を表現する"King of Wobble Bass"、LOEFAH。90年代ロンドンのレイヴ・シーンでハードコア~ジャングル/ドラム&ベースを体感し、4HEROのReinforced、GOLDIEのMetalheadzからの作品群にインスパイアされる。2000年頃には古いダブ、レアグルーヴ、ソウル、ヒップホップを再発見し、音楽的基礎を広げる。やがて友人のDIGITAL MYSTIKZのMALA&COKIと音を作り始め、138bpmでダビーなトラックを作る等、様々な実験を繰り返す。04年にはDIGITAL MYSTIKZとレーベル、DMZを旗揚げし、"Dubsession"、"Twisup"を発表。またBig Appleから"Jungle Infiltrator"、Tempaから"Truly Dread"、Rephlexからのコンピ『GRIME 2』では3曲フィーチャーされる等、彼の存在がダブステップと共に脚光を浴びる。その後もDMZを始め、Tectonic等からフロアーフィラーを連発する。09年からは自己のレーベル、Swamp 81を設立、ポスト・ダブステップの潮流を開き、エレクトロ、ハウス、テクノ、ガラージ、ゲットー等を奔放にmix。BODDIKA、JOY ORBISON、ZED BIASらを擁し、UKベース・シーンの要塞となっている。 ミキシングを自在に操り、様々なアプローチで ダンスミュージックを生み出すサウンド・オ リジネイター。03年に1st.アルバム『GOTH-TRAD』を発表。国内、ヨーロッパを中心に海外ツアーを始める。05年には 2nd.アルバム『THE INVERTED PERSPECTIVE』をリリース。また同年"Mad Rave"と称した新たなダンスミュージックへのアプローチを打ち出し、3rd.アルバム『MAD RAVER'S DANCE FLOOR』を発表。06年には自身のパーティー「Back To Chill」を開始する。『MAD RAVER'S~』収録曲"Back To Chill"が本場ロンドンの DUBSTEP シーンで話題となり、07年にUKのレーベル、SKUD BEATから『Back To Chill EP』、MALAが主宰するDEEP MEDi MUSIKから"Cut End/Flags"をリリース。12年2月、DEEP MEDiから待望のニューアルバム『NEW EPOCH』を発表、斬新かつルーツに根差した音楽性に世界が驚愕し、精力的なツアーで各地を席巻している。
ミキシングを自在に操り、様々なアプローチで ダンスミュージックを生み出すサウンド・オ リジネイター。03年に1st.アルバム『GOTH-TRAD』を発表。国内、ヨーロッパを中心に海外ツアーを始める。05年には 2nd.アルバム『THE INVERTED PERSPECTIVE』をリリース。また同年"Mad Rave"と称した新たなダンスミュージックへのアプローチを打ち出し、3rd.アルバム『MAD RAVER'S DANCE FLOOR』を発表。06年には自身のパーティー「Back To Chill」を開始する。『MAD RAVER'S~』収録曲"Back To Chill"が本場ロンドンの DUBSTEP シーンで話題となり、07年にUKのレーベル、SKUD BEATから『Back To Chill EP』、MALAが主宰するDEEP MEDi MUSIKから"Cut End/Flags"をリリース。12年2月、DEEP MEDiから待望のニューアルバム『NEW EPOCH』を発表、斬新かつルーツに根差した音楽性に世界が驚愕し、精力的なツアーで各地を席巻している。









 メインステージの前でくつろぐ参加者たち。芝生でリラックス © Elisa Lemus
メインステージの前でくつろぐ参加者たち。芝生でリラックス © Elisa Lemus 楽器販売のブース © Miho Nagaya
楽器販売のブース © Miho Nagaya 雑貨とレモネードを販売するブース © Miho Nagaya
雑貨とレモネードを販売するブース © Miho Nagaya  ブランコもあった © Miho Nagaya"
ブランコもあった © Miho Nagaya"  フードトラックが並び、充実した各国料理が食べられる © Miho Nagaya"
フードトラックが並び、充実した各国料理が食べられる © Miho Nagaya" VANSが提供するスケート用ランページも © Miho Nagaya
VANSが提供するスケート用ランページも © Miho Nagaya ティファナ出身のフォークシンガー、Late Nite Howl © Miho Nagaya
ティファナ出身のフォークシンガー、Late Nite Howl © Miho Nagaya 雑誌VICEの音楽プログラム、NOISEYが提供するステージ © Miho Nagaya
雑誌VICEの音楽プログラム、NOISEYが提供するステージ © Miho Nagaya メヒカリ出身の新鋭テクノアーティストTrillones © Elisa Lemus
メヒカリ出身の新鋭テクノアーティストTrillones © Elisa Lemus 会場はペットフレンドリー © Miho Nagaya
会場はペットフレンドリー © Miho Nagaya NRMALのスタッフたちは黒尽くめでクール © Miho Nagaya
NRMALのスタッフたちは黒尽くめでクール © Miho Nagaya マティアス・アグアヨとモストロのステージが始まる頃には満員に © Elisa Lemus
マティアス・アグアヨとモストロのステージが始まる頃には満員に © Elisa Lemus マティアス・アグアヨ © Miho Nagaya
マティアス・アグアヨ © Miho Nagaya コロンビアのLa mini TK del miedo © Elisa Lemus
コロンビアのLa mini TK del miedo © Elisa Lemus