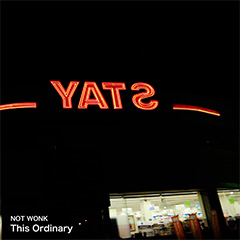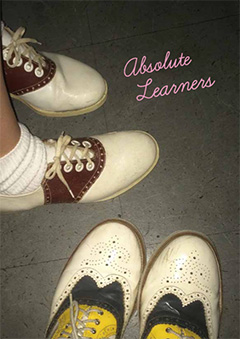2011年の9月、グラスゴーの小さなフェスでモグワイのライヴを見る機会があった。デリック・メイからジ・オーブ、ワイルド・ビースツなどのジャンル、新旧織り混ざったラインナップ、さらにザ・フォールの次という出番のなか、堂々とメイン・ステージの大トリを務めていた。ステージ上にはファンには馴染み深いセルティックのタオル、エフェクター、そしてスコットランドの国旗のシールが貼られたギター。客席にはスコティッシュ・アクセントで騒ぐ、スコティッシュ・ピープルたち。「荘厳」や「轟音」といったモグワイにかぶさる常套句ももちろん当てはまるライヴだったが、サウスロンドンのグライムMCが畳み掛けるような息づかいで自分の団地についてラップするのを聴いたときのような、圧倒的なローカリティに打ちのめされた夜として記憶に残っている。
その年に出たアルバムは『ハードコアは死ぬことはないが、お前はちがう(Hardcore Will Never Die, But You Will)』だったが、彼らはそこにシリアスな意味を込めたわけではない。モグワイは2015年に結成20周年を迎えた平均年齢40歳のレペゼン・グラスゴーの「ヤング・チーム」だが、その20年という短くない期間において、彼らはこれまで音楽について、またそれ以外の事柄についても、あまり深くは語ってこなかったし、言葉を使うときは、シンプルなイメージ表現かジョークかのどちらかだったように思う。モグワイを取材した経験のある先輩ライターが「モグワイって音を聴くと思慮深そうだけど、メンバーはそこまで考えているわけでもない」なんて言っているのを聞いたこともある。音楽がすべてを語っていると言えば、それまでなのだが。
だが近年のモグワイの活動を見ればわかるように、彼らの音や行動の裏には確固たるステートメントが存在しているようだ。2014年にスコットランドのUKからの独立を問う国民投票が行われ、独立派のカルチャー・アイコンとしてキャンペーンの先陣を切っていたのは、何を隠そうこのヤング・チームである。投票が近づくなか、彼らはインタヴューに応え、同郷のミュージシャンたちとライヴまでも行った。投票の結果、反対票が過半数を上回りスコットランドは独立することができなかったのだが、ギター上のナショナル・フラッグが一度もなびかなかったわけではない。彼らのホームであり、スコットランド一の人口を持つグラスゴーでは独立賛成票が過半数を超えていた。あの日、彼らの音楽は人々の声になっていた。
 Mogwai - Atomic Rock Action Records / ホステス |
10年代も折り返した2016年、モグワイから強烈な1枚『アトミック』が届いた。ドキュメンタリー作家マーク・カズンズがイギリスの公共放送BBCのために作成した、広島の原爆投下以降の原子力と人間の関係を描いた作品『アトミック・リヴィング・イン・ドレッド・アンド・プロミス(Atomic Living in Dread and Promise)』のサウンドトラックをモグワイが担当し、その楽曲を発展させアルバムに仕上げた作品というだけあって、楽曲の内容もタイトルも、いままで以上にヘヴィーだ。ドキュメンタリーにはヒロシマだけではなく、フクシマも出てくる。つまり、モグワイの音はスコットランドから遠くに住むわれわれにとっても無関係ではないのだ。何度も繰り返し聴くのには適さないかもしれないが、聴かないでいることはためらわれるアルバムである。
偶然にも米国オバマ大統領が広島を訪問した翌週、モグワイは『アトミック』を携え、広島を終着点とした日本ツアーを行った。取材に応じてくれたのは、チームのキーマンであるギターのスチュアート・ブレイスウェイトだ。彼らが考えてないって? まったくそんなことはなかった。原子力の特別な知識をいっさい使わず、「なんかおかしいよな」という素朴な疑問から編み出された彼のシンプルな言葉にはちゃんと切れ味がある。わからないことであっても閉口しないこと。2011年のあの日以来、列島の人々が学んだ教訓を彼の言葉から思い出す。六本木EXシアターの楽屋裏、スチュアートが口を開けば、そこはグラスゴーだった。
■MOGWAI / モグワイ
1995年にスチュアート(G)、ドミニク(B)、マーティン(Dr)、バリー(Vo,G, Key)によって結成されたグラスゴーの重鎮バンド。翌年、自身のレーベル〈ロック・アクション・レコード 〉 よりシングル「Tuner/Lower」でデビュー。数枚のシングルなどを経て、グラスゴーを代表するレーベル〈ケミカルアンダーグラウンド〉と契約、97年にデビュー・アルバム『モグワイ・ヤング・チーム』を発表する。以来、現在までに7枚のスタジオ・アルバムをリリース。フジロック'06でのトリや、メタモルフォーゼ'10の圧巻のステージその他、来日公演も語り草となっている。2015年10月、ベスト・アルバム『セントラル・ベルターズ』を発表。この4月には、広島への原爆投下70年にあわせて昨年放送されたBBCのドキュメンタリー番組『Atomic: Living In Dread and Promise』のサントラのリワーク集『アトミック』もリリースされた。5月には3都市をまわるジャパン・ツアーを開催し成功を収めている。
去年はまるまる『アトミック』の制作をしていたってことになる。
■とうとう東京、大阪、そして広島を回る日本ツアーの開始ですね。けっこうスケジュールは詰まっているんですか?
スチュアート・ブレイスウェイト:いや、そうでもないな。今日は金曜日に日本に着いてから、伊豆に住んでいる友だちの家でゆっくりしていたよ。
■すごく良いところじゃないですか(笑)。スチュアートさんはまだグラスゴーに住んでいるんですよね? バリー(・バーンズ)さんはドイツに住んでいるようですが、他のメンバーの方もグラスゴー在住ですか?
スチュアート:俺の住んでいる場所はあいかわらずグラスゴーのウエストエンドだよ(笑)。バリー以外はグラスゴー近郊に住んでいるけど、彼もグラスゴーに家を持っている、集まろうと思えば簡単に会える。
■あなたが運営しているレーベル〈ロック・アクション(Rock Action)〉の調子はいかがですか?
スチュアート:おかげさまで忙しくしているよ。2016年に入ってからもマグスター(Mugstar)とデ・ローザ(De Rosa)のアルバムを出したばかりだし、2015年もセイクレッド・ポーズ(Sacred Paws)やエラーズ(Erros)のアルバムを出せたしね。おっと、それから俺たちモグワイの新作も〈ロック・アクション〉からのリリースだ(笑)。グラスゴーのバンドが多い。リメンバー・リメンバー(Remember Remember)のグレアム(・ロナルド)は最近アメリカへ引っ越しちゃったんだけどな。
■ではモグワイの新作『アトミック(Atomic)』について訊いていこうと思います。今作は2015年に放映されたBBCのドキュメンタリー番組(『Atomic Living in Dread and Promise』)のサウンドトラックのために作られたアルバムだとのことですが、制作にはどのくらいの時間がかかったのでしょうか?
スチュアート:最初にできた曲は“ファット・マン(Fat Man)”で最後にできたのは“イーサー(Ether)”だ。制作は2015年の春からはじまって、夏にサントラのためにレコーディングをして、秋にはアルバム用に作業をしていたね。だから去年はまるまる『アトミック』の制作をしていたってことになる。
たしかに、いままでの俺たちのやり方とはぜんぜん違うよな。ジョークを言う余地はなかった。
Mogwai / Ether
■これまでのモグワイのインタヴューを読み返してみると、曲名やコンセプトにそこまでこだわっていないという趣旨の発言もされています。ですが、今回は「原子力」というとても明確なテーマがあり、曲名も“リトル・ボーイ(Little Boy)”や“ファット・マン(Fat Man)”といった、その黒い歴史を象徴するワードが多く、いままでのモグワイとはかなり対照的な作品だとも言えるでしょう。今回は制作にあたって、テーマに合わせて一から曲を作っていったのでしょうか?
スチュアート:まず「原子力」というテーマがあって、それに合わせて曲を作っていった感じだ。核技術、核爆弾、原発事故といったトピックがドキュメンタリーには登場するんだけど、それらに準じた事柄から名前がとられている。曲ができてから曲名をつけたんだけどね。たしかに、いままでの俺たちのやり方とはぜんぜん違うよな。ジョークを言う余地はなかった(笑)!
■曲を作る段階でBBC側からあらかじめ映像や脚本を渡されていたのでしょうか?
スチュアート:曲を作りはじめた初期段階から、監督のマーク・カズンズ(Mark Cousins)とは打ち合わせをしていて、そのときに映像に使用する予定の映像を見せてくれた。戦争や科学など、いろんな側面から核を捉えた映像だったね。ドキュメンタリーが完成する前だったから、そのときに見た映像の時系列はバラバラだったんだけど、着想を得るには十分だった。
■映像制作陣から具体的な曲のディレクションはありましたか?
スチュアート:マークからディレクションがあったわけじゃなくて、基本的にバンドで自由に曲を作っているよ。もちろん映像に曲をフィットさせた部分もある。良いコラボレーションができたと思う。
広島を訪れる前から核兵器に反対していたけど、実際に平和記念公園へ行ってみたら自分は原爆についてほとんど何にも考えていなかったんだなって思わされたよ。
■このアルバムの曲名には、一般的な日本人にはあまり馴染みのないものがあります。たとえば“U-235”は広島に投下された原爆に使用されたウランの同位体のことですが、恥ずかしながら僕はいままで知りませんでした。このサウンドトラックを作っている間、ご自分で原子力の歴史についてお調べになったのでしょうか?
スチュアート:ラッキーなことに、俺たちには化学者の友だちがいてさ。彼にも監督との打ち合わせに参加してもらって、そこで具体的な技術や核の歴史についても話してもらった。じつはその友だちに曲のタイトルをつけるのを手伝ってもらったんだよね(笑)。監督のマークにもテーマに関する助言をしていたよ。名前はアンディ・ブルー(Andy Blue)っていうんだけど、重要人物なのにアルバムにクレジットするのを忘れていたぜ(笑)! ははは!
■アンディさんはモグワイのブレーンですね(笑)。一応事実確認なんですが、スチュアートさんはCND(注1)のメンバーなんですよね?
スチュアート:そうだよ。ドラムのマーティン(・ブロック)もメンバーだ。
■メンバーになったきっかけを教えていただけますか?
スチュアート:俺はずっと核兵器には反対の立場をとってきた。10年くらい前にギグで広島へ行ったんだけど、そのときに平和記念公園にも行ってね。あれはでっかい体験で、その後にCNDのメンバーになることを決心した。 広島を訪れる前から核兵器に反対していたけど、実際に平和記念公園へ行ってみたら自分は原爆についてほとんど何にも考えていなかったんだなって思わされたよ。
■スコットランドでは一般の人々は核兵器や原子力についてどのようなイメージを抱いているのでしょうか?
スチュアート:核は悪いものだって思っている人は多いと思うよ。とくにグラスゴーは近くに原子力施設があるから、核エネルギーに関して危機感を持っている人は一定数いる。それなのに政府は、「原発は雇用をつくっています」的ないい加減な情報を流しているんだよね。数千人規模の雇用を生み出しているって言っているくせに、実際に働いているのは数百人ってところだ。
原発の問題は原子力そのものだけではなくて、かなり複合的な問題だ。
■日本でも同じようなことが起きていました。原発の安全神話が広告やメディアを通して世間に流布して、真実が見えにくくなっていった。原発産業の構造もいびつで、原発周辺住民にはお金を払っていたりしますね。住む場所によっても問題に対する意識が違ったりもします。
スチュアート:うんうん、そうだよな。原発の問題は原子力そのものだけではなくて、かなり複合的な問題だ。スコットランドには人口の少ない北部にも原子力施設があるんだけど、その地域の人々は違った考え方をしているかもしれない。
■2011年の6月に、大量発生したクラゲが冷却装置に侵入したことが原因で、スコットランドのトーネス原発が停止しました。福島の原発事故の後だったので、日本でも反応している人が多かったですね。ちょうどその出来事の後、僕はグラスゴーにいて、それについて現地の人と話してみたんですけど、原発の停止を知らなかったり、「まぁ、事故が起きたわけじゃないだし」と言う人もいたりしました。原子力関連のニュースはあまり話題にならないんですか?
スチュアート:あの事件はよく覚えているよ。スコットランドのメディアはたいしたことないからなぁ(笑)。情報をかなり絞っているから、詳細がなかなか一般層に伝わっていないんだ。
まずはサン・ラーだろ。それからウィリアム・オニーバー(William Onyeabor)の“アトミック・ボム”。あとボブ・ディランの“戦争の親玉”だな。こういった曲を聴ききながら、原子力について考えるようになったのかもしれない。
■スコットランドに限ったことじゃないですよ。ところで、日本には『ゴジラ』や『鉄腕アトム』など、原子力を背景に生まれた文化のアイコンがありますが、そういったものには馴染みはありますか?
スチュアート:『ゴジラ』は大好きだよ! あの作品に原子力と関連した背景があるとは考えて観ていたわけじゃないけど、たしかにその繋がりはかなり説得力があるね。
■原子力について歌った曲で、何が真っ先に思い浮かびますか?
スチュアート:何曲か思い浮かぶな。まずはサン・ラーだろ。それからウィリアム・オニーバー(William Onyeabor)の“アトミック・ボム”。あとボブ・ディランの“戦争の親玉”だな。こういった曲を聴ききながら、原子力について考えるようになったのかもしれない。
自分たちが曲を書いているときも、もちろん同じようなことを考えていた。でも同時期に作っていたすべての曲が、原子力に関する曲だったわけじゃない。自分がやっているもうひとつのグループのマイナー・ヴィクトリーズの曲を作っていたんだけど、その時は気持ちを切り替えて作っていた。自分が作る曲は、その時々でその裏にある伝えたいものは変わってくる。
人間なんだからそれぞれの自分の考えを持っていて当然だし、俺たちがやることに対して反対意見があって当然だと思う。それでも俺は自分の意見を持つことが大事だと思うし、自分とは違った意見を持つ人々に対しても耳を傾けるべきだと思うし、そうすることに間違いなく価値があるんじゃないかな。
■2011年の福島での原発事故のあと、日本では多くのミュージシャンたちが反原発を表明しました。彼らは賛同得た一方で、もちろんさまざまな批判にもあいました。今回、モグワイも原子力への考えを明確にしたわけですが、異なる立場の人々から自分たちが批判を受けるであろうことは予測していたと思います。なぜあなたたちは、そのようなリスキーな選択をする決心をしたのでしょうか?
スチュアート:人間なんだからそれぞれの自分の考えを持っていて当然だし、俺たちがやることに対して反対意見があって当然だと思う。それでも俺は自分の意見を持つことが大事だと思うし、自分とは違った意見を持つ人々に対しても耳を傾けるべきだと思うし、そうすることに間違いなく価値があるんじゃないかな。
多少はリスキーなことかもしれないけど、今回のプロジェクトは素晴らしいものだってわかったから、自分たちの主張を前に出す決断をすることができた。原子力に関するステートメントだけではなく、俺たちのアティチュードや信条とも共鳴する部分がこのプロジェクトにはあったしね。
もし自分たちが特定の意見??今回は原子力に関するもの??がなかったとしても、このプロジェクトを進めることができたかもしれない。俺たちの役割は曲を作ることだったからさ。このレコードにある政治的なテキストは監督のマークが考えたもので、俺たちはその考えを広める役割を担っただけだしな(笑)。でも音楽にだけではなく、さらには俺たちの考えにも耳を傾けてくれた人たちもいて嬉しかったよ。
■原子力に関するバンドのなかでの意見はみんな一致しているのでしょうか?
スチュアート:もちろん。メンバー全員が同じ意見を100パーセント共有している。
■偶然ですが、あなたたちが広島公演を行うのとほぼ同タイミングで、アメリカのオバマ大統領も広島を訪問するんですよね。
スチュアート:彼が訪問するなんて思いもよらなかったよな。日本の人たちがどの程度、普段から広島について考えているかわからないから、今回のオバマ大統領の訪問がどんな意味を持つのか、俺にはよくわからないんだけどね。モグワイがほぼ同じ時期に広島に来ることになるなんて、すごい偶然だよな。
本当に核兵器が必要なのかどうか疑問だし、核兵器を管理するお金を貧困層にまわせばいいのにと思う。なんかおかしいよな。
■核軍縮を訴えたプラハ宣言が大きなきっかけとなり、2009年にオバマ大統領はノーベル平和賞を受賞しました。しかし、現段階でアメリカは核軍縮に向け具体的な努力をしているとは言えません。オバマ大統領に対して何か意見はありますか?
スチュアート:彼が核軍縮を訴える姿はかっこいいけどね(笑)。本当に核兵器が必要なのかどうか疑問だし、核兵器を管理するお金を貧困層にまわせばいいのにと思う。なんかおかしいよな。
■このアルバムやドキュメンタリーのプロジェクトを通して、あなたたちが成し遂げたいこととは何でしょうか?
スチュアート:このアルバムやプロジェクトがどのような効果を及ぼすまでは俺にはわからない。でも、歴史を振り返ってみて、過去に起きたことを知るきっかけになればいいと思う。具体的に何が変わるかはわからないけど、多くの人々が、この原子力について考えるようになればそれでいいんだ。
スコットランドの独立を支持する意見のなかには、UK全体の政治のなかで、スコットランド票がまったく機能していないというものがある。つまりUKの政治にはスコットランドの声が届いていないということだ。
 Mogwai - Atomic Rock Action Records / ホステス |
■それではスコットランドに関連する質問をさせてください。モグワイは2014年のスコットランド独立を問う国民投票に合わせて、独立賛成派として同じくスコットランド出身のフランツ・フェルディナンドらとともに、独立派を支援するキャンペーンを行っていましたが、投票の結果、賛成票が過半数に届かずスコットランドは独立することはできませんでした。現時点から振り返ってみて、あなたはスコットランドの独立をどのように捉えていますか?
スチュアート:いまだって俺はスコットランドの独立を支持しているし、そうするべきだと思っているよ。たしかに俺たちは国民投票前に独立派のキャンペーンにも関わっていたから、票を得られなかったのはけっこう辛い経験だったことは事実だ(笑)。でも機会があればまた俺たちは関わるだろう。
■スコットランド人の学生やミュージシャンに独立について意見を聞いてみたのですが、リベラルな意見を持った人々も独立を支持していますよね。またイングランドの労働党のサポーターにも、スコットランドの独立を肯定的に捉えている人々がいます。ですが、周辺国や日本には、保守派や「クレイジーな右派」が独立支持の多くを占めていると思っている人が多い印象があるんですよ。
スチュアート:実際にはぜんぜん違うのにね。スコットランドの独立を支持する意見のなかには、UK全体の政治のなかで、スコットランド票がまったく機能していないというものがある。つまりUKの政治にはスコットランドの声が届いていないということだ。なぜスコットランドも構成国のひとつなのに、イングランド側が決めた方針で核兵器やイラク戦争に国の金が使われなきゃいけないんだ? 難民問題に対するUKの対応だってひどいよな。独立派のなかには、スコットランドが政治的に自由になって、よりリベラルで社会主義的な姿勢を国政に反映させることを望む声だってあったんだよ。クレイジーな戦争なんてうんざりだって意見もあった。いまは少し変わってしまった部分もあるけどね。そういった人々にとって、当時のSNP(注2)は良いオルタナティヴに見えた。
セルティックは60年代にヨーロピアン・カップで優勝したことがあるんだけど、そのセルティックとレスターが重なって見えてさ。
■残念ながら、日本にはユナイテッド・キングダムがどういう仕組みになっているのか、スコットランドがどういう立場にいるのかを理解している人が多いとは言えません。モグワイがもし次に大きなプロジェクトに取り掛かるとしたら、スコットランドへの理解を深めるようなものがいいかもしれませんね。現に僕はあなたのギターに貼ってある、スコットランドの国旗のシールがきっかけになって、スコットランド人のアイデンティティについて考えるようになりましたから。
スチュアート:日本はスコットランドから遠いからなぁ(笑)。それはやってみる価値があるかも。国際的なサポートを集めるのは大事だよな(笑)。
■最後に政治とはまったく関係のない、フットボールのトピックへ移りましょう。リーグは違いますが、今年イングランドのプレミアム・リーグでは地方の弱小チームだったレスターが優勝しました。あなたはグラスゴーのセルティックの熱心なファンだと知られています。レスターの優勝はあなたのセルティック愛へ何か影響を及ぼしましたか?
スチュアート:隣の国のことだけど、めちゃくちゃ良い話だと思ったよ。とてもインスパイアされた。セルティックは60年代にヨーロピアン・カップで優勝したことがあるんだけど、そのセルティックとレスターが重なって見えてさ。当時のセルティックはいまよりももっと規模が小さなチームだったんだけど、さらに大きなイタリアやスペイン、そしてイングランドのチームに勝利したわけだから。
■去年、清水エスパルスという日本のJリーグのチームが下部のリーグへ降格してしまったんですが、エスパルス・ファンにもレスターは大きな希望を与えたみたいです。国際的にものすごく勇気を与える存在ってなかなかいないですよね。
スチュアート:うわぁー、それは残念だったね。いまもセルティックはヨーロッパのなかでは小さなチームだから、レスターの優勝にはすごく大きな希望をもらったよ(笑)。こんなに広い範囲でインスピレーションを与えるってすごいことだよな。
(注1)
CND(Campaign for Nuclear Disarmament)、核軍縮キャンペーン。1957年に設立された反核運動団体。
(注2)
SNP(Scottish National Party)、スコットランド国民党。スコットランドの地域政党で、UKからの分離・独立、親EUを主張する。2015年5月のUK総選挙で、 SNPは56議席を獲得し、保守党と労働等につぐ第三党になった。